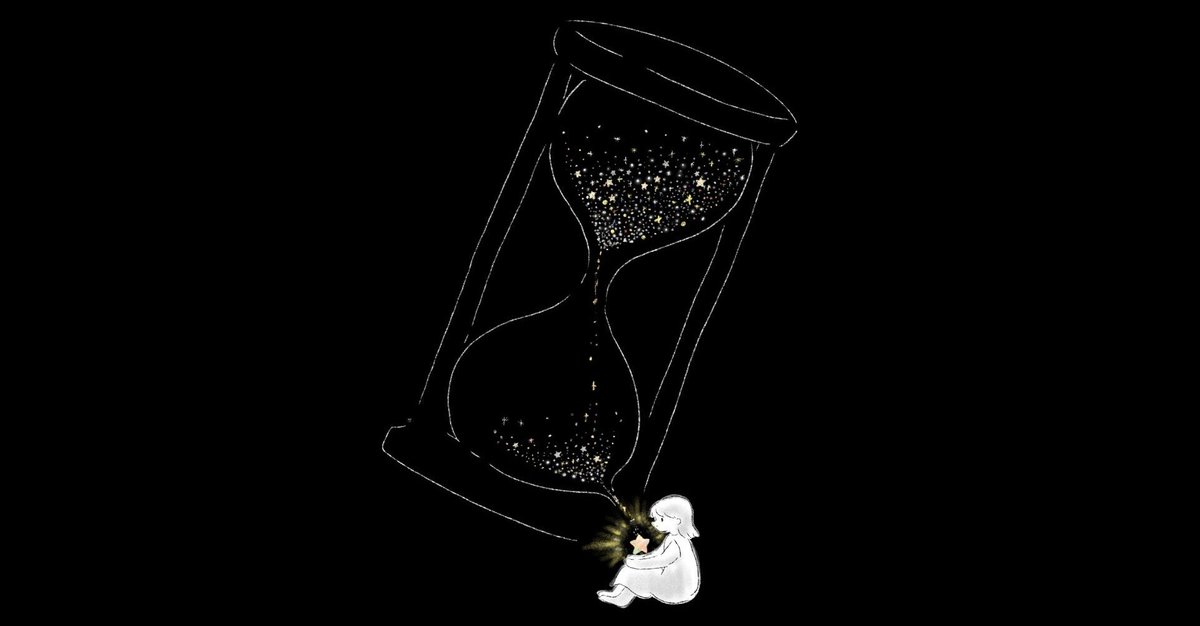
鬼の末裔
――私は毎日、夕方になると、ある言葉を唱えなければいけない。
でないと、「あの世」に迷いこんでしまうから――
オリジナルの短編小説です.よろしければお付き合いを.
1
「近藤さん、一緒に帰ろう」
そう言われ、私はきょとんとして相手の顔を見やった。同じクラスで、一緒に体育祭実行委員をやっている男子生徒だ。ついさっきまで委員の話し合いをしていて、やっと解放されたところだった。
――ごめん。悪いけど、急いでるの。また今度ね――
そんな言葉が喉から出かかったが、ぐっと飲み込んだ。そして、にっこり笑って応える。
「いいよ。用事があるから、途中までになっちゃうけど」
「本当? よかった。それじゃ、行こう」
「うん」
内心ガッツポーズを決めながら頷く。彼のことは前々から気になっていたし、はっきり言えば、体育祭実行委員なんて面倒くさいのに立候補したのも、彼が目当てだった。
腕時計にちらりと目を落とし、まだ今日の日没時刻まで充分時間があることを確認する。すると、それを見とめて彼が言った。
「近藤さん、いつも腕時計してるよね。時間なんてスマホで確認できるのに、何でわざわざ?」
「あ、これ……癖で。うち、親戚も家族も時間に厳しい人ばっかりでさ。スマホだと、とっさに確認できない時があるでしょ? それで、子供の頃から、着けるのが習慣になって、無いと落ち着かないんだ」
そう言ってごまかす。本当は、もっと深い理由があったのだけれど。
私の家――というより、母方の血筋には、代々言い伝えられているしきたりがあった。――夕方の、いわゆる「逢魔が刻」には、必ずある言葉を唱えなければならない――
2
太陽が地平線に消え、空がすっかり暗くなるまでの間、たった一つの言葉を唱え続けるのだ。それを怠れば、たちまち「この世」から足を踏み外し、跡形もなく消え去ってしまうのだという。
それだけなら、他愛のない迷信だと思われるだろうけれど、実際に、私の母は、私が生まれてから数年して「消えて」しまった。
姿だけではない。いったん消えると、「顔」も「名前」も消えてしまうのだ。母が消えた後、母の家族も友人も、誰も母の顔と名前を思い出せなくなった。
写真や名前の書かれた書類なんかが残っているでしょうって? 残ってはいても、見ることができなくなるのだ。写真は誰が見ても、母が写っている箇所だけ靄がかかったようになっているし、書類の文字も、誰かが読もうとすると、その瞬間、訳の分からない不明瞭な声しか出せなくなってしまう。
覚えていられるのは「母が存在していたこと」だけ。それがなぜなのかは分からないけれど、一説によれば、母方の祖先は、「鬼」の血を引いているのだという。
何とも信じがたい話ではあったが、実際にそうして「消えて」しまった人が、これまでに幾人もいるのだ。ばかばかしくても、信じて守り続けるしかないだろう。私の知る限り、「鬼」の末裔は、自分が最後の生き残りだ。
3
「近藤さん」
不意に真剣な調子で呼び止められ、思わず立ち止まる。見ると、彼が真顔でじっとこちらを見つめている。
「〇〇くん、どうしたの」
どぎまぎしながら尋ねる。別れ路は目前で、日没まであと数分に迫っていた。
焦る気持ちと、折角のチャンスを逃したくないという気持ちが心の中で渦を巻いていたが、平静を装って彼を見つめ返した。
「実は、近藤さんに伝えたいことがあって……」
心拍数が急上昇した。彼の少し緊張した面持ちに、もしかして、と期待が膨らむ。その瞬間、私は「しきたり」のことを綺麗に忘れ去ってしまった。
「どうしたの、そんな改まって。用事があるなら、メッセでいいんじゃない」
「こういうことは、やっぱり、直接会って伝えたいなって」
心臓がバクバク音を立て始めた。互いに無言で見つめ合った後、彼がゆっくりと口を開く。
「俺、近藤さんのことが好きです。付き合ってください」
頭の中で高らかに鐘が鳴る。喜びに打ち震えて、私は目を瞑った。
「嬉しい。私も……!」
そう言って目を開けた瞬間、目の前にあったのは、愛しい彼の顔ではなく、奇妙な色がとぐろを巻いて蠢く見知らぬ世界だった。
4
――ここ、どこ……?――
しばし混乱して、私は周囲を見回した。どう考えても、そこは「異空間」としか呼べないような場所だった。
黒の混じったような汚い虹色の光が渦を巻き、色々なにおいや気配が絶えず流れ、生暖かく逆巻いているような不思議な空間。その中に、自分らしき何かがたゆたいながら漂っているのだ。ついさっきまであったはずの手も、足もない。あるのは、やわらかい粘土のように、大きな流れに合わせてぐにゃぐにゃと形を変える「自分とおぼしき塊」だけ。「魂」とでも呼べばいいのだろうか。
その瞬間、全てを悟った。恐らく、あの告白騒ぎに気を取られて、日没に気づかなかったのだ。
私は絶望した。そして同時に、言い伝えは迷信ではなかったのだと思い知った。
――どうしよう――
自分もこのまま、母や、かつて消えていった人たちのように、この世界に永遠に閉じ込められてしまうのだろうか。もし目が残っていたら、涙の一つでも流せたのかも知れないが、粘土の塊と化してしまった今、それは叶わなかった。
しばらく途方に暮れてたゆたっていたが、やがて気を持ち直して決心した。
――帰ろう、何としても、元の世界へ――
せっかく、好きな人から告白されて、人生これからという時に、諦めたくはなかった。
5
「鬼」の血を引く人たちの中には、少ないながらも、「あの世」に迷い込みながら、生還した人たちもいた。
そもそも、私たちが「逢魔が時」に「あの世」へ迷い込んでしまうのは、昼から夜へと移り変わる瞬間に、「あの世」と「この世」の入り口が存在するせいなのだ。元来「あの世」の存在だった鬼が、何かの理由でこの世にとどまっているだけ。そのため、うっかりすると「あの世」に引き寄せられ、そちらへ繋がる路に迷い込んでしまうのだという。そして、「あの世」に迷い込んでしまった瞬間、私たちは「向こうの世界」の自分の名前も、縁のある人たちの顔も名前も、全て忘れてしまう。
しかし、夜になった時「この世」にいれば、夜から朝へ移り変わるとき、「あの言葉」を唱える必要はない。夜の世界から昼の世界へ繋がる路は、1本しかないからだ。
生還した人たちによれば、夜から昼へ変わる瞬間、そちらの世界にいる人間と繋がり、その「誰か」に呼び戻してもらえれば、この世に戻れるのだという。
同じく「鬼」の一族の一員で、数少ない「生還者」だった祖母によれば、「あの世」は「この世」の裏側で、決して遠く離れた異界というわけではないのだそうだ。この世の断片が至る所に隠れていて、注意深く探していけば、「この世」と、そして自分とを繋げるものを見つけ出せる、と言っていた。
6
流れに身を任せながら、全身を目にして、元の世界と自分を繋げるものを探した。と、キラキラした泡のようなものがぶつかってくる。その瞬間、身体(あるのか分からないけど)が突然温かくなった。
――〇〇さんのことが好きです。付き合ってください――
さっきの、告白の記憶だった。それも、私ではなく、彼の記憶の断片らしかった。掴もうとしたけれど、すぐに消えてしまった。
そして、その瞬間悟ってしまった。彼は、私のことなんて大して好きではない、と。
みじめな気持ちで、また流れに身を任せる。やがて、何か暗い青色の泡にぶつかる。
――〇〇ってさ、誘ってもだいたい『用事があるから』って断るじゃん。あれ、ほんとうざいんだけど。っていうかさ、あの子何か冷たいよね。温度差感じるっていうか――
これにも、心当たりがあった。数日前、友人たちが私をのけ者にして、放課後カラオケに行ったときのことだと思う。
「しきたり」のために、友人たちの誘いを断ることが多かった。事情を説明してもどうせ信じてもらえないだろうし、下手をしたら気味悪がられるのでは、と、いつも大事なことははぐらかしていたから、そう思われても仕方なかったのかも知れない。
それからしばらくふらふらしていると、今度は赤黒い液体を浴びた。
――あの子、何だか気味が悪い――
義母と父だった。母が消えてしばらくしてから、父は会社で知り合った女性と再婚した。義母にも、友人たちと同様、しきたりのことは説明していなかった。父から「怖がらせるだけだし、話してもどうにもできないから、黙っていなさい」と口止めされたためだ。
父は、義母と私がうまくやっていくために、とおためごかしていたけれど、実際には、私に、自分の再婚を邪魔されたくなかったのではないかと思う。
その後も、出合う「この世」の断片は、似たり寄ったりのものばかりだった。誰の記憶の中でも、自分は大して重要ではない脇役か、邪魔者でしかなかった。
またしばらくふわふわしていると、今度は濃い灰色のぐにゃぐにゃした塊の中に潜り込んだ。
――この子だけ残されて、どうしたらいいんだよ。どうせこいつも、そのうち消えちまうんだろ――
父の記憶だった。母が消え、一人で私の世話をしていたときのものらしい。もっとも、肝心の私の顔には靄がかかって見えなかったけれど。父が、私を重荷に感じているのがひしひしと伝わってきて、身体があったら泣き崩れていたと思う。
――そっか。私、頑張って帰る必要なんてないんだ――
自分の中で、何かがぷつりと切れた。
7
その後は、何も考えず、何も感じず、生暖かい流れの中で揉まれるままだった。抗うのをやめた途端、それまで恐ろいしとしか思えなかった濁流が、急に心地よいものに感じられるようになってきた。あらゆる生き物の、あらゆる記憶や感情に揉まれるうちに、自分の「個」としての輪郭がぼやけ、自分もこの流れの一部なのだと分かってきた。
――もう、夜は明けてしまったかな――
朦朧とする意識の中で、そんなことを考えた。路を間違えて一夜明けてしまった者の中で、生還した者はいないという。
――まあ、いっか――
そう思った瞬間、冷たい波に洗われた。
――『おなじないの言葉』は覚えたかな?――
母の記憶だった。「鬼」の一族の子供は、7歳になるまで、まじないの言葉を唱えない。7歳までは、夜に「あの世」に迷い込んでも、翌朝には必ず「この世」へ帰ってくることができるからだ。「7歳までは神のうち」なんて言うけれど、私たちの一族の間では「7歳までは鬼のうち」なんて言われていた。
その代わり、7歳までに、まじないの言葉を覚えさせ、毎日、日没から暗くなるまでの間唱え続ける、というのを習慣づけておかないといけないのだ。
私はむくれて、返事をしようとしない。
――どうしたの。お返事は?――
――覚えたら、お母さん、いなくなっちゃうんでしょう――
母が驚いたのが分かった。それと同時に、私の言葉が母にとって図星であることも伝わってきた。
その瞬間、母が消えた日のことを思い出した。この会話の直後、母は消えてしまったのだ。逢魔が時が訪れても、母はきつく口を閉じ、まじないの言葉を唱えようとしなかった。
どうして忘れてたんだろう。そう思うと同時に、何かが腑に落ちた。
もしかしたら、母は絶望していたのかも知れない。今の自分のように。
それなら、自分ももう、この流れの中に溶け込んで、向こうの世界のことなんて忘れてしまおう。そもそも、私たちの祖先は、どうしてあちらの世界に現れたりしたんだろう。異質な存在として、厄介者扱いしかされないのに。
そんなことを考えていると、不意に誰かが私を抱き上げた。見知らぬ、若い男の人だった。男の人は、まじまじと私の顔を覗き込みながら言った。
――大きくなったね――
すると、母がふわりと笑った。その瞬間、忘れていた母の顔を、ようやく思い出せたのだと思い至った。
こんなに優しい顔の人だったんだ。それにしても、この男の人は、いったい誰だろう。でも、母と同じくらい優しい顔をしている。
――きっと、大きくなったら君とそっくりの美人になるだろうね――
――そうかしら。この子は、あなたに似ると思う――
その言葉に耳を疑った。けれど、男性は驚く様子もなく、子供の私に優しく囁いた。
――20歳になったら、また会おうね。葵ちゃん。会えるの、ずっと楽しみにしてるよ――
男性がそう言った瞬間、目が合ったような気がした。
その途端、自分の名前と、その男性の名前を思い出した。
私は思わず、その名を叫んだ。
8
気が付くと、家の前に立っていた。
もうすっかり明るくなって、スズメやカラスが元気に囀っている。
少しためらった後、私はそっと家のチャイムを鳴らした。
しばらくして、家の中から、義母と父が現れた。
両親は私が帰ってきたことを悟ると、複雑な表情ながらも迎え入れた。
その日は体調不良を理由に学校を休み、翌朝、何事もなかったように学校へ行った。
告白してきた男子は、どうやらあの日のことを自分の思い違いか妄想かとでも思ったようで、顔を合わせると少し不思議そうな顔をしながら、
「一昨日、一緒に帰ってないよね?」
なんておかしな質問をしていた。
自分の席に着きながら、どうしてあの時、私はこちらへ帰ってきてしまったのだろう。と、自分自身に問い掛けた。
あの瞬間、自分は確かに、あの男性が何者なのか、思い出したはずなのだ。けれど、こちらに帰ってきた瞬間、全て忘れてしまった。まるで、こちらへ帰ってきた代償、とでもいうように。
それでも、きっと、生きていれば、「この世」のどこかにいるはずだ。そして、20歳になった私と会うことを、心待ちにしているはずなのだ。顔は覚えていないけれど、あの「優しい」笑顔で。
それだけを望みに、私はもうしばらく、こちらの世界にしがみついていよう。そう誓った。
そして今日の「誰そ彼刻」も、祈るような気持ちで、あの言葉を唱える。
完
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
