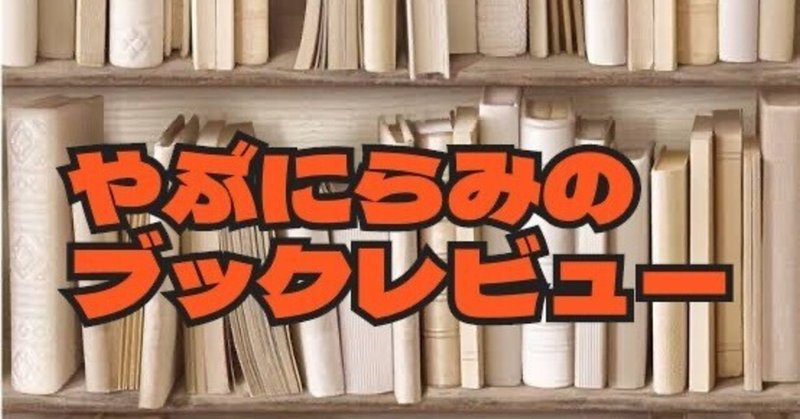
落合信彦『20世紀最後の真実』

いまも戦いつづけるナチスの残党』
1984年 集英社
【落合信彦に見るフェイク・ドキュメンタリーの問題】
ずいぶんと昔の話だが、知人の大学生が一冊の本を持ってきて、興奮しながら、ぜひ読んでくださいと言ってきた。
その本が落合信彦の『20世紀最後の真実』だった。
「国際ジャーナリスト」という肩書きで当時、プレイボーイ誌日本語版などで若者から絶大な人気があった落合信彦の著書だった。
大学生くんは
「南米にナチの小さな国があって、そこでUFOを作っていて、南極にUFO部隊の基地があるんですよ!ヒトラーも生きています。この本はそのことに取材をしたドキュメントです!」
と言うのだ。
全く荒唐無稽な話だが、わたしはこの本ちょっと奇妙な本を読むことにした。
読んでいて、笑ってしまうほどに面白いけれど、全く遊んでいるような内容の本だということがわかった。
著者は自分で取材をしたと大真面目に書いている。ナチの逃亡戦犯を南米に逃したのはカトリックやバチカンであるということを著者は自分が見つけてきたかのように書いているが、この本が出た頃は、もう、そんなことはナチスを研究している人にはお馴染みのことであった。
落合は南米のチリに赴いて、そこにあるチリ政府にも治外法権のドイツ人入植者のコロニー、「エスタンジア」を取材。そこがナチの残党が作って、ドイツ移民を住まわせて第四帝国にするというナチスの小国だと紹介した。
この「エスタンジア」の正体は、チリに存在したドイツ人入植地、コロニア・ディグニダのことだ。
狂信的な元ナチ党員のパウル・シェーファーがリーダーとなって、半ば強制収容所のような施設を運営しており、1970年代から問題となっていたものだ。
まさか、ここでUFOを開発したり、ヒトラーの側近、マルティン・ボルマンを住まわせてたなど、噂でしかなかった。
近年、この問題は映画『ジョン・ラーべ』の監督、フロリアン・ガレンベルガーによって『コロニア』というタイトルで映画化されている。
落合信彦はコロニア・ディグニダを勝手に第四帝国の秘密組織の謀略基地であるかのような印象を本で与えた。
もう一つは、カナダへの取材の部分だ。
カナダにあるナチの秘密組織に接触して、そこのリーダーと大物逃亡戦犯の証言を得たというものだ。
この、組織というのはその後明らかになっていて、ネオナチグッズを北米やカナダで売り捌いたり、南極のナチのUFO基地探索ツアーを企画して売るなどをやっていた、怪しい団体(出版社)で、その長(というか一人だが)がホロコースト否認派でネオナチのエルンスト・ズンデルだった。
ドイツ系カナダ人のズンデルはナチUFOフリスビーの通販をしたり、ともかく、胡散臭い人物だが熱狂的なナチだった。
ホロコースト否定問題で、起訴されたりしている人物で、落合信彦が『20世紀最後の真実』を書いた当時もズンデルはすでに「やましいネオナチ」として海外では知られていた。
もちろん、モサドやCIAが敵とする秘密結社でもなんでもない。怪しいナチカンパニーの一つだったのだ。
1970年代にはネオナチがプロパガンダと商売を兼ねて、北米でナチグッズを売り捌いているのは当たり前のような現象だった。それらの商品は日本にも輸入されていて、新宿にあったミリタリーショップ「アルバン」の店頭にも並んでいたから、珍しくもなんでもなかった。
商品には施販売元の住所も電話番号も書いてあったし、これらの「組織」の目的は西ドイツで違法とされているグッズを北米で売り捌き、西ドイツへそれらを入れてやろうというネオナチの戦略の人だったのである。
問題は落合信彦は、チリのエスタンジアやズンデルの組織が、ただの怪しい団体や出版社であることを知っていたのか? それとも、知らずに本気で危険極まりない国際謀略組織だと信じていたのだろうかということだ。
しかし、それはあり得ないようにも思う。
海外ではコロニア・ディグニダのことも、エルンスト・ズンデルのことも、その時代では知られていたのであるから、確認を取ろうと思えば取れたはずである。
そうなると、やはり、こうした組織を使って、より面白く膨らませてUFOにまで結びつけるフィクションを書いたということになる。
わたしはそこで考える。
これは、松本清張の『日本の黒い霧』と同じなのであると。
『日本の黒い霧』が戦後のアメリカ占領下で起きた未解決怪事件は、アメリカ占領軍が犯人で、その動機が来るべき朝鮮戦争に備えるためであったという推理小説であった。それと同じく、ヒトラーが戦後、第四帝国を建設するためにUFO兵器を開発して、来るべき戦争に備えているという結末にあわせて、全てを繋ぎ合わせたのが落合信彦の『20世紀最後の真実』だと。
どう考えても、これはドキュメント・フィクションなのだ。
その後、落合信彦はいろんなところから、捏造ドキュメンタリーであるとか、盗作疑惑がるなどと書かれてきた。
それは、この話を読者が本当の「真実」だと思い込んでしまったからだ。
驚いたことにネット上では、絶版になってしまった、この本に書かれてあることが真実だと思い込んでいる人は意外に多いのだ。
こんな混乱が起きるなら、落合信彦は最初からフィクションであるということを、松本清張のように述べておくべきではなかったかと思う。
そうすれば売れなかったかもしれないということか?
フェイク史に残る、オーソン・ウェルズの『宇宙戦争』のラジオ放送や、イギリスのフェイクドキュメンタリー『第三の選択』のように、フィクションだと断っていても、みんなが騙されてしまうものだってある。
内容が巧いフェイクなら、フィクションだと断ったところでクオリティーは下がらないものだと思う。
フェイクをフェイクだと知って、楽しむのと、フェイクをフェイクと知らずに騙されてしまうのでは大きな違いがある。
そこにはお決まりのファクトチェックやら、メディアリテラシーなどの力が必要となるわけだが、ドキュメント・フィクションやフェイクドキュメンタリーの作り手が、フィクションであると明らかにすることが何よりも早道なのではないかと思う。
陰謀論も信じるよりは楽しむぐらいのスタンスが、実は文学的な愉しみとして健全であるのだとわたしは考えている。
そういう意味で落合信彦の『20世紀最後の真実』を読んでみるのも、また楽しからずやだと思うのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
