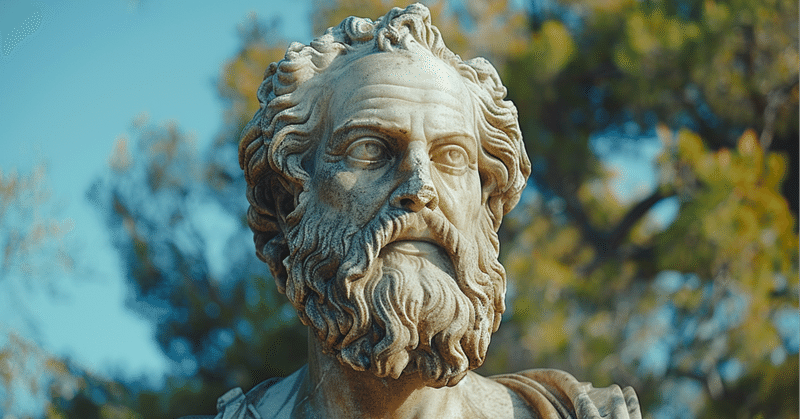
知識は力なのか・・・?
*この記事は約1分で読めます。
数百年前の師を持つこと
今から1世紀ほど前の人がこんな事を書いています。
『五百年、千年、二千年、否もつともつと先の年代に成る幾多の作品に眼を移して視よ。そしてその年代の人間は、天地を貫ぬく自然の美妙を如何に観たか。そして如何に道理にそむくことなく、素直に美しいものを造り遺していつたかに注目せよ。』(原文そのまま)
この文章は北大路魯山人という人の書いた『青年よ師を無数に択べ』という中の一節です。これからを生きる青年に向けて今を生きる人ではなく古代の人を自分の師にせよ、魯山人の熱い想いです。
さて、21世紀を生きる私たちは科学のおかげで色々な事を知っています。ゼウスの怒りだと思っていた雷は雲の中にある微粒子がぶつかった際の摩擦だと知ったり、巨大ナマズが動く事で起きるとされた地震はプレートのズレが原因だと分かったり。
今の僕らから見れば昔の人たちの考える【想像】というのは若干滑稽かと思えるかもしれません。ゼウスだとかナマズだとか奇想天外ですからね。しかし、知識が発展することが一概に良い訳でもないのだと私たちは知っておくべきでしょう。
知識の副作用
知識というのは『思い込み』を増長する要素のひとつとして、我々人類に対してこれでもかと作用します。知識というのは言い換えると、我々から観察する機会を奪うものです。
例えば、目の前に綺麗な花があるとしましょう。近づいてよくよく見てみると、それがスミレの花だとわかる。そうするとどうでしょう。もうあなたは目を閉じてスミレについて頭で考える程度でしょう。決して目の前の花を観察しようとはしないでしょうね。
スミレの例は小林秀雄という批評家の書いた『美を求める心』の一節ですが、ハッとさせられた人は少なくないはずです。例に漏れず僕も言葉を少しばかり失いましたね。
私たちは随分と賢くなりました。自然に抗えないとはいえ、この地球を征服しつつあることもまた事実。現に、私たちは地球を自分たちの所有物として使い続けていますから。しかし、賢くなればなるほどリスクを冒さなくなるのが生き物というもの。生物としては当然なんですが、リスクを冒さないということはつまり、モノを考えなくなることと同じでしょう。知らない難題があるから頭が利口に働くのであって、毎日の歯磨きやら着替えに頭など使わないでしょう。
ノイズの多い現代で・・・
さて、知識というのはある種のノイズ(雑音)です。ガヤガヤした環境で集中できないように、私たちは知識があるせいで思考を巡らせる機会も時間も随分と減ってしまいました。シャーロックホームズの舞台は19世紀のロンドン。今と違ってスマートフォンがないので手紙でのやり取りが当たり前のそんな時代。シャーロックは驚異的な集中力で犯人の残した要素を点から線に、線をひとつの図のように繋いでいく訳ですがそれは現代だと可能なのでしょうか。
色々知ってしまっている私たちだからこそ、冒頭で引用した北大路魯山人の言葉が重要なのでしょう。数百年の人たちが知識(ノイズ)のない状態で考えたり想像したアレやコレやが実は大きな手掛かりとなることを忘れずに生きていきたいモノです。
では、また明日
長濱(2024.4.9)
【他の日のnoteはコチラ】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
