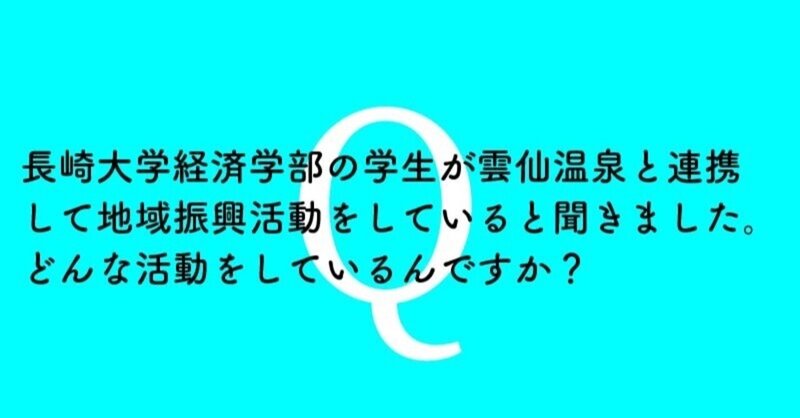
雲仙温泉で「リアルな経営学」を学んでいます。
2021年8月に発生した大雨による土砂崩れで、雲仙市小浜町の小地獄地区及び雲仙温泉街が大きな被害を受けことに際し、尊い命が失われたことについてご冥福をお祈りしますと共に、今なお避難を強いられている方々、やむなく休業しておられる方々、またそのご家族に、心からお見舞い申し上げます。1日も早く安全、平穏が復することをお祈り申し上げます。
Answer 長崎大学経済学部、津留崎ゼミの3年生11人が
「広報活動」「ご当地グルメ」「アクティビティ」の
3つの角度から地域進行に関わるプロジェクトを進めています。

津留崎先生流「地域に交わり実践的な経営学を体で学ぶ」
長崎大学経済学部の津留崎ゼミでは、毎年長崎県内各地を舞台に、民間企業と学生とのコラボレート活動を展開させています。今年の舞台は雲仙温泉エリアを中心とした雲仙市です。
現在、雲仙温泉は雲仙市、観光協会、交通機関、地域企業も巻き込み、地元の総力をあげて、10年計画 の観光戦略のもと、様々な地域振興活動を進めています。若年層や外国人にも注目されるよう新たなプロモーション方法を模索しているほか、自然や泉質の良さなどの恵まれたポテンシャルと相反して、課題となっている「まちの賑わいの減少」「高低差があり歩きにくい環境」「土産品の種類の希薄さ」などの克服を掲げています。
雲仙市の観光戦略を踏まえ、津留崎ゼミの3年生は「広報活動」「ご当地グルメ」「アクティビティ」の3つの角度からプロジェクトを進めています。具体的にどんなプロジェクトなのか、6月下旬のゼミを訪ね、11人の学生と指導教員の津留崎和義先生に話を聞きました。
①【プロモーショングループ(4人)】
テレビ番組を制作して雲仙の魅力を発信します。

プロモーション(promotion)とは日本語で宣伝や広報のこと。経営学では、消費者の購買意欲を引き出すための様々な活動のことを指します。プロモーショングループの4人は、地元のケーブルテレビ局「ひまわりてれび」と連携し、同局で、放送する番組を制作させてもらうことにしました。島原半島の魅力を「食」に絞って調査。番組構成、撮影、編集まで4人で行い、発信します。
【制作番組の概要】
番組テーマ……“魅力的な島原半島の食”
番組の概要……10分番組、5回シリーズ
学生の担当……出演、撮影、編集まで番組制作に関わる全て。グループ4人で持ち回りで全役割を担当する。
島原半島は「1億人の胃袋」と言われる県内屈指の農産物、畜産物の生産エリア。4人がテーマを“魅力的な島原半島の食”に絞った理由はそこに着目したからです。農産物から直売所、さらにその食材を使った料理がいただける食事処を紹介していこうと計画しています。1回目の取材先が決まり、これからアポイントどりです。
②【仁田峠活性化グループ(4人)】
仁田峠で必食!のフィンガーフードを開発します。

仁田峠と言えば、雲仙温泉エリアを観光する上で必ず立ち寄る定番スポットです。その仁田峠に地元の食材を使った”ご当地グルメ”を生み出すことができれば、観光客へのPRになるほか、地元の生産物の流通を活性化させることができます。そこで、観光客にとってお得感があり、手軽に食べれることができるフィンガーフード(手でつまんで食べられるお料理のこと)を開発することにしました。
【ご当地グルメの概要】
■料理のコンセプト
雲仙市の食材を使い、地元の方が手がけたフィンガーフード
■ラインナップ
・ガッツリ満腹系(雲仙バーガーなど)
・美しさを楽しむスイーツ系(花を使ったゼリーなど)
・栄養摂取できる健康志向系(野菜チップスなど)
■開発の手順
学生と地元の調理人のアイディアを組み合わせて商品化。
現在、雲仙バーガーの商品化に向け雲仙温泉エリアの4店舗と話を進めています。伝統野菜の黒田五寸人参を練り込んだバンズを使っていたり、パテにソースをかけて雲仙温泉のマグマをイメージさせたりと、それぞれにオリジナリティを持たせるそう。4店舗全部のハンバーガーを食べたくなりますね。
③【雲仙温泉観光協会グループ(3人)】
雲仙温泉エリアを丸ごと満喫できるアクティビティを考えます。
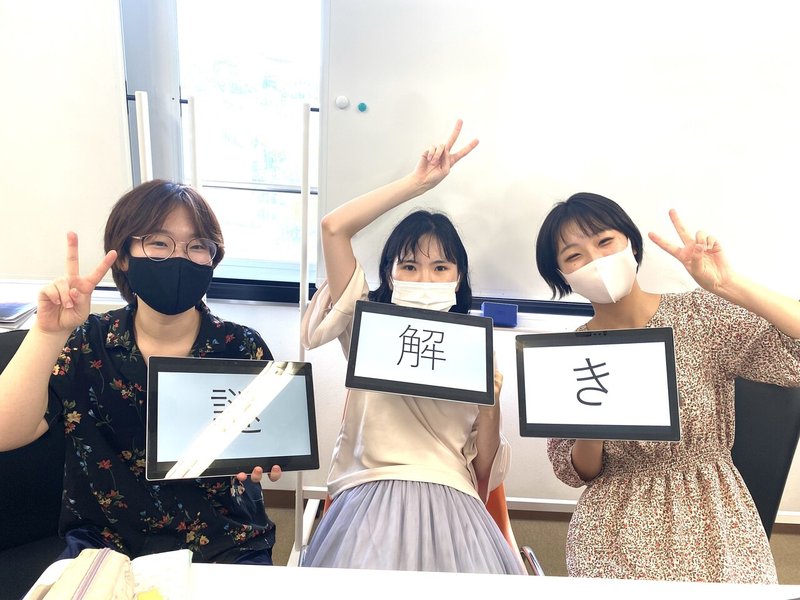
雲仙温泉の魅力の一つに国立公園というキーワードがあります。春はミヤマキリシマ、秋は紅葉に染まる風景や、白雲の池や原生沼の親水エリアなど、雄大な自然を味わい、触れ合えるスポットでもあるのです。雲仙温泉観光協会と連携して自然を楽しむアクティビティ商品を考えている同チーム3人。協会所有の電動アシスト付き自転車の稼働率を上げつつ、近辺の見どころを巡るアクティビティ「謎解き自転車ツアー」を企画しています。
【謎解き自転車ツアーの概要】
■アクティビティコンセプト
「謎解き」を動機付けに、雲仙の自然景観を眺めつつ、観光スポットを複数箇所巡ることができる“1粒でたくさん楽しめる自転車ルート”を考える。
■謎解きの課題
・年代を問わず楽しめるよう、大人向けの難解版、子ども向けの簡単版を準備。
・各観光スポットも楽しんでもらうため、その地に関係のある謎解きも準備する。
全国各地で展開している電動自転車ツアーの事例を参考にしながら、雲仙温泉エリアに最適な方法を検討しています。エリア内には温泉はもちろん、商店街もあることから、五感で味わえる仕掛けや、買い物に繋がる働きかけもできそうです。
「自ら考え、動くことで得られる経験こそが宝」
3グループは進捗状況と今後のフィールドワークの進め方を津留崎先生に報告し、指導を仰ぎました。津留崎先生からは、アポイントの取り方などの社会人としてのマナーをはじめ、地域の特性を魅力として取り上げる方法や、商品の付加価値を高めるコツなどを伝えていました。
津留崎先生に、大学での学びを地域で活かそうと奮闘しているゼミ3年生11人の成長ぶりについて聞きました。

「経済学部にとってのフィールドワークは、理系学部でいう実験のようなもの。学生にとって実体験の場です。彼らが主体的に動けるような環境を準備して、マネジメントを実践させています。
2年生までに、学生はコミュニケーションやプレゼンテーションに関わる実習を受け、フィールドワークに向けた準備をしていますが、知識をインプットしただけで実体験は少ないです。3年生になり、本格的なフィールドワークに赴く時、本人にとっては「当たって砕けろ」くらいの勇気が必要でしょう。しかし、自分で動いて得られた経験はとても大きい。特に失敗から得られる成長は計り知れません。教員に指し示めされて得られた成功より、自分で考えた末の行動から得られた失敗の方が、格段に記憶に残り、教訓として一生彼らを助けるでしょう。
そういうことから、学内で実施するゼミでは進捗を確認し、適宜指導をしますが、現場では主体的に活動させるように仕向けて、指示はしないようにしています。側から見ると、現場に学生を放り投げているかのように見えるかもしれませんが、手をかけ過ぎないことで、実践的な経験ができます。つまり、学生は直面する問題を自分で見極める努力をしますし、地域や消費の動向に敏感になり、マネジメントに関してもより深い思考を持てるようになります。実際、学生が現場から戻ってくるときはいつも成長していることを感じます」。
この夏、11人の学生たちはさらにフィールドワークを重ねて、雲仙温泉の魅力を探り、マネジメントにどう繋げていくかを追求しています。ナガツナでは今後も3つのグループのマネジメント活動を追いかけますよ。お楽しみに!
長崎大学経済学部「ビジネス実践力育成プログラム」はこちら(Click)から。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
