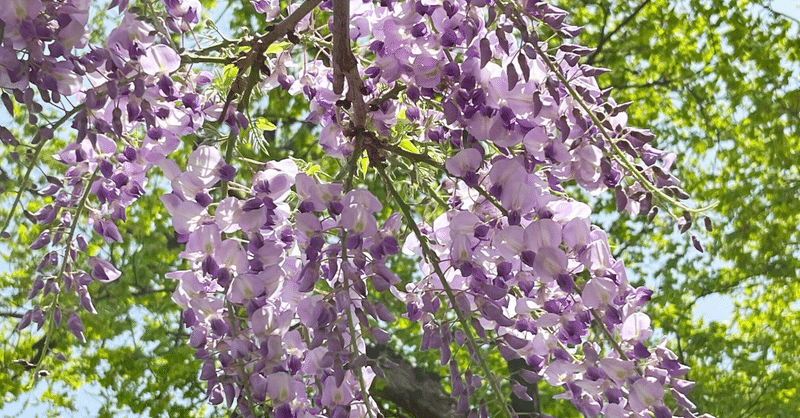
死角にピースが嵌り続ける物語 ~八咫烏シリーズ面白かった感想文。ネタバレなし~
社畜の休みというのは大変貴重なものである。
特にゴールデンウイークというのは新年度の疲れに対して程よい時期に位置しており、気候もすごしやすい、だというのに、今年の私はほぼ引きこもって文庫に齧りつき、その休みもあと一日という夜中にキーボードを叩いている。
それというのも、春クールアニメ「烏は主を選ばない」の原作小説「八咫烏シリーズ」の原作を今時点での最新刊「望月の烏」まで読破し、今の熱量じゃないと感想文なんて書けないと思ったからである。
(より正しく書くと、気持ちが焦るあまり、主~はコミカライズ未収録部分だけを読んで後回しにしてしまっているが)
参入ルート
コミカライズ版「烏に衣は似合わない」から。いつかわすれたが全話無料化公開か何かの折に読んだのが一番最初だった。
今回のアニメ化に合わせて衣と主のコミックスを買い、主~のコミックスあとがきに書かれた松崎先生の力強い「原作読め」に惹かれて小説へ。4日で完走して今に至る。
なお、思い切りが悪かったのでこの間に原作本を求めて何度も書店に足を運んだ。品切れしているところもあり一発で全部買えばよかったと大変後悔したものであるが、今来てる波に乗ってる実感があるのは大変良かった。
感想というか私の身に起こっていたことというか
こんなに夢中になって小説を読んだのはいつぶりだろう。
まだそんな感性や体力が自分に残っていたのかと驚いた。
ここまで巻を重ねたシリーズに途中参入したことがそもそもなかったかもしれない。
社会人になってからは間違いなく初めてのこと。
中学生のころにもあったけど、その時は財力が無かったからこうは行かなかった。
いや、もう圧倒的に面白かった。文字を読めて幸せだった。
筋を追うのに必死で読み飛ばしぎみになってしまっていたので、何れちゃんと読み返す。
八咫烏シリーズについての紹介については特設サイトを見ていただきつつ
https://books.bunshun.jp/sp/karasu
至極簡単に言うと、平安っぽいファンタジー世界「山内」を舞台に、
そこに住まう八咫烏(コミカライズ版では「にんげん」とルビを振る)たちにもたらされる
様々な事件や陰謀や、あれやこれやを描いた話である。
日本産ファンタジーとして切れば、その作りこまれ様は十二国記の系譜に位置付けていいのかなと思う。
実際、文庫版に寄せされた解説にもたびたび名前が挙がっていた。
私が感じたエンターテイメントとしての指向性はなんとなくワールドトリガーに近いと感じた。
シリーズを一気読みすると時系列で混乱するところが出てきてしまうものの、
情報の出し方や、また容赦ない展開にあたって確実な印象を残すための好感度コントロールに卓越したものがあるように思う。
阿部先生は、最新作を読んだから過去作を読み返したくなるような、とインタビュー等で語られているが
まさしくそのような構成になっていて、小説とコミックスの読み比べもまた楽しい。
この記事のタイトルにしたように自分の死角になっていたところにピッタリとピースが嵌って脳汁の出ること出ること。
こうやって作家先生の手のひらでコロコロされるのが大変好きだ。
そういう伏線パズル的なおもしろさもさることながら、しっかり情感でも揺さぶられる。
ピクシブ百科事典で「読む=自傷行為」と書かれているのにはゲラゲラ笑ったが、
それを読むちょっと前には「楽園の烏」でふらふらになり、外伝「烏百科 白百合の章」のある短編で号泣していた。
心おぎなく夢中になれる長期休暇中で良かった。
私は本当に待てができない性質なので、昼休みに職場の自席で読んで号泣する事態にならなくてよかった。まじで。
作品の魅力を全然伝えられていないけれど、何を言っても野暮なきがするので、
もう皆さんもこれ読んで脳汁と情感の血液でべちゃべちゃになろう……。
ここからネタバレっぽい話あるので未読の人は折り返してください。
蛇足というか、所感というかメモというか。
楽園の烏にて、ある人物がある人物を評した「必要性の奴隷」という言葉。
これが気に入っているというか気になっているというか。
こういう合理を突き詰めるタイプのキャラクター造形(ワールドトリガーの修とか)って結構最近(2000年以降?)のもので、タイパ時代にそぐった類型なのでは、と思ったけど他のサンプルがわからんくて語れない。
私がそういうキャラの出る作風が好みというのは間違いなくある。
ただ、映像作品だとこういう作風は難しいように感じていて、小説や漫画のような媒体で活きるのだろうなとは思う。
他の方の感想等も読んでいると「忠義」を大テーマ?中心的にとらえていらっしゃる方が多いようにお見受けするのだけれど、私はちょっと違和感がある。重大なキーワードではあると思うのだけど、現代的な感覚ではないなと思っていて、それを阿部先生がそれを大テーマに置くのだろうかと。なんとなくそうはなさらないのじゃないかという気がする。
価値判断を誰か/何かに委ねることの是非とか、そういう言い換えならしっくりくるので、単に言葉使いから来てる感覚なのかもしれないが……。
ただ、そうすると「玉依姫」のあるキャラクターも、誰にも忠義を捧げていないけれど、同じ枠で語れるような気がするし、奈月彦自身は忠義の何たるかに対してそう思うところがないように感じるのもあって、大テーマかと言われるとそうではない気がしてる。私はシリーズを貫くテーマは「継承」ではないのかなぁ、なんてぼんやり考えている。印象だけで話してるので、読み返さないと根拠が弱いかも。読み返したら考え変わるかも。
そもそもテーマって何かよくわからなくなってきた。
ハリポタとかもそうですけど、いわゆる「親世代」っていうのは、良き時として眼差される印象があるのだけど、第一部から見た親世代が毒の沼なのがちょっと新鮮、と書きながら、第二部時代からみたら第一部がそうなっているのかと思ったり。
こういう時にちゃんと?分析や批評っぽいことができたら楽しいのかなぁと思ったりしました。
ちょっと気になって花言葉ぐぐってみた。
あせび:「犠牲」「献身」「清純な心」「あなたと二人で旅をしましょう」
浜木綿:「どこか遠くへ」「汚れがない」「あなたを信じます」
薄:「活力」「生命力」「精力」「なびく心」「憂い」「心が通じる」「悔いのない青春」「隠退(いんたい)」
藤:「優しさ」「歓迎」「恋に酔う」「忠実な」「決して離れない」
紫苑 :「あなたを忘れない」「遠くにある人を想う」「追憶」
こう並べてしまうと意図がある気がしてくるので、読み返す時には気にしてみよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
