
佐藤可士和さんのクリエイティブシンキングに迫る Part2
こんにちは、グリチキです!
前回の続きで今回はPart2となります。
クリエイティブシンキングを身につけるために具体的に何を意識すればよいのか。
前回の記事はこちらから。
◯ クリエイティブマインドをつくる
「前提が違うから難しい」「常識的に考えて無理」
一度は聞いたことあるかと思います。
物事を考える時に前提や常識に囚われていないでしょうか。
前提や常識の範囲内でのみ考えるのであれば、そこから新しい発想や考えは生まれてきません。
様々な角度で検証してみることが新たな発見に近づくと思います。
円錐を例に例えると、
底を正面に見れば「円」に横から見れば「三角形」に見えます。
見る角度によって同じものでも全く違うものに見えてくることが分かると思います。

注意してほしいのは必ずしも前提や常識を「否定」することではなく、検証してみることが大事ですね。
他の見方ができないか、そもそもなぜこの前提なのかを最初から考え直してみるのも新しい発見がありそうですね。
佐藤可士和さんも著書で以下のように話されています。
その前提が正しいかどうかを検証しないまま見過ごしているのが、一番良くないということです。
まずは常識と言われている事柄に疑問を抱き、冷静沈着な目でさまざまな角度から観察し、検証してみることが、創造的思考、すなわちクリエイティブシンキングの原点になると思います。
◯ 比喩することで本質が伝わる
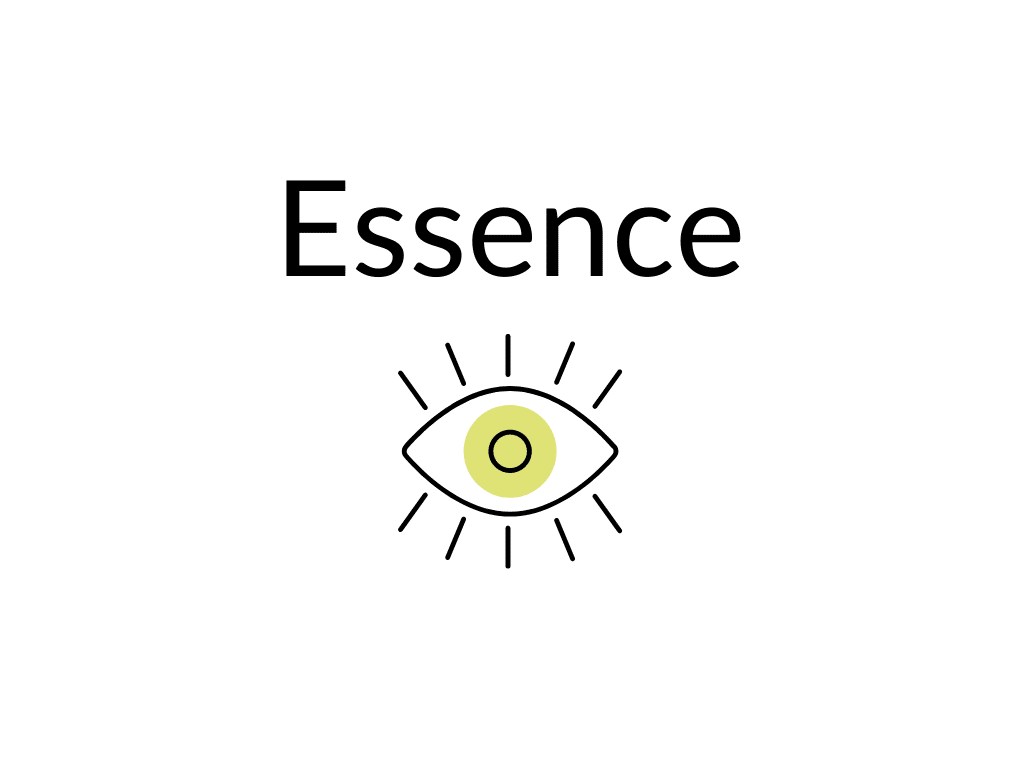
物事を相手に伝えたい時にどんな工夫をしますか。
伝える相手がいる場合には、一番相手が分かるように伝えることが大事だと思います。
日本の伝統表現の一つに「見立て」があります。
分かりやすい例だと、人やイメージを花で表現する生花、落語の世界で扇子や手拭いを使って蕎麦を食べてるシーンや手紙を書く描写を表現することです。

見立ては対象の別なものに例えることで、本来ある対象の姿、本質を表現することで既存の価値を明確にしたり、新たな価値を見出したりします。
実はみなさんも普段の生活で「見立て」をしているはずです。
コミュニケーションを取るときに「あれって〇〇ってこと」「〇〇のようなこと」のように対象を共通認識として分かるものに置き換えているのがまさにそうです。
佐藤可士和さん自身も仕事の話をするときにアートディレクターの仕事を、こう例えて伝えるそうです。
クライアントの課題をカウンセリングを通して見つけ出し、それに対する処方をデザインという手法で行う、いわばコミュニケーションのドクターのような仕事です。
引用:佐藤可士和のクリエイティブシンキング
相手との認識がずれてままでは、プラベートも仕事もうまくいきませんね。
逆に相手が分からないことでもお互いに理解できるように例えながら話せる人は人間関係がうまく構築できる人ではないかと思います。
◯ さいごに
いかがでしたでしょうか。
テーマでクリエイティブシンキングなので、難しそうだなと感じたのが最初のイメージです。
本を読んでいくうちに、デザインだけに関係することではなく、物事の本質をみることはどんなことにも共通して大切なことだと感じました。
日常の物事を「見立てる」ことからスタートさせて、自分のビジネス、人生に役立てていきます。
それではまた!
グリチキ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
