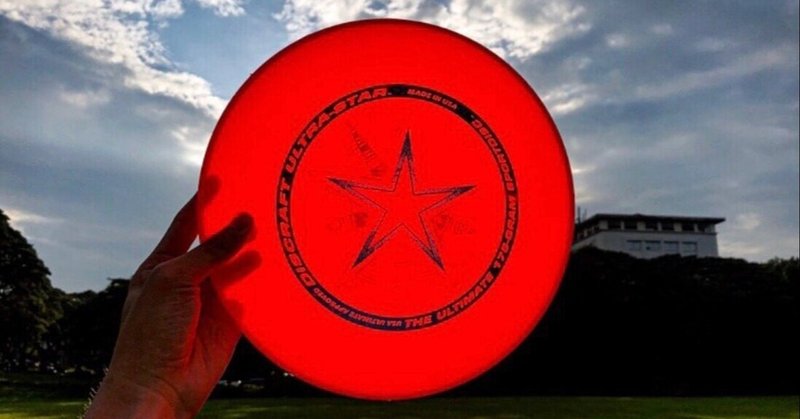
#2 フィリピン大学 留学日記 vol.2 (2019/08-09)
フィリピン生活5週間目(2019.08.25〜2019.09.02)
今週もたくさんの出逢いがありました。
様々なビジョン・目的観を持った方々と交流する中で、やはり明確な目的を持つことがその人の日常の行動を大きく変えるなと感じました。
MACの法則をご存知でしょうか?
キャリアの授業や本を通してご存知の方も多いとは思いますが、私は1年生の頃からこの法則を非常に大切にしてきました。MACとは、Measurable(測定可能性)、Actionable(行動可能性)、Competent(適格性)のイニシャルを取ったもので、海外大学の研究チームが分析したものになります。
一言で表現するならば、
「目標設定は、数字で明確に測定でき、達成までのプロセス(行動)が明確化され、自分の価値観やキャリアに適格であるべき」ということです。
恥ずかしながら、私は大学1年生の時に「2年生でTOEIC730点突破、IPを最後までやりきって、TOEFL-iBT80点取得してフィリピン大学交換留学合格。」という当時の私にはあまりにも無謀な目標を立てました。
しかし、結果的に概ね目標は達成しました(TOEFL-iBTは途中で諦めましたが...笑) それには色々な背景がありますが、達成できた一つの理由は目標がMACの法則に従っていたことが挙げられるでしょう。
さらにもう一つ言えることは、目標を色んな人(家族や友達、先生)に公にしていたことも大きいです。他人に目標を共有することで、有言実行率を高める事が出来た気がします。
ここまで読んでくれる人がいたら、本当にありがたいなと思います。最後に学業に関する自分の留学の目標を“公に“したいと思います。
① 20単位以上(留学先換算)取得
② 留学中にTOEIC920点以上取得
③ 10冊以上を精読して教養を身につける
この目標は変わるかもしれないけど、常に考え続けていく留学生活にします。

フィリピン生活6週間目(2019.09.02〜2019.09.09)
今日で留学生活44日目。早くも6週間が過ぎてしまいました。今週はフリスビーをやったり、一人旅をしてみたりと新しいことがたくさんあり、少しずつフィリピンでの行動範囲を広げていっています。
週に一度、こうやって自分の感じたことや思ったことを自己満足で投稿しているわけですが、毎週続けている事で気づいたことがあります。
「感受性が豊かだから、感想を書けるようになる」
のではなくて
「感想を絞り出すことで、感受性が豊かになる」
ということです。
つまり因果関係が間違っていたわけです。
私が苦手なことの一つに「感想を書く」があります。小学生の頃から感想文的なものを書くのが得意でなくて、いつも物事を羅列して、薄っぺらい文章を書いていました。それは中学、高校、大学に入っても変わらなかったですが、この留学を通して様々な感情や感想をアウトプットするようになり、少しずつ感受性が豊かになった気がしています。(気のせいかもしれないけど、そう思うことが大切)
私は先輩のアドバイス通り、毎日日記を書いているわけですが、その日に何があって、何をして、どう思ったかを文字に起こすことで、自分がどういう時にどういう感情を抱くかという自己分析・自己理解に繋がります。
科学的に見ても「ネガティブ感情を“可視化”することで、冷静に現状を考えられる」という心理学の研究もあります。自己を客観視することによって、冷静かつ的確に自分を知ることが出来ます。
留学に行っている人の中には、なかなか上手くいかなくて辛い思いをしている人もたくさんいるはずです。そんな人はぜひ自分のその感情自体を紙に書き連ねて、なぜこの感情が湧き出てくるのかを分析してみてください。
そしてもし今、日記を書いている人がいれば、出来事を羅列するだけではなく、その時に抱いた感情や無意識的な行動なども記述しておくと、より有意義な日記になると思います。ここまで読んでくれて本当にありがとう。Thank you so much, maraming salamat po.

フィリピン生活7週間目(2019.09.09〜2019.09.16)
フィリピン大学での生活も7週間が経ち、正直言って少しマンネリ化してきた節があります、新しいこと取り組んでいかないと。
最近思うこととしては「世の中、知らないと損する」という事です。学問とビジネスの観点で述べていこうと思います。先に言っておきますが、完全なる自己満足です。
まず第一に学術的観点から言うと、自分の意見として「学問が面白くないのは、自分の責任」だと思ってます。例えば、大学1年生の頃は経済学が面白いとはあまり思いませんでした、それはなぜかと言うと圧倒的に知識が足りなかったからです。経済学に加えて、英語・歴史・統計学・心理学(behavior economics)を少しずつ勉強していった結果、初めて経済学が理解できるようになってきました。
学問が面白いと感じるのは、自分の中に落とし込んで、点と点を結びつけられた時なんじゃないかなと思います。国際連合研究会で経済学や歴史の知識が結びつけられた時は、モチベーションが向上しました。
第二にビジネスの観点から言うと、行動経済学とWEBマーケティングをほんの少しだけ勉強しただけでも、人間の心理を巧みに操った企業戦略が見えてきます。例えば、プロスペクト理論(参照点効果:損得を感じる強さは、元の基準からどのくらい離れているか・正か負かによって決まる)はネットショッピングなどでも良く使われている戦略です。
経済学にも情報の非対称性という情報構造があります。これは理論上、双方で情報の共有ができていないと、市場の失敗を招いて、パレート効率的でなくなる結果を生むというものですが、凄く共感します。情報の格差が生まれている市場では、生産者が有利になり不公平な結果になることもあります。
そして結局、何が言いたいのかというと勉強しないと人生は不利だなと思うわけです。私の好きなユダヤ人の言葉に「知識は奪われない」とあり、知識だけは身体の一部となって奪われる事はないという教えです。やはり、教育の機会はある程度平等であるべきだと思いますし、学校だけでなく読書や課外活動の機会も出来る限り平等であるべきです。
我が大学の創立者が「大学は大学に行けなかった人のためにある」と言われたように、決してお金儲けのためにこの知識や大学で学んだ事を使うのではなく、そこからメタ知識を生み出し、様々な分野から世界平和に貢献する。それが大学生の役割なんじゃないかなーと思った深夜23時45分(フィリピン時間)。

フィリピン生活8週間目(2019.09.16〜2019.09.23)
もうすぐ2ヶ月経つのですが、やはり留学というのはすごく大変で、優秀な学生に劣等感を感じたり、思い通りいかなくて辛い思いをすることも毎日のようにあります。
そんな中、個人的な意見として、自尊心をコントロールすることで、より満足度の高い人生を送れるんじゃないかなーと思うわけです。
まず、自尊心が高い方が基本的に幸福度は高いと思います。ですが、自尊心が低いからといって悪いわけではないです。寧ろそれを利用して、頑張る原動力に変えることが出来れば大きな長所になると思います。私自身、自尊心が高くなるときと低くなるときがあるのですが、上手くコントロール出来る様に心掛けています。
自尊心が高いことのメリットは、何か上手くいかなくても必要以上に自分を責めずに楽観的に捉えられることでしょう。また、自分に自信を持つことは大事で、時には自分のやっていることに誇りを持ち、心酔するぐらいでも良いと思います。
自尊心が低いならば、今の自分ではダメだから変わらないといけないと思えることが最大のメリットです。とある実業家が「自尊心は捨てろ、過去に執着しろ、深く後悔して、反省して、死ぬほど勉強しろ、そうすれば夢は叶う(要約文)」と言っていました。(極端ですが)自分を必要以上に責めすぎて病んでしまう場合もあります。でも自尊心が低いことを原動力に変えることが出来れば、大きく成長できるチャンスに変わるわけです。
どんな人も常に楽観的に捉えられるわけではないと思います。むしろ大きな成功を掴むような人は、自尊心が低くて、自分を変えたくて、死ぬほど努力して、大きな夢を叶えたんだと思います。
私よりも遥かに優秀な人たちに囲まれながら、いまフィリピン留学をしていますが、残り約8ヶ月間も、時には自分を尊敬して大好きになって、時には自分を叱咤して反省できるように人間的な成長をしていきたいと思います。なんか悟り開いたみたいになった🙄
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
