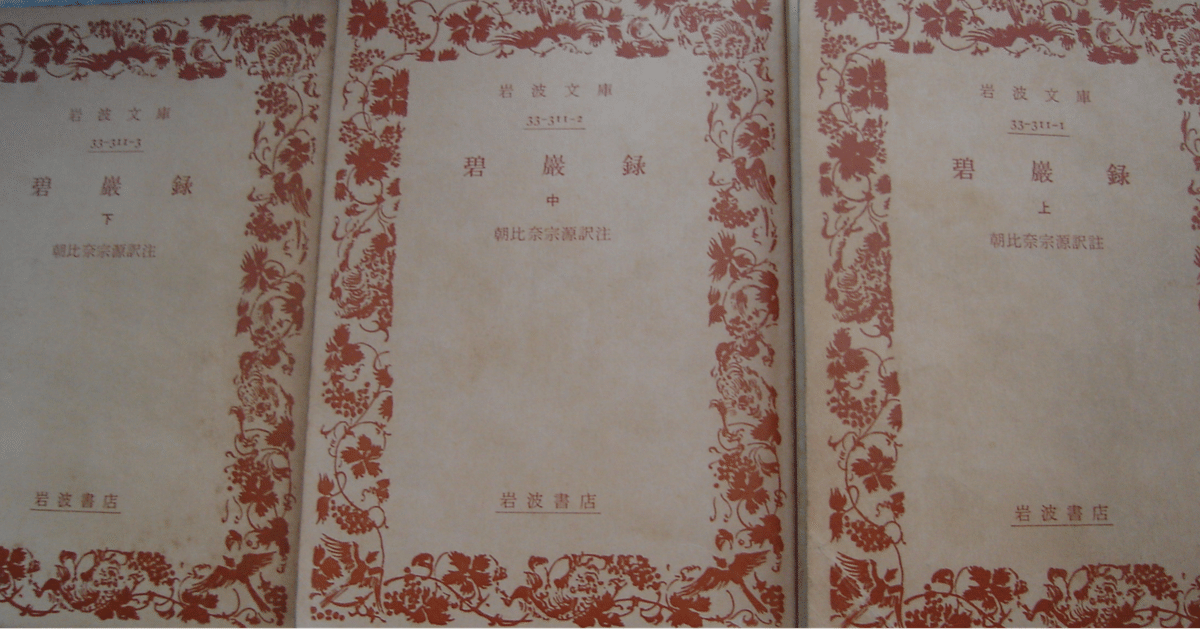
『碧巌録』第一則「達磨廓然無聖」
『碧巌録』の構成は垂示、本則、頌、著語、評唱の五つから成っており、雪竇重顕が本則と頌、その後圜悟克勤が垂示と著語と評唱を追加したものである。
その全部を現代語に翻訳するととても長いので、したがって垂示、本則、頌を中心に著語と評唱の解説を補足してゆくことになる。
まず初めに「達磨廓然無聖」の「廓」とは心が晴れわたり、わだかまりのない意味であり、禅では「廓然無聖」とは真理は聖人と凡夫を区別せず平等に働く能力であるとする。
具体的には千里眼は動物はもちろん人間には誰しも備わっている本能的な働きという。
ただそれには言語的に考えてはその能力は発揮されず、自己の目的を達成する為に考えず、即座に行動することである。
このことに就いては西田幾多郎が「行為的直観」で詳しく説明しているので解説する。
西田幾多郎は日本を代表する哲学者であり禅学者の鈴木大拙に進められて禅の修行も行われたと言われている。
『碧巌録』第一則のテーマは西田幾多郎の「行為的直観」の具体的な実例と考えてよい。
その「行為的直観」を解りよい用語で言えば千里眼という事になる。
それには達磨大師の先見の目という能力、千里眼があったことであるが、視覚的、具体的な表像認識ではなく見えない因果関係を理解していたという事である。
千里と言うと空間的な距離、遠方という意味から未来や人の心を見抜くという意味になるが、時空を超えた歴史的社会的な要因に対する適切な反応といえる。
「廓然無聖」とはまさに心に疑念や執着、偏見などが少しも無く広広としていて見通しが良いという意味である。
「直観」と言えば思考的感覚的ヒラメキと考えられることが多いのであるが、「行為的直観」とは意識にのぼらず行為として反応することであり、行為の後に閃くことでもない。
直観即行為という意味であり西田幾多郎は「行為的直観」において「行為的直観的に物を把握することである」とか「身体的に物を把握することは種的には働くことである」表現している。
したがって千里眼といっても視覚的言語的意識的に物が観えると言う意味ではないことは明らかであり、瞬間的に行動的に反応することであり、間髪を置かずに行うことである。
ここが大切なところであるが個人的な思考を挟まず即行動的に反応することが「行為的直観」と言うことである。
『碧巌録』第一則に達磨大師がとりあげられているのには理由があり、現代の禅に決定的な役割を果たしていたということでる。
垂示に云く。
山を隔てて煙を見て、早くこれ火なることをしり、
牆を隔てて角を見て、便ち是れ牛なることを知る。
挙一明三、目機銖兩は、是れ衲家の尋常の茶飯。
衆流を截断するに至っては、東涌西沒、逆順縱横、与奪自在なり。
正當恁麼の時、且く道へ、是れ什麼人の行履の處ぞ。
雪竇の葛藤を看取よ。
解説
垂示とは本則を読む上での要点であり、どのようなことに気を付けて読めば良いかと言うことである。
本則にはいろんな人物が登場するが、僅かな挙動、言葉からその相手の本心を読み解くということである。
「山を隔てて煙を見て、早くこれ火なることをしり」とは結果からその原因、動機を知ることである。
また言動の一部分を見て全体を知ることを「牆を隔てて角を見て、便ち是れ牛なることを知る。」と言う。
さらに同じ言葉であってもその場面の僅かな違いから意味を判別することを「目機銖兩」と言う。
このような作法は禅家にとっては朝飯前であり、修行者の思考を彼方かと思えば此方に向け、与奪自在に誘導して問題意識を育てることを公案と言う。
また善悪、有無、損得などの世間一般の常識を切断して自由自在に生きる人はどのような人であろうかと問うている。
もちろん、その人とは第一則では本則に登場する達磨大師に違いありません。
本則
擧す。梁の武帝、達磨大師に問う、
如何なるか是れ聖諦第一義。
磨云く、廓然無聖。
帝云く、朕に對する者は誰ぞ。
磨云く、識らず。
帝契わず。
達磨遂に江を渡って魏に至る。
帝、後に擧して志公に問う。
志公云く、陛下還た此の人を識るや否や。
帝云く、識らず。
志公云く、此れは是れ觀音大士、佛心印を傳う。
帝悔いて遂に使いを遣わし去きて請ぜんとす。
志公云く、陛下、使いを發し去きて取えしめんとするは莫道、闔國の人去くも、佗は亦た回らず。
本則解説
『碧巌録』第一則「達磨廓然無聖」は中国禅の開祖といわれる達磨大師の中国における決断と行動の第一歩の状況を語るものである。
この決断と行動が今の中国や日本の禅宗の歴史を決定したと言ってもよいのである。
達磨大師が中国に禅を伝導するために万全の調査と準備をしてきたことは梁の武帝を訪ねたことでわかる。
梁の武帝である皇帝蕭衍が仏教の信者であり、寺を建て修行僧を育てていたことを知ったからである。
当時のインドから梁(今の中国)までの旅は現代とは比べるまでもなく危険で困難であった。
この時代には既に三蔵法師など多くの仏教伝道者がいたが、道中で命を落とす者もいたのであった。
海路で来たという説もあれば、陸路という話もありますが、いずれにしても無謀と言ってよい困難と大変危険な旅でした。
達磨大師はインドの香至国の第三王子だと言われていますが、何故はるばる梁まできたかという理由である。
その理由は解りませんが大きな希望があったことに違いないでしょう。
達磨大師の意志と言った個人的な意思ではなく禅の意志と言った大きな意志が働いていたと言いいたいのは、
達磨大師が梁の武帝に接したときには既に自己を捨てていたからである。
自己の意志であれば、あなたは誰だと問われた時に「知らず」と言わず「識らず」と答えたからである。
達磨大師の心には善悪、損得、成功失敗などの二元思考は消え失せていたのである。
自己を捨てた時に梁の武帝の問いから未来の武帝の運命が「行為的直観的」に伝わってくると考えられるのである。
梁の武帝の運命と共にすれば禅の運命は無かったと言ってもよいでしょう。
危険に対して無謀といえる大胆な行動を行う達磨大師ですが、
安心安全に対しても完璧な注意が働いているのである。
人生の未来は日々の行動の選択によって決まるから、安易な妥協はゆるされないのである。
梁の武帝の信心は話には聞いていたのでしょうが、この目で見る迄は安心できなかったのである。
『碧巌録』大森曹玄著によれば梁の武帝は二、三十年後に反逆に会い亡くなったと言われている。
達磨大師には梁の武帝の未来が見えるわけではないが、自己を捨てて悟りを捨てた時自ずから選択の道が見えてくるのである。
大胆な行動も細心の注意も自らの計らいを捨てた時、禅の働きが決定すると言ってよいである。
意思決定には科学的な思考も必要であるが、科学的な思考では未来の全てを考えることは不可能である。
ましてや人間が瞬時に梁の武帝の未来が解るわけ無く決断の結果から見れば正しいものでした。
だから達磨大師自身も決断の理由は言葉では説明できないのである。
ただ梁の武帝に会うと瞬時に武帝のすべてを見抜いていたのであった。
公案には『無門関』、『臨済録』がありますが『碧巌録』まず最初に書かれたといわれておりますが、
梁の武帝と達磨大師の対話は禅問答と言うような形式や習慣の完成する以前の話である。
禅問答とか公案と聞くと難しいとか、わけのわからない話と思うかも知れませんが、梁の武帝や達磨大師になりきって見れば、その言葉のいみが解るでしょう。
禅では頭で考えてはいけないとか、言葉で理解してはいけないと言いますが、登場する人物の身になってみれば普通の会話と少しも違いないことに気が付くはずである。
梁の武帝にしてみれば達磨大師は名前も素性もわからない髭を生やした普通の人であるから、仏法について問いかけることは当然と言えば当然の成行きに違いなかったのである。
それに対して達磨大師は「廓然無聖」(心に疑念や執着、偏見などが少しも無く広広としていることだ)と答えたのであった。
それは達磨大師にとっては心に浮かんだままの正直な返事に違いなかったのであるが、梁の武帝には理解できなかったのである。
当時としては無名の達磨であった、仏法の徳の何であるかも知らないと思われた、達磨に対して君は何者だと聞くの当然であった。
そこで禅の真理と徳を詳しく説き立場を説明するのが常識ではあるが、達磨大師は「識らず」答えたのであった。
何故なら禅の真髄は言葉でもって言いつくすことはできないからばかりでは無く、自己を捨てていたのは単純な事実であることを知らねばなりません。
梁の武帝が君は何者だと言った意味は氏名ではなく、組織における立場や役職、位を問うているのである。
宗教であれば仏教とかヒンズー教、キリスト教などの組織内における位を聞いているのであるけれども達磨大師はもはやいかなる宗教組織にも属していなかったも同然であった。
達磨大師が「識らず」といったのは、この時点では裸一貫、名無しで無職であるから正直な返答であったのである。
仏教には原因と結果の関係を因果応報と言いこれを三世にまでひろげた過去生や現在生、未来生という考え方がある。
また「過去の因を知らんと欲すれば、現在の果を見よ、未来の果を知らんと欲すれば、現在の因を見よ」と『因果経』にある。
この真理から考えれば達磨大師の梁の武帝との会話と決断がそれ以降の中国禅の発展の原因であり、まさに「現在の果」から「過去の因を知」ることが出来るのである。
もちろん、「識らず」と言ったその一言それだけが原因ではなく達磨大師のそれ以前以後の言動の全てが原因であることに違いないのであった。
その後の達磨大師の面壁9年も同じ原因であることは明らかであった。
また意識的で有る無しに関わらずその協力者、非協力者の存在は縁として働いていたことになる。
ただ当時の達磨大師にすれば未来の日本の禅文化がこのように成っているとは知る由もないことは当然である。
そのことを「因は果を知らず、果は因を知らず」と言うのである。
因果律と意味が正反対の「因は果を知らず、果は因を知らず」と言う『華厳経』の言葉は、対立矛盾する考えかたであろうか。
否、決して矛盾ではないのであって我々が知らないだけである。
時間は過去から現在、現在から未来へと推移しているように考えるが、未来は即現在であり、過去は過ぎ去りしものではなく因果的に考えれば即現在なのである。
達磨大師は今も生きて我々に親しく向かい合って優しく教えを広めているのである。
その意味で当時の達磨大師の決断が原因として働き結果として今の禅が存在しているのである。
それでは何故「識らず」と言って江を渡って魏に至り、更に少林寺に留まって「面壁九年」の間に二祖慧可に出会えた事が現在の禅宗の存在の原因であるのかと疑問に思うのであるが、
当時の達磨大師の言動と実行の選択があって現在の日本の禅宗が存在していることは疑うことは出来ないのである。
頌
聖諦廓然 何ぞ当に的を弁ずべき
朕に対する者は誰ぞ還って言う不識と
これに因りて暗に江を渡る
豈に荊棘を生ずることを免れんや
闔国の人 追うとも再来せず
千古万古 空しく相憶う
相憶うことを休めよ
清風匝地 何の極りかあらん
師、左右を顧視して云く、「這裏に祖師ありや?」
自ら云く、「有り。喚び来たりて老僧がために洗脚せしめん」。
頌の解説
「聖諦廓然 何ぞ当に的を弁ずべき」とは、
心は清風のように一点の曇りや矛盾もなく隠すことも無く晴れ渡っているのに、何故君は誰だと疑う必要があるのかと雪竇言は言うのである。
達磨大師を疑うことは会話の目的から遠く離れて行くと言う意味を「豈に荊棘を生ずることを免れんや」と雪竇は忠告するのである。
誠意をもって対応した達磨大師を疑うような人は信用出来ないと「これに因りて暗に江を渡」って行った。
ただ達磨大師は考えた上での判断や行動では無かったのである。
評唱で圜悟は達磨大師が廓然無聖と言った時の返答は「石火の如く」「閃電光」のような素早い言葉であったことが、善悪、損得、成功失敗などの言語的、二元思考で無かった事の証拠と考えているのである。
禅においては返答に一時の時間をかけても言語的思考とみなすのである。
同じく評唱で圜悟は達磨大師が梁の武帝の「大乗の根器有るを観て」梁の武帝を訪ねたのであった。
この行為、判断は伝導の成功失敗を意識的に考えたものに間違いないのであるが、梁の武帝と会った瞬間には努力が報われることを求めていなかったことは「無功徳」と言ったことで解るのである。
圜悟が「相憶うことを休めよ」とは性急に成功することを期待して交渉せず、無心になって相手の本性を見極めよと忠告しているのである。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
参考文献
『碧巌録』朝比奈宗源訳注 上中下 岩波書店
『碧巌録』大森曹玄著 上巻 下巻 栢樹社
「行為的直観的」西田幾多郎 中央公論社
