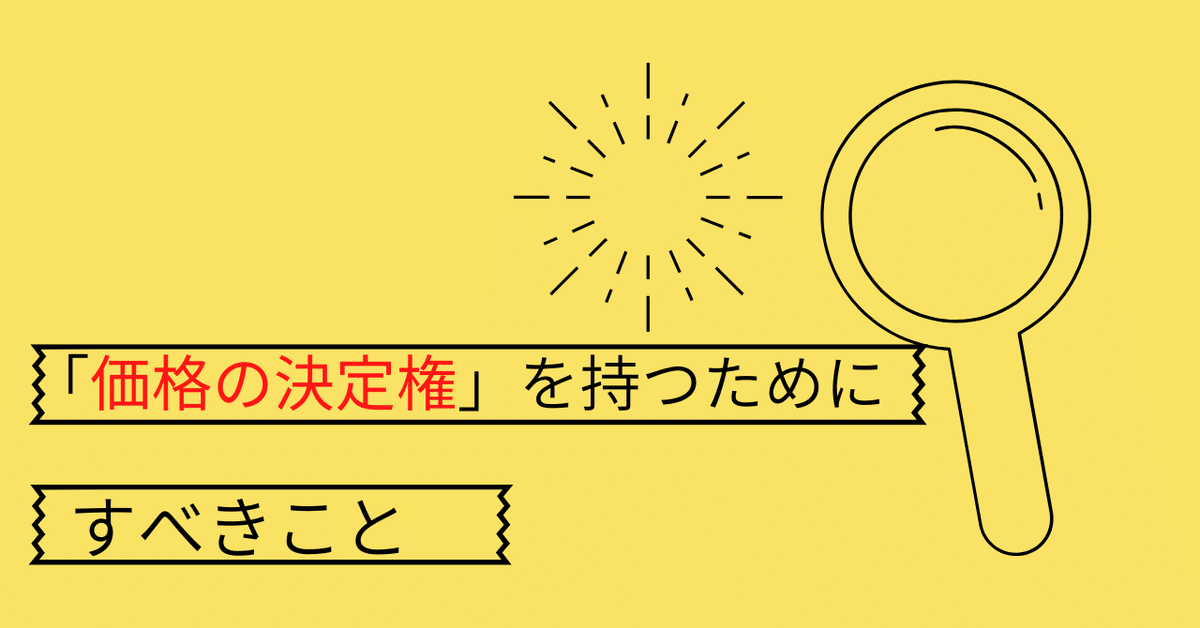
「価格の決定権」を持つためにすべきこと
どのようにすれば、 「価格の決定権を売り手側が持つ」ことが出来るのでしょうか?
価値・付加価値はお客様が決めるものですが、その価値・付加価値の値段、すなわち「販売価格」は売り手が決めるものです。
お客様側に価格の決定権を持たれてしまったら、高収益にはなりません。
お客様は「できるだけ安く買いたい」と思うからです。
価格の決定権を持てない営業の例を紹介しましょう。
同じようなことで当てはまっていないか考えてみてください。
<例>
ある工場用部品メーカーの営業Aさんが、自社で製造・販売している商品について、取引先からこう言われたそうです。
「御社では、この商品の販売価格を300万円と言っていますが、別の会社から同じような商品(模造品)を買ったら、たった10万円で買えるんですよ。だからもっと安くなりませんか?」
さてどうしましょうか・・・
実際、Aさんは、「どうしたらいいんでしょうか?」と困っていました。
そこで私はAさんに、「仮にその取引先が10万円の商品を買ったら、その会社はどうなりますか?」と尋ねてみました。
Aさんは「たぶんエラーが出たり、作業効率が悪くなったりするでしょうね」と言います。「具体的にどれくらいの悪影響が出そうですか?」と尋ねると、「ちょっとそれは考えたことないですね」と言うAさんに、私はストレートにこう言いました。
「それでは、取引先と価格交渉などできないですよ。お客様がその10万円の商品を購入・導入した場合に、お客様側に発生する損失金額をきちんと計算して相手に提示すべきです」
そしてAさんの代わりに、その損失金額を次のように計算してみました。
例えば、
・取引先の工場では現在、「1日に約100個」の製品を製造しているが、模造品を使うと「1日に約95個」しか作れなくなる
・ということは、生産性は現在の「5%」落ちてしまう計算になる
・取引先の工場の1日あたりの生産金額は「約1億円」である
・したがって、「1日に約500万円」の損失が発生することになる
・ということは、1か月で1.5億円の損失が発生する
この数字を示して、私はAさんに「御社の300万円の商品の代わりに、10万円の商品を導入したら、月に億単位の金額が飛ぶんですよ。そう考えると、購入費290万円の差は、取引先にとって大した問題ではないはずです。その事実をはっきりとお客様に主張すべきです」と伝えました。
この事例の問題点はどこにあるかというと、Aさんは取引先に生じる損失金額を提示できていないがために価格交渉ができない、つまり「価格の決定のための情報」を持てていないという点です。
価格交渉において営業がしなければいけないのは、自社商品を買うことによって、「お客様にどれだけの利益が生まれるか」を提示することだけでありません。
自社商品を買わないこと(他社商品を買うこと)で、「お客様にどれだけ損失が出るのか」を相手に示すことも重要です。その場合、「具体的な数字を示す」「図にする」などして具体的に説明することがポイントです。
さて、ここまで書いてきましたがどうでしたでしょうか?当てはまっていませんでしたか?
お客様の損失などわからない!と思うかもしれませんが、お客様の成功を考え、真剣に向き合っていれば、相手のビジネスモデルを理解することも、儲けの仕組みを理解することもできます。
(これもマーケットイン!知れば知るほどおもしろい!)
儲けの仕組みが理解できれば、もちろん損失の計算もできるようになります。
そうすることで価格の決定権を売り手が持つ一手が手に入ります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
