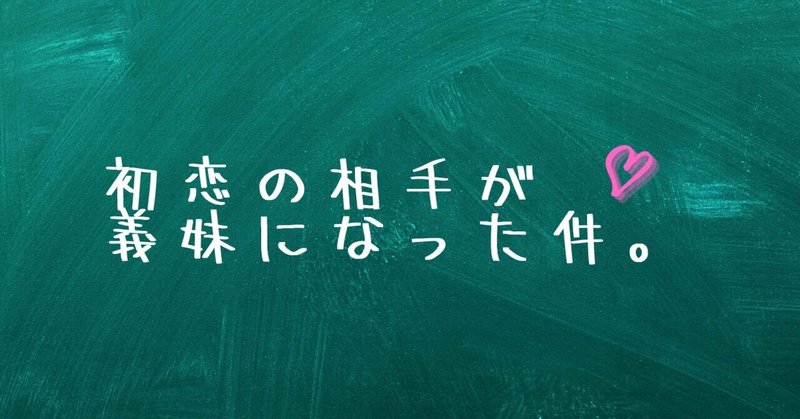
初恋の相手が義妹になった件。第22話
夕飯を終えて風呂に入ると僕は疲れのせいかすぐに眠たくなり、ベッドに入った。
少し早めに起きると、気だるい体を醒ます為に熱いお湯で顔を洗った。
「おはよう。昨日は早かったのね」
「うん。疲れてたから」
母にそう挨拶をして僕はテーブルに座った。
「お弁当置いとくわね。今日お母さん早いから、先に出るわ」
「いつもありがとう。いってらっしゃい」
母は月曜日恒例の全体会議の準備の為にいつもより早く出社しなければならず、普段より1時間早く家を出た。
それより遅く、百花が降りてくると、欠伸をしながら洗面所へと向かった。
「お母さん、今日早い日だったんだね」
「うん、さっき出たよ。百花、それより……」
僕らはおはようのキスをした。実はこれは最近のルーティンになっている。
そして朝食を食べ終え、食器を洗い、僕らは学校へ向かった。
「おはよう」
学校に着くや否や、昇降口で佐伯が待ち構えていた。
「おはよう……あの話本当だったんだ」
「嘘なわけないでしょ。実際、部屋に制服吊るしてあったの見なかった?」
佐伯の部屋を見渡した時にそれは確認していたが、それでもなお、信じられなかった。
「私は二組だから、それじゃあね」
そう言って佐伯は教室へ向かった。
僕らは靴を履き替えて、後を追うように階段を上って行った。
「暗に昼休みとかに会いに来いとかじゃないよな」
「……」
「百花?」
百花の様子が昨日の帰りから変だ。朝はそう感じなかったが、佐伯を前にすると、この様子になった。
「なんでもない……教室行こ」
教室では間宮やエレナと普通に会話をしていた為、僕は特に気に留めなかった。
そして昼休みに弁当を広げて食べていると、僕は扉から顔を出してこちらに視線を向けている存在に気づいた。
「あれ、二組の佐伯さん? 確か芸能人だよね。うちのクラスに何か用かな?」
エレナがそう言うと僕は立ち上がり、佐伯の元へと向かう。
「どうした?」
「悠人君、意外と馴染めてるのね。あなた、変わったわね」
少し、寂しげな目をして佐伯は僕を見遣った。
「変わったつもりはないけど……そう見えるなら、僕を変えたのは恐らく百花だな」
「ふうん……」
素っ気ない返事をしたと思うと、佐伯は僕の胸倉を掴んだ。
「私は、昔の悠人君が好きなんだけど。簡単に骨抜きにされるなんて……」
「流石は女優さん、凄んだ演技もお上手で」
「そう。もっとそういうトゲのある物言いをしなさい……以前のように」
佐伯が手を離すと、教室内の静まり返った空気に僕は気づく。
「ちょっと佐伯さん……この空気どうするの?」
僕は佐伯に問いかけるが、佐伯はそれを嘲笑し、僕の腕を掴む。
「それより、私一緒にお昼食べてくれる人探してるんだけど……」
「お生憎、悠人は私とお昼食べてるのよ」
百花は僕の腕を掴んでそう言うと、僕は両腕を引っ張られてまるで、二人の女子が取り合うような構図になっていることに気づいた。
「ちょっと……恥ずかしいからやめろよ」
昼ドラの男の取り合いのようなシーンを撮影しているような気分だ。
「困った義妹さんだこと……」
「義妹だろうが彼女だろうが、今私とお昼食べてるの。それをいきなり横取りする方が、行儀が悪いと思うけど」
「あら、じゃあ、あのこと、話してもいいのかしら?」
佐伯のその言葉を聞くと、百花は引き下がってしまった。
「物分かりのいい子は好きよ?」
百花は僕に言えないようなことを隠しているのか? 不安な気持ちが僕の心に靄を発生させる。
「……」
僕は黙って弁当を持って佐伯について行った。引き留めもしない百花を少し流し目で見送りながら。
「……佐伯さんい聞くことじゃないかもしれないけど、何か隠していることがあるのか? 昨日、二人で何か話してた時の事とか?」
「悠人君が気にする事じゃない。それから、私のことは侑香って呼んでくれない?」
「わかったよ。侑香」
「うん。そっちの方がいいわ、悠人」
さりげなく呼び捨てにされたことが一瞬引っかかったが、昼休みの屋上で僕らは二人きりになり昼食を取る。
「そう言えば昨日和泉のラーメン屋に行ったよ」
「へえ。あの子のお父さんのラーメン美味しいものね。私、最近は食事制限で行けてないけど、終わったら食べに行きたいわね。悠人と」
「僕と? もっと他に良い人いると思うけど」
「悠人じゃないと、嫌なの」
侑香はそう言うと、やけに色っぽくサンドイッチを食べる。
「だけどさ、百花いるし、一応彼女なわけだから、本当ならこれもダメなわけで……」
「恋愛は人間強度を下げてしまうの、強ち間違えではないかもしれないわね」
僕は残りのご飯をかき込む。蓋を閉めた弁当箱に、母のメモがあった。
「お母さんに愛されてるのね」
「愛情表現がオーバーな継母なんだよ。というか少し天然というか、お構いなしに抱き付いたりしてきたりする」
「へえ……それって悠人が好きなんじゃない? 私も、我慢してるけど、なんなら今すぐここでエッチしたいくらいなんだけど」
「学校では絶対ダメだろ……」
「じゃあ放課後、家来る? 親とか気にしなくていいし、ちゃんとコンドームもあるし」
「だから、行くわけないだろ」
僕は呆れながら侑香に言った。
「ほら、食べ終えたら教室に戻るぞ」
僕が立ち上がると侑香はズボンの裾を引っ張った。
「もっと一緒にいたい……百花ちゃんが羨ましい。一緒に暮らしていたらいつも一緒だもんね」
侑香は立ち上がると、僕の目を真っ直ぐ見た。
百花よりも楽に見れる高さにあるその綺麗な瞳に、僕は秘めたる所をまでを覗かれた気分だった。
「まあ、今は百花ちゃんのだから手を出さないでおくわ……」
「十分、手を出してると思うが?」
「行きましょっか」
僕らは各々の教室に戻った。
そして僕が教室に入ると、その中の空気がまるでナイフのように僕を切り付ける。冷ややかな目で見られながら僕は自分の席に向かう。
「最低……」
間宮が僕を見るなりそう言ったが、僕は無視をした。
僕の前に座る百花は僕に見向きもせず、振り返りもせずに俯いていた。
何も言わないことに少しだけ苛立った。百花は何かを隠しているのではないか? その疑念が常に僕に付き纏っている。どれだけ振り払っても寄ってくるハエのように、鬱陶しい感情だった。お陰で午後の授業は頭に入らなかった。
放課後になると、帰る方向が一緒だから連なって帰る。が、百花はぼくの少し前を歩き、僕はその影を踏んで進んでいた。
「悠人、先に帰るなんて、ひと声かけてくれたら良いのに」
侑香が走って追いかけて来たが、百花はそれを気にすることもなく、歩いたまんまだった。
「喧嘩中?」
その原因である侑香が僕に問うが、僕はそれを無視した。
「修学旅行の時以来ね、こうやって歩くの」
「ちょっと、歩き難いからやめろ」
柄にもなく、侑香は僕に抱き付いてくる。まるで百花に見せつけるように。だが、肝心の百花はこちらを見ることもなく歩いていた。
「……」
侑香は少し、つまらなさそうな顔をした。
「あっ」
侑香がその声を発してくれたお陰で僕は気づいた。
スタスタ前を歩く百花は信号にも目をくれず、赤信号の横断歩道に突入していた。
「ちょっと百花!」
僕は引きずるように、百花を抱き寄せた。
同時に車のクラクションがなり、僕は運転手に謝る。
「……私」
「大丈夫?」
「ごめん、侑香。先に帰ってくれないか?」
「え? どうして?」
「いいから!先に帰ってくれ。頼む」
侑香は僕と百花を見ると、浅いため息を吐いてから承諾し、青信号を渡って駅に向かった。
僕は百花を支えながら近くの公園へ向かった。
「……ごめん。僕がちゃんと断らなかったからこう言うことになってる。全部僕が悪い。本当にごめん」
僕は公園のベンチに座ってすぐ、百花に頭を下げた。
「そうじゃない。私は私を許せないだけ……」
僕はその言葉の本質を見抜けなかった。
「どう言う意味?」
「私、悠人に隠し事してる。とても大事なこと。正直、墓場まで持って行きたいくらいの秘密」
「……聞いてもいいか?」
僕はそう言うと、百花の隣に座った。
「私、嘘ついてた。男の人と付き合うの、実は初めてじゃないの。三年の春に他校の男子と一週間だけ付き合ったことがあって……でもそれ、向こうは完全に体目当てだったの。所謂、ヤリモクってやつ。それで……」
「処女じゃないって言いたいのか? 僕がそんな小さいことに拘ってるとでも?」
「違う!そこでは未遂だったの。私、怖くなってそいつ蹴飛ばして逃げたの。でも、後で気づいたんだけど、下着に血がついてて、処女じゃなくなっちゃったの……」
僕は手を額に当てて少し考えた。
だから何だ? 僕がそれを知ってどうこうなるとでも思ったのか? まず何でそれを侑香が知ってるんだ?
「私がするの怖がってる理由の一つなの。あの時のことがフラッシュバックして……」
「だから、一緒に風呂に入ったりして慣らしてたのか」
「……そう」
僕は大きなため息を吐いた。
「なあ百花、一つ言っておくけどさ、僕は君が初めてだろうがなかろうが、どうでもいい。経緯がどうであれ、それで君が穢れているだなんて思わないし、そんなの興味もない。そう思えるほど、僕は君が好きだ。この気持ち、舐められては困る」
「悠人……」
「君がそれを傷として一生背負っていくって言うなら、僕が半分持つ。だから、僕も君に打ち明けよう」
「え?」
百花はずっと伏せてた目を僕に向けた。
「君の知らない僕の話」
公園に小学生の団体が入ってきたのを見て、僕は「話は家でしよう」と言い立ち上がった。
帰宅すると、母はまだ帰っていないようで、僕らは制服のまま僕の部屋に入った。
「それで、悠人の秘密は?」
「実はファーストキスは侑香なんだ。修学旅行の夜、ばったり会って二人で少しコーヒー飲みながら話してたんだ。その時に、慣れない浴衣を引っ掛けてよろめいた侑香を助けた時の不可抗力で、唇を重ねたんだ」
百花はそれを聞いても同時ず、ずっと手を見つめていた。
「最初はお互い恥ずかしいって話してて、他言無用だとか言いあってて……でも気づいたらまたキスしてたりして……」
僕は百花の横顔を見つめた。
その視線が上がってくるのを期待して、僕はじっと見つめ続けた。
「ねえ悠人、しよっか。エッチ」
「本気で言ってるのか?」
「うん。私達、そうしないと前へ進めないと思う。昨日、佐伯さんに押し付けられたんだ。コンドーム」
百花は自室から昨日見たコンドームを持ってきた。
「……侑香らしいな。不器用なくせに器用なことをしたがる性格」
「多分本当に、私がいなかったら、悠人の隣には佐伯さんがいたんだろうね」
制服を脱いで下着姿になった百花はそう言ってから、僕に組み付く。
「でも、今は私がいる。その場所は私のだから、絶対譲らない」
「元気になってきたな」
「うん。つっかえてたのが無くなった感じ」
「さっき言いそびれたけどさ、百花が処女じゃなくても、僕らがするのは初めてに変わりないだろう? だからそれで良いんだと思う。それに、血が飛び散ったら面倒だし」
「悠人らしいね」
僕らはその後、母が帰ってくるまでベッドの上で思うがまま愛を確かめ合う。お互いの愛を肚裏で感じていた。
僕が動くたび、百花が淡い喘ぎ声を発する。それを何度も聞きたいがために、僕は動き続けた。
その様子はまるで獣のようだったろう。
「百花……」
お互い、消耗しきってベッドの上で仰向けになっていた。
「……怖かったけど、悠人だからできた。ありがとう、悠人」
「その何処の馬の骨かわからないやつのを、上書きしたと思えばいい」
「うん……これからはずっと悠人のものだよ」
僕らは新しい一歩を踏み出せた気がする。高校一年の初夏の夕方。僕らは一段飛ばしで大人の階段を登った。
玄関が開く音が聞こえて僕らは急いで服を着た。
散らかっているそれらを縛ってからティッシュで包んでゴミ箱に入れた。
「ただいま……」
母は僕らを見て何度か瞬きをする。そして、何かを察したように、笑みを浮かべると買い物袋を持って冷蔵庫前へと向かった。
「お母さん?」
「するならするってはっきり言いなさい。あずき買ってきてないわよ……」
「お赤飯?」
「どうしよう。利行さんにも報告したほうが良いかしら?」
「ちょ、ちょっと!別に言わなくていいでしょ!」
百花は母からスマホを取り上げる。
「そっか……二人も大人だねぇ」
「あはは……」
僕は愛想笑いをすると、百花を部屋に連れていった。
そしてとりあえず、終わってから話そうと思っていたことを話し始めた。
「百花……処女じゃないって話してたよね?」
「うん……」
僕のベッドのシーツについた血痕。それが全てを物語っていた。
「あ、確かに、あの日の翌日から、生理始まって……」
「気が動転して勘違いしてたのか……」
「あははー、そうだね……でも、痛くなかったよ? ちょっと押し広げられる感覚はあったけど、マッサージみたいに痛気持ちいいというか……ごめんなさい」
結局、お互いの本当の初めてを捧げられたことにとりあえず喜んだ。
「まあ何というか、佐伯さんには感謝だね」
「シーツ、どうしよう……鼻血が出たとでも言い訳するか」
僕らは抱き締め合った。百花は僕の首筋に吸い付いてマーキングをする。
「これで悠人は私の物だから」
しばらく、ベッドでゆっくりした後、一階へ降りると、まさかの赤飯が用意されていた。
「私に気を遣わなくていいからね」
「使うって……」
「なんなら私も混ぜてもらって……」
「お母さん!」
「冗談だってば……」
僕はずしっと訪れた疲労を感じながら、苦笑いを浮かべた。
よろしければサポートいただければやる気出ます。 もちろん戴いたサポートは活動などに使わせていただきます。 プレモル飲んだり……(嘘です)
