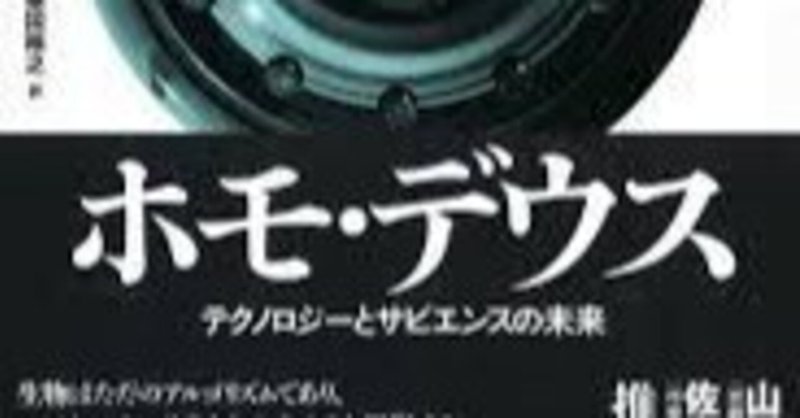
感想 ホモ・デウス下 ユヴァル・ノア・ハラリ 生物はアルゴリズムであり、生命はデータ処理である。

人類は力と引き換えに意味を放棄する取り決めをしたとある。
人類は力の追求をしてきた。
経済成長が多くの問題を解決してくれると信じている。
この世界にある資源は3つあり、原材料、エネルギー、知識だ。
無知の発見が科学の扉を開いたと言っている。
人類は、科学の発展と経済の発展を目指している。
しかし、それは地球をイジメていることになる。
成長が一番の価値であり、そのためなら何でもやる。
例えば、養豚。能力を強化した。工場のような犠牲的な飼い方。
しかし、価格を安価に押さえているので良いこととされている。
資本主義
力を得るために意味を失った説明として
狼はクレジットカードを使えないので殺しても良い
本当に?
自由主義は一番良いシステムだとされた。
宗教では、これの代わりにはなりえない。
しかし、自由とは何なのか。それは人間の意思が生み出した想像である。
進化論によると、人間の進化は経験の蓄積だ。DNAにより行動は規定されている。住む場所、交尾、行動様式。自由という言葉を進化論は否定する。アルゴリズムが生物にはあり、だいたい決まっているというのだ。
自由とは願望を叶えることだ。
しかし、人は願望を選んではいない。君が自民党に投票したのは自由意思なのか?。
著者はそうではないと言っている。人間は物事を自由に選択していない。
次に、人間が自由な存在ではない説明だ。
ラットの実験をあげている。
ロボットラット。つまり、脳に機械を入れて人間がボタンでコントロールするのだ。
ボタンの通りにラットは行動する。ラット自身は自由意志だと思っているはずだ。快楽であるのだ。
これは怖い。ラットは自由意志だと思いつつ、装置を持った人間によって自在に操られているのである。
人間のうつ病を取り除く実験も紹介している。これも意図的にうつ病の症状を消せた。
つまり、未来においては人間もロボットラットのようになるかもしれないのだ。
次は、AIの進化についてである。
AIワトソンという医療の人工知能の紹介をしている。これは医師よりも能力が上だ。
生き物は経験の集積である。
それは生物はアルゴリズムであるとも言うことができる。
ここからAIの素晴らしさを語っている。
野球にもアルゴは使われていて弱小球団アスレチックスは、人工知能を使いスカウトがピックアップしなかった選手を見つけて獲得し大躍進をしたとある。
音楽の例では、人間の曲と判断がつかないほど優れた曲を作れたことを紹介している。
そのうち、人工知能を入れたロボットで仕事はある程度まかなえるようになるかもしれない。
その時、人は何をすればいいのか?。
そうなるとデータ至上主義はこれまでホモ・サピエンスが他のすべての動物にしてきたことを、ホモ・サピエンスに対してする恐れがある
怠け者の人類をマトリックスみたいにAIが扱うことは十分に考えられる。
アプリで血圧や体調がわかるものがある。
便の分析をできるおむつ、将来の病気がわかるというものもある。
女優のアンジェリーナジョリーは将来乳がんになる可能性大とわかり、両胸の除去手術を行った。
グーグルやメタも大量のデーター収集をしている。
マイクロソフトの作っているコルタナというAIは、パーソナルアシスタントになる予定だ。
おそらく、コルタナは妻の誕生日、どんなプレゼントがいいかの相談ものってくれて、ベストな選択をしていれるだろう。
AIは、妻やあなた自身よりもあなたのことを知っているのだ。ネットで出している情報のすべては彼らの知能に入っている。そのうちコルタナは仕事の商談や恋の架け橋もしてくれる。相手のコルタナと勝手に会話するのだ。そうなると、もう人はいらなくなる。
人から権威を奪い、それをアルゴに与えるのかもしれない。
もし、この技術を独裁者が獲得したらどうなるのか。
人の行動だけでなく、脳の中身まで知られるのだ。ゾッとする。
人の経験=データーであるとしたら、人間はAIには勝てない。
AIは日々、進化し続けるのだ。
あなたの声は先祖の声だ。
それは最強のアルゴだった。しかし、今はそれ以上のAIが存在する。
グーグルのアルゴは、あなたよりもあなたのことを理解している。
アルゴリズムはいつか、人間のいけない場所まで到達してしまう。
人間中心からデーター中心に
人の存在はかすんでしまう。
いつしか、人間は豚のように扱われるのかもしれない。
それは 映画 マトリックス の世界のようなものなのだろうか?。
AIに勝つには、人間がさらにアップグレードするしかあるまい。
それは人間と呼べるのだろうか?>
2022 11 6
https://www.amazon.co.jp/dp/B07GGKQFTL?psc=1&tag=+kafka181-22&th=1&linkCode=osi
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
