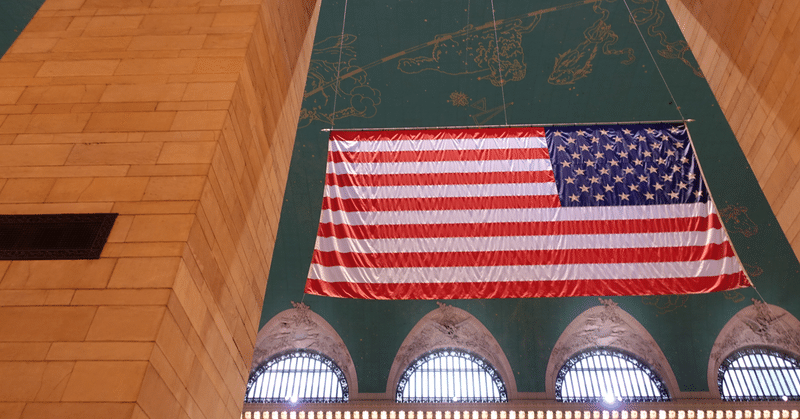
日本、アメリカ、中国の特許制度を比較してみよう①
日本、アメリカ、中国で、知財の法制度って、結構違いますよね。
時系列に、3つの国を比較しながら覚えるのが一番手っ取り早いと思います。
最早、日本の知財制度のみの知識では、足りない時代になってきました。
特許を出したい人は、日本の他に、外国でも出してみたいと思いますよね。
多くの方が、アメリカや中国で、特許を出したいと思うことが多いようです。
やっぱり、国全体のGDPや世界シェアの大きいところで、権利を取りたいですよね。
内容は、法制度の違い、特許明細書作成時の違い、特許出願時の違い、特許出願後の違い、特許要件の違い、拒絶理由応答の違い、拒絶理由通知の応答後の違いの違いについて、説明しようかと思います。
時系列に説明していく感じです。
法制度の違い
日本では、実用新案法、意匠法は別の法律 ですが、米国では、意匠も特許制度で保護されていて、 実用新案権制度はありません(35 U.S.C. 171) 。
そして、中国では、意匠も、 実用新案も特許制度で保護 されています(中国専利法2条)。
日本 では、実用新案権が無審査で出願件数はとても少ないですね。 はっきり言って、日本企業は殆ど実用新案を活用していません。
米国 では、そもそもありません。
中国 では、実用新案権、意匠権ともに無審査です。
日本と違い、実用新案、意匠ともに出願件数が特許出願並みに多いんです。
無審査登録制度をうまく活用している中国企業がとても多いということです。
この点をよく覚えておいてください。
中国では、実用新案と、意匠を活用するのがKEYとなります。
費用も安いんですよね。
それでは、なぜ、日本では、実用新案がまったく使われていないんでしょう。
実用新案権の権利行使前に、技術評価書の提出が必要で、この評価書の内容が肯定的でない場合が多く不安定な権利なんですよね。
一方の中国では、裁判所などが、実用新案権や、意匠権の紛争時に、技術評価書に相当する特許権評価報告の提出必須ではないんですよね(中国専利法61条2項)。
この点が大きく違います。
どのようなものが特許として保護されるか
日本では、ちゃんと発明の定義が有って、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものとされています (日本特許法2条1項)。
米国では、なんと定義が無くて、保護対象(subject matter)や、発明の有用性(utility)の規定があるのみです(35 U.S.C. 101)。
中国では、定義はちゃんと有って、 製品、方法あるいはその改良に対して出された新しい技術構想とされています(中国専利法2条)。
加えて、日本では、産業上利用可能性を特許要件の一つとして、産業上利用可能性を有しない発明を保護 対象から除外しています(日本特許法29条1項柱書)。
たとえば、産業上利用可能性の審査基準の中で、医療行為を保護対象から除外する旨が記載されています。
これに対して、米国では、医療行為を、特に保護対象から除外するという規定はありません。
基本的に、米国では、 有用性(utility)がある限り、保護対象に含まれるんですね (Freeman-Walter-Abele基準、MPEP 2106)。
米国の厄介なところは、判例により保護対象が変化していくんですよね。
中国では、日本の産業上利用可能性に相当する実用性が登録要件 の一つに挙げられています(中国専利法22条4項)。
中国法の実用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用することが可能で、かつ積極的な効果を奏することができることです。
たとえば、科学的発見、知的活動の規則及び方法、疾病の 診断及び治療方法、動物と植物の品種、原子核変換 の方法により得られる物質、平面印刷物の模様などは特許保護の対象外とされています(中国専利法25条)。
各国で、何を保護するかが微妙に変わっているんですよね。
発明した国で最初に出願する?
米国・中国では、発明した国で最初に出願する必要あるんですね(35 U.S.C. 184、中国専利法20条)。
しかし、日本では、発明した国で最初に出願するという規定は無いのです。
この点、発明したら、日本に出願しなくとも、世界のどこにでも出せる日本人は、恵まれていますね。
ただし、日本人は、米国人と中国人との共同開発時に要注意です。
日本では、 特許を受ける権利は、原則、発明者(従業員)に帰属します(日本特許法35条)。
つまり、特許のオーナーは発明した人なんですね。
そして、 特許を受ける権利を企業側に譲渡する契約をして、企業が特許のオーナーになれて、出願もできます。
米国では、職務発明に関する規定は、無いのですが、発明者しか出願できないようになっています。
出願した後に、特許を受ける権利を企業側に譲渡する契約をして、企業が特許のオーナーになれるんですね。
中国では、特許を受ける権利が、原則、所属している企業や組織に 帰属するんですよね(中国専利法6条)。
だれが発明の所有者なのか、国によって本当に違いますね。
出願書類の違い
次に、特許明細書作成時の違いについて、説明します。
日本では、 日本語で出願が基本です。
ただし、外国語書面出願制度を用いれば、英語での出願も可能です(日本特許法36条の2、翻訳文提出要) 。
米国では、 仮出願については、英語以外も出願も可能ですが、本出願の場合は英語でしなければなりません(37 CFR 1.52(d))。
ここで、仮出願については、他の動画で説明していますので、参考にしてください。
中国では、 中国語のみで出願しなければなりません(中国専利法実施細則4条)。
外国語書面出願制度は、ありません。
なお、明細書の説明が足りていない場合に、記載不備といって、特許庁に拒絶されるのですが、日本では、記載不備の拒絶理由は、それほど多くはありません。
中国では、 日本や米国に比べて、記載不備の拒絶理由が多いのが特徴的です。
権利化したい部分を記載する請求項と実施形態で、文章や単語が異なる場合、実施形態の単語に補正させられる可能性があります。
そのため、中国では実施形態を2つ以上用意するなど、広い概念で権利化を認 めさせるための工夫が、必要となります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
