
Foo Fighters 全アルバム聴いてみた
今年6月にリリースされた11th『But Here We Are』が素晴らしい出来だったFoo Fighters。
フロントマンDave Grohlの実母と、そして長年バンドのドラマーを努めてきたTaylor Hawkins、2022年にこの世を去った2人へ捧げる作品として、失意の状況を乗り越えて制作されたアルバムです。
音楽だけを切り取って聴いても素晴らしい作品ですが、背景も踏まえて聴くことでより一層エモーショナルな響きを感じ取ることができます。
ただ、これまで私はFoo Fightesのアルバムを数枚かい摘んでは聴いてきたものの、全作品を網羅できていなかったため、傑作『But Here We Are』に至るまでのプロセスを今一度振り返るという意味でも、デビュー作からの全作品を聴いてみることにしました。
リリース順に、レビューを書いていきたいと思います。
1995年 1st 『Foo Fighters』

Nirvanaでの活動が突如終焉を迎え、失意のどん底に居たデイヴ・グロール。本作は、そんな状況の中でデイヴが個人的に録音したデモ。当初は、本名を伏せ『Foo Fighters』と名乗ることで身元を隠していたといいます。まだバンドは結成前で、ボーカル・ギター・ベース・ドラムの全パートをデイヴが一人で演奏。後にモンスターバンドとなったFoo Fightersですが、デビュー作は極めてパーソナルな内容だったのですね。初期衝動をそのままパッケージングしたようなストレートなロックサウンドで、飾り気は一切無く、削ぎ落とされたシンプルで無骨な楽曲たち。ヘビィでハードなサウンドにメロディアスな歌を乗せるという、後に確立されるスタイルの原型・原点がここにはあります。
"This Is a Call"に始まり、"I'll Stick Around"、"Big Me"の冒頭3曲でもう心を掴まれますね。
1997年 2nd 『The Colour And The Shape』
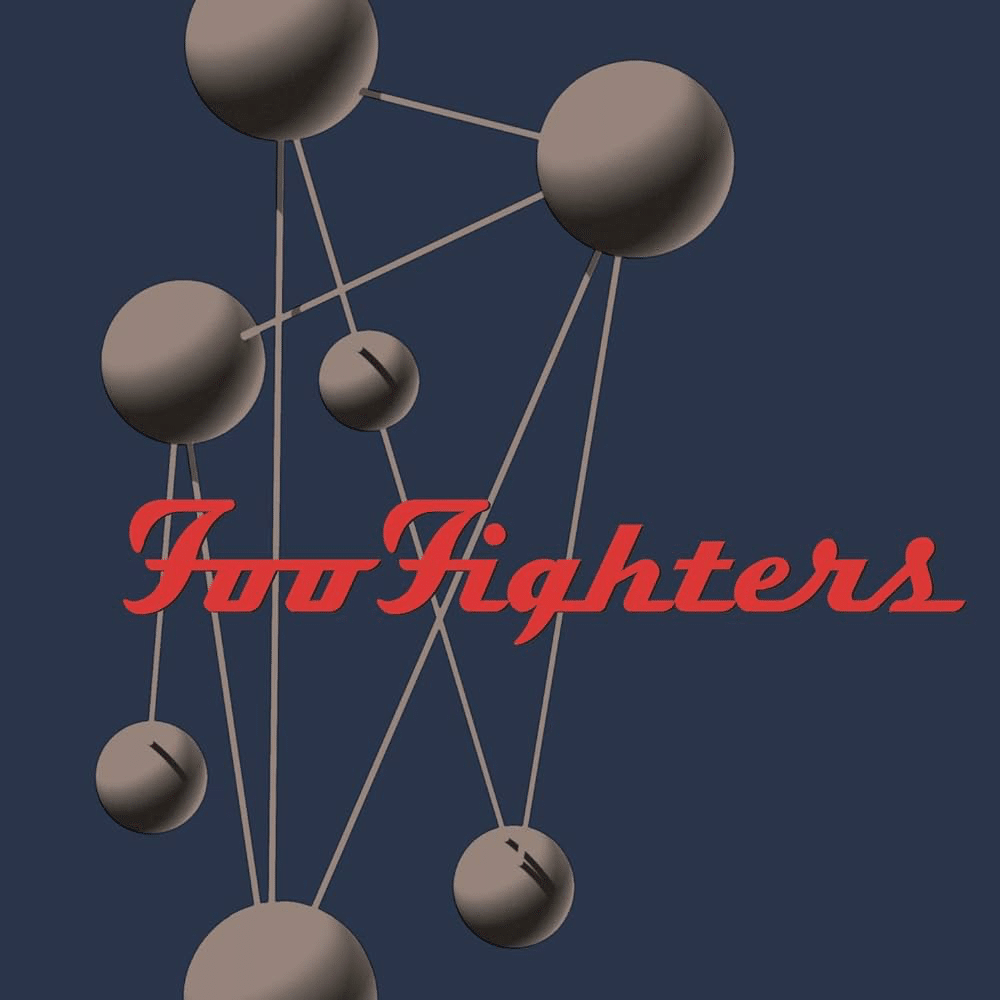
前作での成功を経て、正式なバンドメンバーを迎え入れてのアルバム。ギターには、NirvanaのツアーギタリストであったPat Smearを、リズム隊には、Nirvana時代にレーベルメイトだったEmoの元祖、Sunny Day Real Estateの2人を据えます(ただしドラマーの方はデイヴのお眼鏡に適わず、ほとんど叩かせてもらえないまま本作限りで脱退)。前作のシンプルな楽曲スタイルに、捻りの効いた多彩なアレンジを加え、よりメロディアスに、バンドサウンドはより攻撃的に。無骨なサウンドから、鮮やかな音色へと華麗に変貌を遂げました。"Monkey Wrench"や"My Hero"、"Everlong"など、その後もバンドの代表曲として長く君臨し続ける名曲が目白押しで、一聴して心を掴まれるようなキャッチーさを秘めた楽曲に溢れています。最高傑作との呼び声も高い、初期の代表作。
1999年 3rd 『There Is Nothing Left To Lose』

ドラマーが交代となり、本作から盟友テイラー・ホーキンスが加入。前作のメロディアスさに更に磨きをかけ、サウンド面ではヘビィさよりも軽やかで柔らかな方向性をより推し進めた、軽快で爽やかなアルバム。名作2ndと同路線で、どちらも甲乙つけ難い非常に優秀な作品ですが、個人的には僅差で2ndの方が好きかなというところ。名曲『Learn To Fly』を含む冒頭3曲は彼らの代表曲。
2002年 4th 『One By One』

初の全英チャート1位を獲得するなど、築き上げてきた地位を更に盤石なものとした4th。軽やかなサウンドが目立った前作から一転、ヘビィでラウドでアグレッシヴな作風を追求。重厚なサウンドが主役ではあるものの、常に一定のメロディアスさを保っているところが流石だと思います。キャリア屈指の代表曲である『All My Life』の他、『Have It All』や『Times Like These』など数々の名曲を収録。
2005年 5th 『In Your Honor』
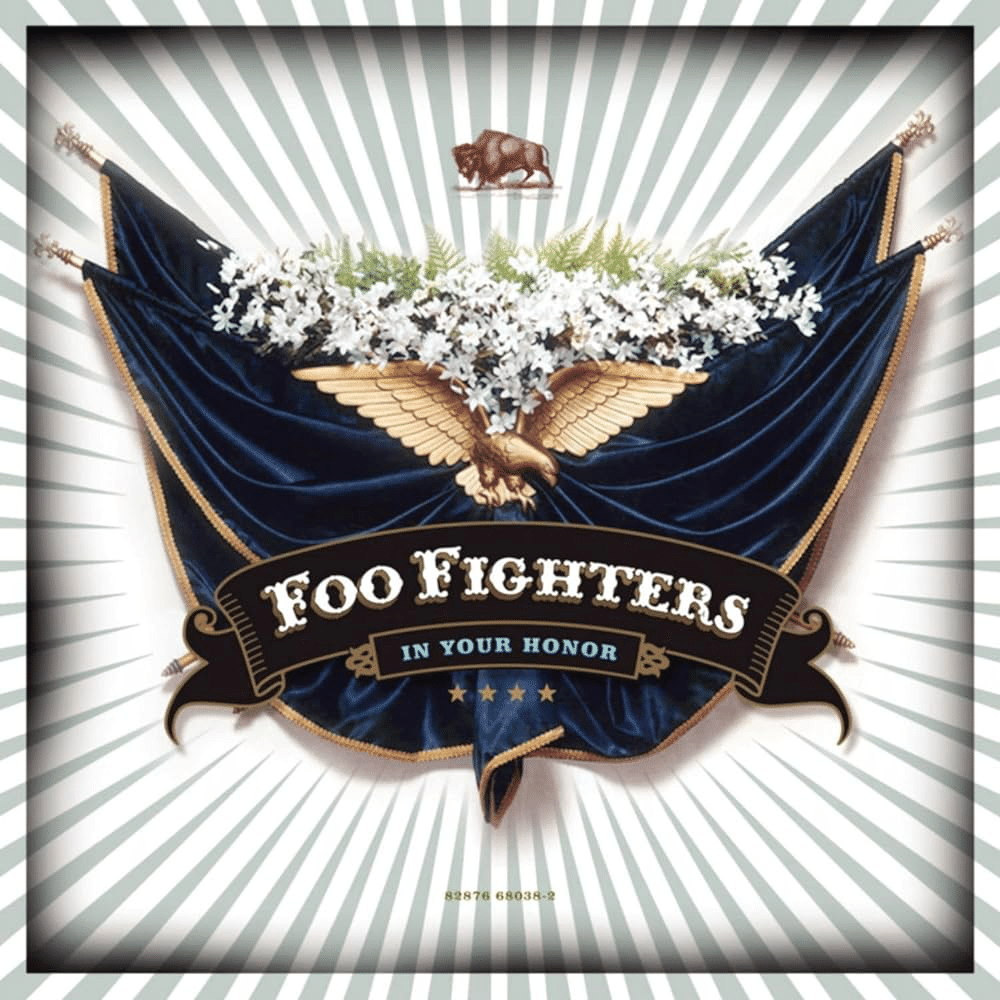
全20曲、総収録時間83分という2枚組の大作。Disc1にはヘビィでロックな楽曲を、Disc2にはメロウでアコースティックな楽曲を収録するというコンセプトを掲げ、結成10周年を迎えたバンドの新境地を開拓しようという意図が込められているそうで。ただ、アコースティック路線で深みのある楽曲を追求しようという取り組みは分かるのですが、2枚組の大作にしてまでやる価値があったかと言えば微妙なところなのかなと。決して悪くはないものの、曲数が多い分、どこか突き抜けた魅力に欠けてしまった感が否めないというか。"No Way Back"、"Best of You"という2大名曲を収録しているだけに、脇を固める面々にもう少し存在感があれば‥と思ってしまった惜しい作品。
2007年 6th 『Echoes, Silence, Patience & Grace』

最高傑作とも称される2nd『The Colour and The Shape』のプロデューサー、Gil Nortonと2度目のタッグを組み制作された6th。冒頭の"The Pretender"から、畳み掛けるように次々とエモーショナルでソングライティングも素晴らしい楽曲を連発。前作のアコースティック路線で得た深みもエッセンスとして上手く取り入れており、新たに開拓した部分が活かされているのも良い。後半やや失速気味な気がするのが惜しいところではあるものの、それでも質の高いアルバムであることには間違いありません。
2011年 7th 『Wasting Light』
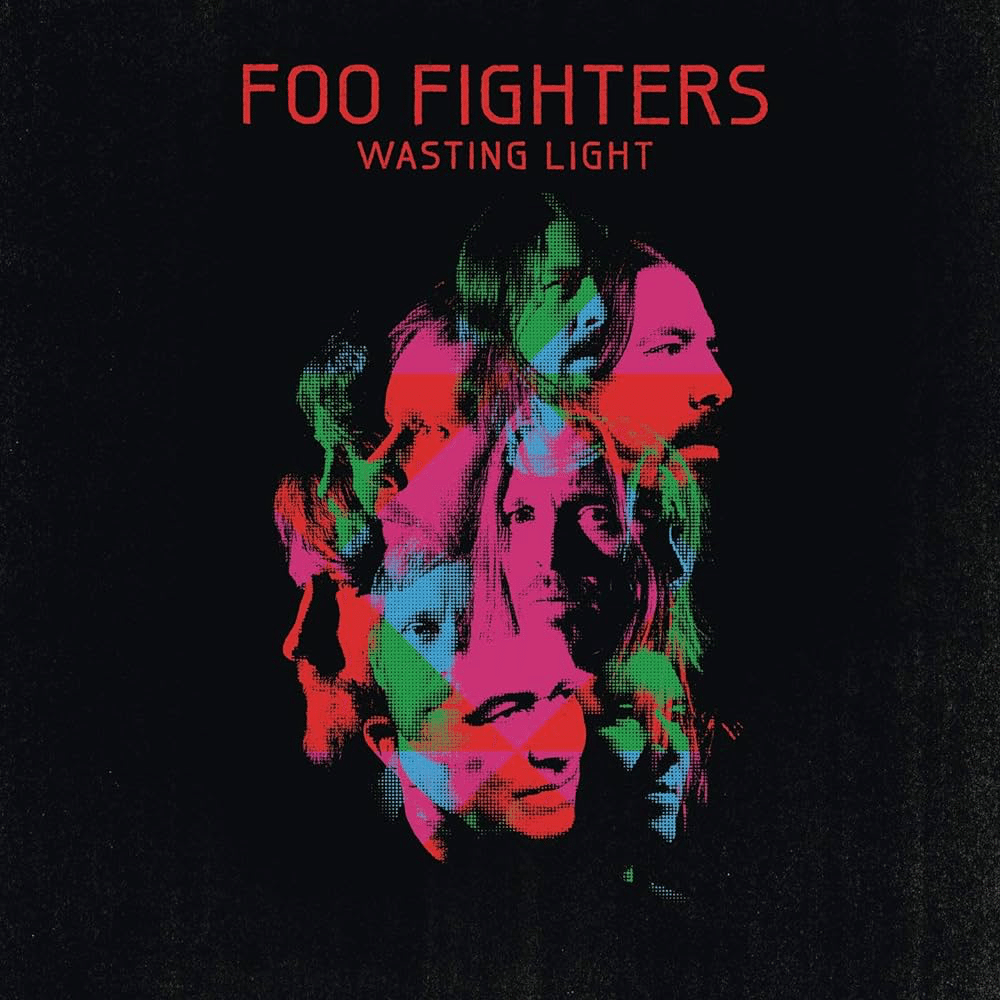
2nd以来の傑作との呼び声高い7th。本作で初めて、全米・全英チャートともに1位を獲得。ニルヴァーナ『Nevermind』のプロデューサーButch Vigを起用し、デジタル録音を避けアナログ機材のみを使用。実験性を排したヘビィでストレートなサウンドが鳴らされています。1曲目から5曲目までは、ラウドなロックサウンドが『ポップス』的に見事に落とし込まれた名曲の連打。疾走感溢れる楽曲が並ぶ中で、しっかりとヘビィで、激しいシャウトを入れながらもポップでキャッチー。6曲目以降は若干スピードを抑制し、深みのあるサウンドメイクで魅せています。最初から最後まで超強力な全11曲。
2014年 8th 『Sonic Highways』

この頃からバンドは新たな音楽性を模索し始めます。私は本作からの3作を「実験3部作」と勝手に位置付けています。プロデューサーは前作に続きButch Vig。アメリカ音楽史へのリスペクトを込めた作品ということで、アメリカの8都市を題材とし、各都市に所縁のあるミュージシャンをfeaturingしているだけでなく、そのミュージシャンへのインタビューから得たインスピレーションを基に楽曲を制作したという非常にコンセプチュアルな作品。録音作業もそれぞれの楽曲の都市で行ったという徹底ぶり。個人的に、曲数をグッと絞り込んで、そこに120%のパワーを凝縮したような、無駄の無い作品が好みなんですよね。全8曲というコンパクトさ、そこに惜しみない労力をかけている感じが好きです。バンドのキャリアを代表するようなアンセムこそ無く、地味な作品ではあるものの、様々なアーティストとコラボした本作ならではのアレンジや楽曲展開が面白い。『Foo Fightersらしいアルバム』では決してないので初心者向けとは言えませんが、定番を聴いた後に、「これ地味に良いな」となりそうな一枚。
2017年 9th 『Concrete and Gold』

シーアやアデルといった人気アーティストを手がけるGreg Kurstinをプロデューサーに迎え、2度目となる全米・全英チャートの両制覇を果たした9th。デイヴ自身が『最もラウドで最も美しい作品』と語っているそうですが、その形容が相応しいのかどうか、個人的には今一つ腑に落ちない部分があります。と言うのも、確かに本作はラウドでアグレッシブですし、華やかなアレンジには美しさもあるのですが、その2つの要素が上手く噛み合ってない気がしています。アレンジはやや大袈裟とも言えるほど華美で、それがヘビィでラウドなバンドサウンドと噛み合ってさえいれば新機軸と捉えることも可能ですが、個人的にはアンバランスな印象を受けてしまいました。あえて言うなら『最も大衆的で最も派手な作品』かと。バンドとして新たな可能性を模索することの意義は否定しませんが、本作だけに焦点を当てて言えば、ちょっと残念な作品かなあと私は思いました。
2021年 10th 『Medicine At Midnight』

ここしばらく続いていた実験精神は本作で頂点を極めます。前作に続きプロデューサーにはGreg Kurstinを起用。これまでに無かったファンクやディスコのリズムを存分に取り入れ、ダンサブルな楽曲の多いキャッチーな作品に仕上げてきました。前作とはまた少し違ったベクトルで派手な作品ですが、個人的には本作の方がバランスは取れているのかなと感じました。音やリズム自体は華やかですが、メロディであったり楽曲としてのインパクトはそこまで無く、絶対的なアンセムは不在なので一概に派手と言い切れない面も。ディスコグラフィーの中にこんな作品が1枚くらいあってもいいよね、とは思えるアルバム。
2023年 11th 『But Here We Are』

テイラー・ホーキンスとデイヴの母、2人の死を乗り越えて制作された、2人に捧げる一枚。デイヴとバンドが経験してきたことへの正直な感情が綴られています。そうした背景を差し引いて音楽だけを切り取って評価しても素晴らしい内容です。#1『Rescued』から5曲目までの前半はひたすらにピュアでエモーショナルな直球のロックサウンドが鳴らされていますが、6曲目以降の後半はバラエティ豊か。パンキッシュな#6『Nothing At All』や、デイヴの愛娘ヴァイオレットがゲストボーカルとして参加したメロウで浮遊感のある#7『Show Me How』、そして極めつけは10分超えの大曲の#9『The Teacher』。10分間の中で様々な展開・起伏を見せるプログレ的楽曲で、デイヴの母と、Taylor Hawkinsの二人について書かれています。アルバム全体の構成としても、随所にロックバラード調の楽曲も配しつつ、彼ららしいヘビィでラウドな楽曲も収録。全体的に非常にメロディックで、エモーショナルな歌唱と演奏がドラマティックさも生み出し、バンドのキャリアをも代表する渾身の作品に仕上がっています。
最後に、個人的に好きだった順にランク付けすると、こんな感じです。

最新作は、間違いなくキャリアを代表する作品だと思います。未聴の方で興味ある方は是非聴いてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
