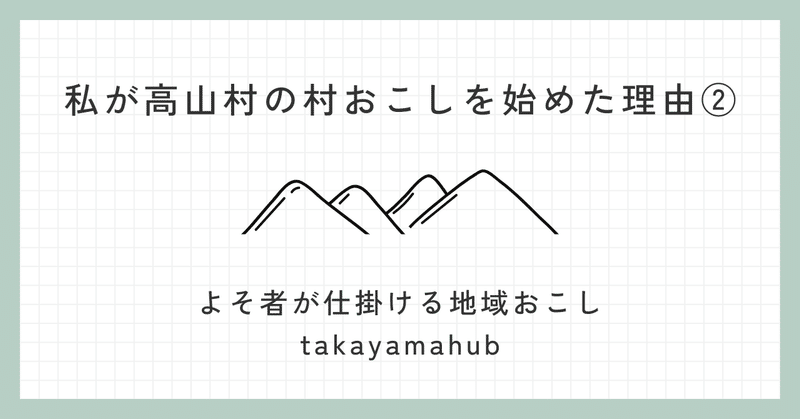
私が高山村の村おこしを始めた理由②
一番目の理由として「やりたい!」と思ったから、という話を前回の投稿で書きました。
様々な魅力にひかれ、自分にとって第二のふるさととも思えるこの村を、次の世代にもその次の世代にも残していきたい、そんな思いを書いています。
今日は、続く二つ目の理由について考えてみます。
それは「やらなきゃ!」という感情に突き動かされたこと。
振り返ってみると今すぐやらなきゃ!そんな気持ちが私の中にふつふつと静かに湧き上がってきたからです。
村の現状
私は高山村が大好きです。
高山村は日本で最も美しい村のひとつです。
前回の投稿にも書いたように、都市で暮らす日常を忘れさせてくれる古き良き日本の原風景、個性的で一級品の観光資源がコンパクトにまとまっているところ、こだわりをもつ職人を引きつけて放さない本物が集まる地の力、純朴でおおらかによそ者を受入れてくださる村の人々など、本当にたくさんの魅力がつまっています。
一方で、この村がもつネガティブな側面も当然あります。
これまで村を見たり村民との対話を通じて私個人が感じたのは、
よく言えば年長者を敬うところ。わるく言えば若い人たちの自由な声があがりにくいところ。
よく言えばリーダーがいると個々人が従順にまとまるところ。わるく言えばリーダーの顔色をうかがわないと個々人が動き出せないところ。
よく言えば対話による意見の調整や協働関係を重視し、思慮深いところ。わるく言えば現状維持志向が強く新たな挑戦が生まれにくいところ。
村をより良くしたい思いや意見を個々人がもつもどこかバラバラ。つながりが弱く村でまとまった大きな動きに発展しないところ。
色んなアイデアも、それは誰がやるのか・・・と生まれては消え、生まれては消え。主体者不在、皆んながどこか傍観者で他人事感が漂うところ。
上記のようなことがあいまって、結局今の村では・・・とあきらめ感や閉塞感がうっすらが漂うところ。
そのような風土を背景に新たな取組みが生まれにくい状況、さらに少子高齢化で村の人口は低下の一途、じわじわと村の活力が低下し続けている・・・それが私から見た高山村の現状です。
※あくまで筆者個人の見解です。
※高山村の人口推移
2020年10月:6,877人
2023年4月:6,636人
2060年(推計):4,800人 第二期高山村総合戦略より
村を変えたい人たちがいる
そんな中でも、村を盛上げたい、どうしていいかわからないけど村を元気にしたい、そう思う村民の方々は確かにいらっしゃる。
前回の記事でふれた、私が高山村と出会うきっかけとなったワイン観光振興のプロジェクトはその一例。
ぶどう農家、ワイナリー、旅館、飲食店、村のワイン愛好家等、プロジェクト中にたくさんの村民の方々のお話をお聞きしました。
その人たちから伝わってくるホントに村が好きな気持ち、村を元気にしたいと思う気持ちにふれ、どんなカタチでもいいからこの村の役にたちたい、このプロジェクトが村が変わる一つにキッカケになれば・・・そんな思いで今後の観光振興の具体策を夢中になって事業計画に落とし込んでいきました。
キッカケは作れた。でもやり続けることの難しさも。
事業計画の提案を終えてプロジェクト終了したのが2021年1月末。
その年は「やらなきゃ!」というムードが村の中に芽生え、観光協会のHPの刷新やワインぶどう収穫体験をコアとしたアグリツーリズムの実現など、村の関係者がつながりながら事業計画中の観光振興施策をひとつ一つ実現していきました。
しかし、もともとは新たな取組みが生まれにくい土壌の高山村。
一時の盛り上がりをみせたものの、村のもつ復元力に引っ張られるかのようにかつての機運は下降しはじめ、2022年度はこれといった施策も実行できず・・・
時間が経つにつれ・・・
それでも一度はできたこと、また何かのきっかけで機運があがり村の中に盛り上がりが生まれるときがくる。
村には村のペースがきっとある。
少しずつでも、ゆっくりでも、良い方向に向かってじわじわと変化を重ねていってくれれば・・・そう思っていました。
そんな私の考えを180度変えたのが角藤農園の農場長、高山村ワインぶどうのカリスマ栽培家・佐藤宗一さんの訃報。
高山村ワインにふれたときから、いつか必ず会いたいと思っていた人。
七十いくつじゃないのかな、早すぎるし突然の出来事、残念ながら会うことは叶わなかった。
その時、私の中でハッとするものを感じました。
高齢化が進む地方では、当たり前のことだけど、その村のキーマン自体が高齢化していってる。
何もせずに時間が経てば、以前と変わらない姿で今もある・・・というわけではない。
キーマン=人的資源が減少する分、何もしなくても時間の経過で村の活力は低下してしまっている。
だとすると、村には村のペースで、ゆっくりでもいいから・・・そんなのんきに構えてていいのだろうか、そんな疑問がわいてきました。
そうこう考えているうちに、
新しい取組みが生まれにくい土壌の高山村で変化を起こすには、私のような外部の人間が新たな風を送り込むことが効果的ではないか、
利害関係もなく村の風土がしみついていないよそ者だからやりたいことを何も気にせずやり続けられる、
そしてやるなら早く始めないと・・・。
本当に村を変えるなら、
よそ者がキッカケをつくった方が早いし効果的。そして今すぐやらなきゃ。
これが私が一歩踏み出そうと思って原動力、高山村の村おこしを始めた2つ目の理由です。
takayamahubでは、村の内外に関わらず、一緒に村を盛り上げていただける仲間を募集しています。
また、インスタ、ツイッター、Facebookで高山村に関する情報を日々発信しています。
ぜひ下記ホームページよりご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
