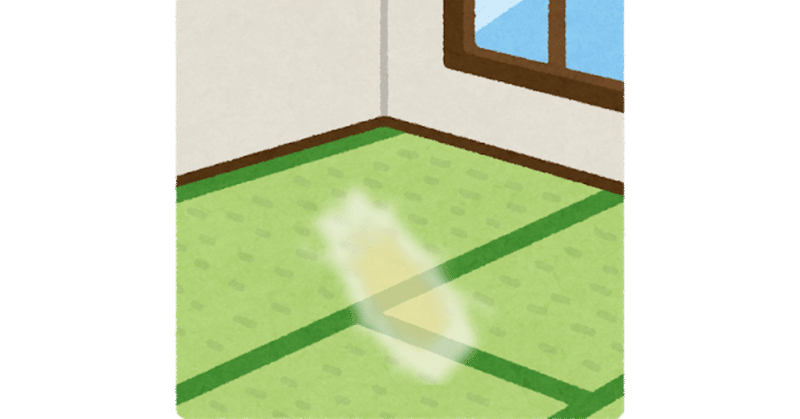
日だまりの昆虫
風もなく、よく晴れて暖かかったので、ベランダに布団を干していた。
すると、硬貨ほどの日だまりが滑るように部屋へ入り込む。
「何かに反射した光かな」
辺りを見回すが、それらしい輝きはなかった。気に留めるほどのことでもなかったので、布団干しを続ける。
部屋に戻ってソファにもたれかかろうとしたとき、天井で小さな日だまりがぽっと光っているのを見つけた。
「さっきのか……」立ち上がって、照り返している辺りに見当をつける。 ここか、と手をかざしてみるが、遮るような光線は見当たらなかった。
「カーテンを閉めれば――」なんとなく意地になって、窓のカーテンを引く。これで、どこからも光が漏れてくることはないはずだ。
ところが、まだ天井に貼り付いている。部屋が薄暗くなった分、いっそう明るく周囲を照らしていた。
「どうなってるんだろう。日が差してくるような隙間なんてないはずだけど」
日だまりの真下に立って、背伸びをしてみる。まるでタマムシのような、細長い円だった。
よくよく見ると、触角や脚もちゃんとある。目に当たる部分も、わずかに明るい。
「影絵美術館で観た、セロファンの切り絵がこんなだったっけ」
じっと見つめていると、光のタマムシがもぞっと動いた。いや、実際には音1つ立てなかったけれど、本物の昆虫のように這ったのである。
「これって、もしかしたら生きてる?」
タマムシは天井をするすると走っていき、壁まで降りてきた。
わたしは、目を離さないように気をつけながら、ゆっくりと後ろ向きに部屋を出ると、台所に置いてある、プラスチック製のボウルを取ってくる。
ボウルを手に、そおっと壁へ近づいた。タマムシは身じろぎもしない。
「捕った!」素早く、ボウルを壁に押しつけた。白いプラスチックを透かして、光が滲んで見える。「何か入れとくものは、えーと」
入れ物の心配をする必要はなかった。タマムシは、再び移動を始める。慌てるでもなく、じたばたともがくわけでもなし。それはのんびりと進んでいった。
ボウルで塞がれている端までやって来ると、そのままするっと外へ出てしまう。
「この虫って、厚みがこれっぽっちもないのかぁ」ようやく気がついた。
ボウルを投げ捨てると、大急ぎで手のひらをタマムシに重ねる。手の甲が赤く透け、通っている血管が見えた。ちょうど、太陽に手をかざしたときのように。
じわっと温かみを感じ、手の甲からタマムシが染み出るように現れる。
「本当に日だまりなんだなぁ。これじゃあ、捕まえられっこない」わたしが手をどけると、タマムシは壁にひっついたままそこにいた。
どうしたものか見当もつかず、志茂田ともるに相談してみようと電話をかける。
「もしもし、志茂田?」
「ああ、むぅにぃ君。いいタイミングで電話をくれましたね」電話の向こうから聞こえる志茂田の声は、心なしか弾んでいた。
「なんだか楽しそうじゃん。どうしたの?」
「あなたこそ、どうなさいました? 用事があってかけてきたのでしょう?」反対に聞かれてしまう。
「あ、そうだった」わたしはこちらの事情を思い出した。「部屋に、不思議な虫が入り込んじゃってさ。日だまりそっくりなんだ」
「おおっ」そう声を上げたきり、うんともすんともなくなる。
「もしもし、志茂田?」電話が切れてしまったのかと思った。けれど、そうではない。
「これは失礼しました」やっと志茂田が口をきいた。「むぅにぃ君、あなたの部屋に迷い込んだそれは、『ヒカリムシ』という極めて珍しい昆虫なのですよ。わたしは、それを長年追いかけていましてね」
「へー。でも、これって絶対に捕まえられないよ。さっきも試してみたんだけど、手でもなんでも透けて逃げちゃうんだ」
「それはそうですよ。なんたって『ヒカリムシ』なんですからね。その気になりさえすれば、光速で飛ぶことだってできるんです」
「じゃあ、見るだけだよね。早く来たほうがいいよ、そのうちいなくなっちゃうから」わたしは前もって言い伝える。そもそも、どこから飛んで来たのかだってわからない。いつ、どこへ行ってしまうかなど、さらに予想もつかなかった。
「捕まえることはできるんです。それも、いますぐに。今回、わたしは運がよかった。まさか、こんな偶然が起こるなんてねえ」
「どういうこと? どうやったら捕まえられるの?」
「つい先ほど、わたしの元へ、『カゲムシ』というものが紛れ込んできましてね」
脳裏に、真っ黒な姿をした平たい虫が浮かんだ。
「それって、ゴキブリだったりしない?」電話越しに顔をしかめてみせる。
「確かにそっくりです。わたし自身、とっさに殺虫スプレーを手にしたくらいですから。ですが、そうではないんです。正真正銘、権威ある原色昆虫図鑑にもちゃんと載っている、ヒカリムシ科カゲムシ属カゲムシなのですよ」
「ちょっと待って。いま、ヒカリムシ科って言わなかった? それって、ヒカリムシとカゲムシが同じ仲間ってこと?」わたしは驚いて尋ねた。
「はい、そうです」志茂田はきっぱりと答える。
「まさかと思うけど、2匹で1つの虫、なんてことはないよね?」
「今日のあなたは冴えていますね。おっしゃる通り、まさしくそうなんです。それぞれは光だったり影そのものだったりするわけで、物理的に捕まえることも、閉じ込めたりすることも不可能です」
「うんうん、それで?」
「けれど、2匹同時に捕らえれば話は別です」
「だから、捕まえられないんだってば」わたしはじれったくなった。
「あなたのいま使っているスマホ、それにはカメラ機能がついているじゃありませんか」志茂田が言う。
「あるけど、それが?」
「こちらとそちら、同時に虫を写真に納めるのです。いいですか、同時にです。そうですね、そろそろお昼です。12時の時報を合図に、シャッターを押すとしましょう」
よくわからなかったが、言われた通り、カメラの準備をしてヒカリムシに向ける。
テレビでは昼を告げる時計が大写しになって、秒読みを始めた。
「プッ、プッ、プッ、プーン」
いまだ! わたしは携帯のシャッターを押す。
直前まで壁を這っていたヒカリムシは、光を吸い取られて灰色に変わっていた。
「もしもし、志茂田? 写真撮ったよ。ヒカリムシ、灰色になっちゃったけど」
「こちらも同様です。その灰色の生き物は、もはや光でも影でもありません。爪で剥がして、テーブルの上にでも置いておいてください。これから引き取りにうかがいますから」
志茂田の「昆虫標本」に、また新しいコレクションが増える。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
