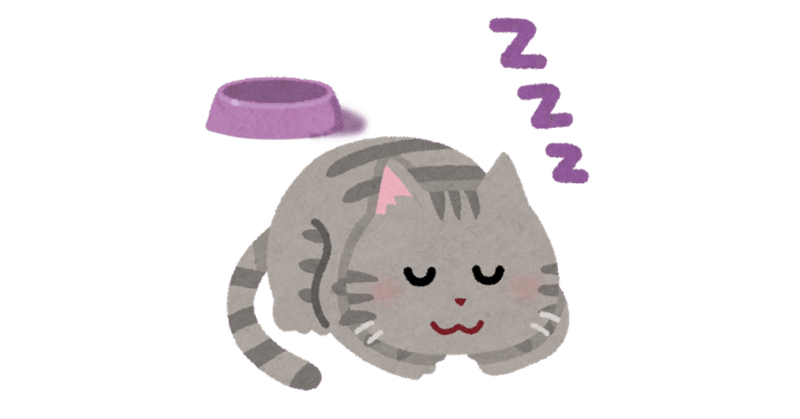
もう、ご飯は要らない
そのキジトラとは、物心がついたころからずっと一緒だった。だからかもしれない。わたしには、彼女の言葉が理解できた。
「ねえ、そろそろお昼ご飯にしてもらえないかしら? あんた、このあと、友達とどこかへ遊びに行くって言ってたでしょ。先だっても、そんなことを言っていて、うっかりアタシのボウルにカリカリを入れ忘れてたじゃないの」
「あ、ごめん、メラ。すぐに袋を開けるから」メラと言うのは、心理学者のメラニー・クラインからもらった名前らしい。名付けたのは父だ。
「しっかりしてちょうだい。アタシを飢え死にさせるつもり?」
生まれつき気難しいのか、それとも、名前に負けまい、と性格までそうなってしまったのか。
わたしは棚からカリカリの袋を取り出すと、ボウルにあけてやった。
「あんたったら、ほんとに気が利かないわね。ご飯には水でしょ。ほら、新鮮な水を注いでちょうだいな」
メラの言葉がわかるのは、家族でもわたしだけだった。両親も2人の妹も、ただニャアニャアとしか聞こえないそうだ。それでいて、わたし達が話をする様子を見ても、不思議とは思わないらしい。
「あなたが赤ちゃんの頃から、ずっとおしゃべりするのを見てきたからね。もう、当たり前のことになっちゃったんだわ」母はそう言って笑う。
「通訳」をさせられることもしばしばだ。
普段は物わかりのいいメラだったが、ごくまれに、ひどく虫の居所が悪くなることがある。お気に入りのゴム・ボールや猫じゃらしにさえ見向きもせず、一家の主と認めているはずの父がなでようとすると、耳を後ろに伏せてフーッと唸る。
「おい、むぅにぃ。メラニーの奴、なにを怒ってるんだ?」困った父が聞いてくる。
そこでわたしが間に立つのだ。
「ねえ、メラったら。今日はどうしちゃったのさ」
メラは不機嫌そうに顔を上げ、
「どうもこうもないわ。さっきから口ん中は乾くし、心臓はバクバクする。おまけに、いまにも吐きそうなのよ。少し、ほっといてもらえないかしら?」
「具合が悪いの? 食欲はある? 何か食べたいものとかは?」わたしは心配になった。もしかしたら、深刻な病気かもしれない。
「さっき、あんたの妹にチョコレートをもらったわ。でも、ほんの数かけらきりだったから、お腹の足しにはならないわね。一眠りして気分がすっきりしていたら、ご飯にしてもらおうかしら」
うーん、大丈夫なのかなぁ。
「何だって?」父が言う。わたしの言葉も、人間語じゃなくなっているので、改めて説明しなくてはならない。
「あのね、体調が悪いんだって。気持ち悪いみたい」
「悪い物でも拾って食ったかな」
「そういえば、妹達からチョコをもらったみたい」
「チョコを? そうか、そいつはまずかったな」父は考え込む。
母も洗い物を終えて、やって来る。
「そうよー、メラにチョコレートは毒なんだから」
「ちょっと、こっちへおいで」父は妹達を呼ぶ。
まだ小さな2人が、「はーい」と無邪気な返事をして駆けてきた。
「お前達、メラにチョコをあげたかい?」
「うんっ!」元気いっぱいに答える。そして、褒めて欲しそうに父を見るのだった。
「そうか、そうか。メラ、喜んでたろ。でもな、チョコはやっちゃダメだったんだ。人間と違って、食べるとお腹をこわしちゃうからな」そう、諭す。
褒められるどころか注意され、がっかりする妹。
幸い、チョコレート中毒はたいしたこともなく、翌朝までにすっかり元気を取り戻していた。
ご飯をあげたり、トイレの掃除をしたりと、メラの世話をするのはわたしの役割だった。初めは母が面倒を見ていたのだけれど、いつからか、わたしの仕事になっていた。
メラは、自分が姉だと考えているらしかった。母によれば、わたしがまだ5つの時、目の開いていない状態でもらわれてきた。
つまり、わたしよりもずっと年下なのだ。
そのことをメラに言うと、
「アタシは、あんたよりも早く年を取るのよ。だから、当然、アタシの方が大人なわけ。あんたなんか、未だに『中学校』とやらに通ってる子供じゃないの。このアタシに意見しようなんて早いわよ」
そう返されてしまう。
わたしは「中学校」をようやく卒業し、高校へ進学した。
人間なら、まだ子供と大人の狭間だったが、メラは目に見えて老け込んでいた。必要のないかぎり動こうともせず、ゴロゴロと寝そべってばかりいる。
「メラ、少しは歩き回った方がいいよ」運動不足が体に良くない、そう聞きかじって忠告する。
「うるさいわね。寝るのがアタシの仕事なの。それより、ご飯はまだ? お腹ペコペコなんだけど」
相変わらず、食欲だけは旺盛だ。
「はいはい、いま用意するからね」わたしは缶詰を開ける。最近は、歯が弱ってしまっているので、カリカリを買っていない。
缶の見た目は、人間用の物とほとんど変わらない。一度だけ、試しにつまみ食いをしてみたことがある。味も薄く、ほとんど塩気がなかった。醤油でも垂らせば、まあまあ、いけそうだ。
ボウルに盛った缶詰のマグロを、もそもそと食べるメラ。以前はあっという間に平らげたものだが、倍以上かけてゆっくりと味わっている。
もう、11歳になるんだもんなぁ……。
冬も近くなり、晩ともなれば冷え込みが厳しくなってきた。
メラは寒い季節、わたしの布団の中で眠る。この夜も、脇の辺りで丸くなっていたのだが、もぞもぞと這い出てきた。
「どうしたの、メラ。トイレ?」枕元の時計を見ると、まだ4時を少し過ぎたばかり。
「アタシ、そろそろ行かなくちゃならないわ」ベッドから降り、ランランと光る目でわたしを見つめる。
「行くって、どこへ?」ふいに、胸騒ぎを覚えた。前にもこんな事があった気がする。
「アタシのボウルに、もう、ご飯は入れなくていいわ。必要ないから」
「でも、だって――」手を伸ばして、捕まえようとする。メラは、歳とは思えない動きで身をかわしてしまう。「待って。お願い、戻ってきて」
「もちろん、戻るわ。そのうちにね。でも、あんたにアタシがわかるかしら。あのときみたいに、また忘れちゃうんじゃない?」クスッと笑った。
そうだ、思い出した。
わたしが生まれる前からいた、エリザベスという三毛のことを。すでに15歳というおばあちゃんで、わたしをいつも可愛がってくれていた。
わたしはエリザベスのことを「きゅぶら」と呼んで、ほんとうのおばあちゃんのように想っていたっけ。
5つのとき、きゅぶらは、わたしの前から姿を消した。出て行く直前、悲しくて泣いているわたしに、こう約束してくれた。
「むぅにぃや。戻るから。きっと戻ってくるから。だから、そんなに泣かないでおくれ……」
入れ替わるようにもらわれてきたのが、メラだった。
「今度は、もう忘れない」わたしはメラに誓う。「でも、次に会ったときはなんて呼んだらいいの? せめて、それだけでも教えて」
「名前なんてどうだっていいの。大したことないもの。あんたの好きに呼んでもらってかまわないわ。それが、アタシのことならね」
振り向きもせず、少し開けてあったドアから音もなく出て行った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
