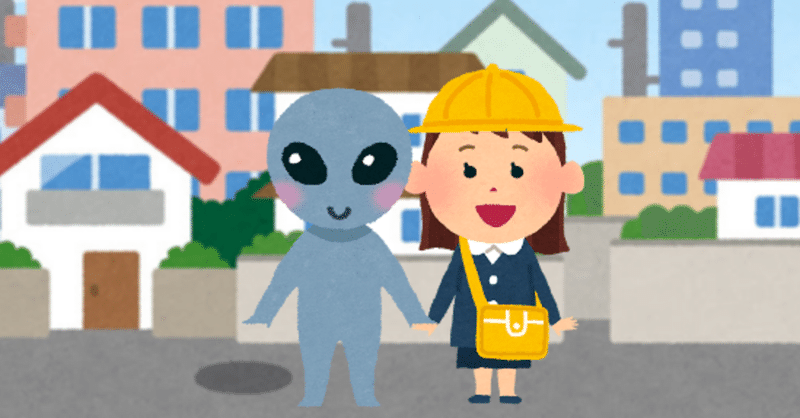
幼なじみの宇宙人
3丁目のラーメン屋「ポンポン亭」2階には、わたしの古くからの友人が間借りしている。
実は彼、宇宙人なのだ。
出会いは幼稚園の頃、同じもも組で隣の席だった。
男の子なのにやたらと生っ白い顔をしている。それもただ白いのではない。灰色がかって、妙にてかっていた。まるで、プラスチックかナイロンでできた人形のよう。
「あんたってば、なんかちょっと変」わたしは、初対面の相手にずけずけと言った。
「ぼく、変かな、やっぱり」気を悪くするでもなく、ぽりぽりと頭の後ろを掻く。さらによく見れば、頭からニョッキリとアンテナが突き出ている。その先っちょには、ピンポン球のようなものが付いていた。
「うん、変だよ。どう見たって、普通じゃないもん」つくづくわたしは遠慮がない。
それにしても、どうして誰もおかしいと気がつかないのだろう。これほどあからさまなのに。
「ねえ、ちょっと耳を貸しておくれよ。内緒の話があるんだ」男の子は言い、わたしの耳に手をそっとあてがう。
子どもは「秘密」だとか「冒険」が大好きだ。わたしも、もちろんそうだったので、ワクワクしながら身を寄せる。
「なになに? どんな話?」
男の子はひそひそと語り始めた。それは、本当にびっくりするような事だった。
「実はぼく、テフロン星からやってきたんだ。銀河系の、ちょうど反対側にあるんだよ」
生まれて間もなく、両親の都合で星を立ったのだという。だから、故郷の事は写真でしか知らない。テフロン星でつけられた名前は「フニャラ・ツルツン・テッカテカ」とか、そんなだった気がする。
いまは地球人として日本国籍を取得しているため、「佐藤太郎」と名乗っていた。
「いいかい、このことはぼくと君だけの秘密だよ。宇宙人だ、なんて知られちゃったら、園が大騒ぎになっちゃうからね」男の子は、口に指を当て、しーっというしぐさをしてみせる。
「うん、わかった。絶対、誰にも言わない」わたしは固く誓った。
そんなわけで、これまでもずっと人に話さずにきた。
佐藤太郎は、夜はラーメン屋の手伝い、昼は母校の大学で界面活性剤の研究をしている。
「洗剤ってあるだろ? 水と油がしっかりと馴染むことで、汚れを落としやすくしてるのさ」佐藤太郎が、前にそう話してくれた。「ぼくの研究はね、水と油ではなく、酸素と暗黒物質についてなんだ。それも、馴染ませるんじゃない、反対に分離させる試みなのさ」
難しいことはわからないけれど、宇宙には暗黒物質が充満しているのだそうだ。酸素と分離することによって、両者の間にはわずかな真空の隙間ができるという。
要は、それを体に塗れば、例え裸のままでも、宇宙旅行ができるようになるらしい。
「へー、すごいじゃん。宇宙服って、あれ高いんでしょ? 安上がりですむねっ」わたしは感心した。
「まあ、コスト・ダウンもその1つではあるけど。これが完成すれば、月にだって住むことができるんだよ。それこそ、素晴らしいと思わないかい?」
その瞳は、どこまでも純粋な輝きを放っていた。
「よく、そんなことを考えついたと思うよ。まるで、魔法みたい」
「うん、魔法のようだね、本当に。でもね、これは正真正銘、科学なんだ。パパがテフロン星から取り寄せている科学雑誌『フロム・テフロン』に、そのヒントが書かれていてさ。それが研究のきっかけになったんだ」
研究は大詰めで、近い将来、実現可能だという。そうなれば、故郷テフロン星を差し置いて、銀河系で最初に技術を確立させた惑星となる。
「生きているうちに完成するかな?」わたしは聞いた。
「きっとできるよ。いや、やってみせるさ。なんてったって、ぼくは地球人なんだ。例え、生まれは違ったとしてもね」
そんな佐藤太郎の夢は、国際宇宙ステーションの傍らで、ラーメンの屋台を引くことなのだという。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
