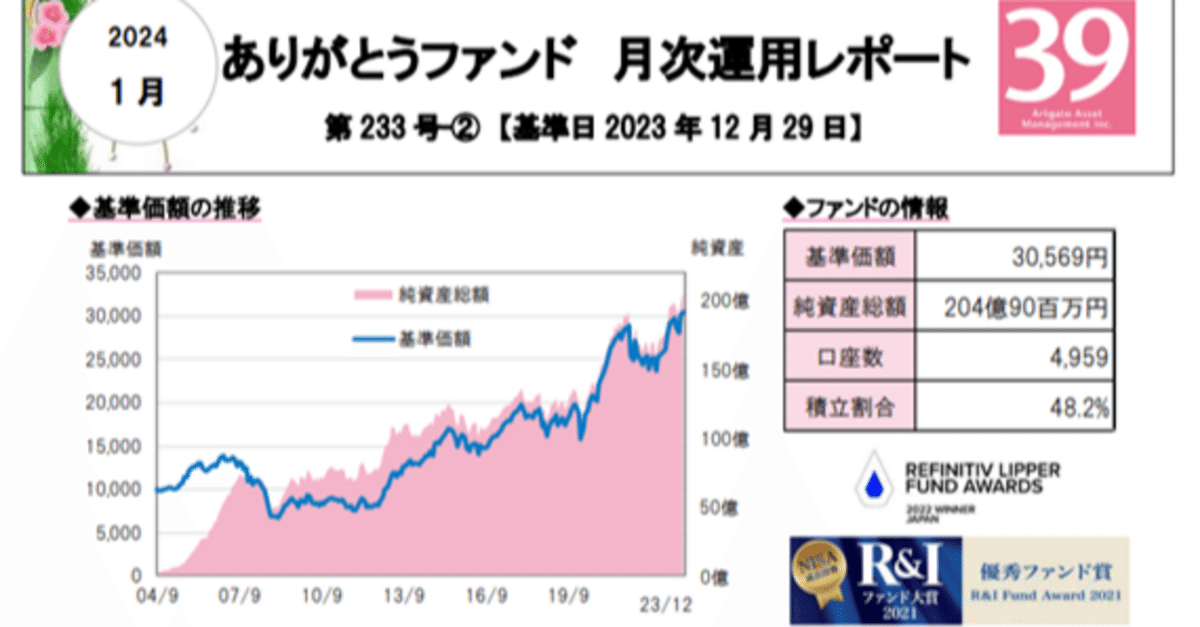
ありがとう投信・ありがとうファンドの運用レポート、わたしの読み方〜(23年12月運用分)〜
はじめに
わたしが読む視点で書き出していきたいと思います。
わたしの読み方ですので偏っていますことをご承知ください。
記載していない部分は、読み飛ばしたり、流し読みしている部分のイメージです。
ありがとうファンド
ファンドオブファンズ
ありがとう投信が運用する「ありがとうファンド」。
ファンドオブファンズという形式をとるファンドです。
自らのファンドでは投資先の会社の調査は行わず、
ファンドオブファンズのメリット、デメリットがあると思いますが、デメリットとしては、以下が挙げられています。
(1)は事実なので、それに納得できなければ投資を見送るしかないですね。
それを超えるメリットがあるかどうか。
(2)は、説明の仕方の問題なのかなと思います。
組み入れるファンドが多いほど、それぞれの組み入れファンドに組み入れられた銘柄を追うことは難しくなりますから。
でもそれは、アクティブファンドも、説明が不足しているファンドでは同じことになる可能性がありますよね。
一方でメリットとして挙げられていること。
2つのサイトに書かれたことを2つの視点にまとめてみました。
上段は自分でも出来ることとも言えます。
でもプロにお任せする手数料として捉えれば、良いんじゃないのかなぁ程度に思っています。
特に「トウシル」の筆者は、随分と否定的な感じですが、価値観の問題かなと思います。
下段も目利きの問題で、「トウシル」の筆者は否定的です。
普通の投資家では投資できないファンド(私募ファンド)や、日本では投資が簡単に出来ないファンドなどに投資できることはメリットと思っています。
特に、日本株式以外の投資で、インデックスファンド以外を考えるのであれば、メリットは大きいんじゃないかと思うんです。
お客様レター
今月のお客様レターでお伝えしたいことはこちら。
時間を味方につけること。
コツコツ積立を続けること。
予測が難しい先行き不透明な波乱の時代だからこそ私達にとっては、今まで以上に資産運用が大切になってくると考えます。今年から新NISA制度もスタートして、今まで預貯金しかしてこなかった人たちにも資産運用を始めやすい環境が整ってきています。インフレや地政学リスクの高まりなどから自分達の資産を守っていくためには分散投資で資産運用していく必要があるでしょう。また、短期的な価格変動リスクに対しては時間軸を長期で捉えることが大切で5年、10年、20年単位で投資継続していく心構えが資産運用の目的・目標を達成する上で重要になってきます。今年から資産運用を始められる方も、既に資産運用をされている方も、新しい年の年初に初心を大切にして是非資産運用を継続していって頂ければと思います。「継続は力なり」というように、資産運用で大切なことであり、最も難しいことは、長期で継続することです。マーケットの過去の実績を振り返れば、長期で継続すれば良かったことは誰にでも理解できますが、先行き不透明な将来に向かって1年、3年、5年、10年、15年、20年と投資をずっと継続して実践できる人はそれほど多くありません。マーケットが大きく調整すれば怖くなって投資を止めてしまったり、逆に大きく上昇すれば途中で利益確定してしまったり、資産運用をずっと継続することは、私達がロボットではなく感情のある人間なので行動経済学から考えても簡単なことではありません。
また、「今月の FP 情報コラム」も確定申告を前に、注意点が書かれています。
『確定申告で節税したつもりが 負担増になってしまうかも』との注意喚起がされていますので、ぜひご一読ください。
運用レポート
運用レポートも、興味がない部分についてはざっと流し読み。
特に相場環境には興味がないので、ざざざーっと。
組み入れファンドの売買について、気になる記載がありました。
アバディーン北米小型ファンドを全売却しました。一方、アリアンツ・US・ラージ・キャップ・バ リューファンドを新規組み入れファンドとして登録し、投資を開始しました。
1月に予定されている新春企画セミナーでは、詳しく説明されるんでしょうか。
面白いと思ったのは、ファンドマネージャーの真木さんが書かれた「『おもてなし』は一日にしてならず」について。
ぜひ読んでほしいなと思いましたので、リンクを貼っておきます。
『おもてなし』は『サービス』とは明確に異なるという点は確かだと思います。『サービス』には対価が発生しますが、『おもてなし』自体には対価は発生しないと考えるからです。また、『おもてなし』は一方行のおこないではなく、双方向的な関係だと考えております。『もてなし』したら、次は『もてなされる』といった関係です。相手を『もてなす』際に、次回以降の『もてなし』を期待するわけではなく、自然とそういう関係になることが文化としての『おもてなし』だと私は理解しました。よって、『おもてなし』を具現化するためには、それぞれが相手のことをよく理解する必要があり、そのためには長い時間が必要だと考えられます。
投資も寄付も一日にしてならず。
投資も寄付もコツコツと。
では。
関心を持ってくれてありがとうございます。 いただいたサポートは、取材のために使わせていただきます。 わたしも普段からあちらこちらにサポートさせてもらっています。 サポートはしてもしてもらっても気持ちが嬉しいですよね。 よろしくお願いしますね。
