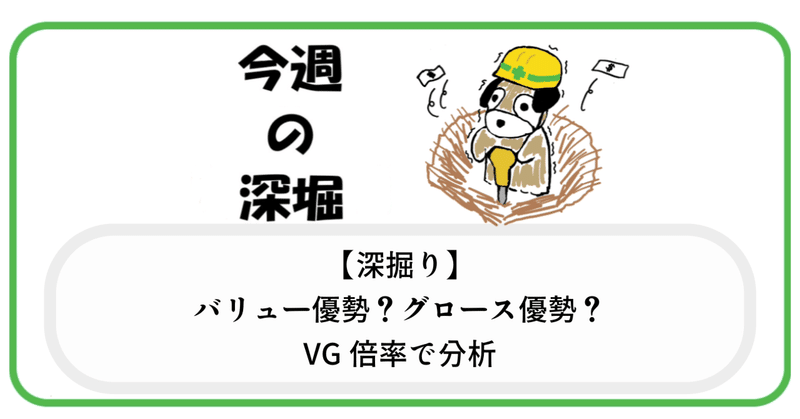
【深掘り】バリュー優勢?グロース優勢?VG倍率で分析
このnoteでは、
バリュー優勢か、グロース優勢か……
日経平均株価とTOPIXの強弱にも出やすい一方、ともに上昇することもあって明確にどちらか優勢かは決めつけづらい。
そこでTOPIXバリュー指数とグロース指数の強弱をVG倍率として計ってみる。
日経平均株価が過去最高値を更新してきた今年の1-3月のVG倍率をみてみると……
という話などをしています。
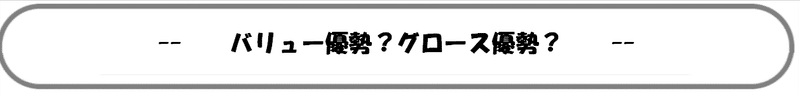
先週水曜日に最近の「NT倍率」を深掘り記事で紹介しました。
株価指数の揉みあいの中では明確な動きがないようにみえていても、日経平均株価とTOPIXのどちらが優勢かという傾向がみえることによって今後の戦略も立てやすくなるかも?という考えでまとめました。
その中でも触れたように、日経平均とTOPIXがどちらが優勢かについては、
「日経平均の構成銘柄最上位を占めるグロースが優勢か、TOPIXの構成銘柄最上位に多いバリューが優勢か」
という点が大きく左右しがちです。
そのため、逆にNT倍率でグロース、バリューの力関係をみたくなる気もしますが、構成比率の差はあれど大型株であればどちらの指数にも上位として構成されているため、あまり参考にならない部分もあります。
そこで、「グロースか、バリューか」という点に特化した見方はないかということを考え、次のVG倍率をみてみることにしました。
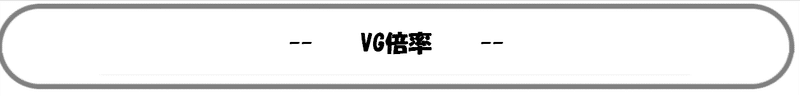
VG倍率については以前にも少し触れたことがありますね。
一般的に使われる言葉では無いため、改めてその定義を確認しておきましょう。
NT倍率が日経平均株価をTOPIXで割って求められる倍率であるのと同様に、VG倍率はバリュー指数をグロース指数で割って求められる倍率とします。
VG倍率 = (TOPIXバリュー指数) ÷ (TOPIXグロース指数)
では、TOPIXバリュー指数とTOPIXグロース指数は何か。
これは上にリンクを貼った過去の(11月半ばの)週間noteにおけるコラム欄『バリュー・グロースの尺度』の中で紹介していますので、再掲しておきます。
一般的に、グロース株とは名前の通り"成長性"が期待されている銘柄、それに対してバリュー株とは"割安"である銘柄を指して使っています。
とはいえ、「成長性があること」と「割安であること」は相反する性質ではないため、「グロースを選ぶか、バリューを選ぶか」という話を聞くと違和感を感じる面もあると思います。
東証ではTOPIXグロース指数、TOPIXバリュー指数という"スタイルインデックス"というもので分けていますので、現時点(23/11/25)での定義をみてみましょう。
まず、TOPIXは”TOPIX 500”と”TOPIX Small”の2つに分かれています。
これは「流動性の高い上位500銘柄」と、「それ以外」という形で分かれており、”TOPIX Small”がいわゆるTOPIXの中での"小型株"の定義となります。
(同様にTOPIX 500のうち、流動性上位100の銘柄である"TOPIX 100"の銘柄が"大型株"ということになります。)
TOPIX500のうち、連結PBR上位約3分の1の銘柄を"TOPIX500 グロース"の構成銘柄に、同じく下位約3分の1の銘柄を"TOPIX500 バリュー"の構成銘柄にします。
残りの3分の1に関しては、浮動株時価総額を半分ずつに分配する形で"TOPIX500 バリュー"、"TOPIX500 グロース"の両方の構成銘柄にします。
(この分け方をみても、「成長性があること」と「割安であること」は相反する性質ではないことが分かりますね)
同様の方法でTOPIX Smallの中でも"TOPIX Small グロース"と"TOPIX Small バリュー"を決め、"TOPIX500 グロース"と"TOPIX Small グロース"を合わせたものが"TOPIX グロース"になるそうです。(バリューも同様に決めます)
(小型と大・中型で予め分けておかない場合、グロースが小型株で占められやすくなってしまうため、まず規模で分割してからバリュー・グロースを決めているのでしょう……)
ちなみに連結PBRとは、(親会社だけでなく子会社なども含めた)連結決算でみたPBRのこと。
PBR(Price Book-value Ratio)は1株当り純資産のこと。
今年は"低PBR"や"PBR1倍割れ"などの用語で話題になりましたね。
これによりTOPIXバリュー、TOPIXグロースが定義づけられています。
さて、再び話をVG倍率に戻すと、
VG倍率 = (TOPIXバリュー指数) ÷ (TOPIXグロース指数)
として求められるものとしました。
これにより、バリュー指数がグロース指数より強ければVG倍率が上昇、逆にグロース指数が強ければVG倍率が低下します。
NT倍率と似ていますが、NT倍率でバリュー・グロースの力関係をみようとしたときに困るのは、大型グロース株が上昇した際、日経平均株価もTOPIXもともに持ち上げられるため、「(グロース・バリュー株の)構成比率がどちらが大きいか」に左右されるという点がNT倍率の値動きにとって重要なのであって、本質的にバリュー・グロースの力の差を見られるものではないという弱点があります。
もちろん、その構成比率が日経平均はグロース優位、TOPIXはバリュー優位と傾向はあるものの、例えばこの前のNT倍率に関する深掘り記事の構成比率の差を見た時にもあった通り、ソニーグループの構成比率はTOPIXの方が高くなっていますので、銘柄によってはグロースであってもTOPIXをより動かすということになります。
その点を補う意味で、VG倍率という「バリュー・グロースではっきりと分けられた指数」の強弱を計る尺度をみてみることにしました。
こちらもまたやや弱点といえる点があります。
それは、TOPIXバリュー指数・TOPIXグロース指数を動かしやすい銘柄がやはりそれぞれあるということ。
例えば、バリュー指数では銀行株の影響が大きいため、株価全体が下がっても銀行株だけは強いという相場ではバリュー指数がやたらと底堅い動きをします。
これは2022年末~2023年の日銀会合においてサプライズ的な政策修正となった際に見られた動きとして経験があります。
この場合は「銀行株・保険株が強かった」のであって、「バリュー優勢」と言っていいのか怪しいですね。
このように、バリュー・グロースそれぞれの中での強弱感にも左右される面があることには注意です。
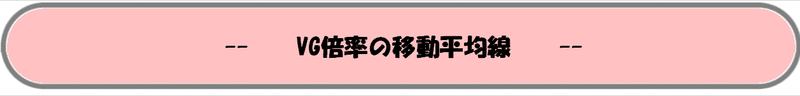
ここから先は
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
