
正解を探すな。まずは苦労を語れ。経営学者・宇田川元一が説く、組織を変える「語り」の力
仕事で正解を探すのは、失敗したくないという感情が働いているため。それよりも信じられるものを見つけて、できることから実践してみて、その苦労を語ることから始めよう。苦労のないところからイノベーションは生まれない。それは、「語り」の中から生まれる。
※EightのビジネスメディアBNLの終了に伴い、許可を得てnoteに転載しています。
記事公開:2017年5月31日

埼玉大学大学院人文社会科学研究科准教授
1977年東京都生まれ。2000年立教大学経済学部卒業。02年同大学大学院経済学研究科博士前期課程修了。06年明治大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得。 06年早稲田大学アジア太平洋研究センター助手、07年長崎大学経済学部講師、准教授、10年西南学院大学商学部准教授を経て、16年より現職。 専門は、経営戦略論、組織論。 主に欧州を中心とするOrganization StudiesやCritical Management Studiesの領域で、ナラティヴ・アプローチを理論的な基盤として、イノベーティブで協働的な組織のあり方とその実践について研究を行っている。
07年度経営学史学会賞(論文部門奨励賞)受賞。
"武器"で問題は解消できない
あるMBAの受講生に、宇田川元一は「なんでMBAを学ぶことにしたの?」と聞いてみた。
すると、「いまの上司に任せていたら会社はうまくいかない。MBAを取ったんだから、わたしの方が正しいことを証明したいんです」と返されて、とてもショックを受けたという。その学生は自分の会社を変えるための「武器(=正解)」を求めていた。それでは問題の核心には触れられないと、宇田川は指摘する。
「本当の問題は上司と自分との間でうまく接点が見つけられないこと。いろんな武器を集めても、根本的な問題の解消にはつながりません」
これは決してMBAの受講生に限った問題ではない。「成功する7つの法則」といった類いのわかりやすい"武器"を並べたビジネス書や経済誌の特集はたくさんある。そうしたコンテンツが必ずしも悪いわけではないが、読み手がその中に正解を求める心理状況はよくないという。
「法則を教える「あっち側」と、自分の日常との間には大きな断絶がある」
「多くの人は会社の中で困っていることに対して、なんらかの答えを探してしまうんです。いわゆるManagement Guru(経営の権威)と呼ばれる人たちの本はよく売れますし、講演会は大変人気がありますが、それによって実際に組織が変わっている実感はほとんどありません。つまり、あっち側(法則を教える側)の世界と、自分の仕事の日常とがつながらない。両者の間には大きな断絶があるように思うのです」
BNLでは、これまでビジネスネットワークを活用して活躍している人たちの話をお届けしてきた。前提として彼らの話に共通しているのは、イノベーションを生み出すには、多様なアイデアをもつ外部の人に会って話すことに価値があるというものだ。
しかし、改めて考えてみると自分の会社に戻って何かを変えられる状況でなければ、わざわざ外に出向く意欲も削がれる。そこで今回は、イノベーションを阻害する組織の問題について、経営学の視点から考えてみたい。
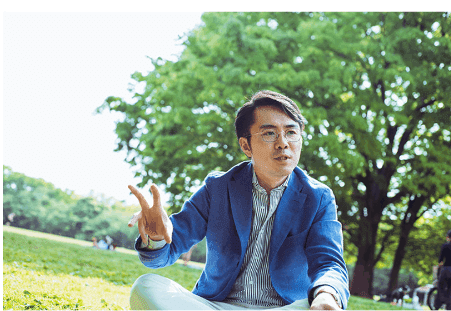
正解を探すより、信じること
ある会社で社員のモチベーションが低いことが明らかな場合、「〇〇をすればモチベーションが上がる」という法則があるとする。いっけん普遍的な正解のように思えるかもしれないが、実際のところはひとつの参照点に過ぎないと宇田川は語る。
法則はひとつの参照点に過ぎない。いまの自分の状況とイコールであることは証明できない
「科学が基本的に目指すところは『y=ax+b』といった、なるべくシンプルな方程式・法則で世界を説明することです。ただし、個々の状況とイコールであることは証明できません」
法則が導き出された状況と、いまの自分の会社の状況がイコールであることを証明するのは難しい。自分の会社にとっての正解を探し続けることよりも、とりあえずその法則を道標に実践してみよう。そこから何か糸口が見えてくることだってあるかもしれない。そう宇田川は助言する。
信じて実践する重要性を説いているのは宇田川だけではない。彼は、ミシガン大学の教授、カール E. ワイクが1980年代の論文に記している、雪山で遭難したハンガリー軍偵察隊の生還ストーリーを例に挙げる。
「まずは信じるものをつくることが大事。ひとつ拠り所となるものがつくれたら、それを媒介にして、次の世界が初めて見えてくる。これはそういう話なんです」
何か面白い話を聞いたとき、それを信じて自分の仕事に取り入れてみる。その話は違う会社の「地図」かもしれないが、その地図の観点から自分の会社を見てみると、何か新しい気づきが得られるかもしれない。
「自分に許されている範囲って意外と広いんです。裁量の範囲でできることをちょっとずつやってみる。そうすると何かが起きて次に活かせる。会社の外で何かいい話を聞いたり、いい考え方を知ったりしたら、それを参照点にして仕事のやり方をちょっと変えてみる。それだけで、世界は少しだけれども確実に、変わるんです」

メタファーは次のメタファーをつくる
雪山のストーリーを用いて実践の重要性を説いたワイクと同時期に、ガレス・モーガン(ヨーク大学特別研究教授)は、メタファー(隠喩)と組織分析の関係を考察した書籍『Images of Organization』を1986年に出版し、ベストセラーとなった。宇田川によると、1990年代に欧州で最も引用された文献なのだという。
「メタファーというのは言語的な活動のひとつですけれども、われわれが日常的に経験する出来事は、言語的な働きを抜きにしてはあり得ない。そうであるならば、言葉が変わることで組織も変わる。それが80年代半ばくらいから段々と明らかになってきたのです」
言葉が変わることで組織も変わる。以前は見えなかった課題や可能性が芽生えてくる
その後、ほかの研究者らによって「カウンターメタファー」の存在が提示された。あるメタファーが表現されることによって、別のメタファー(カウンターメタファー)が対応して出てくるというものだ。
例えば企業がリストラをする時には、「剪定」といったメタファーで語られることが多い。「すっきりさせる」、「枝葉を切り落とす」といったものもある。しかし、そのうち「枯れ木」や「切りすぎてしまった」といったカウンターメタファーが登場する。それは、剪定などのメタファーがなければ表現できなかったものだ。
「何か現象を起こすときには、言語的な何かを通じて語ろうとするわけです。実際に何かをやっていくと、以前は見えなかった課題や可能性が芽生えてくる。それを続けていくと、また別のものが見えてくる。どうやらこの連鎖が起きているのではないか、ということが最近の研究でわかってきたのです」

語る、そして苦労する
法則を教える「あっち側」と、自分たちの日常の間の「断絶」を埋めるために、どのような方法をとればいいのだろうか。宇田川は、対話を促すことで組織の問題を解消に導く手法、「ナラティヴ・アプローチ」を推奨する。
「正解を探す行為は、失敗しないようにする意識が働いているものです。ある会社で成功したことを一般法則にして、自分の会社に移植しようとしている。でも会社によってコンテキストが異なるので、そう簡単に移植できるわけがないんです。当然失敗して、苦労するわけです。そのとき、なるべく失敗しないようにたくさん知識を集めても無駄が増えるだけ。まず失敗を恐れずに自分にできることからやってみる。そこに苦労があれば、その苦労を語ることから始めてはどうかと思うのです」
いい話を聞いたが、自分の会社ではどう適用すればいいかよくわからなくて困っている。そのように語ることで、自分の苦労に気づく。「苦労はあっていい」と宇田川は言う。「それをないものにしようとするから一歩も進まない。言葉にすることで、新しい言葉が見つかる。結局のところ、組織とは、そうやって語ることからしか変わることはできないのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
