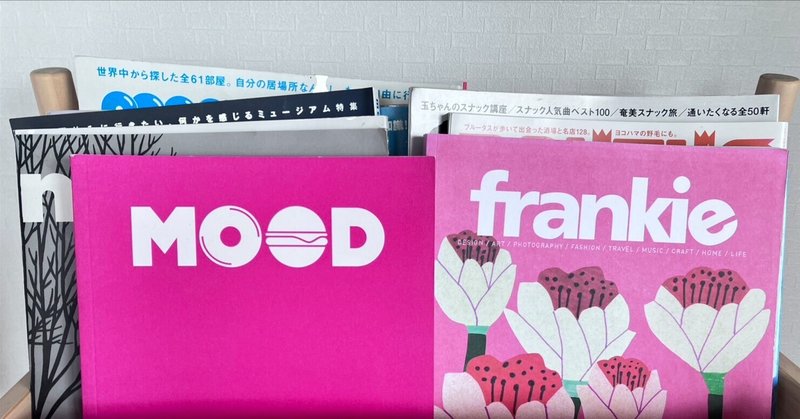
雑誌づくりの現場に未来はあるか?
数年ぶりに雑誌をつくってみて
俺はもともとライター上がりの編集者で、出版社で数年地域雑誌の編集長を務め、その後クリエイティブカンパニーに移り、企業や自治体のブランディングを行ってきた。
4年前に独立し起業、今では企業を中心に戦略設計、ストーリーの構築からアウトプットまでを行っている。
アウトプットは紙もWEBもイベントも動画も店も、課題に最適なものであればなんでもやる。
まあ、簡単に言うとクリエイティブディレクターだ(いつまで経ってもこの肩書にはこっ恥ずかしさを覚えるが)。
そんな自分が、縁あって8年ぶりに雑誌をつくることになった。
校了した今、色々と思うところがある。
出版社の一編集者だった当時には気づかなかった、あるいは気づいていてもスルーしてきたさまざまな問題点が、現在の立場だとありありと見えてきた。
逆に言えば、かつては俺もこのような思想とふるまいを他者に対して平然と行っていたのかと思うと恥ずかしい。
自戒も込めて、この気づきを言語化しておく。
あくまで個人的見解だが、一定の出版社に通底する問題でもあると思う。
リスペクトなき“外注”意識
そもそも、この案件は俺にとってマインドドリブン案件だった。
自分の愛する地域の雑誌をつくりたく、自ら古巣に企画を持ち込んだ。
だから、そもそもフィーなど当てにしていない。
もともと在籍していた会社だから、懐事情はよく分かる。
金についてはなにも言わない代わりに、求めるものはひとつ、「リスペクト」である。
クリエイティブの会社に移ってから、クライアントと制作の関係性はイーブンであるという意識が強くなった。
自分の仕事はいただくフィー以上の価値を提供している自信があったし、クライアントもチームとして受け入れてくれ、平等な関係が築けていた。
逆に言えば、俺が依頼するディレクターやライター、カメラマンなどとの外注者との間にも、上下関係はない。信頼関係で結びついたパートナーである(この外注という言葉も、チーム感がなく嫌な響きがある。よく変換で害虫と出てくるし)。
転職〜独立後はそんな仕事の価値観で、自分の信用するチーム(クライアント含めて)のみとストレスのない仕事をしてきた俺は、今回も当たり前のようにそうしたパートナーシップを期待した。
だが、旧態依然とした出版社において、外注はいまだ問答無用に外注なのである。
版元の編集者は外注に命令する者としての意識が染み込んでおり、やたらとコントロールしようとする。
建設的な注文ではなく、勝手に内容を変更しようとしたり、挙げ句には表紙も意味不明なものを通そうとする(後述する)。
ちなみに担当編集者は出版者時代の一同僚にすぎない。
別に神様のように崇めてほしいわけではない。
それにしても、コンセプトも企画も取材先(彼らはこの地域をまったく知らないのだから当たり前だが)も全部考えて動かしている俺に対し、あまりにも敬意がなかった。
マインド案件なのに、自分のマインドが腐っていく気がした。
外注=暇で金で動く人たち
そもそも、彼らは外注は暇だと思っている。
この企画とて、本来は製作期間は1年、最低でも半年はほしい(優に130ページは超える媒体だ)。
だが、企画提案からしばらくして、急に発行が決定したからと連絡が来て、みれば発売日は4ヶ月後だった。
俺は暇ではない。
その時点では、大きいもので7社のブランディング/クリエイティブ、小さいものを入れれば10を超える案件が同時進行していた。
俺に限らず、クリエイティブで飯を食う人間は、数カ月先まで仕事は確定しているものだ。
逆に、雑誌はいつでも暇な人間を安く使っているから、クオリティはどんどん落ちるのだ。
驚いたのは、「(この案件で)チャリンチャリンだね」と、むしろ儲かる案件のように編集者が言っていたこと。
……いやいや。
俺は自分に時給を設定しており、案件ごとに予算に応じた作業時間を算出している。
この案件は、対予算想定時間と実作業時間の差はなんと-130時間。
大赤字である。
数十万が大金だと思っていることも、業界の闇をあぶり出している。
電話大好き編集者。
コミュニケーションツールがあるのに、バンバン電話が来る。一線で仕事をしている人間の常識だが、電話はいまや緊急事態以外には使ってはいけないツールだ。
一日の仕事の進め方を決めている人間にとって、電話はリズムを乱すノイズでしかないからだ。
俺は基本的に1日2〜3回しかコミュニケーションツールを見ない。そこでまとめて返信する。都度都度見ていては集中力が途切れるからだ。
それなのに「ここの確認ってどうする?」「この表記ってこれでいいの?」など些細なことで1つひとつ電話がよこされる。
当然俺は出ないのだが、それでも頭には残るし、ノイズである。
電話はやめてと言ってもお構いなしだ。
版元に時間感覚がまったくないことの証左である。
人の時間を奪い生産性を下げるのはもはや犯罪である。
セルフコントロールができない環境
出版社の人間が、生産性の意識が低いのは無理のない話かもしれない。
彼らは、毎月のように雑誌を出している。
そうなると、目の前の作業をこなすのに目いっぱいになる。
主体的なコントロール感はなくなり、仕事に追われるようになる。
根本的な業務改善には思い至らなくなる。
今回、俺もそういう状況に陥った。
人間は、自分で自分をコントロールできているかどうかが、心の余裕を生むカギだ。
それが失われると、全体が見通せなくなり不安になる。
不健全な状況では、クリエイティビティも落ちる。
結果として雑誌は売れなくなり、ギャラも安くなり、一緒にものづくりを行うパートナーも離れていく。
制作環境を合理化し生産性を高めることは、実は何よりも優先して行うべき業務なのだ。そのどうでもいい1ページを作る前に、今すぐ。
雑誌は誰のものか?
さて、今回ちょっとした事件があった。
表紙が、俺がつくった覚えのない謎の、不可解で醜いパターンになりかけたのだ。
聞けば、それを指示したのは出版社の社長だという。
この顛末には、見覚えがあった。
俺の出版社時代、表紙を決めるのはお偉方だった。10数回も修正を重ね、最終的に最初の案に戻るなんてことは日常茶飯事だった。
そこにロジックもセンスもない。
その年老いた決済者の趣味と、あさましいプライドしかない。
まさかあれから十年弱たって、それが継承されているとは思わなかった。
当然、社長は今回の雑誌づくりに携わってはおらず、パッと見た印象でのジャッジだ。
それがセンスが良ければ、百歩譲って良しとしよう。
それが、なんとただの丼の写真の切り抜きだった。
この媒体は、食の本でもガイドブックでもない。地域の実情を映し出すライフスタイル誌だ。なのにぴあムックよろしく、どかーんと丼。
俺は目がくらむ思いがして、担当編集に電話した。緊急事態だから、この電話も許してほしい。
なぜこの案じゃだめか、自分の案にどういう意図があるかを、必死に喋った。
そりゃ必死だ。
こんな表紙の雑誌が世に出たら、恥ずかしくて俺は外を歩けない。
さらに、その社長あてに手紙を書いた。
表紙は雑誌の内容を表すシンボルであること、この丼にまったく正当性がないこと、ターゲットとの著しい乖離があること……。
こうした活動を経て、担当編集がなんとか俺の案で通してみようという気概を見せてくれた。そこは大変感謝している。しているが、そもそもこんなことが起きうる構造に問題がある。
現場をなにひとつ知らない人間が、表紙を決める。
あまりに馬鹿げている。暴力的ですらある。
雑誌は、現場でパッションとミッションを持って汗をかく編集者のものだ。
その分、リスクも背負うのだ。
せめて表紙くらい決めさせてくれ。
もしこのやり方を貫いている出版社があれば、即刻現場編集者に判断を委ねるべきである。
広告依存ビジネスの限界
商業雑誌はいまだに広告収入がマネタイズの軸だ。
この雑誌も、営業先をこちらがリストアップして、版元の営業マンとともに当たることになった。
地域の企業と触れること自体は、楽しいことである。
普通に過ごしていては会うことのない地域の中小企業のリアルな課題意識を知れ、傑物の経営者もいる。
だが、その課題解決に誌面がどれだけ貢献できるのか…?
正直言って、2Pや4Pでは、たいした効果もないだろう。
掲載自体が話題になるような有名媒体やニッチな顧客のある媒体以外で、紙媒体に広告を出す意義はあまりない。
もちろん、そうしたブランド価値を得るべく、良い誌面づくりに精進することは忘れてはならない。
だが、上述したようなマインドとクリエイティブ意識の低い編集部でそれができるわけもない。
今回乗ってくれた企業も、課題解決を期待して、というよりはある種の「応援」も込めて出稿いただけたのだと思う。
企業の志を当てにした不確実な戦略が、この業界の柱にあるのである。
メディアを入口に企業課題の本丸へ
このマネタイズ構造をどう変えるべきか?
私見だが、雑誌はあくまでシンボルに過ぎない。目的ではなく手段である。
メディアのいいところは、どんな人や企業とも会えることだ。最強のパスポートだ。
だからまずはメディアで関係性をつくり、そこでのつながりを活かした事業を進めていくべきなのだ。
たとえば今回接触した多くの企業の悩みはブランディングにまつわるものだったし、発信がうまくできていないという意識も多かった。
特に地方の企業では、クリエイターとのつながりは薄く、彼らはそうした人材を欲している。
であれば、それらの企業のブランディングだったりHPだったり紙媒体だったりを手掛け、本質的な課題解決に乗り出すべきである。
ローカル雑誌の可能性は、ここにこそある。
一冊必死に時間をかけて作るよりも、いろいろな意味ではるかにヘルシーだ。
その意味で、雑誌でタイアップページをつくる意義は、彼らから「こいつはできる」という信用を得ること。これひとつである。
仕事の進め方から問いの立て方、コミュニケーション、ページのクオリティ。すべては今後のためのページづくりだ。
なのに、現場ではそのときだけのお付き合いと考えている。
編集者だけでなく、営業マンも!
そこに豊かな金脈が広がっているのに、みすみすとそれを取り逃がしているのである。
雑誌編集屋とビジネスのわからない営業マン
しかし、チャンスを取り逃がすのも仕方がない。
編集者は雑誌編集屋にすぎず、営業マンは経営戦略など描けない。
ものすごい狭い世界で戦い続けているから(でも彼らは何と戦っているのだ?)、ブランディングの発想さえない。
たとえば、俺は今回一つひとつの企業に対して提案を行ったわけだが、同行していた営業マンは驚くわけだ。
「こんなプレゼンなんてはじめてです!」と。
スペシャルなことはしていない。せいぜいパワポで「問いの設定」「コンセプト」「誌面表現案のパターンAB」くらいだ。
営業提案としてむしろミニマムだが、それに驚かれることにこちらが驚く。
つまりは、彼らは「問い」を立てられない。「問い」がないから、「コンセプト」もほんとうの意味での「企画」もつくれない。その重要性すらわかっていない。
彼らが手掛けているのは、文字や写真、イラストの集合体に過ぎない。
編集という“スキル”の拡張
編集はスキルである。
一言で言えば、文脈を可視化するスキルである。
点と点のあいだにストーリーをつくってつなげて表現する術である。
編集はジョブではない。
編集というスキルをもって、雑誌をつくったり戦略をつくったり、イベントをやったりする。
それが編集者だ。
そこにアウトプットに限定した肩書がつくと、途端にその自由な精神は失われる。
雑誌編集者、映像編集者、WEB編集者…。
もちろんひとつのジャンルで腕を磨き、その中でスペシャリストになることは有効だ。
いきなりなんでもできるようになるわけではない。
俺自身も雑誌編集で編集の本質を掴んだからこそ、他のフィールドに転用できている。
しかし、固有のジャンルでのみ活動していると、そこしか見えなくなる。
そうなると、企業や社会の問いに接した時に、課題解決の選択肢が非常に狭まってしまう。
今回で言うならば、雑誌の枠でしかモノゴトを考えられない。
もったいないことだ。
昔から、こうした編集そのものの可能性に気づき横断的な動きを見せる先人たちは一定程度いるのだが、今もなお大多数の人はアウトプットが固定した編集者であることに甘んじている。
編集とは、自由な精神で最適解を生み出すプロフェッショナルではなかったか?
世の編集者は、もっと自由になるべきだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
