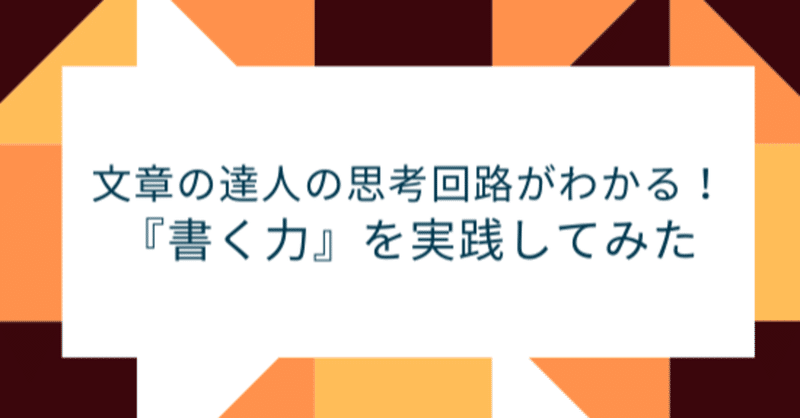
文章の達人の思考回路がわかる!『書く力』を実践してみた
「この本、役に立つの?」
そんな思いを持った方の少しでも力になれればと思い、始めた文章ノウハウ本実践シリーズ。8回目の今回は『書く力』を実践してみました。本書は説明がわかりやすいと有名なジャーナリスト池上彰さんと、読売新聞の一面を下から読ませる男という異名を持つ竹内政明さんの対談形式で進んでいきます。竹内政明さんは読売新聞のコラム「編集手帳」を担当していた経歴もあるのです。だから読売新聞の一面を下から読ませる男なんて呼ばれているんですね。池上彰さんが影で勝手にそう読んでいるだけだそうですが。そんな二人が、あらゆる名文を解説してくれるなんて、そんな贅沢な話はありません。ついつい飛びついてしまいました。その幸せを皆さんにも少しだけ分けようと思います。もちろん実践もします。今回のテーマは著者にあやかって、
もし自分が今編集手帳に一回だけ書くとしたら
を想像して実践したいと思います!
まずはテーマを決める
今の時代にあったテーマといったらやはり新型コロナウイルス関連でしょう。お盆休み前に感染が再び拡大している状況だけど、東京都の1日の感染者数は400人超えたあたりをさまよっています。これから果たしてさらに爆発していくのか、この人数を超えないまま推移して縮小していくのか、どちらに転ぶか不安になっている気持ちを書いていきたいと思います。
「身近な話」には魅力がある
竹内政明さんが面白いな、と思うのは、筆者の半径2,3mの世界で書かれた話なのだそう。池上彰さんはこれに同意していて、
読者は「自分の知らない話」を面白がるものですよね。
と。だから自分の実体験は他人にとって魅力的なものであることが多いのです。さて、ではどんな身近な話を引き出してこようか、と悩みます。これは次の章と合わせて考えた方が出てきやすいので次にいきます。
読者に展開を予想させないブリッジの掛け方
今の日本は感染が拡大しないよう「我慢」しているように見えます。そこで「我慢」をブリッジにするのですが、以前の章の話も考えると
・読者に展開を予想させない
・身近な話
にするべきです。「我慢」と聞いて真っ先に上がってきたのは外出自粛なのですが、これでは面白くない、もっと新型コロナウイルスの話とかけ離れていた方が読者に展開を予想されなくて済む、と思います。
私はここで便意エピソードを持ってきたいと思います。便意と新型コロナウイルス、これなら展開を予想されなさそうです。
「誰に読んでもらうか」を意識する
ざっくりと、30~50代男性で現役のサラリーマンと括りましょう。そうすると、仕事に関するエピソードが良さそうです。便意×仕事 のエピソードなんてそうないな、、どうしましょう。
失敗談こそがもっとも面白い
実践シリーズでも何回か紹介してきたように、人は失敗談こそ読んでくれます。人の不幸は蜜の味とはよく言ったものです。便意エピソードを持ってくると決めたのに、便意の大きな失敗談はありません。だから書くとしても少し工夫しなきゃいけなさそうです。もしあってもありのままのエピソードを書きたいとは思いませんが。
出来上がったもろ流「編集手帳」
これまで紹介した手法を使って作成した文章が以下になります。
こんな経験はないだろうか。大事なプレゼンの前、緊張してお腹を下した。だが、自分の出番まであと5分。気合いで乗り越えよう。自分の出番が回ってきた。話している最中、我慢の限界がきた。拍手を受ける代わりに、そこに本来あるべきでない匂いが充満してしまった。
皆さんはこんな経験ないだろう。私もない。考えただけでゾッとする。だいたいの人は我慢する。さて、1ヶ月後の日本は耐えているのだろうか。
新型コロナウイルスの感染者が再び日本で増加している。東京都で1日の最大感染者数が400人を超えたあたりで上下しているのは、かろうじて、といったとこだろう。もちろん感染拡大の波は東京都だけではない。これ以上の拡大は控えたい。だからお盆休みに入っても移動を控えるよう、首相や知事らが呼びかけている。
日々のニュースを観ていると1ヶ月後の日本はさらにひどくなっているんじゃないかと、嫌でも思ってしまう。仮に我慢ができなかったとして日本中に本来あるべきでない匂いは充満しないだろうが、どんよりとした空気に包まれてはいるだろう。
いかがでしょう。冒頭に失敗談を持ってきたのは、読者を引きつけるためです。先ほども申し上げましたが、人の不幸は蜜の味ですからね。結構強引ではありますが
さて、1ヶ月後の日本は耐えているのだろうか。
とブリッジをかけることで、全体のロジックとして成り立つよう意識しました。起承転結の承→転の部分ですね。転に移行してからどうやって話を締めるか、に関してはここでまだご紹介していない最後をちょっと緩めるに書かれていることを意識しました。気になる方はぜひ本書を手にとってみてくださいね。
文章の達人らの頭の中身が丸見え
池上彰さんも竹内政明さんも面白い文章を書かれる方なのですが、本書では文章の基本みたいなことが多く書かれていました。ただブリッジのかけ方に関しては、
・ES
・ブログ
など比較的長い文章を書く際に必須のスキルかなと思いました。本書ではもっと詳しく書かれています。ぜひ書店で手に取るか、ポチってみてください。
サポートありがとうございます!頂いたサポートは自己啓発のための書籍代に使わせていただきます!!
