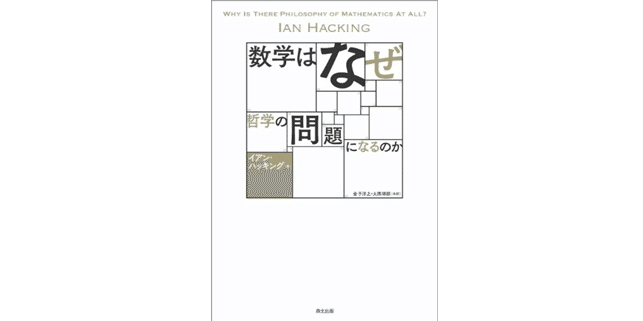『数学はなぜ哲学の問題になるのか』(イアン・ハッキング著、金子洋之・大西琢朗訳) 【訳者あとがき公開】
2017年10月発行『数学はなぜ哲学の問題になるのか』の「訳者あとがき」です。
『数学はなぜ哲学の問題になるのか』訳者あとがき
著:金子洋之
本書は、Ian Hacking, Why Is There Philosophy of Mathematics At All? の全訳である。この書名を直訳すれば「なぜそもそも数学の哲学などというものが存在するのか」という具合になるだろうが、邦訳では『数学はなぜ哲学の問題になるのか』とした。「数学の哲学」という限定的な用語を避けたかったことと、このタイトルでも著者の意図は十分反映されていると考えたからである。他の多くの著作がそうであるように、本書でもハッキングの博学多才ぶりはいかんなく発揮されており、読んで面白いエピソードには事欠かない。とはいえ、その面白さの背後にはかなり鋭い刃が隠されていることは期待していただいてよい。そして本書を理解し味わうために、必ずしも分析的な「数学の哲学」という観点に立つ必要はないのである。実際、ハッキングは本書では「数学の哲学」という用語をかなり広い意味で使っている。
著者のハッキングは、確率論の歴史から、科学哲学、社会構成主義、彼独特の歴史的存在論にいたるまで数々の著作をものしてきた哲学者である。主要な著作の多くは邦訳されているから、いまや彼はわが国でもかなり名前の知られた人物の一人であろう。彼の経歴の詳細は他の翻訳の解説に譲るが、本書でも述べられているように、このように多才なハッキングも、その出発点は実は「数学の哲学」に関する博士論文であった。しかし、このテーマにかかわる論文はその後の経歴の中でいくつか公表されてきたものの、彼自身はこれまで「数学の哲学」を広範かつ本格的に論じてきたわけではない。それが、ここにいたって本書が刊行されたのである。とすると、本書はハッキング自身の「数学の哲学」を満を持して開陳したものなのかと考えたくなるかもしれない。だが、原著のタイトルから推察されるように、この本は、通常の意味での「数学の哲学」本ではない。もちろん、数学について書かれた哲学の本という意味でなら、本書も数学の哲学のまっとうな一冊である。しかし、彼の他の著作、たとえば本書とよく似たタイトルの『言語はなぜ哲学の問題になるのか』や最近訳された彼の出世作『確率の出現』を読まれた方などはお気づきと思うが、本書はそれらと共通する、ハッキングならではのきわめて独特なアプローチで書かれている。
とすると、最初に問題になるのは、本書がどのような意味で通常の「数学の哲学」本ではないのか、そして次に、本書がいったい何をねらった著作であるのか、そして彼の独特のアプローチがいかなるものか、ということであろう。その答えは本書を読めば自ずと、ということになるかもしれないが、ここでは本書の特異性を理解するための手がかりをいくつか指摘して、あらかじめ本書にまつわって生まれかねない誤解を取り除いておきたいと思う。
そのようなことをあえて行う理由は次のような事情にある。本書の刊行以来、かなりの数の書評が出されてきた。私はそのすべてに眼を通したわけではないが、いくつかを読むかぎり、その評価は思ったほど芳しいものではない。ハッキングの独特なアプローチが必ずしも理解されているとは言えないのである。多くの書評が指摘しているのは、本書で用いられている概念の規定が明確ではない(たとえば、「デカルト的証明」と「ライプニッツ的証明」)とか、話に繰り返しが多いとか、全体としてとりとめがないといったようなことである。しかし、そのような評価は、この本を通常の「数学の哲学」についての本の一冊として捉えたことによる誤解であるように思われる。したがって、そのような誤解を晴らし、本書のねらいをいくらかでも明らかにしておくことは、長年培われてきたハッキングの哲学的方法論の一端を明らかにし、ひいては本書の意義をある程度明確化することに資するはずである。
さて、本書は、タイトルからも、また最初の数ページを読んだだけでもわかるように、数学(数学的活動)と数学の哲学についてメタ的な視点から書かれた本である。そういう視点から書かれた書物が興味深いものであるためには、対象となっている活動自体が活況を呈していなければならない。(衰退していく活動についての面白い研究はもちろんたくさんあるが、もし「数学の哲学」が誰も顧みないような領域ならば、それについてあえて歴史的なメタ認識論を試みる意義は大きくないだろう。)あるいは、そうした活動が少なくともリサーチプログラムとしてあまり退行的であってはまずいであろう。(ただし、リサーチプログラムという語を使ったからと言って、そこに単一の方法論的な何かがあると言いたいわけではない。)その点では、数学的な活動については何も問題はないように思われる。現在の数学研究が停滞しているという話は聞かないし、数学の諸分野への応用が行き詰っているという話も聞かないからである(本文で指摘されているように、もちろんそこに何の変化もないということではない)。
では、数学の哲学についてはどうであろうか。じつは、数学の哲学もここ数十年はたいへんな活況を呈している。このことはわが国の状況を見ているだけではわからないかもしれないが、少なくともハッキングをとりまく文化圏においては、刊行される書籍や論文の数も膨大であるし、博士論文産出の機構としても機能しているのである。『フィロソフィア・マセマティカ』という数学の哲学に特化した雑誌も出版されているくらいである。そして、大事なのは、こうした数学の哲学の隆盛がここ数十年の特異な一時的現象ではないということである。二千数百年に及ぶ哲学の歴史において、数学をめぐる哲学的議論の活発化は何度も生じてきた。ハッキングは、これを本書では「永続的」という言葉を使って言い表している。まずは、このような背景的状況を踏まえておきたい。
では、こうした数学の哲学が繰り返し活発化してきたという歴史的事実から、われわれは何をくみ取ることができるであろうか。議論が活発に行われるということは、そこに異なる意見の対立があるということである。そして、その対立が十分に解消されないまま、歴史的に見て、そうした対立が何度も繰り返されている。もちろん、そこで生じている対立が、いつも同じ話題をめぐっての対立だというわけではない。しかし、こうも繰り返し対立が生じてきたという事実は、数学、あるいは数学的活動そのもののうちに、そうした対立を引き起こすような何らかの要因があるのではないか。ひどく大雑把に言えば、本書の大筋をこのような流れの話として読むことはできるかもしれない。そして、数学的活動のうちにあって、哲学的な対立を引き起こす要因が何であるかについての示唆も本文中にはきちんと述べられている。
先に、本書が通常の「数学の哲学」の本ではないということを述べた。それがどういうことなのかを次に見てみよう。こういう場合、通常の「数学の哲学」についての本をもってきて比較してみるのが手っ取り早い。次は、シャピロという人が書いた数学の哲学への入門書『数学を哲学する』(筑摩書房,2012年)からの一節である(自分が翻訳した本を持ち出すのは気が引けるが、他に適当な邦訳がないので、あしからず)。
この本は数学についての哲学書である。まず、形而上学の問題がある。数学は何についてのものなのか。それは主題となる対象をもつだろうか。この主題となる対象は何か。数、集合、点、線、関数、等々は何か。それから意味論的な問題がある。数学的言明は何を意味するのか。数学的真理の本性は何か。そして認識論。数学はどのように知られるのか。その方法論は何か。観察が入り込んでくるのか。それともそれは純粋に心的な活動なのか。数学者たちの間での論争はどのように裁かれるのか。証明とは何か。証明は、絶対に確実で、合理的な疑いを免れたものなのか。数学の論理は何か。われわれの知りえない数学的真理は存在するのか。(シャピロ,邦訳,iv)
数学の哲学における多くの本、とくに分析的な数学の哲学の本は、典型的には、上の引用にあるような問いに対して答えを与えようとする。たとえば、「数学は何についてのものなのか」という問いについてであれば、プラトニストは「数や集合といった抽象的な数学的対象が存在し、数学はそれらの対象に関する真理を明らかにする活動だ」と主張するだろうし、構造主義者ならば、「そのような対象は存在せず、あるのは一定の構造だけだ」と答えるであろう、という具合である。しかし、ハッキングは本書においてこのような答えを探ろうとしているわけではない。
それでは、ハッキングはいったい何をやろうとしているのか。彼は一応は分析哲学の系統に属する哲学者だとみなされているし、本人もそう自覚している。しかし彼自身は、分析哲学の方法、あるいは分析哲学的な問題設定をつねに全面的に肯定しているわけではない。とくにフーコーからの明らかな影響のもと、彼は様々なところで次のように指摘している。すなわち、重要なことは、ある哲学的な問いが発せられ、その問いにいかに答えるべきかが論じられるとき、そこには、暗黙に一定の前提がはたらいているということである。ハッキングは、そのような問いにいかに答えるかよりも、その問いそのものが、あるいはその問いを含む問題圏が、いかにして成立しているのかに興味を抱いている。ここはハッキング自身に語ってもらうほうがよいかもしれない。次は、『知の歴史学』の第13章「ライプニッツとデカルト―証明と永遠真理」からの一節である。
というのは、いまある憶測が私の頭を悩ませているからだ。それは証拠があることでもないし、独創的なものでもないが、こういうことである。すなわち、哲学的問題の「空間」は、それらの問題提起をそもそも可能にしている条件によって、大部分決定されるのではないか。ある問題は、ある一定の概念を用いることではじめて、一個の問題として立てられる。そして、それらの概念を用いてそもそも何ができるかは、当の概念が出現してくるための前提条件によって、呆れてしまうほどに決定されてしまっている。そうした「問題の空間」のもつ性質をわれわれは認識できないが、それが容易には見通せないほどの広がりをもつこともまた確かである。問題の肯定的な解決であれ、否定的な解決であれ、さらには問題の解消であれ、結局それらはすべてそうした空間の内部で行われるのではないか。(邦訳,pp.396-397)
この発想を、ハッキングはのちに「推論のスタイル」および「歴史的存在としての概念」というアイディアにつなげていく。このうち、前者の「推論のスタイル」は、本書でも第4章の22節で「科学的推論のスタイル」として取り上げられている。また、後者についても、第1章にある一文「証明こそが現在の数学者たちが目指す最高基準である(そしてかつてはユークリッド的な最高基準であった)というのは、偶然的な歴史的事実にほかならない」からも推察されるように、本書の基調を形作っている。つまり、「証明」のような概念ですら、特定の時代や文化に限定された概念であり、ある特定の推論スタイルのもとで初めて、「証明」が証明としての意義をもちうるのだとハッキングは言いたいわけである。もう少し言えば、ハッキングは、何が真で、何が偽であるかに興味を抱いているわけではない。彼が関心を抱いているのは、あるものを真であったり、偽であったりする候補とするものは何か、ということである。あるものをそうした候補にするものが、上で言う「問題の空間」であったり、「推論のスタイル」だったりするわけである。そしてそのような空間やスタイルを探るには、そこに登場する概念がどのような歴史的経緯を経てきたかをたどってみるしかないのである。
もしハッキングがこのような関心を抱いているのだとすれば、通常の「数学の哲学」で扱われるような問いそのものについて彼が比較的冷淡である理由も明らかであろう。彼はそもそも「数学が何についてのものか」とか「数学的真理の本性は何か」といった問いに答えようとはしていないのである。彼がやろうとしているのは、そのような問いを成立させている数学の哲学の問題圏そのものの由来を問い、その問題圏を成立させている基本前提を明らかにすることであり、そうした基本前提のなかでわれわれが暗黙に受け入れてしまってきた前提を問い直すことなのである。
そのように見てくれば、本書の全体的な構造も比較的容易に理解できるのではないだろうか。たとえば、現代の数学の哲学は、「数学」というものを「当たり前のもの」として、すなわち「誰から見ても数学が何であるかは明らかなもの」として受け取っているのではないか。だが、そのようなことをはたして前提にしてしまってよいのだろうか。この問題は、本書の第2章で集中的に扱われている。次に証明。われわれは、数学には証明がつきものだと思っている。そして、「証明」とか「合理性」といった概念は、「誠実さ」とか「狂気」のような概念とは異なり、固定的で、時代や社会によってその中味が変わるようなものだとは思っていない。だが、すでに先取りして述べたように、ハッキングによればそれは思い込みである。ハッキングは、「デカルト的証明」と「ライプニッツ的証明」という両極端な捉え方を提示しつつ、「証明」概念が多様なものであること、さらには証明のない数学の可能性までも考察している。これが第4章である。そして第5章では、同様の問題意識でもって、数学の「応用」や純粋数学と応用数学の区別が取り上げられている。
そして最後に6章と7章。第6章では、数学者が自らの数学的活動(あるいは数学的生活)をどのように捉えているのかという観点から、プラトニズムという哲学的態度(ここは学説ではなく、態度であることが重要)とプラトニズムに反対する哲学的態度とが比較対照されている。これは、第7章で、哲学者のプラトニズムや反プラトニズムを、数学者のプラトニズムや反プラトニズムと対比するための背景を用意するという意味もある。その上で、第7章において、現代の数学の哲学における中心的な論争、すなわちプラトニズムと唯名論の論争がいかにして成立してきたかが論じられるのである。ここにいたって、ハッキングは、議論の対象を、「証明」や「応用」といった個別的な概念から、「プラトニズムvs反プラトニズム」の論争そのものの来歴へとシフトさせている。そして、そのようなプロセスを介して、彼は、これまでの「数学の哲学」が暗黙の前提にしていた事柄のいくつかを明快に取り出してみせている。以上が、本書の大まかな流れである。
こうした全体的な流れのなかで大事なのは、これらの議論を、ハッキングは概念的な分析によって行っているのではなく、歴史的な様々な事実の積み重ねをもって行っているということである。だから、これらの章での議論は、すべて上で指摘したハッキングの方法論――「推論スタイルの分析」や「歴史的な存在としての概念」――を数学に適用した結果にほかならない。
数学の哲学という分野では、近年、数学的活動を捉えるために使われる様々な既成の概念を自明のものとすることをやめて、それらをもっと社会学的な視点から理解しようとしたり、歴史的な文脈に位置づけられたものとして理解しようという傾向が強まってきており、その一部は本書でも言及されている。とはいえ、本書におけるハッキングほどそれを徹底した哲学者はほかにはいないように思われる。
出典:『数学はなぜ哲学の問題になるのか』訳者あとがき
【訳者紹介】
金子洋之(かねこ・ひろし)
1956年、北海道生まれ。北海道大学大学院博士課程単位修得退学。専修大学教授。専門は論理学、数学の哲学、言語哲学。著書に『記号論理入門』(産業図書,1994年)、『ダメットにたどりつくまで』(勁草書房,2006年)など、訳書に『フレーゲ著作集3』(共訳,勁草書房,2000年)、スチュワート・シャピロ『数学を哲学する』(筑摩書房,2012年)などがある。
大西琢朗(おおにし・たくろう)
1978年、香川県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。2019年現在、京都大学特定准教授。専門は論理学、論理学の哲学。論文に「間接検証としての演繹的推論」(『科学基礎論研究』42-2,2015年)など、訳書にイアン・ハッキング『知の歴史学』(出口康夫,大西琢朗,渡辺一弘共訳,岩波書店,2012年)がある。
****
――イアン・ハッキング、「数学の哲学」を語る。
「なぜ数学では“証明”ができるのか?」
「なぜ数学は“応用”できるのか?」
数学者や哲学者がそう問うとき、「数学」「証明」「応用」は何を意味しているのか……。
自身もまた「数学の哲学」からキャリアをスタートした科学哲学の巨人、イアン・ハッキングによる、本テーマ初の著作。プラトンに始まる古今の哲学者から、親交のある現代数学者の見解までを取り込み、数学とは何か、数学の哲学は何を問題にしてきたのかを、独自の視点で描き出す。
【目次】
第1章 デカルト的序論
第2章 何が数学を数学たらしめているのか
第3章 なぜ数学の哲学というものが存在するのか
第4章 証明
第5章 応用
第6章 プラトンの名において
第7章 プラトニズムに対抗する立場
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?