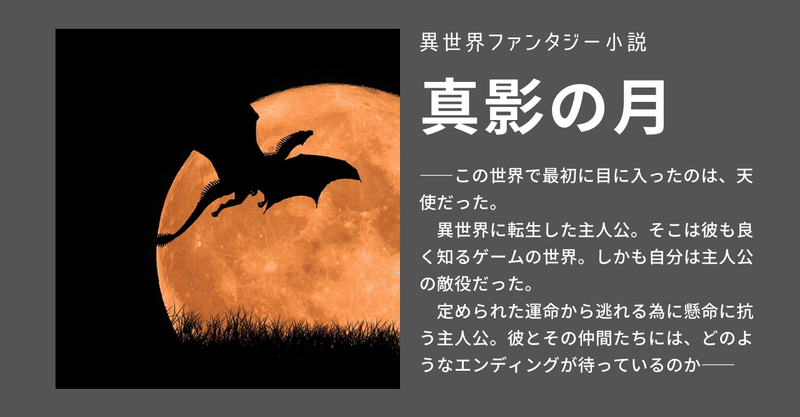
真影の月 朔の刻:第15話 自分が何者かを忘れそうになる
レイモンドは二週間後には必要な準備を終えて、レインウォーター伯爵領に発つことになった。戻ってきてすぐに次の準備をしていたのだ。二週間という期間は、レイモンドではなく同行者の準備の為に必要な期間だった。
前回と異なり、今回はかなり大所帯になっている。子爵夫人であるキャサリンが同行する為に、付き従う者の数も荷物も前回の何倍にもなっていた。
レイモンドの望むものではないのだが、キャサリンを誘ったのはレイモンド自身だ。それにキャサリンに不自由な思いをさせるわけにはいかないという気持ちもあって、何も意見を言うことなく好きにさせていた。
準備が整い、いよいよ出発。
レイモンドとキャサリン、そして近習の者たちが乗る馬車が一台。キャサリンの侍女たちが乗る馬車が一台。さらに荷馬車が三台という行列が出来上がっている。
護衛の騎士の数も前回とは大違い。二十名の騎士が前後左右を囲んでいる。
これは前回、レイモンドを軽視していたというわけではない。荷馬車のうち一台はレインウォーター伯爵家への贈答の品が積まれている。急ぎで用意した物だが、それでもそれなりに高価な品ばかり。盗賊などに狙われる可能性が遥かに高くなっているからだ。
街道をゆっくりと進む馬車の行列。普通であればレイモンドがストレスを溜める状況なのだが、今はそうはなっていない。
「今日も晴れて良かったわ。見える景色がとても綺麗ね」
目の前で子供のように無邪気に旅を楽しんでいるキャサリンが、旅の間のレイモンドの癒しとなっていた。
「もう見慣れたでしょう?」
景色といっても街道沿いの景色など、それほど大きく変わるわけではない。少なくともレイモンドは外の景色にすでに飽きている。
「そんなことないわ。街を出るのは久しぶりですもの。まだレイが小さかった頃に避暑地に行った以来かしら?」
「……そんなに?」
避暑地に連れて行ってもらった記憶がレイモンドにはない。つまり物心がつかないくらいに小さかった時ということだ。
「仕事が忙しくなって、家族旅行なんて行けなくなったから」
「そうですか……」
ずっとマルケットの街に閉じこもったままの生活。それで幸せだったのかとレイモンドは考えてしまう。
これは異世界人としての感覚だ。これから向かうメルク村には、一度も村を出たことがないという人は沢山いる。この世界では、そういう人の方が圧倒的に多数なのだ。
「どうしたの?」
正面に座っているキャサリンにはレイモンドの表情の変化は丸見えだった。
「いや、退屈じゃなかったかなって」
「そんなことないわ。レイの成長を見ているだけで毎日楽しかったわ」
「そうか。本当にそう思ってくれているなら良かった」
「……なんだか大人びて。子供って数日で成長するのね?」
旅の間、レイモンドは何かとキャサリンに気を使っている。気持ちだけではなく、行動でも大切に扱われているのをキャサリンは感じていた。まるで恋人か夫のような振る舞いだと。
「さすがに数日はない。これだけ一緒にいるのは久しぶりだから、そう思うのではないですか?」
そして、レイモンドにとっては一緒に過ごしていると意識した初めての機会。こうした時間を過ごせば過ごすほど、気付かないうちに子供としてのレイモンドの意識を超えそうになっている。
「そうかもしれないわね。これから会う人たちも貴方を成長させた人たちかしら?」
「どうだろう? そうだとも思えるし、まだそれほどでもないとも思う」
メルク村で過ごした時間は八日に過ぎない。それで自分の成長に影響を与えているとはレイモンドは思えない。
「そう感じるということは、その人たちは貴方にとって大切な人たちということだわ」
「どうして?」
「だって自分を成長させてくれると、頭ではなく心で感じているということでしょ? そういう人とは、なかなか巡り合えないわ」
キャサリンの話も理屈ではなく直感的なものだ。そうであることが、レイモンドの気持ちを揺らした。
「……そうなのかな?」
「そうよ」
「そうか……」
敵キャラである自分にも運命の出会いというものがあるのかもしれない。だが、それは不幸に向かっての出会いである可能性が高い。レイモンドの気持ちは複雑だ。
「……レイモンド様。そろそろ」
同乗していたデニスが声を掛けてきた。メルク村にまもなく到着するのだ。レインウォーター城に寄ることなく、真っ直ぐにメルク村に向かって来た。
レインウォーター城に先に寄ってしまうとメルク村に向かう説明をしなくてはならないからだ。レイモンドだけであればまだしも、キャサリンまでが同行するとなれば、何事があるのかと怪しまれるに決まっている。それが面倒だった。
「母上、ここで二つに分かれます。こんな大勢で押しかけては村の人たちが驚いてしまいますので」
「そうね」
キャサリンの同意を得たところで、レイモンドは馬車を止めさせて外に出る。メルク村に連れて行く者を選別する為だ。
選んだのは騎士を四人だけ。本当は近習だけで十分だと思っているのだが、それでは揉めると思って、騎士を最低限連れて行くことにした。それでも騎士たちは不満気だが、レイモンドの指示に正面から逆らうわけにもいかず、何も言わないでいる。
残りの者たちはレインウォーター城に向かわせる。レイモンドたちは後からゆっくり来るという言い訳を持たせて。
馬車一台となったレイモンドたち一行は、メルク村に向かって進んだ。
レイモンドたちの到着にメルク村の住人たちは驚く……様子は全くなかった。
「おや、到着かい。今回は人数が多いね?」
顔見知りの村人がレイモンドに親し気に話しかけてくる。話しかけてくるのは、前回それなりに親しくなった覚えがあるレイモンドも気にしない。気になるのは、村人が到着を知っていたかのように話して来たことだ。
このレイモンドの疑問は、続く言葉ですぐに解けることになる。
「妹さんが待ちくたびれてるよ」
「えっ?」
レイモンドには妹などいない。だが、メルク村でこれを言われれば、一人の女の子が頭に浮かぶ。
「レイ! 遅かったね!」
頭に浮かんだ女の子が駆け寄ってきた。クレアだ。
「どうして?」
「先触れを出したじゃない。来ることが分かっていれば、後のレイの行動なんてお見通しよ」
いきなりレインウォーター伯爵家に行くわけにはいかない。訪問を事前に告げる使者を先に送り出していたのだ。クレアはそれだけでレイモンドの行動を読んで見せた。レイモンドが用があるのはメルク村だけと分かっているのだ。
「お見事というべきかな?」
「そうでしょ?」
誇らしげな様子のクレア。だが、この表情が掛けられた声で一変することになる。
「クレアさんも来ていたのね?」
レイモンドの後ろにいたキャサリンがクレアに声を掛けてきた。
「えっ? ええっ?」
レイモンドの行動は読み切ったクレアだったが、キャサリンまでメルク村に同行してくるとは思っていなかった。まさかの事態に、素直に驚きを表に出している。
「あら、驚いたのはこちらの方よ。よく分かったわね?」
「あ、はい。レイは剣の修行に夢中なので、まっすぐにここに来るだろうと考えました」
「そう。それは大したものだわ。レイの考えを知ることが出来れば、気配りも出来るでしょう。きっと良い妻になれるわね?」
「はい! あっ、ありがとうございます」
キャサリンに褒められて、有頂天になっているクレアだった。
「母上。ここではレアと、そして俺の妹ということで」
小声でレイモンドはキャサリンに告げてきた。クレアがレインウォーター伯爵家の令嬢で、自分の婚約者だという事実は、出来ればクレア村の人たちには知られたくないのだ。
「どういうことかしら?」
「領主の娘だと知れると、クレアが不自由します。ここでは俺もクレアも気兼ねなく過ごしたいのです」
「そういうことなのね。でもそうなるとクレア、レアは私の娘ということになるわね?」
悪戯っぽい笑みを見せて、キャサリンはレイモンドにこれを話してきた。やはり普段とは違って、少し浮かれているのだ。
「そうか。そうなりますね。レア、母上は母上だから」
「あっ、そうね。でも……」
キャサリンに娘の振りをして馴れ馴れしく接して良いのかと、クレアは戸惑いを見せている。
「練習だと思えば良いわ。いずれはそうなるのだから」
「はい! お母さま!」
実にあっさりとクレアは気持ちを娘に切り替えられたようだ。
「レア、それで師匠たちは?」
「広場にいるわよ」
「じゃあ、母上。師匠と兄弟子たちを紹介します。こちらへ」
「そう、いよいよね。楽しみだわ」
レイモンドの後に続いて、キャサリンは広場に向かう。クレアはその後に、そしてデニスと共に、何だか分からないまま騎士や侍女が続いていく。
クレアの言う通り、広場にはマーヴィングと子供たちが集まっていた。レイモンドたちを待っていたわけではなく、普段通りに剣の鍛錬を行っているのだ。
そこに現れたレイモンドたち一行。
レイモンドが来ることは分かっていたが、その母親まで付いてくるとはマーヴィングたちは知らされていない。レイモンドの到着を伝えたクレアが知らなかったのだから当然だ。
広場は思わぬ緊張状態に包まれることになった。
「こ、このような、場所に、わざわざ、お越しくださり」
マーヴィングがひどく緊張した様子で挨拶を述べている。子供のレイモンドやクレアであれば、まだ普通でいられるが、キャサリン相手ではそうはいかない。
貴族としての風格のようなものをキャサリンは発している。本人は意識していないのだが、大勢の前に出ると自然とそうなっていまうのだ。
「らしくない。もっと普通に話せば? 俺の師匠なんだから」
「師匠だからって無礼を働くわけにはいかんだろうが?」
レイモンド相手とあって、マーヴィングの口調は滑らかだ。
「身分に関係なく弟子は師匠に敬意を払うものだ。弟子である俺の母上だから、かしこまる必要はない」
「……屁理屈にしか聞こえん」
実際に屁理屈だ。敬意を払われる立場だからといって、無礼が許されるはずがない。
「そのようなことはお気になさらずに。今回の旅行はお忍びくらいのつもりでおります。貴族として振る舞うつもりもありませんし、扱われたくもありませんわ」
「……そこまでおっしゃるなら。息子さんに剣を教えておりますマーヴィングと申します。どうぞよろしく」
「マーヴィング殿。お名前は聞いておりますわ。騎士をなさっていたのね?」
マーヴィングの振る舞いがこれを示している。騎士と何度も接しているキャサリンにとっては、明らかなことだった。
「ずいぶんと昔のことです。今は趣味で剣を教えているだけです」
「良いですわね? 好きなことを続けられて。羨ましいわ」
「それは……はい、そう思います」
何かを言いかけたマーヴィングだが、何も口にすることなく、キャサリンの言葉を肯定した。
「鍛錬の邪魔をしてはいけませんわね? 私は横で見学させていただきます」
「ああ、では、こちらへ」
マーヴィングはキャサリンを椅子の置いてある場所に案内しようとしている。いつも自分が鍛錬の様子を見ている場所だ。
「俺は?」
キャサリンを連れて、この場から去ろうとするマーヴィングにレイモンドは自分はどうすれば良いのか尋ねてきた。
「到着したばかりだ。今日は皆と一緒に行動しろ。どうせ、立ち合いは出来ていないのだろ?」
「分かった。じゃあ……」
「じゃあ、私と立ち合いね!」
レイモンドに立ち合いが許されたとなれば、クレアが他人に譲るはずがない。
「……ほどほどに」
キャサリンの前では嫌だとも言いづらく、レイモンドは渋々、受け入れた。ただ、キャサリンの前で女の子にコテンパンにやられるのも、出来れば避けたいところだ。
「それじゃあ、鍛錬にならないわ。全力で行くわよ」
残念ながらレイモンドの思いはクレアには伝わらなかった。どうして、こちらにとって都合の良いことは伝わらないのだろうと思いながらも、レイモンドは広場の中央に歩いていく。
中央で向かい合うレイモンドとクレア。その様子をキャサリンは椅子に座って眺めている。
「レイは少しは強くなりましたか?」
「正直申し上げればまだまだです。今は基礎を固める時期と考えております。前回はほとんど立ち合いもさせませんでした」
「それで強くなれるのかしら?」
レイモンドは信頼しているようだが、だからとってキャサリンもマーヴィングを信頼出来るわけではない。無名の退役騎士だ。内心ではもっと優秀な剣の師匠はいるだろうと思っている。
「しっかりした基礎がなければ高く積み上げることは出来ません。息子さんの目指す場所は、かなりの高みのようですので」
「……あの子はそんなに強さを求めていたのですね」
「そのようです」
話をしている間に、レイモンドとクレアの立ち合いが始まった。本気でといっていたクレアは、言葉通りの本気のようで、レイモンドはクレアの速さに全く付いて行けていない。
「あらあら、目指す場所は遠そうだわ」
「相手が悪いですから。他の子供相手であれば、それなりに太刀打ち出来ます」
「……レアが凄いのね?」
「ええ。世の中は不公平だと思ってしまうくらいに」
クレアの強さは才能によるものだ。それをマーヴィングは不公平だと感じている。クレアがどうということではなく、ずっと昔から感じていたことだ。
「レイには才能はないのかしら?」
「全くないとは申しません。しかし、才能の質が違います」
「才能の質とは何ですか?」
「レイの才能を花開かせるには血のにじむような、という表現でさえ生ぬるいと思える努力が必要です。努力を不要とする真の天才とは違います」
「それは喜べないわ」
血のにじむような努力さえ、キャサリンはレイモンドにさせたくない。そうであるのに、マーヴィングはそれを超える苦痛がレイモンドには必要と言っている。
「……喜ぶべきです」
「どうして?」
「人殺しの才能がない。これは母としては喜ばしいことではないですか?」
「……そうですわね」
「だが、レイはその才能を望んでいる。辛いのは彼であって周りの人間ではない」
「……それは母親というものを知らない人の発言ですわ。子の痛みを自分の痛みとして受け取るのが母親というものです」
キャサリンの普段の気の強さが表に出てきた。レイモンドの気持ちが分からないと言われたことが、納得いかないのだ。
「これは失礼しました。確かに女性が子に向ける愛情は私には分かりませんな」
「いえ、私も失礼を申しました。母であろうと父であろうと、子供に向ける愛情は同じはずですわ」
「……また失礼を申し上げますが、必ずしも同じとは言い切れないと思います。男親が息子に向ける愛情は、母親のそれに比べれば淡白なものです」
「……そうなのですね」
マーヴィングの言葉はキャサリンには少し辛かった。自分の夫がレイモンドに向けている愛情は、確かに自分のそれと同じとは思えない。
「一つ込み入ったことを伺ってもよろしいですか?」
「何でしょうか?」
「レイには何がありました? 彼はとても十才の子供とは思えません。妙に大人びていて、どこか達観していると思えるところまであります」
「……周囲に認められておりません。ただこれだけなのかは母である私にも分かりません。レイはもう親離れを、それを超えて、ずっと遠くに行ってしまったように感じています」
キャサリンにもレイモンドは随分と大人びているように見える。子供としてではなく、一人の男性として振る舞っているように感じていた。母親としては寂しいことだ。
「そうですか。では彼女に期待するしかありませんな」
マーヴィングはキャサリンの言葉を違う意味でとらえた。
「彼女?」
「レア。彼女はレイモンドを繋ぎ止める鎖になれるかもしれない」
「……レアのことを? いえ、それよりもレイモンドには鎖が必要なのですか?」
マーヴィングはクレアの正体に気が付いている。それが分かったキャサリンだが、それ以上に驚いたのは鎖という言葉だ。自由を奪う鎖がどうしてレイモンドに必要になるのか、理由は分からなくても不安にはなる。
「母である貴女にとってはです。申し訳ありませんが、師としては、どこまでも飛んで行って欲しいと思っております」
「あの、どうして、そこまでレイに期待を?」
目の前で立ち合いをしているレイモンドは、女の子であるクレアに圧倒されている。マーヴィングも天才と呼べるような才能はないとはっきりと言った。そうであるのに、マーヴィングがレイモンドに期待を寄せる理由が分からない。
「どうして……?」
キャサリンの質問にマーヴィングはハッとした顔をして、そのまま琥珀色の瞳をキャサリンに向けて固まってしまった。
「……あの?」
何故か空虚さを感じてしまうマーヴィングのその視線にキャサリンは不安を感じてしまう。
「あっ、失礼しました。何故か分からなかったものですから、自分で自分に驚いてしまいました」
マーヴィングの表情に感情の色が戻る。恥ずかしそうにしながら、視線を広場の中央に戻した。
「それは……変ですわね?」
「はい。何なのでしょう? 弟子をやる気にさせるのが師の役目であるのに、どうやら弟子にやる気にさせてもらっているようです」
「まあ、それは良かったわ。レイモンドもお役に立てているのね?」
「……そうですな」
マーヴィングの表情に今度は愁いが浮かんだ。マーヴィングにも何か特別な事情があるのだと感じたキャサリンは、難しい話は止めることにした。
深く話をすればするだけ不安になってしまいそうに思ったからだ。
村の暮らし、特産品など他愛もない内容で会話を紛らわす。そんな会話でマーヴィングの気持ちも解れたのか、キャサリンの知らない村の生活を色々と語り始めた。
「……楽しそうですね?」
不機嫌な声が二人の会話の邪魔をしてきた。
「あら、レイ。鍛錬は終わったの?」
「……いえ、少し休憩を」
自分の立ち合いを見ていなかったと知って、さらにレイモンドは不機嫌そうになる。
「膨れないで。途中まではきちんと見ていたわ。レイは、まだまだ頑張らないとね?」
「……ええ」
見られていても、やはり不機嫌になるのは変わらなかった。
「レイは頭で考え過ぎなのよ」
一緒にやってきたクレアが後ろからレイモンドの駄目な所を指摘してきた。
「勘に頼るのか?」
「勘じゃなくて、感じるの」
「それが勘だろ?」
「違うわ。ちゃんと分かるもの」
「……それって」
誰にでも出来ることではない。マーヴィングがキャサリンに話した努力の要らない真の天才。生まれ持った天性の才能がもたらすものだ。
これはレイモンドにはない。ヒロインと敵役の格差というものを、またレイモンドは感じた。
「慣れれば出来るようになるわ。だからレイも頑張って」
「ああ……」
慣れても出来るとは思えない。レイモンドに出来るとすれば、ただ修練の積み重ねで身につけるしかない。そもそも身につけられるかも分からないが。
「レア! レイとの立ち合いが終わったなら、俺の相手をしてくれ!」
広場の真ん中でブラッドが叫んでいる。
「行って来れば? ブラッドはレアじゃないと鍛錬にならない。一緒に大会に出るんだから協力しないと」
ブラッドの願いを無視しようとしているクレアに、レイモンドは立ち合うように言う。半ば本心、もう半分は自分の鍛錬に専念したいからだ。
「……分かった。じゃあ、行ってくるね」
「ああ」
少し躊躇いを見せながらも、クレアはレイモンドの言うことを聞いて、ブラッドの所に駆けていく。
「さっきも思ったけど、レアは雰囲気変わったわね?」
「えっ? そうですか?」
「レイ相手だと、年相応の顔を見せているわ。うまく行っているようね?」
レイモンドとクレアの関係が明らかに深まっている様子を見て、キャサリンは喜んでいる。
「……どうでしょう?」
レイモンドの感情は複雑だ。関係をどうしようと意識はしていないが良好に見えるのは悪いことではない。ただ、それをキャサリンが喜んでいるのが気に入らない。
こう思うことが根本的に間違っているのだが、レイモンドは分かっていない。
「大切にしてあげなさい。決して寂しい思いをさせては駄目よ?」
「……はい」
こういう言われ方をされてしまうと、レイモンドも素直にそうしようと思うしかない。だが、それ以上に、今寂しい思いをしているであろうキャサリンを何とかしてあげたいとも思ってしまう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
