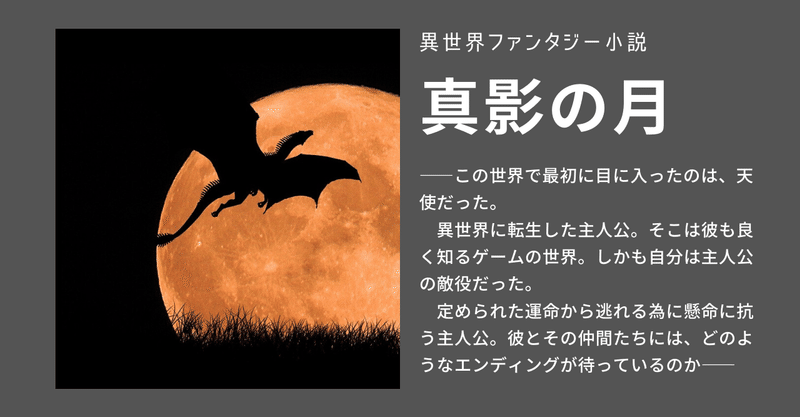
真影の月 上弦の刻:第89話 物語は新展開を迎える……はず
城内の大広間。普段は舞踏会などに使われるその場所だが今は、煌びやかではあるが無骨な雰囲気に包まれていた。その場に集まっているのは騎士団の制服に身を包んだ軍部の高官たち。行われているのは王国騎士団の入団式だ。
近衛騎士団長や王国騎士団長といった各騎士団の頂点とそれに続く武将たちに囲まれて、やや緊張した面持ちで中央で整列しているのが新入団の騎士たち。
アーサーやランスロットたち、そしてクレアの顔もその中に並んでいる。総勢で二百名。これが今年の騎士団への入団者。例年に比べると異常なほどの大人数となっている。
その新入団騎士の緊張がさらに高まる。国王の入場を告げる言葉が会場に響いたからだ。正面に置かれている玉座。それに向かって正面のそでから姿を現したブリトニア国王エドワード三世がゆっくりと歩いて行く。それに続くのはエバート王太子だ。中央の玉座に国王が座り、その隣の一段下がった場所に置かれている椅子にエバート王太子が座る。
それを待って入団式の開会が宣言された。
開会宣言の後は王国騎士団長による簡潔な祝辞。それが終わるとすぐに新騎士たちに対して辞令が発せられる。余計な装飾を省いた実務的な式なのだ。
「ロッド・チェンバース! 王国騎士団、第百一小隊長に任命する!」
「はっ!」
名前を呼ばれた新入団騎士が前に進み出ていく。
「デニス・ハッカー! サミュエル・ロー!」
続けて名を呼ばれているのは第百一小隊の隊員となる者たち。小隊長については騎士団での審査があるが、それ以外の人事は原則、新騎士の希望が優先される。希望と言っても誰と同じ小隊に程度の希望だ。
「以上の者たちに第百一小隊所属を命ずる!」
「「「はっ!!」」」
呼ばれた九名が前に進み出て小隊長となったロッド・チェンバースの後ろに並んだ。続いては第百二小隊長の任命。そして百二小隊に配属される者たちの名が呼ばれていく。
小隊の列が増えていく。それが十五列になったところで王国騎士団長が進み出てきて新騎士たちが並ぶ列の前に出る。
「国王陛下に申し上げます! ここに並ぶブリトニア王国騎士百五十名は王国の剣となり盾となり! その全てをもって王国に尽くし! 国王陛下に忠誠を捧げることを誓います!」
「「「誓います!!」」」
「どうか彼らの忠誠をお受け取り下さい!」
「「「お受け取り下さい!」」」
一斉に唱和したところで全員が腰に差していた剣を抜き、剣先側を持って柄を前に向け、そのままその場に片膝をつく。
「……許す」
その彼らに向かってエドワード三世王が小さく呟いた。
「「「はっ! 有り難き幸せ!」」」
これで新騎士の入団が正式に認められたことになる。本来は一人ずつで行う国王に対する騎士の誓いをまとめて行ったのだ。無駄な時間を省くということではない。新騎士は実質は見習い。まだ国王陛下に正式に騎士として認められる身分ではないというのが、簡略化されている理由だ。
さて王国騎士団の入団式はこれで終わり。だがまだ五十名、五小隊が呼ばれないままだ。彼らの表情には戸惑いが浮かんでいる。自分たちは王国騎士団に入団出来ないのかという不安、そして不満の色が顔に出ている。
「続けて新設の近衛騎士団特務部隊の入団式に移る!」
式はまだ終わっていなかった。近衛騎士団の入団式が残っていたのだ。だが新騎士たちの表情から戸惑いは消えていない。新設という言葉の意味に戸惑っているのだ。
「アーサー! 近衛騎士団! 特務第一小隊長に任命する!」
「は、はっ!」
会場に驚きの声が広がる。それに不満の色が混じっているのは小隊の番号が原因だ。王国騎士団に入団する新騎士の小隊の番号は百番台と決まっている。仮の番号であり、経験を積んて一人前として認められたところで正式な番号が与えられるのだ。それは近衛騎士団も同じ。近衛騎士団の場合は新騎士を入団させること事態が本来はないのだが。
ところが今アーサーは特務第一小隊長に任命された。新設とはいえこれは異常なことだ。小隊の番号の中でも更に一桁番号は特別で、実力順に若い番号が与えられることになっている。王国騎士団の第一小隊は王国騎士団の中でもっとも強く、実績をあげている小隊ということなのだ。
「続いて、クレア・レインウォーター! グリフレット! ガレス、ガウェイン……」
次々とアーサーの小隊である近衛特務第一小隊のメンバーの名が呼ばれていく。それが終わると次は。
「ランスロット・ハートランド! 近衛騎士団、特務第二小隊長に任命する!」
ランスロットが特務第二小隊長に任命された。小隊番号が序列を示すということであればランスロットにとっては不満であろうが、それをこういう場で顔に出すランスロットではない。
結果、新設の近衛騎士団特務部隊には五小隊が作られることになる。そもそも特務部隊とは何なのか。事情を知らない人たちの疑問はすぐに解消されることになった。彼らの前に進み出た近衛騎士団長の宣言によって。
「エバート王太子に申し上げます! ここにならぶブリトニア王国近衛騎士五十名は王家の剣となり盾となり! その全てをもって王家に尽くし! 国王陛下並びにエバート王太子に忠誠を捧げることを誓います!」
また会場に驚きの声が広がった。今度は純粋に驚きの感情だけが含まれている声だ。特務部隊は国王ではなくエバート王太子の近衛、王太子直属の近衛が特務部隊だと分かったのだ。王太子にも近衛騎士はついてはいるが部隊を持つというのは異例のこと。その意図にまた人々は悩むことになる。それを理解している者はわずか。新騎士の中ではランスロット、マーリン、グリフレット、そしてクレアくらいだ。
近衛騎士団特務部隊はエバート王太子が黒龍退治の栄光を手に入れる為の手足。そしてその後の大陸制覇の尖兵となる存在だと。近衛騎士団特務部隊の新設はエバート王太子が図ったことだと。
アーサーたちにとって夢に向かっての第一歩であったはずの入団式は、微妙な影を落として幕を下ろすことになった。
◇◇◇
城の大広間で騎士団の入団式が行われていた頃、そことは比べものにならない小さな執務室でもう一つの入団式が行われていた。式といっても参加者は二人。アルフレッド管理官とレイモンドだけだ。
「お前一人か?」
本来の予定は二人きりではなかった。他のメンバーが来ていないことにアルフレッド管理官は不満そうな表情を見せている。
「入団式とはいっても特に何があるわけでもないですよね? であれば一人で充分ではないですか?」
「実際そうだが小隊の人数は確認しておく必要があった」
「そんなの隠しませんよ。人数は俺を入れて五人です。名前は必要ですか?」
必要ないのは知っている。アルフレッド管理官であれば誰であるか分からないはずがないのだ。
「ない。しかし、五人のままか……」
小隊の定員は十名。退学からここまでの期間でレイモンドはメンバー集めをしているものとアルフレッド管理官は思っていた。レイモンドがあちこち動き回っていたのはその為だと。そうでないとするとレイモンドは何をしていたのかがアルフレッド管理官は気になる。
「人数が多ければ良いというものでもありません」
これはレイモンドの本心。レイモンドに必要なのは決して裏切ることのない信頼出来る仲間だけ。仲間の振りをして裏切る人間など近づけたくないのだ。
「そうは言っても五人では少なすぎる。任務は十名をひと単位として計画されるのだ」
実行役、見張り役、伝令、バックアップ要員などなど。実際の任務には様々な役回りが必要になる。その最低限が十人という数。足りなければ他の小隊と合同でということになるが、他小隊とはまず顔を合わせることなどない特務小隊ではなかなか連携が上手くいかない。任務を失敗する可能性は一気に高まることになる。
「まあ良い。足りない人数はこちらで用意する」
「それはどうも」
レイモンドにとってはありがた迷惑というものだが、嫌だといってもアルフレッド管理官が引き下がるはずがない。レイモンドは無断な交渉はしないことにした。
「さて小隊の番号だが何番がいい?」
「はっ? そういうの自分で決めるものですか?」
他の部隊では決めない。王国騎士団特務部隊が特別なのだ。
「特務部隊ではそうなっている。ちなみに王国騎士団特務部隊が正式な組織名だ。まあこの組織名が公になることはまずないがな」
「裏騎士団ではなかったのですね?」
「そんな怪しげな組織名が使えるか。それで? 番号は何にする?」
仕事の内容はかなり怪しげなのだから、それで充分だとレイモンドは思ったのだがこれも余計な会話を増やすだけだ。
「何番が空いているのですか?」
レイモンドは後半の問いにだけ答えた。
「それを教えれば特務部隊の人数が想像出来てしまう。使われていればそう言うから好きな番号を言え」
これが番号を好きに選ばせる理由の一つ。存在を秘匿しているくらいの組織だ。このあたりの情報管理も徹底している。誰が所属しているか以前に何人いるかも、普段どこにいるかも分からない。レイモンドに出る正式な辞令も全く異なる部署になるのだ。
「じゃあ……」
「ああ、一桁番号は駄目だからな。一桁ナンバーズは勝手に名乗れるものではない」
一桁番号が特別であるのは王国騎士団特務部隊も同じ。実力に応じて与えられるものなのだ。
「……では十三番は?」
少し考えてレイモンドは十三を選んだ。
「ふむ……問題ない。では第十三特務小隊でいいな」
「はい」
使われていなかったようで、レイモンドの希望通りに十三番で決まり。使われていないだろうと思っていたのでレイモンドには何の感情もない。
「何故、十三番なのだ?」
だがアルフレッド管理官はそれで終わらなかった。
「それ必要ですか?」
「いや、好きな番号をと言うと大抵は縁起の良い番号か語呂合わせを考えるものだ。だが十三はそれのどちらでもない。それとも語呂合わせになっているのか?」
十三番は縁起の良い番号ではない。だがアルフレッド管理官の説明を聞く限り、縁起の悪い番号でもないようだ。この世界ではそうなのだとレイモンドは知った。
「十三番に意味はありません。意味はこれから生まれるものです」
「……そうか」
十三という数字がどのように人々に認識されるかは自分次第。レイモンドはこう言ったのだと理解してアルフレッド管理官は少し驚いている。結果は別にしてレイモンドは常に目立たないように振る舞っていた。そのレイモンドがこのようなことを言うのは意外だった。
「あとは?」
「これが表向きの辞令だ。王国騎士団所属であることに違いはないが後方管理、文官のような仕事だ」
アルフレッド管理官は表向きと言ったが、辞令そのものは正式なものだ。逆に特務部隊所属であることは王国のどの記録にも載らないことになっている。
「他のメンバーの分は?」
「それは後で配属先に直接届けられる。これは配属がどこか知らせる為に用意した写しだ」
「……ちなみに任務のない時は普通に働くのですか?」
「ああ、そうだ。だが日常の仕事などない閑職だ。それに執務室には関係のない職員はいない。何をしていようとまず分からないから好きにしていれば良い」
一般職員はレイモンドたちが特務部隊所属だということを知らされることはない。気づかれることのまずない部署が配属先として選ばれている。
「それは有り難いですね」
身分を隠すための仮初めの仕事に時間など取られたくない。任務がなくてもレイモンドたちにやることは沢山あるのだ。
「さてこちらからは以上だ。質問はあるか?」
「『封印の森』の件はどうなりました?」
「ああ、そうだった。転移装置を用意する。執務室から直接は無理だがいくつかの中継点を通ればわずかな時間で行き来出来る」
「ああ、それも有り難いですね」
当面やることの多くは『封印の森』にある。移動時間が短いのは良いことだ。
「定期報告はしてもらうぞ」
「もちろん。ちなみにいつ頃というのはあるのですか?」
エバート王太子がいつ黒龍討伐に動くつもりなのかは、知っておきたい情報だ。それによってやるべきことの優先順位が変わってくる。
「ないな。倒せるだけの戦力が育ったらとしか今は言えん」
だがアルフレッド管理官の口から具体的な時期は聞けなかった。
「その戦力というのは?」
「今頃、その戦力たちの入団式が行われている。近衛騎士団特務部隊。エバート王太子の直属部隊が新設された。五小隊五十名。半分くらいはお前も良く知っている者たちだ」
「なるほど……考えましたね」
黒龍を倒せるのはアーサーたちしかいない。そのアーサーたちをエバート王太子は自分の配下に組み込んだ。知らないで行ったことではあるがそうであれば尚更良い考えだ。アーサー、というよりランスロットやマーリンが思うとおりに動くとはレイモンドには思えないが。
「そうか。王国騎士団と近衛騎士団という違いはあっても特務部隊が二つ出来たわけだ。表と裏と区別することになるな。区別をする必要は普段はないと思うが」
区別が必要なのは裏の特務部隊の存在を知っている人たち。ブリトニア王国の中でも極々限られた人たちとなっている。
「それはどうぞご勝手に。あとはこちらから連絡を取りたい時はどうすれば?」
「呼ばれたと言って執務室に来れば良い」
「普段は学院にいるのでは?」
アルフレッド管理官の表向きの仕事は王立学院の管理官。普段は学院にいるはずだ。実際にレイモンドは学院で何度も会っている。
「学院とこの建物は目と鼻の先だ」
「なるほど」
小型の転移魔道装置でも余裕で届く距離。ただ転移魔道装置を個人の移動に使っていることにはレイモンドは内心で驚いている。
「あとは?」
「武具とか物資はどうすれば?」
「原則、自己調達だ。費用は当然支給される。使い切れないほどの物資が購入出来るだけの費用だ」
「それは給料ではなくて?」
「まあ、そうだな」
高給ではあるが必要経費は全て自己負担。良いか悪いかなんとも微妙なところだ。わざと微妙にしているのだろうかとレイモンドは思った。とりあえず死にたくなければ経費を惜しまないこと。これは心に決めた。
「自己調達か……」
ただ問題はそれをどこで調達するか。
「あてがないのであれば紹介する。というか紹介先から調達したほうが良いな。余計な詮索をされない」
「では教えて下さい」
「マクベニー商会。初回は紹介状が必要なので用意しておこう」
「……お願いします。その一カ所だけですか?」
レイモンドが聞いた覚えのある名前。そこだとすれば出来ることなら関わり合いになりたくない商会だ。
「そこで手に入らない物はまずない」
「そうですか」
他の調達先を探そうとレイモンドは決めた。王都からは離れているが実家があるマルケットの商人という選択肢もある。余計な詮索はやはりしないはずだ。父親に知られる可能性はあるにしても。
「まだ何かあるか?」
「いえ、もうありません。これで失礼しても?」
「ああ」
入団式というよりも打ち合わせというべき会談は終わり。レイモンドは席を立って部屋を出ようと扉に向かう。
「ああ、すまん。こちらにもう一つあった」
そのレイモンドにアルフレッド管理官がまだ用件が残っていることを告げてきた。
「何ですか?」
「存在が秘匿されている組織だ。第十三特務小隊なんて言葉を口にすることは許されない」
「……分かりました。別に問題ありません」
「そうではない。小隊のコードネームが必要だ。何か希望はあるか?」
「……あります」
小隊のコードネームについてはアルフレッド管理官に言われる前からレイモンドは考えていた。考えていたというより知っていた。
「ほう、それは何だ?」
「グリム・リーパー」
「それは……?」
「『死に神』という意味です。くそったれの特務小隊には相応しいコードネームだと思いませんか?」
「……分かった。では第十三特務小隊のコードネームは『グリム・リーパー』で決まりだ」
『グリム・リーパー』。レイモンドの剣の師でありブラッドの祖父であるマーヴィングの通り名だ。だがレイモンドはこの言葉をこの世界に来る前から知っていた。ゲームの中でレイモンドが自分の部隊につけていたコードネームとして。レイモンドの部隊がこれを名乗ることは初めから決まっていたのだ。
王国騎士団第十三特務小隊、コードネーム『グリム・リーパー=死に神』。これが将来、十三は不吉な数字と世の中に言い伝えられる原因……になるかどうかはレイモンドが何を為すか次第だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
