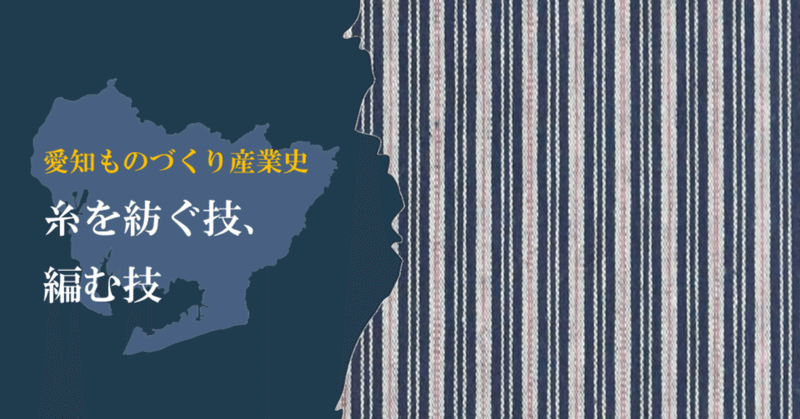
糸を紡ぐ技、編む技⑩ 主力事業の転換(一般消費財から生産財へ)
昭和48年、変動相場制が導入されると円高が進展し、窯業と同様に安価な東アジア製品が台頭し始める。これによって国産衣料品の価格競争力が急速に低下、愛知の繊維産業も大きな打撃を受けることとなった。
その一方で新たな展開もおこっている。
一つ目は欧米のハイブランドとの提携による高級路線化で、その最たる事例が尾西の毛織物である。業務提携を通じて品質のよさが海外でも広く知られるようになり、現在、BISHU(尾州)ブランドは世界三大毛織物の一つに数えられている。
二つ目は自動車産業への進出で、「化学繊維を使った事業の拡大」と「繊維と樹脂とのすり合わせ」が大きく進んだ。豊田紡織(現トヨタ紡織。大正7年設立)の事業展開が最たる事例である。明治44年創業の豊田自動織布工場をルーツとする同社は綿紡績に始まって、昭和40年代には自動車産業に本格的に進出する。以後、化学繊維製の自動車内装品(シート、シートベルト、フロアカーペット、エアバッグ)、樹脂製の外装品(バンパーやフェンダーライナー)、さらには、多彩な素材(繊維、樹脂、金属)によるユニット部品(フィルター製品、エンジン周辺製品、電動化製品)を手がけてきた。近年では、ケナフ繊維(一年草植物)と樹脂とをすり合わせたバイオプラスチックを実用化し、自動車内装品の素材として展開している。


自動車産業以外では、福井漁網(現福井ファイバーテック。昭和22年設立。豊橋市)が知られる。同社は明治43年創業の福井作蔵商店をルーツとし、綿漁網を生産していたが、昭和36年にナイロン漁網、同50年頃にスポーツ・レジャー用ネットやインテリア関連製品、同63年には繊維強化プラスチック(FRP)製品といった具合に、製品群の拡充を図ってきた。現在では複合型繊維メーカーとして、産業用ネット、自動車内装品、FRP製の引抜成形品などの幅広い事業を展開中である。
以上、愛知の繊維産業(糸の技)のあゆみをたどってきたが、木綿や羊毛の印象が強いため、よくいえば伝統産業、悪くいえば衰退産業というのが一般的な見方であろう。しかし、機械部品の素材に適した化学繊維やFRPが実用化されたことで、今や機械産業には欠かせない存在となっている(このあたりはファインセラミックスを実用化した窯業と同様)。この進化した姿にもっと光をあてて愛知の繊維産業を再評価すべきと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
