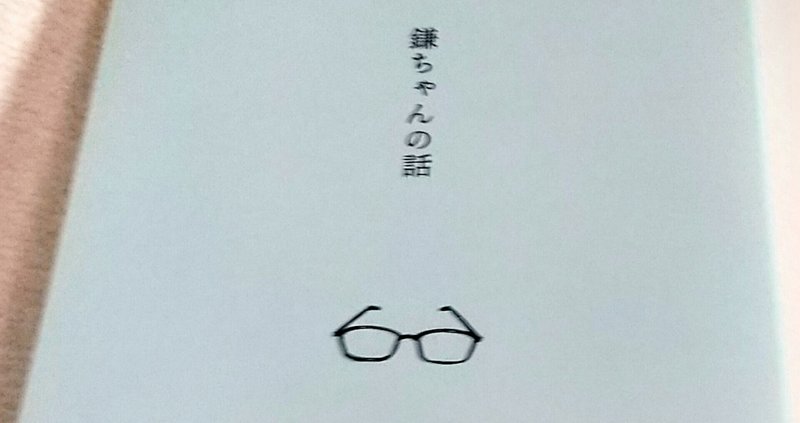
あのとき、きみが嬉しそうに電話していた相手はだれやったん?
遺言により、旧友の伝記を作成しました。でも、本人が語る場面はありません。
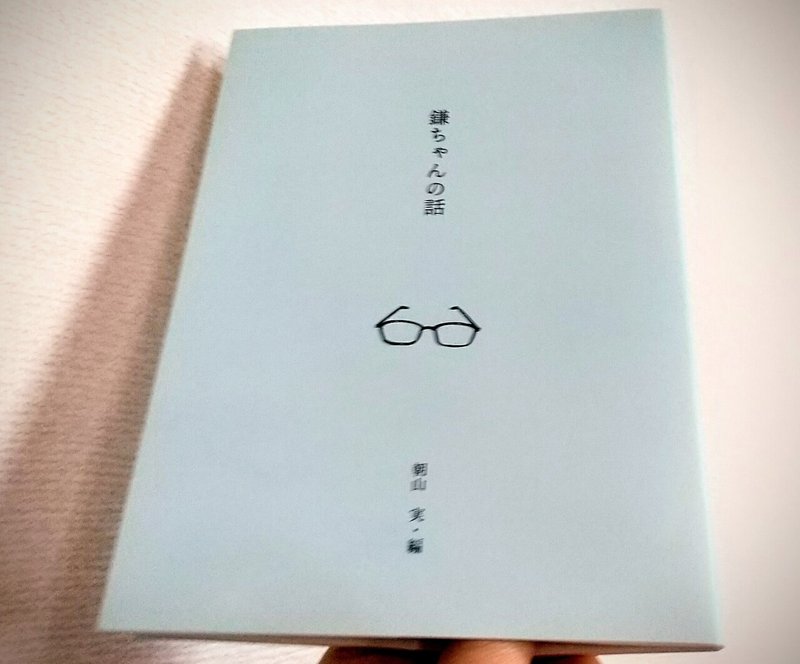
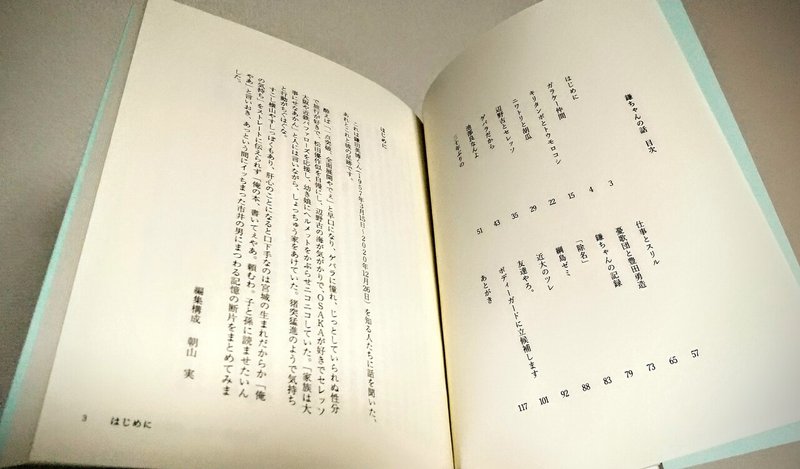
先日、数年ぶりに会った編集者でノンフィクション作家のナカムラさんに、あれ面白かったよと言ってもらった。昨年のクリスマスのあと、大学以来の旧友が病気でなくなり、遺言?にしたがい、百頁余りの本をつくった。遺族と協力してもらった友人知人たちにも配布したけれど、まだ手元に残ったので、何人か読んでもらえそうなひとにも送った。彼のことを知らないひとにも、読んでほしい。シンプルにそう思った。
「いきなり三里塚の闘争の話から入るから、たしかに読むひとを選ぶ本だとおもうけれど、十数人の語り手たちがカマヤンのことについて話すんだよね。ぼくはそのカマヤンのことはまったく知らないんだけど、アサヤマさんのインタビューを受けて話すひとたちがカマヤンだけでなく、カマヤンとのつきあいからそれぞれ自分の半生を語っていて、ときにはほとんどカマヤンは話題の中心からはずれ出てこなったりするんだけど、カマヤンを含めそのひとたちが生きた時代の光景がみえてくるんだよねえ」
ナカムラさんともうひとり、その日はオオナミさんという編集者のひとも交えて会ったので、ナカムラさんはオオナミさんに説明するように話しくれていた。カマヤンではなく、カマちゃんなんだけど。言いそうに何度かなったけど、やめた。嬉しかった。ちゃんがヤンに変形するくらいナカムラさんのなかで彼は存在することができ内面化したんだろうと考えた。
ほかにも、「走れアルマジロの歌が好きだった」とワンフレーズを唄ってくれるひとがいた。アブノさんは同志社大学生のときに学園祭の実行委員会に関わっていて、豊田勇造(旧友がライブをするので呼んだ話を、中の語り手のひとりが回顧している)を呼んだことがあったとその頃の話を愉しげに話してくれた。
もうひとり、スタッズ・ターケルが好きだというライターのカナイさんは、「だめだよ、鎌ちゃん」と怒ってくれた。面白く読んでいたら最後に出てくる彼の妻が、世話好きの外面がいいDV夫だったか。どんなに泣かされたか。まったく異なる家人としての姿を語っているのだけど、ちゃんと彼のことを叱ってくれるのを聞いて、ほっとした。
その『鎌ちゃんの話』という私家版。非売品ですが、目下のわたしの代表作です(ジブンでいうのもなんですが)。10年前、父がなくなったあと相続のゴタゴタがあり『父の戒名をつけてみました』という本を書いたことがあり、熱心に周囲のひとにその本を販売してくれたのが彼でした。彼の本をつくってみて、父がなくなるのがいまだったなら、父の介護にあたってくれたヘルパーさんや父が息子のように応援していたという税理士さん、村の青年団や、葬儀にもかけつけてくれた証券会社のひとたちに話を聞いてまわり、父がどういうひとだったを語ってもらいながら、そのひとたちのことを聞いていく本をつくろうとしただろう。
「おれの本、書いてえやあ」とわが友カマタくんから言われたのは、余命宣告を受け、会えるのは年内かもしれん。それが去年(2020)の春。最新治療は受けはしたけれど、宣告通りに、足早にいってしまった。
あの日は、自分史本流行りとはいえ読者は当人ひとりきりという結末がみえている、誰も他人の自分史なんか読めへんよ。有名人ですら本を売るのに四苦八苦する時代に、やめときやめとき、といさめはしたが、納得いかない顔つきの彼が「孫に読ませたいんや」と抗弁した。コロナで閑散とした大阪上本町の駅側のホテルのラウンジの窓際の席だった。夕陽がさしてくるのをおぼえている。
孫って? 彼の孫に会ったことはなかったが、おそらく小学生とか中学生くらいだろうか。そんなこどもが、じいさんの自慢話など読むわけがないやろう。冷たく言ったのは、わたしが、とくに同居していた祖父母との関係が最悪だったからで。「孫なら、よけいそんなん読まんで」と言うと、わが友はむすっと口をとじ、しばらく黙っている。言い過ぎたかなあ。余命宣告受けているんやし。落ち込ましてしまったかなあ。でも、これで話は終わったと思ったら、そうではなかった。
「えっ、なんぼあったら出来るんや」はあ、、まったく何も耳にはいってなかったのか。あきらめさせようとして「そら、本にするんなら百万くらいは」と多めにふっかけた。「そうか。なら、いまから電話するわ」とわが友。パカッとガラケーのケータイを開いて、どこかに電話をし始める。
あのとき彼は、ガラケーを耳にあてながら笑っていた。「おれ癌なんや。治療は難しいねん」と耳にしたときもそうだったが、ふだんと変わらない調子で、「かわいそうやろう」と口にするが、態度はいつもと一緒。ついさきほどまでも昼から居酒屋で酒を飲みまくっていた。だからいまひとつ現実感がない。
「ヨッシヤ、百万やな、用意できた」電話を切ると、声がはしゃいでいる。どこの誰だか知らないが、スポンサーが見つかったという。え? 百万即決なん? ホンマかいな。たった数分の電話で、大金を投じてくれるひとがいるとはどういう人間関係なんやろう。
後ろ楯を得たわが友はえらく元気な声で「決まった、頼むでえ」と身を乗り出す。そばにいたイトウくん(この日、辺野古でおうたんやわというカマタくんの仲立ちで大学以来40年ぶりで再会した)も、なりゆきにあきれている。どうしたものか。頼むでえっ、て。この男とこれから何回か膝を交えてインタビューするために帰阪する自分を思い浮かべようとする。
が、まったく浮かばない。彼とはこの十数年、年に一回か二回会うことはあってもちゃんとした話をしたことがない。たいてい彼は泥酔していた。深夜に電話してきては「アサヤマくん、友だちやろう。ナガブチのサインもらってくれやあ」。ざわざわした声が電話ごしに聴こえてくる、なんてことが度々。翌朝になると電話したことを忘れてしまっていた。
それでもうちの父がなくなり遺産相続の相談をしたときは、シラフのマメな彼の仕事ぶりには感心した。酒が入ってないときの彼は税務には長けていた。頼れる男だった。酒さえなきゃなあ。
もう何年もきちんとした話をした覚えがない。それで本など作れるのか。あらたまって、彼の生い立ちから、いまさら情熱大陸のように聞いたり出来るだろうか。どうしょう。
あれから一年半。本は出来た。本人には一切インタビューをしなかった。希望どおり、孫の七人には、奥さんを通じて渡してもらうようにしたが、感想は聞いてない。こわくて聞けない。いまとなっては、まあ、余命を告げられた彼があのとき、暗い顔も見せず、楽しそうに笑いながらいったいどんな心境で「俺の本を」と言ったのか。何を考えていたのか。なにひとつ聞くことなく結局、彼はいってしまった。
本を作ってくれと言った数日後、彼が「10万だけ前金振り込んだから」と電話してきたものの、直後に、家族が反対しているからと依頼じたい曖昧になった。その後あのことやけどと問いかけても「まあ、待って」で真意が見えなくなってしまった。結局、彼が生きているうちに完成させられたらそれがよかったのだろうが、できなかった。というか、着手もしなかった。で、前金が宙ぶらりんなままにのこった。
彼を知る友人知人十数人にインタビューを重ねていったのは、年明け、葬儀から何週間後かしてからだった。年末の通夜と葬儀にはコロナの渦中というのに各々、百五十人近い列席者が集まった。こんなご時世だから、てっきり家族だけの葬儀だろう。東京から行くのもなあ。躊躇していたら、報せてくれたひとが「本人の希望で、友だちに送ってほしいと言うてたそうやわ」。それならと通夜の日に新幹線に乗った。
盛大な葬儀に驚いた。道々ひっそりとした葬儀を想像していたら会場に並んだ花の多さに、ヘエー、すごいなあ。有名人の名前もある。わたしの知らない世界で仕事をしてきた彼の人生の一端に触れた思いになった。ちょっと、嫉妬した。うらやましかった。
告別式のときに弔辞を読んだコシモさんは、カマタくんが夜中の電話で「コシモくん知っているやろう」としばしば名前をあげていた彼の旧友で、わからんわというと、「おかしいなあ。覚えてへんのか」と不思議がり、ほら、あのときのと説明する。結局、会って話したのは数年前、共通の知人の17回忌のあと散会し、三人で呑もうと入った居酒屋だった。そのときも「ええっ。初めてか。そんなことないやろう」と彼は口にしていた。
コシモさんの弔辞を聞いていて、彼が引き合わそうとしていた理由がわかりかけてきた。コシモさんも、友人が多いほうではないらしく、カマタくんに強引に呼び出され辺野古支援の催しに参加したりしていたらしい。ちょっと控えめなところの質感は、わたしに似ているかもしれない。弔辞を読みながら嗚咽してしまっているコシモさんを遠目に、カマタくんとの付き合いを聞いてみたい。そんな心境になっていた。最後の献花になったとき、棺を囲んで小学校の制服を着た女の子二人が泣いているのを見て、この子らが大きくなったら読めるものを残そうとおもうようになっていた。時期はともかく、ファミリーヒストリーを知りたくなったときに手がかりになる本はあったほうがいいわなあと。
とはいえ、本人のインタビューはもう不可能だから代わりに友人知人たちに、彼について覚えている逸話と、それぞれの個人史も聞かせてもらって収録することを考えた(だからカマタくんは本の中では、狂言回しめいて、話題に出てくるものの一向に姿をあらわさない傍役にみえることも)。カマタくんを中心にしながら、彼の友人知人たちがどんな人生を歩んできたのかを併記することで、何か浮き出るものがあると考えたからだ。
彼が参加した学生時代の三里塚闘争のことを当時のセクトのひとたちから。その後に勤めた税務関係の職場の後輩のひとたちからは、彼の社会人としての仕事ぶりなどを聞き、最後に彼が学生時代に出会った奥さんに話を聞いた。
彼は「おれのことはアサヤマくんが全部知っている」とひとに話していたらしいが、まあ知らないことばかりだった。なかでも印象深いのは、反戦集会に小さい娘を連れていき、ヘルメットを被せては「よう似合うわ。ローザルクセンブルグやあ」とはしゃいでいたとか。音痴なのに酔ってスナックでカケオケを熱唱、それも清志郎のスローバラードを歌詞もむちゃくちゃに絶叫していたとか。それに付き合わされ、閉口しながらも自分も歌っていましたという、年の離れた職場の後輩がいたこと。案外好かれてたんやなあと。
酒癖は悪いが仕事に関しては誠実。ヘエー、そうなんや。と感心していたら、最後の奥さんのインタビューで頭を抱えた。暴力夫ぶりに何度も離婚を考えた。「悪いところばっかり」と堰をきるように出てくる逸話のひどさに呆気にとらわれた。これ載せていいものか。オブラートに包もうか。
迷った末に、ほぼそのままに書きとどめた。リベラル志向な男が家庭では暴君だったというのはよくあることだし、カマタくんもまたその一人だったわけだが、悪口をつぎつぎあげながら「はやすぎたわあ」と泣き声になった妻のトモミさん。その苦労はしっかり残さないと意味がないと考えた。
トモミさんいわく「いいかっこしい」のカマタくんはそこは誤算だったのかもしれないが。でも、そのうち向こういったときには感想を聞いてみたい。
制作に関しては、カンパなどもいただいた。おかげで希望者百人近くに本を届けることができた。が、いまだにナゾなのは、あのとき愉しげに電話をかけた相手が誰だったのか。彼に聞いておけばよかったのだが。いまだ届けられていないのが、残念だ。まさか、エア電話なんてことはないわな、カマタくんよ。

鎌田英博くん(撮影©️j.ASAYAMA)
最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。
