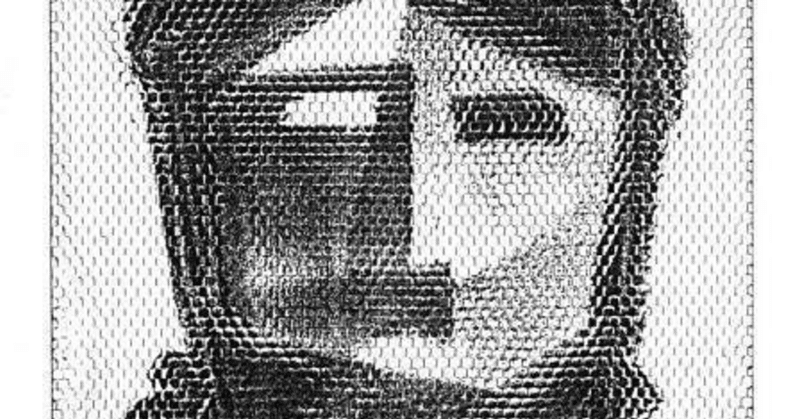
何食わぬ顔で
私は耳が聴こえない。
そういうフリをしている。
実際ははっきり聴こえているし、むしろ聴力は優れている方だ。しかし、聴こえないフリをしている。
理由は単純。甚だ、他人の声が煩わしくなったからである。
あれやこれやと必要もなく零された戯言、怒りの矛先が分からず理不尽に発せられる奇声、自分自身を守るかのような他人の悪口、蔑みの声。
それらが私に向けられたものかどうかは別に問題ではない。寧ろ、そういう汚らしいもので占められた空間に自分が存在していることが問題なのかもしれない。かといって逃げることもできない。それは単に私が臆病であるという理由だけでなく、どこに逃げたとてこの世の中はそういった汚れた声で溢れているからである。逃げようがないのだ。
だから、私は耳が聴こえないことにした。誰に話しかけられても振り向かない。反応しない。全力で無視。それ以外にも、例えば、外で雷が鳴ろうと、近くで悲鳴が聞こえようと身体の一つも動かさず、何事もなかったかのように歩くのである。
最初は多くの人に心配された。中には面倒臭そうな顔をするものもいた。
基本的に仕事などで必要事項が生じた際は殆どメールで、そしてたまに筆談で言葉を交わすようになっている。私は耳が聴こえないだけで話すことはできるが、それもひどく苦手である。小さい頃、授業中に先生に当てられて答えられなかった時、クラスメイトがじろじろとニヤニヤした目線を向けてきたことがトラウマになってしまっている。それっきり、私は心許した人にしか口を開けなくなってしまった。職場では、最初は「私たちは文字で伝えるけど、あなたは口で答えてくれれば良いんだよ。」と伝えられたが、頑なに自分も文字で伝え続けていたら、誰も何も言わなくなった。
不思議なことに、メールや筆談で使われる言葉は口から出る言葉よりも何倍も優しい。心優しい人は感嘆符や疑問符、そして顔文字をつけることもある。その小さな心配りを有難いと感じてしまうのも変なものだ。
悲しいのは、身内も騙してしまっているということ。初めは身内にはこんな仕様もない演技をせずに今まで通り接しようと思っていた。しかし、仮にそれ以外の人間の前で身内が私に話しかけているところを見たら、不気味がられるだろう。「こんな近しい距離の人なのになんで知らないの?」という具合に。さすがに、「私が耳が聴こえないフリをしているのを知らないフリ」を身内にさせるのは気が引けた。なので、身内の声にも決して耳を傾けない。まぁ、身内なんてこれっぽっちしかいないけど。
さて、勘の良い方なら気付いているかもしれないが、自分の耳が聴こえないからといって、自分の周りを纏っている汚い言葉が消滅するわけではない。他大勢の人は耳が聴こえるわけだから喧嘩をしたときには罵詈雑言が生まれるわけだし、私は実際耳が聴こえるのだから汚い言葉が存在していることを嫌でも認めなくてはならない。しかし、面白いことにこのフリを続けてから、何だか以前よりも心が晴れやかになった気がするのだ。「耳の聴こえない人に対してはわざわざ悪口なんて言わないだろう」。そんな安直で人の僅かな善良に訴えるような発想から始めた"フリ"だが、実際自分に直接向けられる罵倒や悪口は減っていった。勿論、褒め言葉や慰めも減ったが。しかし、耳が聴こえないことを良いことにわざわざ大声で罵ってくる人もいる。その行為自体物凄く阿呆らしいが、それに傷ついてしまう自分もみっともない。また、直接向けられる言葉が減った分、私に対する陰口は増えた。生憎、私は聴力が優れているので、そういったものも聞き逃さない。何が陰口だ。もっと隠れて言えよ。そんなことを思いながらも、私はただただ何食わぬ顔をして聴こえないフリをし続けるのだった。
ある日、私は大手会社と合同で行われる重要な会議に参加する人員として選出された。なぜ耳が聴こえない(フリをした)私が選ばれたのか疑問に思ったが、何かと仕事は卒なくこなし、業績も平均以上に上げていたので、そういったものが評価されたのかもしれない。勿論、声が聴こえないので意見を主張したりメモを取ったりすることはできない。どうやら単純なる人数合わせだったようだ。「人数合わせとか合コンかよ」と突っ込みたくなったが、内心悪い気はしなかったので素直に参加させていただくことにした。
会議が始まった。見知らぬ人たちに囲まれて緊張したが、その分安心感もあった。なんせ私は声が聴こえないのだから。ただ何食わぬ顔をして座っておけば良いのだから。
プレゼンテーションや質疑応答が活発に行われる。そんな中でも汚い言葉は飛び交っている。もう少し優しい言葉で伝えられないか。なぜそんな意地の悪い聞き方をするのか。訳がわからない。そんなことを思いながらも会議は滞りなく進んでいく。
そして、終盤に差し掛かろうとしたそのとき、事件は起きた。
大手会社のプレゼンテーターが私に意見を求めてきたのだ。普段共に仕事をしている人は限られており、その人たちは私の耳が聴こえないことを知っているため、話を振られることは皆無である。さらに、稀にあるこういった会議でも上司が参加者に私の耳のことを事前に伝えておいてくれるので、意見を求められたことは今まで一度もなかった。しかし、今回は違う。今まで経験したことのない状況に心臓が高鳴る。しかし、動揺したら今までの演技が台無しになってしまう。私は動揺を必死に隠し、何食わぬ顔をする。
すると、私の事情を知っている同僚が口を開いた。
「申し訳ありません。実はこの方、耳が聴こえないんです。」
助かった。冷や汗が脇や背中に伝うのが分かる。しかし、その安堵も表情に出してはいけない。私は何食わぬ顔をする。
プレゼンテーターを含め、私の事情を知らない多くの人が驚いた顔をする。その表情には心配や気遣いといったものの欠片はなく、ただただ「訳がわからない」といったものだった。悪意とまでは言わないが、何か冷たいものを孕んでいた。
暫く沈黙が続いた後、ある人が言った。
「病院には行っているのですか?」
勿論、私は答えられない。先ほど、助けてくれた同僚が答える。
「ええ。週1回のペースで通院しているそうです。かなり難しい症状で、治るとしても莫大な時間がかかると...」
即座に先程の人物が言う。
「いや、私の知り合いに名医がいてね。耳鼻という領域に関しては日本でも3本の指に入るらしい。その方の元では何人もの難聴者が救われている。きっと彼女もその方を訪れたら、耳が聴こえるようになると思うが。」
すると同僚。
「そうなんですか!?是非、紹介していただきたいです。彼女もきっと喜ぶと思います。」
何を勝手な。私は耳が聴こえないことを"望んで"いるのだ。いや、実際その望みは叶っているわけではないが、叶っていることにしているのだ。そんな余計な治療、私には必要ない。
そう言いたかったが、無論言えない。私は耳が聴こえないのだから。私は再び何食わぬ顔...ではなく、この場合は少し不思議そうな顔をする。さすがに周りの大袈裟な動きや表情など視覚では理解できる範囲においては、周囲に絶妙に合わせた雰囲気を出さないといけないのも、この生活の難しいところである。
そして、結局その会議の1週間後、名医を紹介されることになった。最初は筆談で断ったのだが、会社で医療費を全額負担すると言われ、どうしても断ることができなかった。まぁ仕方ない。私は何食わぬ顔をして、聴こえないフリをするのみだ。
名医は思いの外若かった。医者特有の堅苦しさはなく、白衣を着ていなければテレビで活躍するコメディアンだと勘違いするほどの愉快さを感じる。その雰囲気が今まで私を看てくれた医者とは違って、不気味で仕方なかった。
その医者は筆談で意思疎通を図ってきた。「耳が聴こえなくなったのはいつ頃か」「そのとき何をしていたか」。そんな基礎的な事柄に加え、「聴こえるようになったら何をしたいか」「まず誰の声を聴きたいか」といったことも尋ねられた。その質問が不気味さを一層引き立たせる。
筆談が終わると、彼は突然立ち上がった。一瞬驚きそうになったが、我慢する。しかし、すぐに我慢する必要がないことに気がつく。耳が聴こえなくても目の前の人間、それも不気味な存在が突如動き出せば驚くだろう。
そして、彼は"口に出して"こう伝えた。
「今から大きな音を耳元で流しますね。聞こえないと思いますが、これを使って原因を確認させていただきますね。」
今まで経験したことのないような恐怖に襲われたのも束の間、医者は私の耳にスピーカーを近づけた。何百匹の蚊が飛び交うような不快かつ暴々しい大きな音。私は必死に我慢した。ここで少しでも反応したら、私の今までの演技は台無しになる。あの頃のように、この世に溢れる醜い言葉に潰されてしまう。
「君ってなんか鼻が変だよね」
「えー、そんなこともできないの?」
「あの子、最近男に捨てられたらしいよ」
「ねぇ、あっち行ってくれない?」
「君って本当に才能ないよねー」
「お前なんか死ねばいいのに」
嫌だ。絶対に嫌だ。こんな言葉ともう向き合いたくない。一生聴きたくない。私は何としてでも逃げ続けるんだ。何としてでも...!
30秒ぐらいは続いただろうか。ようやくスピーカーの音が止んだ。
どうだろうか。必死に表情筋の動きを殺していたが、果たして私は何食わぬ顔ができていただろうか...。
不安と願望で溢れた私の横で医者は優しくこう言った。
「もう大丈夫ですからね。検査はこれで終わりです。」
勝った。私の勝ちだ...!これからも逃げ続けられる。一生逃げ続けよう。もうあの頃のように言葉に殺されなくて済むんだ...!そう思うと、一気に安心と幸福が舞い降りて、思わず笑みが溢れた。
あっ。
気づいたときにはもう遅かった。
その笑みを見た医者は、私が顔に浮かべたものとは違った、不適さを孕んだ笑みを浮かべて再び言った。
「さて、検査はこれで終わりです。」
Twitter:檸(@nei_monologue)
★ラジオ始めました!★
〜檸のひとりがたり〜
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
