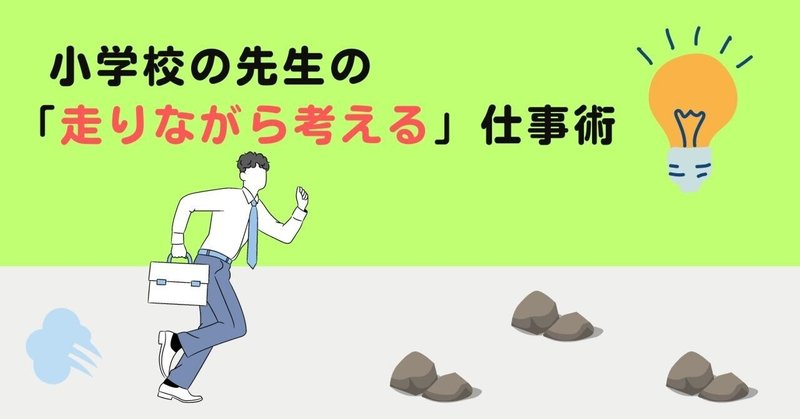
小学校の先生の「走りながら考える」仕事術
私は小学校で働いています。近年、教員の労働環境は、ブラックだと言われています。定額働かせ放題という言葉も出てきていますが、私は限られた時間の中で効率的に動くことで定時内で仕事をすることができるようになってきました。小学校の教員の仕事は、児童と対峙している場面が多く、児童が下校後の時間にいかに仕事を進めるかがポイントになってきます。今回は、そんな私の仕事術をnoteに書いていきます。
1.目の前を見渡せる一本道に
効率的に仕事をするために、私が1番大切にしているのは『見通し』です。4月に担任や校務分掌が分かったら、最低でも夏休みまでに関わってくるものを把握します。できたら1年間を見通したいところです。何があるか分からない道から、目の前にすっと先が見通せる一本道を作るイメージです。一本道には、途中にいろんな仕事が石のように落ちていますが、その石があることを知っておくことが大切です。石は基本的にいきなり現れない状態の道を作ります。ここには時間が必要なので、これをするために4月は残業が多くなってしまうこともありますが、ここを乗り越えたら比較的安定して仕事を勧められます。
2.「すぐできる仕事」と「考える仕事」を把握する
目の前を見渡せる一本道を作ったら、最低でも2ヶ月先くらいの石まで確認します。そこで、すぐできる仕事と考えないとできない仕事を仕分けします。私は、TODOリストに2か月先くらいまでの仕事を書き出します。自分の中で、これは空いた時間にすぐできる、これは考える時間がいると分かっていることが大事です。
3.隙間時間に「すぐできる仕事」をする
すぐできる仕事は2、3分の隙間時間があれば少しでも進めます。例えば、指導案なんてのも一見じっくり考える仕事に思えますが、日付やタイトルなど考えなくても書くことはできます。だから、ちょっとでもできる仕事、作業的な仕事はしておくと、頭の中にフックがかかるし、少し進んだ感じがして負担間が減ります。ちょっとずつ作業レベルで進めるがコツだと思っています。
4.「考える仕事」は走りながらする
私は机にじっくり座って考えるという仕事の仕方はしません。だいたい「考える仕事」は頭の中にあって、作業しながら考えています。頭の中に2か月先までの「考える仕事」にフックが掛かっている状態なので、毎日見ている景色や入ってくる情報もそれと繋がったりして良いアイデアが浮かんできます。そうやって、ある一定の時間だけで考えるのではなく、なんか頭の中にあって、いつも考えているイメージです。動きながら、日常を走りながら常に考えています。そして、私の経験として、廊下の移動中、日直のカギ閉めをしている時など比較的、動いているときの方が良い考えが生まれてきます。
それには科学的にも根拠もあります。アンデシュ・ハンセンの著書『新版・一流の頭脳 運動脳』にも以下のように書いています。
近年、こういったテストのおかげで、運動をすると創造性が増すことが科学的にも立証されている。そのなかでも抜きんでて目覚ましい結果を報告したのがスタンフォード大学の研究チームが行った実験だ。~中略~この研究論文のタイトル「アイデアを歩かせよう:創造的思考におけるウォーキングの効能」こそが、結果をそのまま表している。被験者が歩きながらテストを受けた場合、5人に4人の割合で好成績を挙げたのである。とくにブレーンストーミングと新しいアイデアを出す能力において、歩きながらテストを受けた被験者の成績は、歩かずに受けた被験者のおおむね60%も引き離していた。
また、著書には、実際にアルベルト・アインシュタインが相対性理論を思いついたのは、自転車をこいでいるときであったことや、アップルの共同創業者でCEOを務めたスティーブ・ジョブスはしばしば歩きながら会議を行ったことで知られていると書かれています。
つまり、じっくり机に向かうよりも、体を動かしながら考える方が良いアイデアが出やすいのです。しかし、切羽詰まった状況だと良いアイデアは出にくいと考えます。ですので、2か月ほど余裕を持って、考えておくことにフックをかけて頭の片隅に入れておくことが必要になってきます。見通しを持って、仕事にフックをかけ、頭の中で余裕を持って動きながら考える。そんな風に仕事をすることで、作業的仕事を進めながら、同時に考える仕事もすることができます。
これが、慌ただしい小学校の教員の仕事を効率よく進めるわたしなりの仕事術です。今、忙しくて大変なあなたの仕事が少しでも効率よく進むきっかけになればと思っています。最後まで、読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
