
小説 「僕と彼らの裏話」 4
4.僕は馬鹿だ
その日の昼食のメインは、僕が好きな東北名産のサバ缶を使ったスパゲッティーにした。
彼女の家で、2人で向かい合って食べる。
「坂元……少しは、落ち着いた?」
「何?体調?今、すごく良いよ」
彼女には「うつ病」とだけ伝えてあり、幻聴や幻覚、パニック発作の話はしていない。札幌に帰ってきたあたりから、それらの症状は ほとんど出なくなっていたからだ。
「私を『連れて帰る』なんて、はんかくさいこと、まだ考えてる?」
「はんかくさいって何だ!」
(※はんかくさい……北海道弁で「馬鹿げている」「あほらしい」を意味する単語。)
「あんた……久しぶりに会えた私が、偶然 独身だったから、舞い上がっちゃったんでしょ?」
(それは、否めないけれども……!)
あの時、僕は ある意味【躁】に近い状態だったのかもしれない。
しかし、僕は今でも「本気」だ。さすがに「休み明けに連れて帰る」気は無いけれど、本気で、いずれは彼女と暮らしたいと思っている。遠距離になってでも、真剣に交際したいと考えている。
「私の……『本体』を見たら、幻滅するかもしれないよ」
「そんなことは、無いよ」
「……わかった。今日、帰る前に見ていきなよ」
(えっ……!?)
一瞬、フォークを回す手が止まった。
食後、彼女は平然と自分の寝室に僕を招き入れた。
照明をつけて、ベッドの脇まで進む。
そこで、もはや密着も固定もさせていない、本当に見せかけだけの『作りもの』を外して、腕と、短い脚を使ってベッドの上に移動する。ズボンを穿かせたままの『作りもの』は、そのまま車椅子上に放置されている。
僕はただ、その様子を黙って見ていた。話には聴いていたけれど、本当に両脚が短くなっている様を目の当たりにして、心臓は少なからず動揺した。それでも、顔には出さなかった。
冬場なので厚手の黒いスパッツを穿いていて、僕が靴下を履くのと同じように、彼女も断端を保護する何かを履いている。名前の分からない それを脱ぎ捨てると、大きな縫い痕が露わになる。
人間の体の中で、一番太い骨を切ったのだ。当然、そうなるだろう。
「これが、今の私の『本体』だよ……」
彼女はそう言いながら、特に短い右脚をさすっている。毎日 長時間座っているから、同じ場所に負担がかかるのだろう。
「何か……“別の動物“みたいでしょ?」
「そんなことはないよ」
僕は、首を横に振った。
彼女は、何も言わない。
「隣に座ってもいい?」
「……いいけど」
僕は、彼女の右隣に座らせてもらった。
恥ずかしいようだけれど、所詮は僕も一介の「男子」に過ぎないから、好きな人の大腿部というのは……「魅力的だ」としか思わない。かつて、学校指定のスカートや短パンに隠れていた部位が、今……本人の意思によって、僕の目の前にある。
「幻滅なんて、するもんか……」
触ったら引っ叩かれそうなので、ぐっと我慢する。
「宮ちゃんは、変わらないよ。
あの頃から、ずっと……僕の『太陽』だ。世界で一番きれいだ!」
高校生の頃に好きだった曲の歌詞を、唐突に思い出して口にした。僕は当時、よく それを聴きながら絵や漫画を描いていた。
「僕の気持ちは変わらないよ」
これは、自分の本心だ。
「……あんた、いつから『僕』って言ってる?」
「職場では、基本的に『僕』って言うよ」
「マジか……」
「変かな?」
「いや……」
「……ハグしてもいい?」
「訊くの?そういうのって……」
「え?じゃあ……」
僕は一方的に彼女を抱き寄せる。上半身は がっしりして力強いけれど、脚元が不安定だから、彼女に体重をかけてしまわないよう、気をつける。
「脚、寒くない?」
「大丈夫……」
「良かった」
すごく良い匂いがする。
うつ病で すっかり萎えていたはずの身体が、久方ぶりに「雄」としての欲求を露わにする。高校当時の、いかがわしい空想や願望が、脳裏をよぎる。
それでも、今の僕には【成人としての理性】がある。そして、事故当時の彼女の心境を想えば……あの頃のように、舞い上がっている場合ではない。
どこかで、一歩間違えれば、彼女は亡くなっていたかもしれない。まずは、生きて再会できたことに感謝する。
自分を『別の動物みたい』とまで言ってしまうほど、体の形が変わってしまったわけだけれど、それでも僕は、そんな彼女に「貴女は素敵な人だ」「逞しく生き抜いてきた、立派な人間だ」「僕は、そんな貴女が好きだ」と、どうにか伝えたくて……抱き寄せた勢いのまま、欧米人の真似事のような、精一杯の愛情表現を試みる。
これを、彼女に「セクハラだ」と言われてしまったら、もう『お終い』だ。反論の余地は無い。平謝りする他はない。
やがて、僕は捕まえていた彼女を解放し、親愛と感謝の気持ちを込めて、背中をさすった。
「ごめんよ。いきなり……」
そう言って立ちあがろうとしたら、彼女が僕の手首を掴んだ。
僕は、もう一度座る。
「坂元……内地に帰る前にさ。一回、泊まりにおいでよ」
「良いの?」
彼女は、黙って頷く。
「『一緒に暮らそう!』なんて、言うからにはね……」
「……ありがとう」
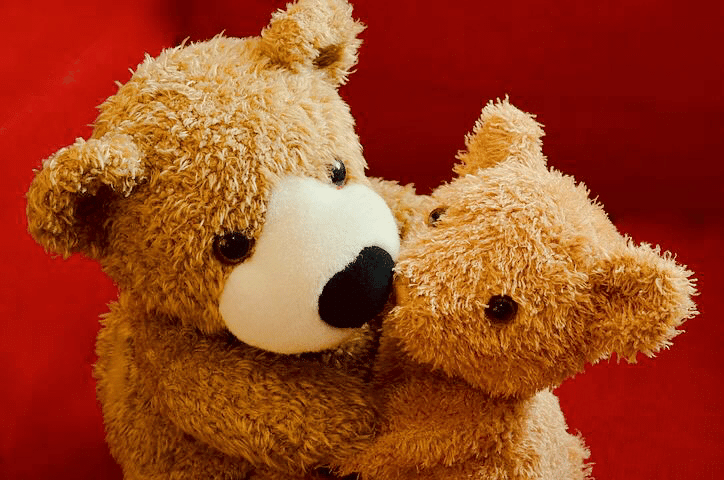
僕はその日、帰宅した修平には、スーパーで買った寿司を出した。味見すらしないで作った味噌汁も添えた。
彼は、それを何の文句も言わずに平らげた後、つい先日買った新しいゲームをやり始めた。
僕は、横でプレイ画面を眺めつつ、宮ちゃんとLINEのやりとりを し続けた。
次のエピソード
【5.幸せ】
https://note.com/mokkei4486/n/nb8cc1bdecbb4
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
