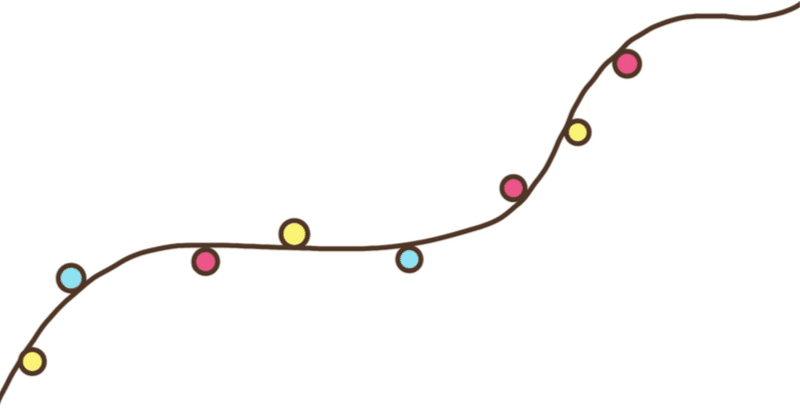
「書きたいだけ書ける」ことの功罪。
「小説を書こうとすると、どうしても長いものになってしまう」といった類の文章を見るたびに、昔から「何で?」と思っていた。「長く書かなければならないのがツライならわかるが、長くなってしまうのはそこまで書かなければいいだけじゃないか」という思いがあったからだ。
ちなみに自分は昔から長編小説に幾度となく挑戦したことがある。そして書き上げたことがない。途中で「あ~この先どうすりゃいいんだっけ、長いなあ」となって投げ出してしまうのである。そして「そうだ、書けないのはちゃんとしたプロットがないからだ。プロットを先に書こう」と思って、結局プロットを作るのが面倒になる。その結果「最初からオチまで思いついている短いものしか書けない」体質になってしまった。
まあ自分語りはともかく、こんな状態であるからして小説投稿サイトみたいなので、多数の人々が長編を書きあげて投稿しているのが信じられない偉業に見える。面白いかどうかはさておいても、書き上げるという最初のハードルを越えているだけで尊敬ものだ。
てなことを思っていたら、糸井重里とリリー・フランキーの対談で「今は自己表現の場に文字数制限がないのが大変な時代」という話が出ていた。
昔のライターやエッセイストは、もともと文字数制限がある中で原稿を書いていた。故・ナンシー関など1500字のために4500字書いてそこから削っていたという(上記の対談より)。文章の上手い人が、出来上がった文章から削って作るわけだから、より研ぎ澄まされたものになっている。それは単純に誌面スペースの都合だったりもするのだが、結果的にはそれが訓練だ、と。ネットでコラムやエッセイ(このnoteもそうだ)を発表する際には、それがない。自分で文字数のルールを厳密に決めているなら別だが、だいたいの人が「書きたい量」を書いているであろう。文字数の制限とは、「2000字だとちょっと長いから50文字削ろう」とかのレベルではなく、どれだけ言いたいことがあっても400文字以内、とかだったりするわけで、圧倒的に労力が違う。
冒頭の長編小説をガンガン書いている人も、当然だが全員人気が出るわけではない。もちろん元々の発想やら表現力やらもあるだろうが、もしかすると「面白くするために削ったうえで仕上がった長編」と「書きたいだけ書いた結果的な長編」が混在して差が生まれているのかもしれない。
世に出ている小説というのは大半が編集の目などを経てブラッシュアップされているので、「なんだこりゃ」というものは少ない。それに対してネットに投稿されたものは作者しか読んでいなかったりするので差が大きいのではないかと推測する。ただこれも海外の小説になると考え方が違うのか、これまでの感覚からすると「読みづらいなあ」と思うことがある。
「エドウィン・マルハウス」という、昔BSの番組で紹介・絶賛されていた小説を読んだことがあるが、これが非常に読みづらかった。なんというか編集されていないドキュメンタリーのような感じ。具体的に言うと「情景描写が異様に細かく長い」。例えばキッチンの描写の場合、皿があってティーカップがあってその横にシリアルが置いてあって、そのテーブルにはクロスがかけてあって…ということが全部書いてあるようなイメージ(実際の描写ではない)。日本の娯楽小説を読みなれているとどうしても「この描写が後々の伏線なのか」という感じで捉えてしまうのだがまったくそんなことはなさそうだと分かってからかなりすっ飛ばして読んだ。しかし伊坂幸太郎や西加奈子など名だたる作家たちが褒めまくっているので何か自分が全く気付けていない部分でもあるのかもしれない。まあそれでも正直に言うと退屈だった。なんとか結末だけ知りたくて読んだが。ちなみに、結末は悪くなかったのが救い。
この小説は別に削らないから長くなったわけではないと思うが、通常の文章のレベルを上げていこうと思ったら自主的にでも制限をかけていくべきなのかもしれない。「趣味だから好きにやってんだ」という場合は別にいいんだが。普段は制限があるものばかり書いてたりしたらなおさら。
サポートいただけた場合、新しい刺激を得るため、様々なインプットに使用させていただきます。その後アウトプットに活かします、たぶん。

