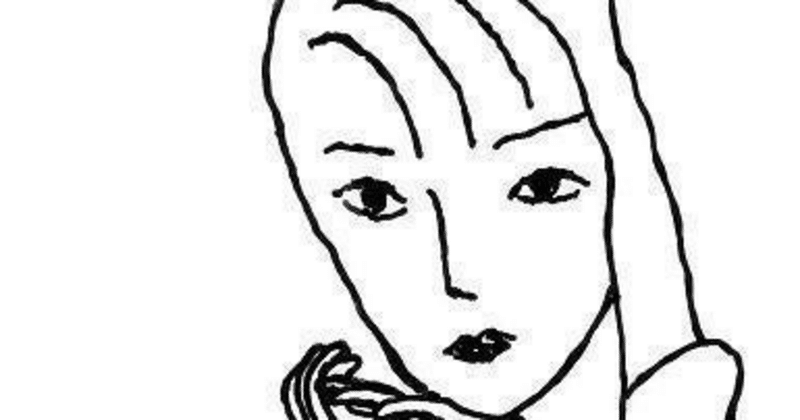
にんげんかんけいはむずかしい。
自分自身よく思うのが、常に神経を頭に貼り巡らないと闇のあの悶々とした、
妄想のドグマにハマってしまう怖さを自分は知っている。
気づかないうちに、無意識の中で自己否定、自己嫌悪、周りからの目の意識などの思考が自分の脳を占めていく。これに客観的に気づく事で解決する。
メタ認知と言われるものだ。
客観的に自分を観ることで今現在行なっている行動、状況を意識的に把握し、
風のそよ風、花の甘い香り、鳥の囀りなど様々な音や風景に気づくことができる。
このメタ認知が行われた際、なかなか面白い現象を感覚的に知る。
視界がクリアになるのだ。視界というか、なんというか、説明しずらい現象なのだけれど、目の奥がグググーっと引き締まり、頭のモヤモヤがなくなり、朝スッキリ目覚めた時と似ている感覚に陥る。この状態になり始めて、メタ認知が行われているとなるのではないか。
メタ認知とはマインドフルネスと同じことなのではないかと思っている。
辞書を引いてみるとこのように出る。
マインドフルネス(mindfulness)とは意図をもって、今の瞬間に、評価や判断を手放して、注意を払うことから、わき上がる気づきの状態(アウェアネス)という語義。
まさにメタ認知ではないか!!
ちなみにメタ認知の定義も辞書を引いてみる。(google検索)
メタ認知(メタにんち、英:Metacognition)とは、「メタ(高次の)」という言葉が指すように、自己の認知のあり方に対して、それをさらに認知することである。
認知することを認知する。という客観的思考はマインドフルネスの意図を持ち今に注意を払う。という行為と似ている部分があると思う。
自分自身はやはりこの状態をいかに1日をとうして続けられることができるかが重要だと思う。自分の場合は人間関係で悩むことが多い。
自分の今いる学校はイギリスに属しているのだが、同調圧力が日本同等、いやそれ以上と言っても過言では無いくらい強く存在している。
2000人以上がいる学校で、グループが多々存在しており、そのグループに属さない人は、誰だ?的な扱いを受けるのである。そこでやはり他人から嫌われる、グループから除外されるのを嫌う自分はヘコヘコペンギンのように周りを気にして
しょげて落ち込み、立ち直りを繰り返しているのである。
やはり同調圧力に負けたくはないと、孤独を恐れるな、という回答は出てくるのだが、言ってみるのは簡単で実際にやってみるのとは別問題である。
しかし、ここで言ったメタ認知を行うことで自分の無意識的に存在している認知の歪み、すなわちヘコヘコペンギン歪みを客観的に把握することで、引っ込ませることに貢献する要素の一部となり得る。
それに、メタ認知を取り入れることにより物事をフラットにみることが可能となる。フラットにみる事で人間関係に対しての期待感などを極限までに下げることが可能になる。 極端に言ってしまうと、
『自分以外の生命体とは絶対に分かり合えないから期待せんとこーっと』
的な事が起こるのである。
そしてさらに自分自身をメタ認知することで『自分は何者でもない存在』に、
いい意味で気づく事ができるのである。
何者でもないからこそ、変なプライドや承認欲求を捨てることで自分に素直に
なり『圧倒的開き直り力』で生きる事が楽になるような気がする。
しかしここまではなかなかに難しい。なんたって1日でできるものではなく、最初のうちは友達にリソースを使いすぎてしんどくなる事もあるだろう。
だからと言って諦めるのではなく、自分自身と物事全てを客観的に認知する事が
ラクに生きる真理なのである。
ここで面白いのが、子供はメタ認知力はないがマインドフルネス能力は高いのである。子供は大人より何倍も純粋で、欲望、本能に忠実であり今、この瞬間を生きている。
しかしここで気になるのが、メタ認知はないのにマインドフルネスとはどういうことだという事だろう。
確かにメタ認知力はない。子供たちが自分自身を客観的に見れたらそれはもう天才だ。ならなぜマインドフルに子供達は生きているのだろうか。
それは子供の純粋さに影響している。子供は何事も縛られる事なく、やりたいようにいき、ドッチボールや隠れんぼなど、ありとあらゆる遊びを考えて遊びまくっているのである。この純粋性の塊である子供達にとって、反芻思考や妄想などの経験はほぼ皆無であると言っても過言では無いだろう。
嫌な事や悲しい事があっても、号泣して泣くか10分で忘れるかの二択なのだ。
そう、異常な気持ちの切り替えがあるのである。
この子供心の持つ純粋性を超客観的思考とはその悪い部分を抑える仕組みを放つ。これは人生に於いてとても重要な部分である。純粋性が強すぎると物事に強く影響されやすくなってたり我が強くなりすぎたり、癇癪を起こしてしまったり、純粋性の悪い部分が出てくる。
その部分を超客観的思考で客観的に判断することでアンガーマネジメントのような役割や疑う心などを持てるようになる。純粋性を持っていても疑う心は存在するのだが母親などの絶対的支柱の前では疑うという概念は消滅する。
そもそも、ここでいう疑う心の定義を見つけてみよう。
疑う心とは、バイアスを一才無くしフラットな状態で物事を判断できる心のことを言う。メタ認知によって人に対して意識的に聴き、意識的に理解することによって、物事を的確に判断する事ができる。
ただ自分の場合人によって無意識的に態度が変わる気がするため、そこは気をつけたいところではある。
人に対して判断をせずに受け入れ、ただただ聴く、と言う行為はマインドフルネスにおいて最も望まれる行動である。判断をせず受け入れるという行為はマインドフルネスに直接的に繋がっている要素だからだ。
ここで出てくる疑問は、『でも子供はそんなの気にせずにズバズバ
聞いてくるよ?』 確かに子供は素直さの結晶でもあるため何も判断せずに本質をついてくるような批判的質問が多いと思う。
この二つの違いはやはりメタ認知を取るか、子供心をとるか。だろう。
子供心はそもそも失礼かどうかなど全く考えていない。
メタ認知により、客観的に把握することで受け入れる事が可能となる。
人間関係というものはシンプルに見えて実は結構複雑なのである。
ここで思うのは、人間関係は意識的に、客観的に行動することで
特有の悩みや苦悩が消えると信じている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
