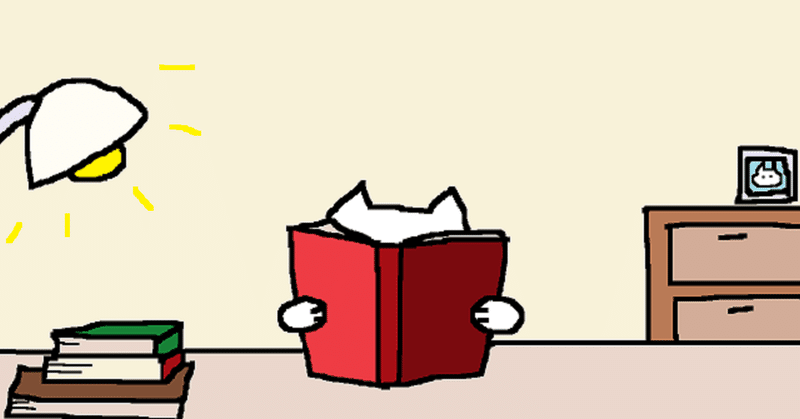
Photo by
nyakopan
#8 「教師は5者たれ」
「教師は5者たれ」という言葉がある。
5者とは、「学者」「役者」「易者」「芸者」「医者」の5つを指す。
それぞれ見ていこう。
「学者」とは、豊富な知識をもっている人のことである。1教えるのに1しか知っていなければ、子どもがより発展的な疑問をもったときに答えられない。1教えるためには10でも100でも知識を蓄えておかなくてはならない。多くを知っていることで話にも深みがでるというものだ。
「役者」とは、人を魅了する人のことである。話し方、動き、身だしなみの他、新しい視点を与えてくれる人には魅了されます。子どもと信頼関係をつくるためには、子どもを惹きつける役者の一面を持っている必要がある。面白さや教え方を高めていくことが大切である。
「易者」とは、占い師のように先を見通せる力をもつ人のことである。未来を見据えて指導をしたり、先回りして助言をしたりする力が必要である。不安を取り除き、励まし、背中を押す役割が求められる。
「芸者」とは、周りを楽しませる人のことである。周りを巻き込んで楽しい空気づくりをするのが、芸者の役割である。そのために授業を考えたり、環境を整えたりする役割を担っている。
「医者」とは、その人の特徴をとらえ、伸ばしていく人のことである。医者はその人のことを診て、病気を診断し、治し方を教えてくれる。同様に教師もその人の特徴を見極めて、その特徴の伸ばし方を教える人であることが求められる。そのために様々な指導方法をもっていなくてはならない。また、精神面でのサポートも医者の役割である。
このように様々な役割をもっていること、それを使い分ける必要があることを常に意識しなくてはならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
