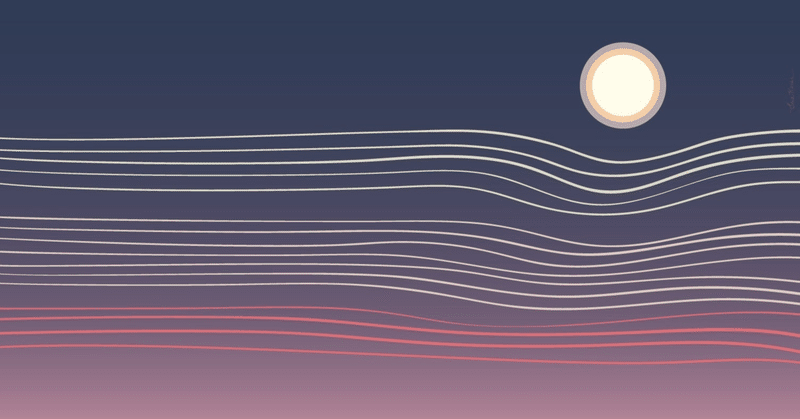
共感
心理カウンセラーという職業はまだ珍しいようで、初めて会う方に自己紹介をすると興味をそそられるらしく、色々なことを訊かれます。
カウンセラーってどんなことをするのか、どんな悩みが多いのか…
そんな中でほぼ皆さんに訊かれる質問があります。
「カウンセラーって他人の悩みを聴いていて、自分はつらくならないんですか?」
他人の悩みばかり聴いていてストレスは溜まらないのか、とも訊かれますが、これらの質問に対する答えは「ありません」です。
普段からストレス解消をココロ掛けていることもありますが、基本的にカウンセラーとしての「共感」を身に付けていくことは必須スキルとなっているからです。
カウンセラーとしての必要なスキル「傾聴と共感」は学び始めから徹底的に叩き込まれるスキルで、一生をかけて学び続けるスキル、と以前お伝えしました。
それだけ難しく、奥が深いとも言えるのですが基本的にはお客様の感情と自分の感情を切り離す、これが必要になります。
ここで比較されるのが「同感」です。
似たような言葉に「同情」がありますが、これらはカウンセリングの中では「してはいけないこと」であると学びます。
どう違うのか?
共感とは「お客様が感じているように自分も感じることであり、そこに自分の感情を持ち込んではならない」ということです。
自分と相手は違う人間です。
育った環境も違えば受けて来た躾も違い、全く違う人生を送って来ています。
ですから、相手と全く同じ思いや感情を持つことは出来ません。
そこでなるべく、相手が抱えている感情に近付けるように相手の話を聴き、自分でもその感情を感じられるようにしていく、これが傾聴と共感です。
イメージとしてはお客様と向き合う時、カウンセラー側は自分の感情をひとまず横に置く、という感じです。
一方で同感とは、相手の話に自分の経験を重ねてしまいその時の「自分の感情」を思い出してしまうことを言います。
映画やドラマの悲しいシーンなどを観て泣けてくる、というのはこの「同感」です。
これは相手の感情に自分が呑み込まれてしまっている状態で、自分が平静な状態ではなくなっていることを意味します。
これがカウンセラーだったとしたら、もうその時点でカウンセリングは成立しなくなります。
ちなみに「同情」とは相手の話を聴いて「かわいそう」などと感じることですが、これは「この人よりまだ自分の方がマシ」というようないわゆる「上から目線」的な感じ方といえます。
共感と同感、一文字違いではあるのですがその中身は大きく違います。
同感してしまうということは、自分の中に在るつらさや苦しさを思い出すことであり、それはストレスとなってしまいます。
私もカウンセリングを学び始めた当初はこの同感ばかりになってしまい、共感の難しさを実感していました。
これは共感する意識を常に持ちながら実践を重ねていくことで、身に付いていくモノであるため、私も時間をかけて実践を重ねて、何とかお金が頂けるかな、と思えたところで開業をしました。
それでも常に学びの姿勢を持ちながらお客様と接すること、また日常の会話の中でも傾聴と共感を意識することは大切であり、一生をかけて学んでいくモノとして、これからも精進しなければなりません。
頂いたサポートはカウンセリング普及活動などに使わせて頂きます
