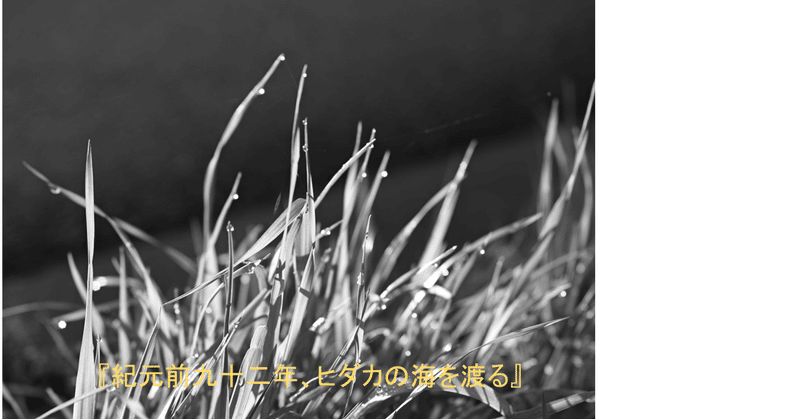
『紀元前九十二年、ヒダカの海を渡る』[122]騎馬と騎射
第5章 モンゴル高原
第9節 季節は巡る
[122] ■3話 騎馬と騎射
生まれつきおとなしくはあっても、決して従順とはいえない馬を手懐け、そのために工夫した用具を使って乗りこなす技は、長い年月を掛けて編み出されたものだとたいていの匈奴は知っている。もともとそれは、北の草原の道を通って西から渡ってきたサカ人がモンゴル高原に伝えたものだという。
匈奴には、ヘーベ――ものを入れて運ぶためのヒツジの毛で織った大型の肩掛け袋――を馬の背に左右に振り分けておいて跨いだり、叩き布や毛皮を掛けて乗ったりする者はいるが、鞍は使わない。踏ん張りに使う鐙もない。両の腿で馬腹を挟み、ときには足先を掛け、落馬しないように姿勢を保ちながら騎乗する。
どの騎兵も馬銜から回した手綱を操り、さらに戦闘時にはその手綱をも放して矢をつがえ、弓を引くという技を習得している。騎射に巧みであるとは、決して弓のことだけをいうのではない。体が利いて、身軽で、落馬を恐れずに動くことのできる心と技を身に付けているということなのだ。
騎兵の武器は第一に腰に下げた弓袋に入れて持ち歩く弓と矢だった。鏃には射る獲物と用途に応じていろいろな形がある。それと、ここぞというときのために槍を持ち、剣を帯びる。背に負う者も多い。
剣はもとは両刃の直刀だったが、いつのころからか匈奴には、少し短めの反りのある剣を使う兵が現れた。その方が馬上での使い回しがいいという。
木製の盾を持つ騎兵もあるが、いざ使うとなると片手がふさがるし、素早く動けないからと、左賢王の護衛に回るときでなければメナヒムの騎馬隊に盾を使う者はいない。
剣や槍に替えて、長めの木の柄をもつ手鉾を使う者もある。エレグゼンがそうだった。剣であれ、手鉾であれ、修練した者が馬で駆け抜けながら薙げば、ひと駆けで歩兵数人の首を刎ねることも稀ではなかった。
エレグゼンは、仲間内ではそのような手練れの勇者として知られていた。騎射に長け、馬上から後方に向けて矢を放つ。その三翼の鏃を首に受け、血を噴いて命を落とした敵の将兵をエレグゼンの仲間は戦場で幾人となく見てきた。
また、刃に厚みのある手鉾も巧みに使った。革の短甲を身に付けて、左右を払いながら敵の騎兵の列に正面から突っ込み、敵の圧力を一気に削ぐ。そこに味方の騎兵が殺到して敵陣を真っ二つに割り、後ろへと回り込んで総崩れに追い込んだことが何度もある。
エレグゼンは他に、亡くなった父親の形見の反った短剣を革の胡帯に挟んで持ち歩いている。柄に凝った彫り物が施してあり、もとは名のあるペルシャ兵が使っていたものだという。
匈奴の兵はこのように、弓を持ち、使いやすさを考えて自分に合った武器を思い思いに選んで、戦いに臨んでいた。
匈奴とは違って、長い間、漢には馬の脚力を活かして戦うという考え方がなかった。よい戦馬が手に入らなかったためだろう。そのためか、戦場では戟を手にする者が多かった。匈奴兵は避けようとするのだが、仮りに、馬を止め、あるいは下馬しての白兵戦になると、この戟は決して侮ることができなかった。
現代日本にいまも残る流鏑馬や笠懸の騎射がそうであるように、馬上の匈奴騎兵は、左下方に矢を放ち、あるいは、上半身を捻って左後方を射る。前で外したり、または、手ごたえは感じたというときには、素早く二連射してとどめを刺す。流鏑馬ではそれぞれを弓手筋違と押捻と呼ぶそうである。
押捻という騎射法は、胸の張りをいっぱいに使うので矢に力がある。それは岩をも貫き通すほどだったのだろうか。
この物語で、後に、ニンシャ人を移住させた漢の英雄として登場する李廣将軍は、漢の史家司馬遷によれば、母の仇の虎と見るや、それに似た石に矢を羽ぶくらまで突き立てたというほどの弓の名人として匈奴の間に知られていたという。
高速で、かつ、長時間の移動が可能な戦闘馬と、騎乗したまま射撃し、弓矢と剣槍を使いこなす戦闘術を身に付けた人馬一体の騎兵がどれほどの破壊力をもって歩兵と対峙したかを知ることは、この後の物語の展開を追う上で大事かと思う。
杉山正明氏の著書によれば、その好例を米国人の東洋史家ポール・スミスが「天府に課税して」という著作に記しているという。それを引用して示すことにしよう。一二世紀の初めに北宋という中国の王朝下で実際に起きた小事件だという。
『北宋が、宿敵のキタイ遼帝国を、新興の女真族の金朝とむすんで打倒した直後のことである。金朝側の講和使節団は、十七騎で本国との連絡のため、河北を北へいそぎつつあった。それを途中で、北宋側の在地軍事指揮官が、二千の歩兵をもって襲撃した。討ちとって、戦功としようとしたのである。
ところが、武装していた十七騎は、ただちに左・中・右の三隊にみずからを小分けした。中央に七騎、左・右両翼に五騎ずつである。手なれた戦闘隊形であった。このささやかな三隊は、駆けめぐり、射たて、敵陣を攪乱し、縦横に馬を走らせた。二千人はさんざんに翻弄され、なすすべなく潰走した。十七騎は、一騎もそこなわれなかった。これは、北宋側の記録にあり実話である。』
――杉山正明著『遊牧民からみた世界史 増補版』日経ビジネス人文庫、43ページより引用――
騎兵と歩兵とでは働きが全く違う。この物語では、騎馬の技術をモンゴルに伝えたのはサカ人としている。実際にはどうだったのだろうか?
紀元前六世紀の終わり頃、ペルシャ王ダレイオス一世の軍を騎馬戦術によって打ち破ったと古代ギリシャの歴史家ヘロドトスが記すスキタイは、カスピ海から黒海の北岸一帯を移動しながら、国としてのまとまりをもっていたとされる。
この、カザフ草原に起源をもつとみられるスキタイの騎馬技術は現在のロシア連邦・ハカス共和国の草原を経て、紀元前四世紀後半頃までにはモンゴル高原に伝わった。それには、ペルシャ系やテュルク系の人々も大いにかかわったと想像されるが、この物語ではこれらを敢えて区別せずにサカ人とする。
漢王朝の時代に北方にいた北狄と総称される異民族のうちの塞はこのサカ人を指しているという。
騎兵の威力は単騎でも大きい。それが十騎、百騎とまとまると、歩兵ではまるで歯が立たなくなってしまう。匈奴への言及が初めて現れるとされる『戦国策』が成立した中国の戦国時代末期から前漢初期において、匈奴の軍事力はどの王朝をも圧倒していた。
そのような戦場における力の不均衡は、漢の劉徹という王――武帝――が良馬を手に入れ、羌族や降って服属した匈奴の将兵などの騎兵を漢の地方軍である郡国軍に組み入れるまで続いた。
第9節4話[123]へ
前の話[121]に戻る
