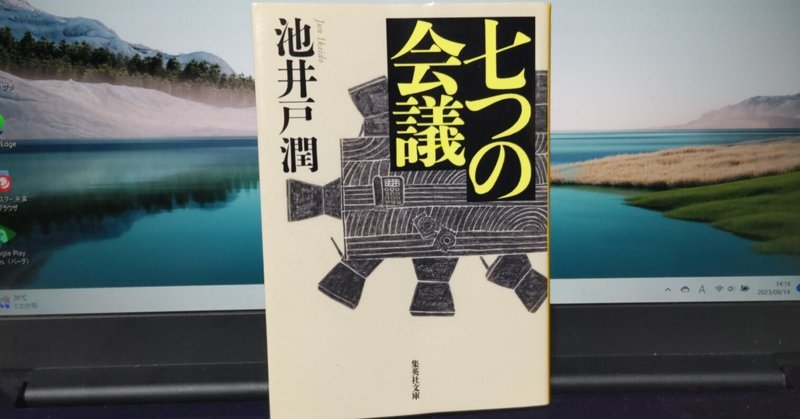
8/12 『七つの会議』を読んだ
父が亡くなった後、遺品整理とは名ばかりの父の部屋漁りをしていたときに見つけた本。へー池井戸潤なんて読んでたんだ、しかも結構最近の、と手に取ると、本の真ん中あたりに栞が挟まっていた。父はある日前触れもなく急に脳梗塞を発症して、あれよれよと入院、そしてそのまま家に戻ることなく逝ってしまった。この本がいつ購入されたものなのか、父はこの本を、この栞をいつここに挟んだのか、定かではない。もしかしたら「あの日」の前日まで読んでいて、そしてこの先を読むことなく逝ってしまっていたのだとしたら、代わりに読んでやりたいと思った。まあ、そう思ったはいいものの、長々と積みっぱなしにしていたらいつの間にか七回忌まで迎えてしまっていたのだけど。
読む前の動機はそんなしっとりした深イイ話であったが、読んでる間はそんな感傷とは特に関係なく面白く読めた。ちなみに僕自身は池井戸潤の小説は2冊目、『架空通貨』を過去に読んだことがある。『半沢直樹』のドラマはほとんど観てない。小説はいずれ読んでみたいと思う。お仕事小説というかサラリーマン小説というのか、結構好きなジャンルだ。他人の仕事場を覗き見るのは面白いからだ。それもこういう、サラリーマンのお仕事なんてのはドラマとかじゃ「映え」ないから、なかなか見られないし(そういうのを「映え」るように面白くしたドラマが『半沢直樹』なのかもしれないが。ちゃんと観てないのでわからない)。
各章ごとにクローズアップされる人物が替わるが、そのたびに彼らの来歴が語られるのが面白い。こう言うと失礼だが、全員ただのサラリーマンなのに、誰々の次男坊として生まれたとか、歴史上の人物の系譜でも語るように語られる。彼らの親も同じくサラリーマンだとか小さい工場の経営者とかだし。妙に仰々しいが、そここそ魅力のひとつだとも言えるか。サラリーマンたちの時代小説。言われてみれば、専務とか常務とか取締役とか、あの何がどう違うのかよくわからない役職って、どこどこの守とか何々の介みたいなののわからなさと通ずるものがある。
章と視点人物が替わると話のスケールも肥大化していき、片方からは見えなかった側面が見えてくるところは『ブギーポップは笑わない』をもほうふつとさせる。あれはひとつの学園内で起こった事件が、実は世界の存亡にも関わる危機につながるというものだったが、今作もだいたい似たような話だった気がする。八角がブギーポップだったかどうかは、わからないが……。解説を読むと、八角がここまで事態の中心に座すとは思いもよらなかっただろう、と言われているのだが、僕はそうは思わなかった。実は今作の映画を、半分くらいまで観ていたせいだ。映画じゃ野村萬斎主演で八角がど真ん中にいるのだから、そりゃあ注目しないわけがない。冒頭に書いた経緯があったから、映画も最後まで観ずに結末はとっとこうとなっていたわけだが。何も情報入れずに読んでたらまた違った印象だったかもしれない。映画もまた今度しっかり観てみよう。
ちなみに、父の栞が挟まれていた箇所は、物語の核心でもあるねじの品質問題に、まさに切り込まんとしている場面だった。もしここで中断していたのだとしたら、さぞかし続きが気になっていたことだろう。僕としても映画を途中で止めていたので、奇しくも状況は似ていた。こうして物語の結末を見届けられて感慨深い。ちょうどお盆どきに読み終えたことだし、墓参りに行ったら報告しておこう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
