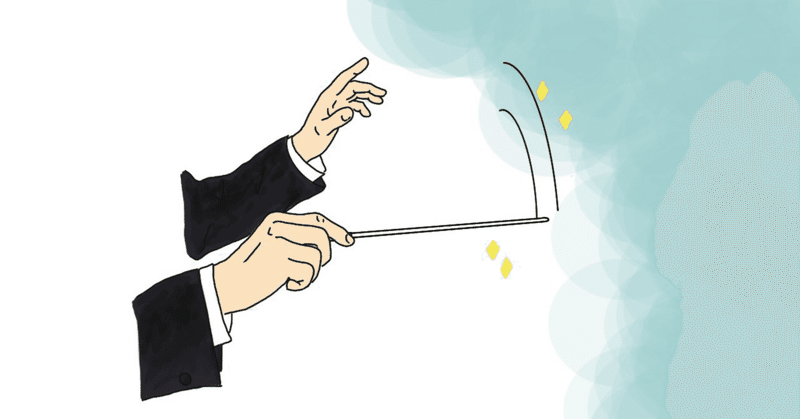
耳をそばだてる
指揮をするようになってからは何事も先んじて動いていなければ現実に対応できない、という姿勢が身についたように思う。現実に身を任せるのではない。現実の波に乗れるかどうかは自身の身構えの問題なのだ。そういう考え方ができるようになった。
それは「聞く」という姿勢について最も顕著である傾向がある。音の真ん中ではなく、音の先端を聞くようになったということだ。「子音」が鳴るその前の瞬間を捉える、とでもいうのだろうか。聞き耳を立てる、というのはまさにこんな感じだろう。
その聞く姿勢は実に「日本語」的ではない。いや、むしろ意識的に日本語的な耳を乗り越えようとしている。ここに大きな違いがあるように思うのだ。
日本語の発音は母音と子音が混ざり合わさって音になる。だが、ドイツ語や英語は、日本語的な耳でいう「音になる前」に子音という音がある。日本語耳には「ノイズ」の類かもしれない。だが、それをキャッチして「聴く」ようになると、音楽はそれまでとは全く違う快楽にあることがわかった。
さて、その転換へのきっかけは大学時代によく通ったN響に負うところが大きい。
「80年代のサヴァリッシュ」という括りが自分にはある。この頃のサヴァリッシュには鋭いキレのある演奏が聞かれ、夢中になって演奏会に通ったものだったし、その中継録音やテレビ録画も宝物のようにしていたものだった。
さて、今から思うと、この頃のサヴァリッシュはN響やコーラスに対する「子音」に鋭いものを求めていたように思う。直接的にそういうリクエストがあったかどうかはわからないが、その演奏からは明らかにそういう指向が聞いて取れるのだ。限りなく透明な響きと鋭さ。氷のナイフのようなコンビの演奏は毎シーズン楽しみだった。
85年ごろのブラームスプロでのop90やop98の第4楽章などでも聞けるが、時にはあからさまにアンサンブルの入りをずらすこともやって退けたが、それも鮮やかな効果だった。
自分が惹きつけられたの原因はそこだったのだろう。というのも当時、その他のドイツ系の指揮者もたくさん演奏していた(贅沢な時代だったなあ。スイトナーとかホルストシュタインとかライトナーとか当たり前のように聴くことができた)がこの鮮やかさは他では聴くことができなかったからだ。
同じような嗜好を感じたのは晩年のベームとウイーンフィルとのコンビだった。この頃の演奏には、特にバイオリン群の音の美しさとキレがとても鮮烈だった。78年のザルツブルクでのK.551の第1楽章や最後の来日公演でのベートーヴェンop92の終結部に聴く2ndvnと1stvnの熾烈な争いは聞いていて興奮させられたものだった。レコードでもFM放送でのライブでもこの強靭かつしなやかな艶のある演奏が聞けたものだった。
いや、それらを聞き取ろうと必死だったのかもしれない。前倒しにそれらを聞こうとしていたのだろう。
こういった音の先端を捉えることは結果として演奏の発音に大きな影響を与える。それとともに、その先端を確実に捕まえるために音楽の骨格を聴くようになる。
それらに気がついたことは大きな転換点だった。
だが、少し油断をすると、日本語耳に戻ってしまう自分がある。そんな時思うのだが、モスキート音が聞こえなくなるのは老化の問題だけではないのではないだろうか、ということだ。それは意識の問題も関わっているのではないだろうかと。つまり、日常生活上ではその音域は関係ない。だから意識が向かなくなる。それが「モスキートか聴こえなくなる」ことに関わっているのではないだろうかと。
仮にそうだとした場合、音楽耳においても同じような「意識」の問題が大事なのではないだろうか?油断すると日本語耳になってしまうのもそのためなのではないだろうか?
油断して聞こえないのではない。聞こうとしていないのだ。「意識する」「耳をそば立てる」は大事なのだ。「聴こえる」のではなく、「聞かねばならない」のだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
