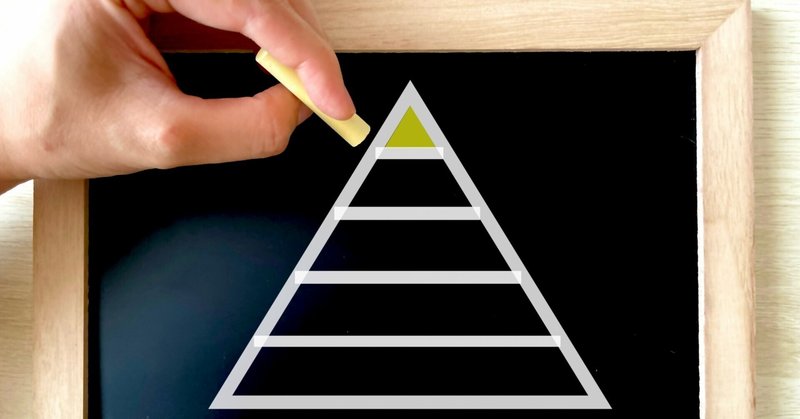
社長の決裁は重いー使用者からの過払い残業代の返還請求が否認された事例ー
労働者が労働契約や労働基準法で定められた基準以上に働いた場合、使用者は労働者に残業代を支払う必要があります。
その場合、ほとんどのケースでは労働基準法37条により残業代が計算されます。
具体的には、1日8時間・週40時間を超える時間外労働には125%、午後10時から午前5時までの深夜労働には25%、休日労働には135%の割増がつきます。
それでは、この水準を超える残業代が労働者に支払われていた場合、使用者は過払い分の残業代の返還請求をできるのか。
今回は、この点について参考となる事例として一般社団法人奈良県猟友会事件(大阪高裁令和3年6月29日判決・労働判例1263号46ページ)を取り上げます。
どんな事件だったか
本事件は、原告に支払われていた残業代が被告法人における労働契約や就業規則で定める水準以上であるため、被告法人が原告に対して過払い分の返還を求めたという事案です。
なお、この過払いの残業代についてはその支給を当時の代表理事が容認しているという事情がありました。
これに対して、第一審(奈良地裁令和2年8月12日判決)は被告法人の請求を認めました。しかし、控訴審は被告法人の請求を否認する逆転判決を下しました(原告側勝訴)。
裁判所が認定した事実
裁判所が認定した事実の概要は以下のとおりです。
平成27年4月、原告が被告法人から正職員として採用される(労働条件は労働時間が1日7時間・週40時間以内、給与は月額15万5000円)
原告、被告法人の職員Bより残業代算定の基礎賃金の算定方法を「基本給÷(1週当たり勤務日数×4週)÷1日当たり所定労働時間」とするように指示される
ただし、被告法人のA前会長から原告はまだ仕事に慣れていないという理由で平成28年8月まではBと同じ基礎賃金1071円で計算。
平成28年9月以降は2.の計算式に基づいた基礎賃金の計算が行われる
A前会長、平成29年4月から原告の基本給を月額18万円とするように指示。原告、この指示に基づき同月分から11月分まで基本給を18万円とする給与計算を行う
平成29年5月1日、A会長、監事会において出席者に対し原告を含む事務員の基本給を平成29年4月から2万5000円増額した旨の報告を行う
この計算の結果、原告は被告法人の就業規則で定める水準以上の残業代を受領する結果となる
裁判所の判断内容
裁判所は以下の理由で被告法人の残業代の返還請求を否認しました。
時間外、休日及び深夜の割増賃金に関する労働基準法の規定の趣旨は、時間外、休日、深夜労働に対し、使用者に一定以上の割増賃金を支払わせることになるので、その趣旨に反しない限り、同法所定の計算方法と異なる(労働者に有利な)計算方法を採用することができる
被告法人の代表理事には、事務員の通常の労務管理についての業務執行の決定を委任されていた
そのため、A前会長の決定に被告法人の利益を害する権限濫用があったとしても、行為の相手方が濫用の事実を知り又は知り得べきものであったときに限り、当該行為は無効とされる
本件ではA会長が代表理事としての権限を濫用したという事実自体がない。そのため、原告への残業代支払は有効
したがって、被告法人による過払い残業代の返還請求は認められない
判決へのコメント
賃金過払いの案件を扱う上で非常に参考になる裁判例だと感じました。
近時、過払いの賃金について労働者に対する不当利得返還請求(民法703条)を認める事例が散見されます(例えば社会福祉法人恩賜財団母子愛育会事件・東京高裁令和元年12月24日・東京地判平成31年2月8日労働判例1235号40頁)。
この愛育会事件では、管理監督者の立場にない労働者に管理監督者手当としての性質の手当を支給していたものについて、労働者に対する同手当相当額の返還請求を認めました。
この裁判例が出たとき、いったんは労働者を管理監督者として扱って残業代を未支給としておきながら、いざ訴訟で管理監督者性が否定された場合には手当を返還請求すればよいということになりはしないかが危惧されました。
しかしながら、今回の裁判例は使用者の代表者には通常の労務管理について委任を受けているので、その範囲内の行為は有効であるとしています。
この判断によると、愛育会事件と同様の事件が起きた場合でも、使用者側は代表者に与えられた代表権・人事権に基づいて就業規則よりも有利な賃金を労働者に支給していた以上、その賃金支給は原則として有効である、そのため賃金の返還を請求することはできない、と構成することができそうです。
この論理構成は、信義則(労働契約法3条4項)や権利濫用(同条5項)という一般論に依存しなくて良い点で説得力が強く映ります。
最後に
このように、今回の裁判例を使えば使用者側からの過払い残業代の返還請求を拒絶できる余地をかなり大きくできるように思われます。
とはいえ、今回の裁判例は飽くまで一事例の判断であり、また、「代表権の濫用」という論理構成を用いた点も新しいことから、そのような判断が一般化するかはこれからの議論を注視する必要がありそうです。
ただ、このように会社法をベースにした新しい法的論理構成を編み出せるようになるためにも、普段から他分野の論点にもアンテナを張っておく必要があると考えさせられた次第でした。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
