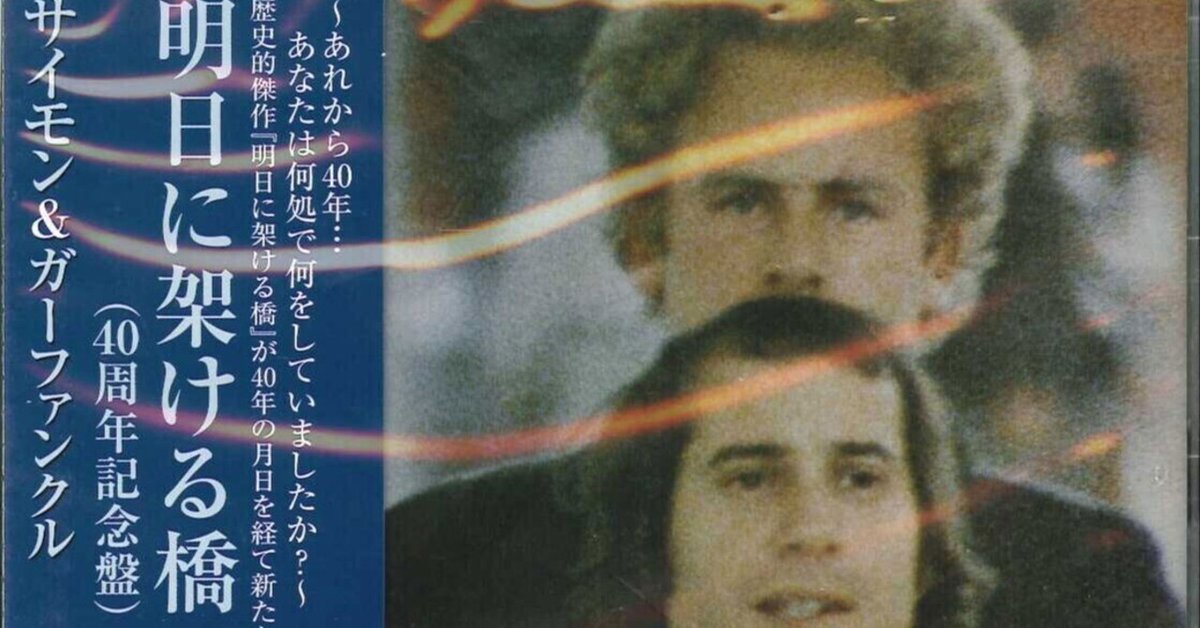
ネタニヤフ首相に捧げる世界の平和を訴える東西詩集 ―仲間には友情、敵には忍耐
「世の平和は二つで成り立つ。仲間には友情、敵には忍耐」-ハーフェズ(イランの詩人:1325~1389年)
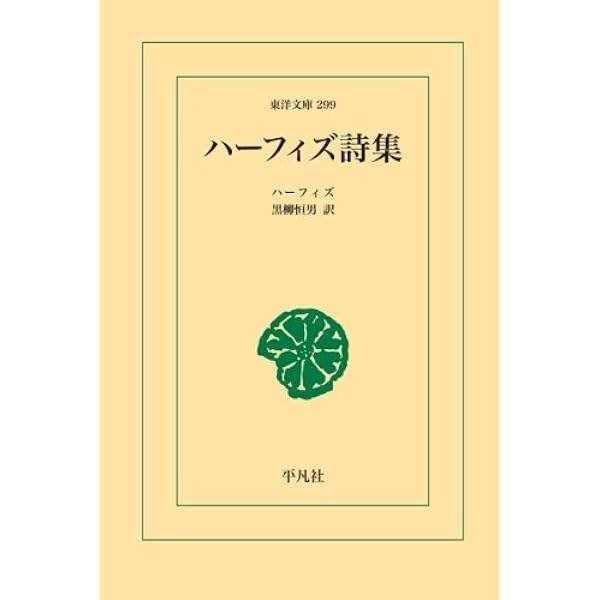
これは、言うまでもなく現在戦争を起こしているイスラエルのネタニヤフ首相あたりに教えてあげたい言葉だが、同様な情感や表現は時空を超えてある。ベトナム戦争の頃、1970年のビルボード年間チャート1位となったサイモンとガーファンクル楽曲「明日に架ける橋」も反戦運動が高まる中で歌われ、戦争の時代に苦悶する若者たちへの配慮や気づかいを表した。歌詞は苦しみや悲しみという激流を越える橋になるという身を挺して救い手になる想いを表現したものだ。ベトナム戦争の頃、戦争という大きな矛盾に反対する人々の連帯や共感にも通じるものがあった。
「明日に架ける橋」はアレサ・フランクリンによってもカバーされ、反アパルトヘイト運動の歌として広く聴かれ、歌われたが、南アフリカの白人政権はこの曲を放送で流すことを禁じたほど、この歌は反アパルトヘイトのシンボルともなった。アパルトヘイトが南アフリカで撤廃されると、この歌は教会で歌われる賛美歌にもなるほど南アフリカの人々の間で定着した。(NHKハイビジョン特集 「世紀を刻んだ歌 明日に架ける橋 〜讃美歌になった愛の歌〜」)
君が生きる事に疲れ
惨めな気持ちになり
思わず涙ぐんでしまう時
僕はその涙を消してあげるよ。
僕は君の側にいる
辛い時も
友達が見つからない時も
激流を越える橋のように
僕がこの身を捧げるよ
激流を越える橋のように
僕がこの身を捧げるよ

同じ頃、世界のポップシーンをにぎわしていたビージーズのデビュー曲「ニューヨーク炭鉱の悲劇」(1967年)も1941年にニューヨーク炭鉱で起こった落盤事故という設定で、坑内に閉じ込められた人々(ベトナム戦争の戦場に赴き、社会から隔絶された兵士たち)への同情を歌ったものだった。実際には1966年にイギリスのウェールズ地方アバーファン村の炭鉱事故を題材としたものだったが、太平洋戦争が始まった1941年を舞台にして反戦の想いがいっそう強調された。
(歌のユーチューブ動画は https://www.youtube.com/watch?v=xxB9xpb7ywsにある。)

ヘルマン・ヘッセ(1877~1962年)は、祖母はフランス系スイス人、父はドイツ系ロシア人で牧師、叔父はアメリカで牧師、また従兄は日本に渡って、能や禅の研究をするなど世界市民的な家庭環境の下に育った。第一世界大戦が始まると、ドイツの知人、文化人までも戦争を煽るようになっていったが、ヘッセは平和へのアピールを、戦争を煽る人々を諫めるように、「おお、友よ、その調子をやめよ!」という論稿をチューリッヒ新聞に寄稿し、「地上の平和と友情は、われわれの最高の理想である。」と説いた。ヘッセはこの論稿を読んで感銘したフランスの文学者ロマン・ロランとの親交を深め、友情の手本を示し、平和の理念を強調した。

わが友よ、友情の価値を識りなさい
これはあまりにもわかりきったこと、敢えて語る必要すらない ―ハーフェズ
(佐々木あや乃「ハーフェズ詩注解(12)」より)
「友には友情、敵には譲歩、現世来世の安らぎは、この二つを心得てこそ」-イランの詩人サーディーの言葉
サーディーは「何よりも重要なのは、後に引けなくなるような対立に至らぬよう、必ず歩み寄りの余地を残しておくこと。暴力的手段に訴えるのではなく、相手に対して寛大さを示すことが説かれる。」と説いた。(清水直美「実践道徳」『イランを知るための65章』明石書店)サーディーの考えは、アラブ、モンゴル、現代ではサダム・フセインのイラクなど外的の侵攻を受け続けたイラン人の知恵といえるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
