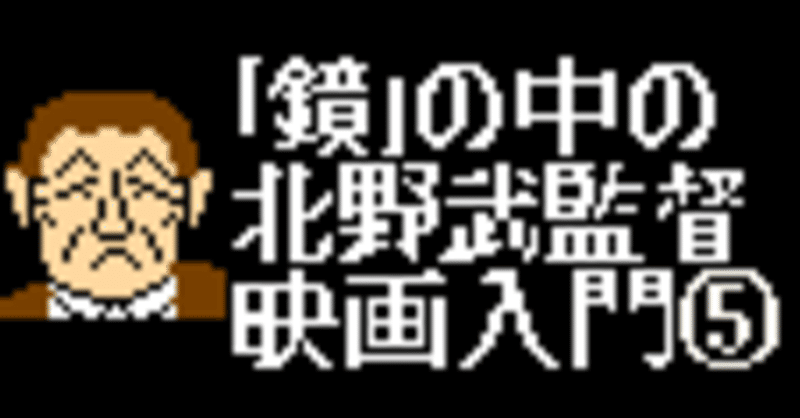
生命と存在を自己否定するエンディング:「鏡」の中の北野武監督映画入門⑤――『その男、凶暴につき』をテキストに
(この「『鏡』の中の北野武監督映画入門」シリーズでは、『その男、凶暴につき』を含め、多くの映画作品のネタバレを含みます。文章内容の性質上ご了承ください)
締めくくりに入るべく、ラストシーンを論じる。北野映画で一番有名なラストと言えば、『キッズ・リターン』(96年・5作目)だろう。マサル(金子賢)とシンジ(安藤政信)はそれぞれの道で成長し、大きな挫折を味わう。そして2人が出会った高校の校庭で自転車に乗りながらこう言う。
シンジ:「マーちゃん、俺たちもう、終わっちゃったのかな」
マサル:「バカヤロー。まだ始まっちゃいねえよ」
人生に躓いた2人の「再出発」ととるか、「強がり」ととるか。ポジティブにもネガティブにもとれる(これもまた反対の対立軸を作っている「鏡」といえるかもしれない)のシーンの印象は、観た人間の感性にゆだねられるだろう。いずれにせよ『キッズ・リターン』で描かれた青春と失敗は、シンジとマサルにとって終わりも始まりもどちらの意味も成していないいない。ある意味これも「映画の物語そのものの否定」ともいえる。
こうした「否定」する映画術は常に長らく北野映画の芯となってきた。『ソナチネ』、や『アウトレイジ』では監督のたけしが、スクリーンの中のたけしを自殺させたり殺したりすることで生命を「否定」し、「たけしの死」以外にも『座頭市』のラストでは最強の侠客があっけなく小石に躓き、『アキレスと亀』では芸術を追いかけ続けた主人公が、「芸術作品」である空き缶を蹴っ飛ばしている。作品の根幹をなしていたアイデンティティを、いともあっさり否定していしまうのだ。
では北野映画の第1作、源流たる『その男…』はどうか。
(清弘のアジト)
①:我妻が清弘の潜伏するアジトに侵入し、互いに発砲しあい、我妻の弾が清弘を顔を貫き、清弘死亡
②:物陰から灯が現れるが、既に清弘の部下にヤク漬けにされていた灯の精神は完全に崩壊しており、清弘の死体に「クスリ、ちょーだいよ」とすがす。その姿を見た我妻は灯も銃殺
③:2つの亡骸を背に歩き出す我妻は仁藤の部下である新開(吉沢健)に銃殺される。文字通り死屍累々となった現場を見て「どいつもこいつも気狂いだ」とつぶやく
(橋の上)
④:サティの『グノシエンヌ第一番』をアレンジしたBGMをバックに我妻が面倒を見ていた菊池がさっそうと歩いていく。映画序盤にも全く同じBGMと場所で我妻が歩いていくシーンそっくりの構造である
(かつて仁藤のオフィスだった場所)
⑤:生前の我妻に殺され、死んだ仁藤の後を継いだらしい新開に「岩城の代わりが出来るか」と聞かれ、菊池は「僕は馬鹿じゃないですから」と厚みのある封筒を受け取る
ついに自分の「鏡」である清弘を殺し、自らの暴力の意義を果たしたと考えたであろう我妻はつかの間、②ですぐさま否定される。なぜなら暴力のきっかけとなったはずの妹がもはや、「自分の知っている妹」ではなくなったからだ。そして③で結局我妻も殺され、互いの存在を消そうと躍起になっていた2人は同じように銃殺死体となり、「気狂い」という放送禁止用語でイコールにされ、第三者から存在を否定されるのだ。
④で冒頭の我妻そっくりのシーンを演じることで、ひ弱だった菊池が我妻の後継者となったように見せかけるが、これは監督であるたけしが巧妙にしくんだフェイントで、すぐに⑤で最終的にどうも誅殺されたらしい、汚職刑事の後を継いだことがわかる。つまり凶暴な刑事と殺し屋の壮絶な殺し合いは「無駄死に」であり、激しい暴力を生んだ環境にリセットされてしまったのだ。我妻は死後もなお、作中でしてきたことを否定されるのである。
黒澤明の『生きる』(52年)では、志村喬演じる主人公の葬儀で、役所の同僚たちが遺志を受け継ぎ、役所改革へ一念発起する。しかし翌日には元の木阿弥となり、いつも通りのお役所仕事に戻ってしまう。ここで主人公の死を「否定」しつつも、主人公が作った児童公園は子供にあふれ、「肯定」もする。「ハッピーエンドというわけにはいかないが、主人公の死は全くの無駄ではなかった」という絶妙なバランスのラストで知られている。
反対に『その男…』は、我妻の死を角度を変えて執拗に「否定」していく。マイナスにどんどんマイナスを足していき、精神的な「死体蹴り」はいつ終わるのかと、観客への心理的ダメージや憂鬱を倍増させてくる。やはり映画の本質は観客の感情を揺さぶることだ。しかしたけしは暴力をただの、物理的な殴る蹴る撃つでは終わらない。主人公が死んでもなお、観客を心理的に痛ぶる強さを持った暴力である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
