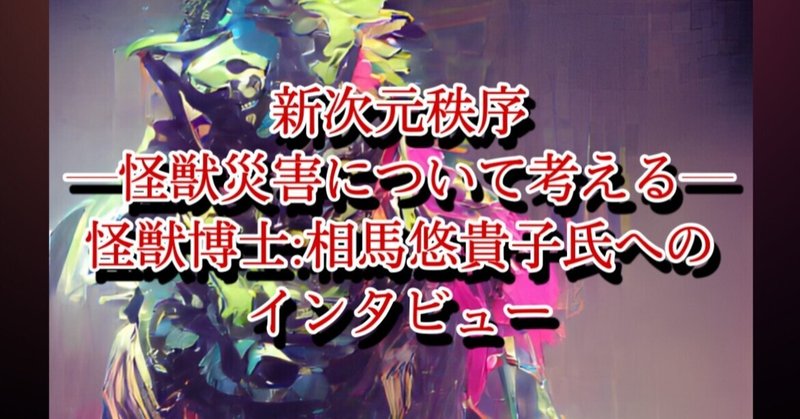
新次元秩序 ─怪獣災害について考える─ 怪獣博士:相馬悠貴子氏へのインタビュー
年々増加する怪獣災害について、怪獣の専門家に話を聞いた。
相馬悠貴子氏へのインタビュー
先日行われた新次元秩序フォーラムにて登壇された怪獣学者の相馬悠貴子さん。当フォーラムでは今後も対策の危ぶまれる怪獣災害について詳しくお話しいただいたが、怪獣とはいかなる存在であるのかを改めて彼女に聞いた。
●怪獣災害に遭遇したら。
──フォーラムでの発表ご苦労様でした。フォーラムでも話されていましたが、相馬先生は怪獣学者として怪獣とどう向き合っていくべきと考えていますか。
怪獣災害と言っても十年前の西新宿怪獣災害のような大きなものから、全国各地で起こる小さなものまで色々です。
後者のような小さな怪獣災害に関しては毎年のように発生しているので、対策する側の設備も技術も年々向上していますね。
先日、千葉県松戸市で怪獣が発生した際は住宅街にも被害が出ましたが、幸い死傷者は0人でした。
それだけこの数年で気象庁の怪獣対策が進んでいる、ということでもありますが、同時にそれは市井の人々の怪獣への危機感が薄らいでいる、ということでもある。
いつまたアルファT のような大怪獣が現れるとも知れない。その可能性はいつでもついてまわります。怪獣という存在が、他の災害と同じように身近になってしまった今だからこそ、人々は改めて大怪獣の出現に備える必要があります。
──実際に怪獣に遭遇してしまった際、我々が気をつけるべきことはあるでしょうか。
何事もそうですが、まずは慌てないこと。貴方が第一発見者であれば必ず気象庁の怪獣対策センターに通報すること、です。
そして必ず未知の怪獣からは距離を取ること。人に害を為さない怪獣が人と共存し、町おこしに使われた例もありましたが、それはあくまで例外的なものです。見た目が凶暴そうであろうが、どんなに無害そうであろうが、そんなことは関係なく、怪獣からは即座に逃げること。
先日の松戸の怪獣災害で死傷者が出なかったのも、怪獣からの避難が徹底されたからです。
松戸は以前、怪獣災害で犠牲を出してから怪獣対策としての避難訓練を毎年していたそうですから、それが功を奏したと言えるでしょう。
──それは怪獣に襲われる危険性を低くするためですか。
それもありますが、彼らは野生動物とも違う。怪獣は本来、この世界の存在ではありません。怪獣は自身の生存が可能な形に周りの環境を変えてしまう。怪獣の生存可能領域で人間が耐えられない可能性も決して低くない。
怪獣とは言ってしまえば、ただそこにいるだけで危険を孕む存在です。決して他の生き物とは相容れない。
●怪獣保護研究施設の必要性。
──怪獣愛護を訴える団体の影響力も、近頃ではかなり下火になってきました。
当然です。怪獣が現れてすぐの頃は、そうした怪獣の危険性があまり知られていませんでした。だから他の野生動物なんかと同じ感覚で、愛護を訴える人々もいたわけですが、それは無知故の過ちです。
とは言え、今は怪獣が当たり前の世界、共存はしていかなくてはならない。怪獣と向き合うのに必要なのは、無知故の愛護ではなく、知識を下地にした保護と研究です。
新次元秩序フォーラムで多くの方々のお話を聞けたことは、私にとっても勉強になりました。
──当フォーラムが相馬先生の今後の研究の参考になったのであれば何よりです。
こういう集まりであればまた是非参加させていただきたい。次の開催を心待ちにしています。
──怪獣の生存可能領域で人間が耐えられない例を教えてください。
比較的スタンダードな例としては、生息環境の汚染です。怪獣が存在する半径数キロメートルの範囲内が全て、既存の生態系とは根本的に変わってしまう。
木々から魚から鳥まで、在来種は死滅し、代わりにその全てが小型の怪獣 に置き換えられる。
こうなれば当然、人間はそこに住むことはできません。だから環境汚染が明らかになったならすぐにでも、対怪獣部隊が派遣されることになります。怪獣を駆除できて解決すればいいですが、そう上手く行く例は実はそう多くはありません。怪獣を駆除してもその死体から周囲への汚染は止まらないことが多く、そもそも駆除自体ままならず、怪獣保護研究施設 への移送くらいしかできないことすらあります。
また、怪獣が周囲の物理法則すら書き換えることもあります。
──俄には信じがたい話です。
大怪獣アルファTも周囲の物理法則を書き換える怪獣だったと言われています。
アルファTは全長100メートル超、体重60,000トンを超える大怪獣でしたが、その大きさに関わらず、猫のように俊敏だったため、多くの人々を震撼させました。しかし、それだけの大きさで何故あれだけの動きができたのか、しばらくの間不明でした。
あの巨体であれば、体を動かすどころか、自重で潰れてしまうのが自然です。
──けれども生存していたのは物理法則を書き換えていたからだと。
はい。アルファの周囲では、重力値の異常があった。大なり小なり、怪獣はそれに近いことをしているのだと思います。
だからこそ、駆除できた怪獣も、できなかった怪獣も適切な形で施設に送られなければならない。
──怪獣保護研究施設の不足も近年の課題の一つですね。
駆除できないのであれば施設で隔離する他ありませんからね。怪獣災害は年々増加する一方です。怪獣保護施設の増築は、放射性廃棄物の処理以上に切迫した問題です。
──本日はお話いただきありがとうございました。
※1…アルファは西新宿怪獣災害の原因となった怪獣の呼称。単に大怪獣とも。往年の怪獣映画に出てくる怪獣の名で呼ばれることもあったが、後に定められた怪獣の名称付けルールに則り、正式にアルファTと呼称されることとなった。
※2…怪獣の出現と共に現れることの多い小型の怪獣は小怪獣、クリーチャーと呼ばれることもある。大きさは小型犬程度のものから、昆虫サイズ、微生物サイズまで様々。
※3…怪獣を移送し、周囲への影響がないように隔離された施設をまとめてそう呼ぶ。怪獣保護研究施設の名の通り、怪獣の研究は専らこの施設内に移送された怪獣相手に行われる。
後日談
「なあ君」
インタビューを終え、会議室から退出しようとした手前、インタビュー相手の相馬博士に呼び止められた。
「何でしょう」
私は極めて平静に、インタビューをしていた時と同じトーンで、相馬博士に相対する。
相馬博士は、初めて会った人間を少し萎縮させるところがある。
何せ、業界の第一人者である若き女性研究者でありながら、髪はモヒカン刈りであり、独特の雰囲気を醸し出している。
そんな姿にも、話を重ねるうちに慣れたと思っていたが、いざ急に呼び止められると、その威圧感すらあるモヒカンにどうしても目が行く。
そんな私の視線をものともせず、相馬博士はずばり言った。
「君、怪獣だろう」
その指摘は、予想していた。インタビューの最中、彼女は私のことをつぶさに観察していたし、その視線のせいで寧ろこちらがインタビュー対象であるかのように感じていたくらいだ。
「……どうしてバレましたか?」
私は口につけていたマスクを外し、相馬博士に笑いかけた。
普段はヒトに擬態している口元を、本来の蜥蜴のような形状に変化させる。
「色々ね。半分はカマ掛けなんだが、こんなにあっさりと正体を晒すとは、正直ビックリしている。いやしかし、いつかは現れるとも思っていたがまさか人型の怪獣とはね」
相馬博士は落ち着いた様子で、自分に用意された粗茶に口を付けた。私が先程、相馬博士に用意したものだが、インタビュー中は一度も口をつけなかった。
「通報しますか」
「んにゃ。しない」
相馬博士は即答した。拍子抜けする。あまりのことに、肩が下がり、スーツがずり落ちるかと思ったくらいだ。
「さっき貴方が言っていたことと違う」
「怪獣と会ったら必ず通報しろって? だがそれは普通の人の場合だ。私は怪獣の専門家だ。それも優秀な。だから君が比較的無害な怪獣であることもわかっているし、今通報するデメリットの方がキツくてね」
「デメリット?」
「せっかく初めて会った人型の怪獣と、話す機会を逸する」
「……それだけ?」
「それだけ」
相馬博士は、正直な気持ちでそう言っている。それが短い間とは言え、正面から彼女と向き合っていた私にはよくわかった。
「君の目的は何? 侵略? 研究? それともフォーラムで語っていたことが全てかな。人と怪獣の共存。私は人を見る目はないが、怪獣を見る目はあるつもりだよ。フォーラムを開き、その願いを口にした君の言葉に嘘はない、と私はそう感じているが」
「……その言葉に嘘はない」
この世界に人間と同じ姿で迷い込んでしまった。最初は孤独を感じていたが、段々と使命感のようなものを感じるようになってきた。
この世界で生きて行くことしかできないのなら、世界のどこかにいる、私と同じような存在が、生きやすい世界の下地を作るのが私の役目だと。
「怪獣対策が進歩してきたとは言え、君のような存在を受け入れられる程、まだ社会は育ち切っていないだろうからね。私も君が人に仇なさないなら今感じたことは、それに今見たことは忘れることにする。だからその口はさっさとしまいたまえ」
相馬博士に指さされ、私はおずおずと口元を改めてマスクで隠した。
「君の講演は何度かネット上でも見たけれど、それだけの講演を重ねているのに周囲の環境への影響が見受けられないなら、それは誤差みたいなものだろ。たとえ、実はとんでもない影響を今後うんでしまうのだとして、だったらそれはそれで手遅れだ」
「なるほど」
「だから私の方とて、インタビュー中の言葉は嘘ではないよ。また機会があれば呼んでくれたまえ。喜び勇んで馳せ参じるとも」
相馬博士はそう言って粗茶を飲み切る。そして自分の荷物を持って、その特徴的なモヒカン刈りの髪の毛を少し整えてから、会議室を後にした。
私はその様子をぽかんと見つめていた。
……こんな私を、本当に彼女は放っておいた?
しばらくの間、立ちすくんでいたが、その後問題なく会議室を出て、ビルを出ることもできて、本当に相馬博士は何も見なかったことにしてくれたのだ、と理解した。
私は喜びに唇を噛むと、相馬博士の連絡先を携帯デバイスに表示した。
この世界で一人だと思っていたが、彼女のような人がいてくれれば心強い。
人と怪獣の共存する世界。
不可能なのかもしれないとしても、彼女は現実的な観点から、それを目指してくれていることは、このインタビューではっきりわかった。
また、会いましょう。
私は相馬博士の連絡先に、次に予定しているフォーラムの開催日を送った。
帰り道の私の足取りは、重力値が変わったかのように軽やかだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
