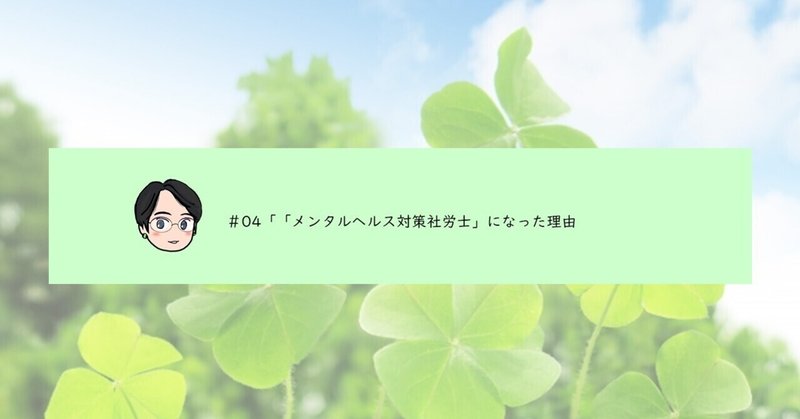
「メンタルヘルス対策社労士」になった理由
こんにちは。
とくほ社会保険労務士事務所の徳保美和です。
社会保険労務士の仕事は多岐にわたります。今日は、そのなかでも「メンタルヘルス対策」を専門にした理由を書いてみました。
そもそも社会保険労務士の仕事とは?
労働保険・社会保険に関わるの手続の代行、助成金申請のお手伝い、会社の就業規則の整備や人事制度、賃金制度、退職金制度の相談や指導。
平たく言うと、
企業を相手にするときは、人を雇う上でのあれこれに困ったり手が回らなかったり悩んだりした会社さんの手続代行や相談に乗ることができます。
個人の方を相手にすると、障害年金など複雑な手続の代行や、年金や労働関係の相談に乗ることができます。
メンタルヘルス対策を扱う理由
メンタルヘルス対策は、上記の業務の中の「会社の就業規則の整備や人事制度の整備」にあたります。
私が、その分野を自分の専門として決めた理由は2つあります。
1つ目は、私自身が、大学の後半からメンタル疾患を患って、新卒で入った会社を一年で退職したことです。
そのあと、25歳で拾っていただいた小さな会社で社会保険と給与計算を任され、30歳で社会保険労務士を取得しました。
働きながらの社労士取得はそこそこ大変でしたが、社会人として何も知らずに病気で退職し、失業給付をもらうのも諦めてしまった自分のような人を助けてあげたいなという思いがありました。
「メンタル疾患は治らない」と言われることもありますが、治らない病気ではないこと(ただ発症前とは心身ともに違っていること)を身を持って体験しました。
2つ目は、近い家族をメンタル疾患によって失ったことです。
彼女が亡くなったとき、私の病気はだいぶ寛解して、人生を楽しめるようになっていました。
彼女が病気であることは知っていましたが、離れて暮らしていたこともあり、そんなに重い状態とは考えていませんでした。
自分のように、治療すれば治るものだと思いこんでいました。
それから10年以上が経ちました。
「30代後半でまだ若いのに」「3人の子どもを遺してなぜ?」と考え続けているけれど、もちろん答えは出ません。
今考えると、シングルマザーであることや病気のために仕事につくことが難しく、将来に不安を抱えていたことも複合的な原因の一部なのかもしれないと感じています。
自分と家族の体験から、メンタル疾患は治る場合もあるし、治らない場合もあることを知りました。
「メンタル疾患に罹った社員が出たら、周りの迷惑だから辞めさせればいい」という方は身分に関係なくいますし、一概に否定するわけではありませんが、辞めたあともその人の人生は続くんですよね。
会社にい続けるにしても転職するにしても、その人が働くことが可能なのであれば、それを助けることはできないかと考えています。
メンタルヘルス対策は、会社にとってもいいことです
中小企業では、休職についての規程やルールが定まっていない場合が多く、いざメンタル不調者が出てから慌ててしまう場合も多いですよね。
休職関係の制度が整っていて、メンタル疾患の人に理解があって、なんなら先輩社員にメンタル不調経験の人がいたら、かなり「優しい会社」アピールできると思いませんか?
「うちの社員はみんな元気だからいらないよ」と思われるかもしれませんが、メンタル疾患に限らず高齢化社会を迎える上で社員の健康への配慮は、余剰人員を抱えていない中小企業こそ不可欠です。
今働いている従業員への遡及になりますが、それだけではありません。
過去、メンタル不調で退職を余儀なくされた人は、再就職の面接で病歴を隠す場合が多いです。
病歴が知られてしまうことや、再発のリスクに怯えています。
けれど、その中には実は会社と相性のいい人が隠れているかもしれません。
「うちはメンタルヘルス対策しています」という企業と、「過去にメンタル不調で職を離れている人」を繋げられないかな、という発想はそんなところから生まれました。
何が最善かを考えたい
繰り返しになりますが、メンタル疾患にかかった人は、会社を辞めるにしても辞めないにしても人生が続きます。会社もまた、その社員がやめたあとも事業が続きます。
会社にとって「たまたま一人メンタル疾患の社員が出ただけ」とは限りません。
会社が潜在的に抱えている問題やストレスを、その人が症状として教えてくれたのかもしれません。
今まで退職した人の中には、ストレスを抱えて自己都合退職した方もいたかもしれません。
今、元気そうに見える社員も、いつかストレスや不満、不安が顕在化して、病気になったり辞めてしまうかもしれません。
ここまで読んでいただいた方の中には「この社労士は病気の社員の味方なのでは?」と思われた方も、いるかもしれませんね。
自分が当事者になった経験があるからこそ、手放しで社員の味方はできません。あくまで労働者には労働契約上の義務を果たす必要があり、病気なので労働が猶予されているというスタンスです。
退職したほうが会社にとっても社員にとってよい場合もありますので、双方にとって良い選択をケースバイケースで考えています。
単に「病気になった社員を切り捨てる」のではなく、
①これを機に会社の状況を整理して改善することで
②のちのち起こるかもしれない問題を予防することができるのではないか
と考えています。
「はじめはいらないと思っていたけど、あとから考えると最善の道を選んでいた」そう思って頂けるように、一緒に策を練ります。
もしご興味がありましたら、こちらのお問合せフォームより、いつでもご連絡下さい →https://tokuhosr.com/inquiry/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
