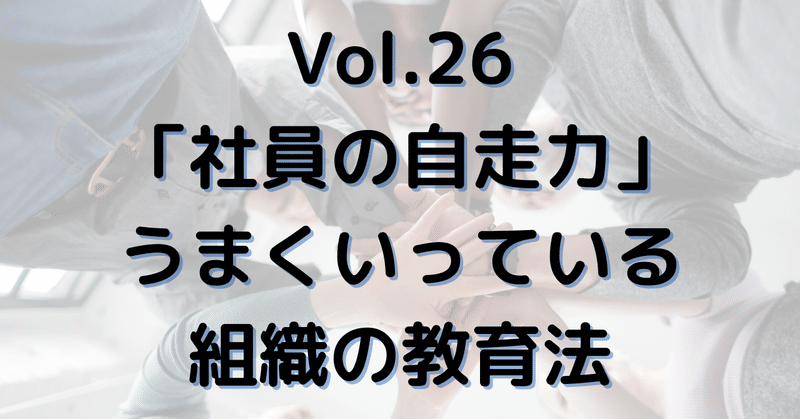
Vol.26 「社員の自走力」うまくいっている組織の教育法
業績が伸びている企業とそうでない企業
活気のある職場とそうでない職場
企業そしてそこに含まれる関係部署の姿かたちは千差万別であり、一つとして同じものは存在しません。それは、生まれも育ちも違う多様な人間によって組織というものが構成されているからです。
だが組織構成は無限であっても、突き詰めれば組織は「たった二つの分類」しかないのです。それは、
「うまくいっている」か!
「うまくいっていない」か!
というシンプルな分類です。
冒頭には「業績」と「活気」を挙げてみたが、他にもいろいろな例で比較することができると思います。
では、その両者の違いが生まれる要因を説明しよう!
■要因となるのは「社員の自走力」である。
「社員の自走力」とは、社員ひとりひとりが自分で考え決断を下し、責任を持ちながら仕事に向き合うことである。
仕事は無数に存在する選択肢から、より正解に近い答えをより早く選び出しながら進めていきます。単純であれば選択肢は少ないが、複雑化してしまえば正しい選択をする事は困難になります。そうした選択肢に上役の判断を仰がなくとも、個人個人が即座に正確な選択ができれば、合理的かつ効率に業務を行えます。それが組織としての理想形であり、私の職場でも目指すところです。
個人そして集団、それぞれの「自走力」が大きければ大きいほど、企業はより高い業績を上げることができ職場の雰囲気も高まり「うまくいっている」組織が出来上がるのです。
■上司が果たす役割が大きい
部下の「自走力」を育むには教育が必要です。通常、その教育は上司が行うものであるから、部下に対するマネジメント力が大きく問われることになります。
では、そのポイントを2つ紹介しよう。
■チャレンジさせること
自走力を育むには部下へとにかくチャレンジさせることが重要です。みずから考え判断させるのですから、舗装した道を歩ませるのではなく、未開拓で舗装もされていない土地へ放り出しチャレンジさせるのです。
ガイドは不要です。
上司がガイドとなれば、そこに道ができてしまうからです。共に進むが決して前に出てはいけない、部下の一歩うしろを歩く感じで進み、危険があれば飛び出し守ってあげる事が上司としての役割となります。
初めは地雷原の中を進むような足取りでも、経験を踏むごとに正しい判断力や自信が身に付き、その足取りも軽快となっていくものです。
新しいことをどんどん任せ、チャレンジさせましょう。
上司の役割は「見守ること」「危険から守ること」
「自走力」を育むには時間はかかる。だが将来的に必ず大きなリターンとなり返ってくるのです。
■部下を責めてはいけない
チャレンジにはリスクを伴います。必ずミスやトラブルが起こると考えておいた方が良いでしょう。上司としてはその後の対応が重要となります。
チャレンジ中のミスは決して責めてはいけない!
上司自らの判断でチャレンジさせているのであるから、ミスが起こってもその責任は上司にあり、決して責めてはいけないのです。これをやってしまうと組織は崩壊へ進みます。上司の顔色をうかがうだけの、全く意味をなさないものへ形骸化してしまうのです。結果、「うまくいかない」組織が作り上げられてしまいます。
だが、必ず責めなければならないポイントもあります。
①相手を問わず人を中傷した時
②組織を混乱させるような行動をした時
③チャレンジを放棄した時
上記の3つをした時は責める必要があります。
①②のような、人としてやってはいけない行為をした場合は論外です。
必ずその行為を上司として戒めねばなりません。「自走力」を育む上で大きな障害となるからです。なぜなら、物事を判断する上で最も根底となるのは「人としてどうあるべきか」が基準となるからです。
その基準がしっかりしていない者が、横領をしたり不正な行為を働くのである!
「未熟な者にチャレンジをさせるべきではない。」
個人的にはそう考えています。そうした人に対しては、しかるべき対応が必要であり、直接指導できる環境を整えるべきでしょう。
そして③に関しては考慮が必要です。それは、人によりチャレンジ内容が合わない事もあるからです。そもそも行動していないのであれば論外だが、しっかりと行動した上での中断であれば、別なチャレンジに進ませるといった判断をすべきでしょう。
すべては上司の責任です。
しっかり部下と向き合い方向性を決めてあげて下さい。
今回は「社員の自走力」についての投稿でした。
2つのポイントとしてはごく当たり前の話であったかもしれませんが、上司が果たすべき役割について再認識していただければ幸いである。
「自走力」は強い組織を作るためのキーワードである!
ではまた次回(^^)/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
