
肩こりの科学
今回は前回の記事で触れました肩こりについて、4つの観点で肩こりの解説をします。
前回の記事はこちらになります。
筋肉の緊張
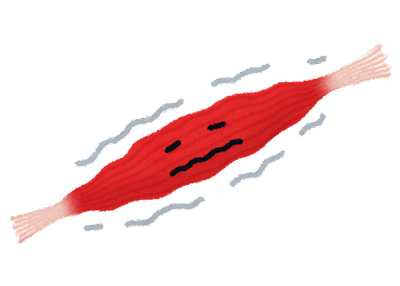
筋肉は筋細胞という細胞が、たくさん集まって出来ています。生きている細胞の集団で成り立っているため、強い力でもみほぐしたりすると、細胞を壊してしまう恐れがあります。
何度も強い力で刺激を繰り返すと、どんどん筋肉は固くなり、細胞が本来持つ痛みを感じるセンサーが鈍くなる性質があるからです。
筋肉はリラックスした状態で緩やかにほぐすことが重要です。
内臓反射の生理学
内臓の機能をコントロールしているのは、自律神経系になります。(交感神経と副交感神経)
胃や肝臓が飲みすぎ食べすぎで疲れると、交感神経が緊張し、神経系のひとつである運動神経の緊張も促し、背中の内臓と連動する筋肉が緊張して硬くなってしまいます。
これを医学の世界では「内臓皮膚反射」と呼んでいます。

背中の筋肉が硬くなると、すぐ上にある肩甲骨周辺の筋肉も影響され、硬くなります。
筋肉はひとつひとつ別々に別れていて、働きもそれぞれ別と捉えがちですが、実際は筋膜という組織ですべての筋肉を繋げているため、背中の一部の筋肉が硬くなっても、近いところにある肩甲骨周辺の筋肉も硬くなり、肩甲骨の自由な動きを止めてしまい、肩こりの原因になってしまいます。
こりとだるさ
こりとだるさの原因の多くは血液の流れにあります。
血流が悪いと筋細胞の酸素と栄養が不足し、排泄等がうまくいかなくってしまいます。

ここでの排泄物は、本来代謝されるべき疲労物質のことを指します。
酸素がたくさん混じり、栄養分(ブドウ糖)を含んだ血液が常に細胞に配られ、筋肉が働いたあとに自然とつくられる疲労物質が、きちんと外に出されてなくなれば、こりやだるさは限りなく解消されます。
緊張し続けていた筋肉の中に溜まった疲労物質が、血流の改善によって代謝され、綺麗な血液が供給された筋細胞たちは、元気に働くことができるようになります。
自律神経への影響
日常・仕事・勉強・運動などで活発に活動してる時や、何かを懸命に考えているときなど、ストレスを抱えている時は、交感神経は緊張状態を続けて内臓は休止状態になってしまいます。

肩こりがあると、自律神経の交感神経は本人の自覚なしに緊張状態になり、この状態が続いてしまうと、血管が縮まり血管が細くなってしまいます。
理由は、多くの血管は交感神経がコントロールしているためです。
肩こりの原因となる、筋肉の血液循環が悪いとさらに肩こりが進んでしまいます。
交感神経の働きが、常に副交感神経より活発な状態が続いていると、副交感神経が本来するべき消化・吸収・体温調整機能などが休止状態になってしまいます。
肩こりは自律神経にも影響し、内臓系の病気にも影響しますので、ぜひ日頃から温熱セルフケアで労ってあげてください。
最後に
最後までお読み下さりありがとうございました。
三井温熱では、セルフケア講座を開催しております。
今回の記事で温熱のセルフケアにご興味を持たれましたら、三井温熱のホームページから、セルフケア講座にお申し込みください。ご参加お待ちしております。
また、三井温熱の施療を受けてみたいと思われましたら、ぜひ店舗や各地の療法院にお越しください。
三井温熱株式会社公式ホームページサイト
三井温熱公式オンラインショップ
