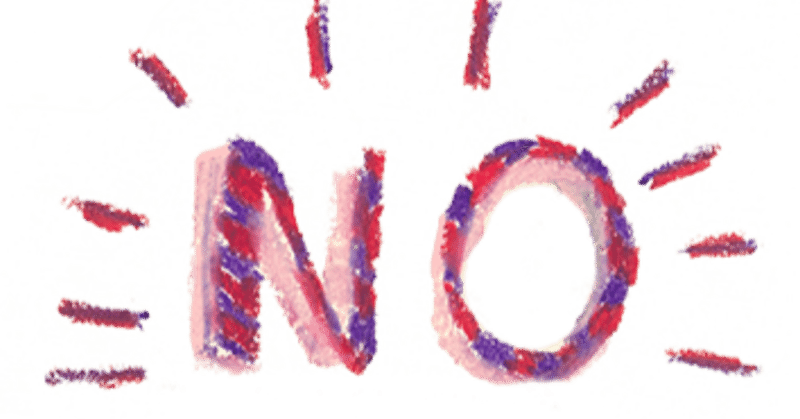
子育て時短勤務への現金給付がいらない理由
少し前に出てきた「子育て時短勤務への現金給付」の検討は、今どうなっているんだろう…。
私は第一子の産休育休時短勤務を経て、現在は第二子の育休中の身であるが、こんな給付金は絶対絶対絶対絶対いらない。
本気で勘弁して欲しい!!!
どうにかこの法改正が決まらない方法はないかと考えたが、何者でもない私が阻止することなんて到底できない。
でも、何かを発信することで、もしかしてもしかすると、この声がどこかの誰かに届くかもしれない。
そう思い、わたしが思う「子育て時短勤務給付金がいらない理由」を書くことにした。
この想いに賛同してくださる方がいたら、どうか多くの人にこの想いが届くよう、お知恵を貸していただきたいと思っています。
どうかよろしくお願いします。
子育て時短勤務給付金がいらない理由
1.短時間勤務は自分で選んだ選択
給付金を検討する理由として「慣れない両立に不安を抱え、賃金も減るため働く意欲が低下、離職につながりやすい」と書かれていた。
しかし、本当にこのような理由で退職をする人は多いのだろうか?
前半の「慣れない両立に不安を抱え」という部分に関しては大いに分かる。
実際に私自身も不安を待つワーキングマザーであり、実際これが理由で会社を辞めた友人も数人いる。
しかし、「時短勤務で賃金が減るため働く意欲が低下」して辞めるという友人には出会ったことがない。
そもそも、賃金が減るのは当たり前である。
だって6時間しか働いていないのだから。
賃金を減らしたくないのであれば、時短勤務にしなければ良い。
わたし達には「時短勤務をしない」という選択肢もあるのだから。
私たちは「働けない」のではない。
「働かない」のだ。
賃金が下がる事を承知で時短勤務を選択したのは、誰でもなく自分である。
その分の給料を国のお金で補填される理由など、さっぱり分からない。
確かに、時短勤務な上、更に子どもの体調不良などで休みが多くなれば、給料はどんどん減る。
そのほとんどが保育園代に消えて、何のために働いているのか分からないよね。なんて会話もよくしていた。
しかし、そんな状態はいつまでも続かない。
こどもが成長し、子育ての負担が少し減れば、また8時間勤務に戻ることができる。
その後、定年まで働く事を考えれば、一時的な収支がプラマイゼロだとしても、働き続ける価値は十分にある。
働く側の私たちは、一時的な収支結果に落ち込まず、将来への投資として、モチベーションを持ち続ければよいのである。
2.ますます肩身が狭くなる
時短勤務者は、とても肩身が狭い。
人員に余裕の保てない中小企業などでは、時短勤務者分の仕事のしわ寄せがフルタイム勤務者にいってしまうというケースも多く、冷ややかな視線に耐えながら「お先に失礼します」と会社を後にする人もいるだろう。
しかし、「働く時間が短い分、貰っているお給料も少ない」という事実で、少し気が楽になるのはわたしだけだろうか。
さっさと帰るのにもらっているお給料は同じとなると、時短勤務者の肩身はますます狭くなり、フルタイム勤務者の不満は、ますます増してしまうのではないだろうか。
「それは社員教育が足りない」と言われればそれもその通りだが、世の中そんなに心の広い人間ばかりではない。
不平等・不公平さから職場の人間関係が悪くなれば、それこそ退職を考える人は増えるのではないだろうか。
3.意欲低下のタイミングが変わるだけ
今回「慣れない両立に不安を抱え、賃金も減るため働く意欲が低下、離職につながりやすい」為、時短勤務者に現金給付すると言っているが、もしこのような実態があるのであれば、現金給付を実行しても、意欲低下のタイミングが変わるだけである。
そのタイミングは「時短勤務からフルタイムに変更する時」だ。
わたしは第一子の時短勤務中に第二子の産休に入った為、まだ子育て+フルタイムの経験はないが、フルタイム勤務への不安はとても大きい。
今でも、育休から復帰するタイミングより、こどもが3歳になりフルタイムに戻る時の方が断然不安である。
もし時短勤務中に給付金をもらうことになった場合、「育児とフルタイム勤務への両立の不安を抱え、賃金も時短勤務時と変わらないため、働く意欲が低下、離職につながりやすい」という状態に陥るはずである。
つまり、この施作を実行しても、意欲低下や離職につながりやすいタイミングが1年か2年程度変わるだけである。
このことに、頭の良いであろう政治家の人々はなぜ気がつかないのであろうか。
不思議で仕方がない。
4.辞める理由は「お金」ではない
「慣れない両立に不安を抱え、賃金も減るため働く意欲が低下し、会社を退職する人」がどんな人か、考えてみて欲しい。
正解は
「お金に余裕がある人間」だ。
お金に余裕がなければ、多少給料が減っても働き続けるし、上述したように本当にお金が必要であればフルタイムで復帰するだろう。
給料が減ることが理由でこのタイミングで会社を辞める女性は、働かなくても生活していける女性である。
働かなくても生活していける女性に「お金あげるから退職しないでねー」というのは、てんで検討違いではないだろうか?
では、どうすれば育休明けの離職を防げるのか。
それはやはり前半部分の「育児と仕事の慣れない両立への不安」を払拭することではないだろうか。
どこかの新聞社で「仕事と育児の両立で何が必要か」を調査した結果、圧倒的に多かった答えは「柔軟な働き方」だったと、育児本に書いてあった。
そう。わたしたちが求めているのは「お金」ではない。「柔軟な働き方」だ。
短時間勤務制度を小学校入学までのばす。
フレックス勤務を認める。
などの方がよっぽど離職を防げるはずである。
もしお金をばらまくのであれば、時間勤務者にではなく、時短勤務者を雇用する事業主にすれば良い。
そうすれば、結果的に短時間勤務制度を長期化する会社も増えるであろう。
また、より改善すべきは昨今よく話題に挙がる保育園の様々な問題である。
わたしたちに「母」とって「こどもの心身の健康」より大切なものはない。
こどもを安心して預けられる場所がなければ、働き続けたいと思う女性の数は絶対に増えない。
お金を使うのであれば、ぜひ保育園の品質改善の為に使って欲しい。
これらはわたし個人的な意見で、もちろん時短勤務時の現金給付が嬉しいという人もいるとは思う。
しかし、わたしと同じ考えを持つ働く女性も一定数はいるはずである。
どうか政治家の方々には、働く女性のニーズを正しく調査・理解した上で、新たな施作を考えて欲しいと切に願う。。
長文最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
