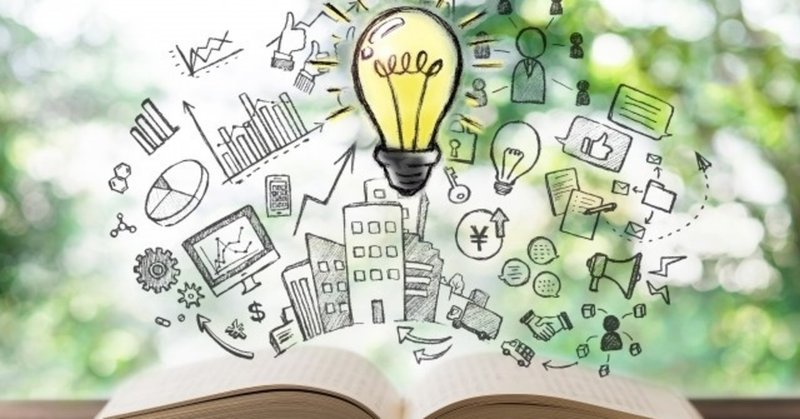
読書感想文とは「読書体験記」/キーワードは「変容」
国語教員による「『読書感想文』って必要なくない?」というツイートが話題になっています。
マジに聞きたい。
— 南部吟遊詩人 (@nanngin) June 27, 2020
「読書感想文」って必要なくない?
あれで読書が憂鬱になるし、いちいち本読んだ後に普通、感想文とか書かないでしょ?
日本人の読書嫌いと作文嫌いを助長していると思うのよ。
国語の教員なのにこういうこと言うのはどうかと思われるかもしれませんが、ぜひ意見ください。
(続く
分かる…ッ!深い頷きと共に、「くっ…分かるっ…‼」って口から洩れてしまうくらい、分かる。
誤解なんですっ!読書感想文自体が悪いんじゃないんですっ!リプ欄にもあるけれど、読書感想文を取り巻く問題で1番悪いのは、生徒が読書感想文の書き方を教わっていないのに、夏休みの宿題に出てしまうことなんです!
夏休みは嫌いになっても、読書感想文のことは嫌いにならないでくださいっ!
ーここで、俺が小学生の頃「やり方を習ってないのに、当然のような顔をして夏休みの宿題だった」メンバーを紹介するぜ!
まずは!お父さんお母さんの熱心さが勝利の鍵!
俺が小さいときは理科研究だった!
―自由研究!(ダカダカダカダカ、ッドンッドン、スッパーン!!)
そして!どれがどれだか区別がつかない!
カリキュラムには入ってたかもしんないけど
時間の関係で飛ばされがち!
―詩・短歌・俳句・川柳の、グループ短詩!(ブン、ブンブン、ブン、ブブブンブーン)
最後に!あらすじで字数の8割を埋めたあの日!
クラスで一人は提出するまで居残りさせられてたぜ!!
―俺、読書感想文!!(ギュイイイーン、ギュルルンギューン)
時を戻そう。
私自身は、教員免許を持っていないどころか教職課程すら履修していないただの経営学部卒生なので、読書感想文に関する指導要領がどんなものかほとんど知りません。
そして学生の頃は、もれなく読書感想文を書くのが嫌いな生徒でした。本を読むのは好きだったんだけどね。
しかし、知人の依頼で学習塾で働くこととなり、さまざまな教材にある読書感想文の模範解答を見るうち、この課題の答えとして求められているもののが見えてきたのです。
教師が読書感想文に書いてほしいことは、「この本を読んで、自分の考えがどう変容したか」
よくある認識として「読書感想文は本の内容を書くもの」という「本が主役」の思い込みです。しかし、それでは作文用紙をあらすじで埋めることにしかなりません。
「感動した場面と、どう感動したかを書こう」というアドバイスもあまり役に立ちません。「どう感動したか」と聞かれて、「うーん、面白かった」しか出てこないのが一般的な小学6年生。「〇〇くん、野球部なんだね。どうして野球が好きなの?」「うーん、面白いから」「△△くんも野球部だったよね、△△くんはどうして野球が好きなのかな?」「うーん、面白いから」…別に彼らが壊れかけのradioなんじゃなくて、マジでこれが普通なのです。
6年間何やってきたんや…と目の前が真っ暗になること、度々。
そこで教師は「『どんなふうに面白いのか』を説明するために、何を糸口に考えたら良いか」を、やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、 褒めてやらねばなんねーのだけれど、それには時間がかかるし、教師によってはどう指導してよいか分からず、とりあえず答えられそうな子に模範的回答をさせて終わり…ということが多々起こっているようです。
最悪なのは、生徒が教師に「質問ができない」状況、つまり夏休みに読書感想文が課されることです。
課題図書は読んでみたけれど、書き方が分からない。
友達とTSUTAYA前で500mlの「丸ごと絞ったオレンジ」を飲みながら、「まだ読書感想文書いてないんだけどー」と自虐し合っているうちに、8月31日が容赦なく到来する。
仕方がないので、あらすじを書いて(あらすじが書ければまだいい方)ところどころに「面白かったです」を判のように押し、指定の字数を埋めて提出する。
先生はコンクールに出す読書感想文を選んで指導するのに忙しく、死屍累々たる「面白かったです」にフィードバックをすることができない。
そしてあっという間に月日は巡り、また翌年の夏休み、彼らは読書感想文に「面白かったです」を書くことになる。そう、教師はまた「面白かったです」を救うことができなかったのである…。え?これタイムリープもの?
読書感想文の主役は「本を読んだあなた」です。この本に出会ってあなたはどう変わったか、before→afterを書いてほしいのです。その意味で、読書感想文とは「読書体験記」と言えます。読書という体験を通して、自分が何を知りどう「変容」したのかを自覚してほしいーそれが、読書感想文の狙いです。たぶん。知らんけど。
「その本を読んで、自分は何を知って、それ故これからはどうしたいか」
例えば、環境問題に関する本を読んだとします。
『まだ使えるものがたくさん捨てられていると知ってショックだった。私もこれまではまだ使えるものもを捨てていたが、これからはものを大切にしようと思う。』
これが「読んだ、知った、変わった」の変容プロセスでふ。ここにボリュームを持たせることを意識しつつ、話題をつけ足していきます。
ますは、「その本と出会った経緯」を書きましょう。正直に「課題図書の中で1番薄い本だったから」と書いてもいいんです。タイトルがヘンテコだったから、挿絵が可愛らしかったから、字が大きかったから…。本の作り手は、その本を読ませるために様々な工夫を施しているのですから、そこに乗ってみましょう。もちろん理由を盛っても構いません。事実だけ書くようにとは言われていないし、ちょっと脚色された方がおもしろいに決まっています。
どんなふうに読み進めた、というのも書くといいですね。本が嫌いだから1日1ページずつ読んだとか、飛ばし飛ばし読んだとか、読書時間を決めたとか…。読みたいところだけ読んだ、だっていいかもしれません。頑張って読んだのはえらいのだ。えらい!(肯定ペンギンさんで)
本の「まだ使えるものがたくさん捨てられている」という記述がある部分、つまり本を読んであなたが分かったことが書かれている場所は、思い切って引用しましょう。ここをまとめようとすると、あらすじ沼にはまります。悪いこと言わないから止めとけって。
数字が書いてある部分なども引っ張ってくると、説得力も増しますし(エビデンスや、エビデンス)、ついでに字数も稼げます。
次に、それを知ってどんな気持ちだったかを書きましょう。「驚愕した」とか難しい言葉を使ってもいいけれど、ここで悩んで手が止まるなら、表現力を発揮しようなどと考えなくて良き良きです。「びっくりしました」で十分です。
そして、「これまでは…と考えていたけれど(before)、この本を読んで…と考えるようになった(after)」という変容を書きます。「私もこれまではまだ使えるものもを捨てていた」というbefore部分は、膨らませどころです。ものを無駄にしてしまったエピソードを細かに、もしくはエピソードをたくさん書けると、変容のギャップが大きく感じられていいでしょう。作文を書くこと、物語を書くことが好きなら、ここが腕の見せ所です。
「これからはものを大切にしようと思う」のafter部分は、考えが変わったことで、行動はどう変わったか(どう変えたいと思うか)を書けると良いですね。例えば、小さくて着られなくなった服はメルカリで売ってリサイクルに努める、など。もちろんフィクションで構いません。
さらに、after部分は、「どうしたらよいか分からなかったので家族に聞いたところ、~というアイディアがあった」「インターネットを使って調べてみた」など、飛び道具が使えるので、アイディアが湧き出てこなくても大丈夫です。本が好きなら、「関連する本を読んで、〇〇をすればよいと知った」という「入れ子式」もあるでしょう。
なお、課題図書が伝記や物語などの場合は、登場人物の言動の中で「自分には到底できないと思った(感動・驚き)」というところに注目すると良いです。
例えば「ジャイアンに自分ひとりの力で勝つために、のび太は何度殴られても挫けなかった」ところに感動したとします。
知ったことは、「のび太が勝ったこと」、感想は素直に「のび太の根性はすごいと思った」とか「人に頼ってばかりではいけないと思った」などと書きます。
そして、beforeに自分はこれまで、こののび太のようにはできなかったこと=「できない問題があると、母や友人にすぐに答えを教えてもらっていたが」、afterに今後はとうしたいか=「これからはできるだけ自分でやりとげたい」とか続けちゃいます。
なお、本の主人公が自分と同世代であると、自分の行動や感情との比較がしやすく、afterに取るべき内容も想像しやすいでしょう。課題図書の物語はだいたいその点を配慮していますが、読む本を自由に選んでもいいときは留意するべしです。
もう少し真面目な参考文献はこちら。
齋藤孝「だれでも書ける最高の読書感想文」 (角川文庫)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
