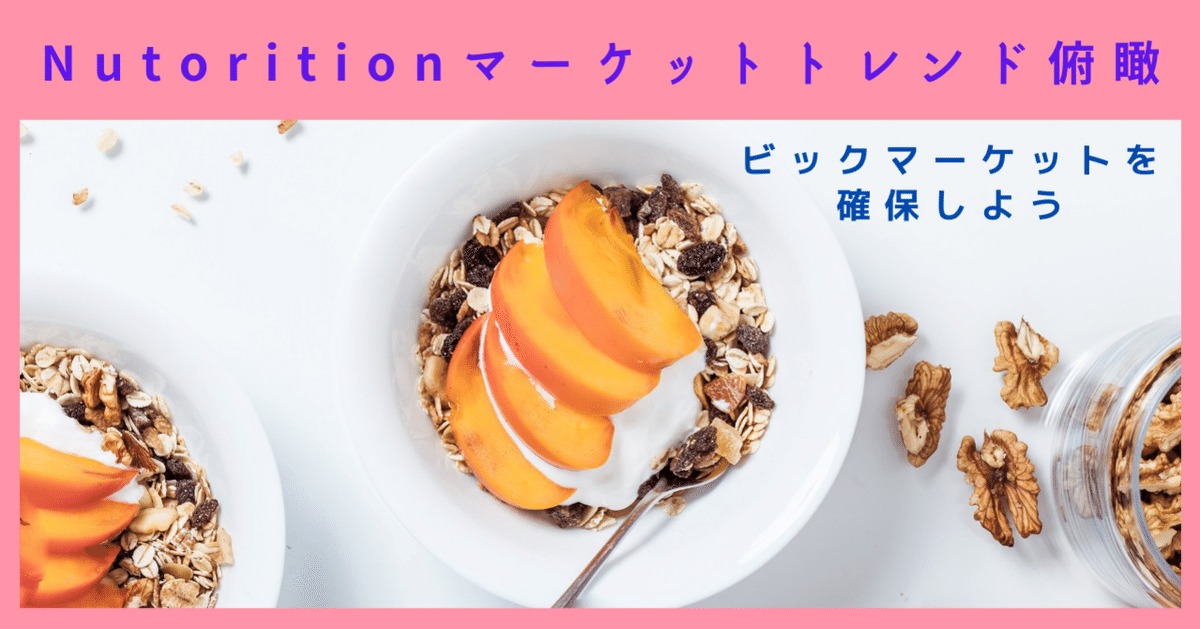
Nutrition(栄養・機能性)マーケットについて(Supplementではない領域):FooD&Drink:食カテゴリーの一翼として捉えればマーケットポテンシャルはとても大きい。(×10-Overかも)
前回はサプリメメントについて、健全化していくマーケティングについて私見を展開してみました。今回は、Supplementと並列に語られることの多い、Nutiritionについて、俯瞰と深堀をしていきたいと考えています。
食カテゴリーの一翼として捉えればマーケットポテンシャルはとても大きいと捉えています。同様の食カテゴリーで言えば、おいしい:特別を訴求した食品(特産品とか、おせち・うなぎ)通販マーケットなどがありますが、通常のヘルシー需要ってまだまだ健在化、健全化できますね。
まずは、確認
サプリメントは「食事の(dietary)」 「不足を補うもの(supplements)」の意味で、「dietary supplements(ダイエタリーサプリメント)」とUSAでは定義されています。EUではフードサプリメント(food supplement)と定義されています。
Nutrition=栄養 ということになります。「食」そのものや、食材から由来される素材成分については、エビデンスで検証されていることが少ないものもあるけど、効果については認識できる摂取形態であるものとします。
*プロテイン
*プロバイオ×プレバイオ
*きのこ
*ハーブ
などなど。(この後、順次展開していきます。)
消費者のトレンドについて
Nutiritonに限らず、消費者のトレンドについてまずは整理しておきます。
1:Natural/clean products 天然でクリーンな商品
スキンケア、化粧品、マルチビタミン、サブスクリプションフードサービス、睡眠エンハンサー、アパレルなどのさまざまな分野で、天然・自然/清潔な製品・商品・サービスを選択するようになってきました。
2:More personalization パーソナライズ
パーソナライズされたマーケティング機能を開発は必須です。商品・サービスに最も関心を持つ可能性のある正確な消費者セグメントをターゲットにする必要があります。
それらの消費者に合わせたメッセージングとストーリーテリングを展開することがマストになっています。
事例
ウェルネススタートアップは、クイズを通じて提出する情報に基づいてパー
ソナライズされたビタミンとサプリメントのサブスクリプションを提供することが普通になってしまいました。
フィットネステックは、ユーザーにパーソナライズされた睡眠とフィットネス情報を提供するために生理学的データを収集するフィットネストラッカーを展開しています。
それぞれの、サブスクメンバーシップのベネフィットサービスには、トラッカー、毎日分析、コーチングへのアクセス、オンラインコミュニティへの参加機能などが含まれ提供されます。
3:Influencers インフルエンサー というメディア
消費者はソーシャルメディアのインフルエンサーを重要な情報源にしています、インフルエンサーのポストに基づいて、評価・購入している傾向は顕著です。インフルエンサーを利用して、ソーシャルチャネル全体で消費者と勝コミュニケーションする必要性が高まっています。ブランドを、ターゲットの消費者に対して共鳴するインフルエンサーを醸成する必要性が高まっています。
4:Rise of Services サービス化 への進展
消費者=私たちは、サービスが当たり前として捉えています。全体的なウェルネスサービスで、商品提供ではなく、サービスにFeeを払う傾向があります。
ウエルネスとウエルビーイング
メンタルヘルスの意味合いを持つウェルビーイングと混同されているのが、ウエルネスカテゴリーです。
【メンタルヘルス】とは、
身体的
社会的
に自己を超えて影響を与える要素として定義しましょう。
(自分で定義は見つけてみてください、というくらい視点・視座で表現が変えられます。)
健康を維持することの最大の目的は、
わたしたちの身体を機能させ続けることです。
わたしたちが歳を経るにつれて、
わたしたちは自分の肉体は、若年時代に比べて様々なもの(免疫とか、細胞の活動とか、ホルモンとか)が減少していくことが知られています。
また、その減少によって肉体や、身体部位などの機能が低下していきますので、それを、補い、身体の各部位の機能を維持するために最善を尽くそうとします。
・全体的な体(身体)の健康
・栄養
・フィットネス
・睡眠
・これらからもたらされる外観
は、最近のウエルネスで、注目・流行りとなっているトレンドの一部であることは認知・体験されていると思います。
・疾患・病気を和らげたり
・予防したり
・痛みや、不備・不和のない永い人生を送りたい
という私たちの深い願望を利用している点もここでは抑えておきましょう。(これが目的ではないのですが、この状態になって、〇〇をしたいが本当の願望なのです。これを取り違えているので、MD、マーケティングを間違えます。)
これらを実現するために、顧客が、消費(時間、費用、行動)するカテゴリーとしては
・脳・認知: Nootropics
・瞑想/マインドフルネス
・アンチエイジング製品
・美容サプリメント
・非侵襲的な美容施術・Gear
*Nutrion・栄養
スポーツ栄養
ジュースクレンジング
成分・素材強化食品
があります。そのNutrion・栄養について俯瞰していきます。
Nutoritionに限らず、顧客が求めるトレンドになるかどうかの視点・ポイントとは
1つめは、当然のことですが、定着性視点です。
1:トレンドとして長く継続して、生活に取り入れられるものかどうかです。
単なる、ブーム、バズワードではどうしようもありません。卑近な事例では、TVで紹介されると翌日にSMでその商品が売り切れになるけど、翌週からは通常以下の販売とかです。
2つめは、収支視点です。
2:そのトレンドから、継続的に利益を創出出来るかどうかです。
スポットでマーケットがグロースがされていても、1年しか顧客購買が継続されないのであれば顧客の支持を得たわけではありません。トレンド以前よりはマーケットボリュームは、成長か肥大して、残存しているかも知れませんが、多くの参入事業者が収支を黒字化させていける全体のマーケット規模ではないかも知れません。
言い換えれば
一時的な流行ではなく、事業者がイノベーション計画、戦略を立てる際に有効となる長期的視点に立った強力なトレンドに注目して、DTCブランドとして育成することです。
「成長のチャンスがあるトレンド」
「各企業にとって売上増、利益に結び付くトレンド」
であることです。
これは、マーケティングでも語られることなので今回は多くを記載しませんが、
健康表示(ヘルスクレーム)の有効性・機能性に関してついての顧客態様について、USAでは下記のクラスター・フェーズとして分析をしています。
1:テクノロジーコンシューマー:高付加価値の商品、メディカルなど機能性を重視する消費者層
発売時などに、先進的にそのカテゴリー商品を消費してトレンドを生み出す基礎となる層
マーケット概要的には
・低マーケットボリュームマーケット
・プレミアム価格
2:ライフスタイルコンシューマー:ウェルネス、疾病予防に対する関心が高い。 新ブランドを取り入れる傾向がある。
これは、多くの消費者層(クラスター)に訴求でき、それが各クラスターのベネフィットとして認知、利用されるフェーズ
多くはこの層ターゲットとなることです。
マーケット概要的には
・ニッチマーケット
・プレミアム価格
3:マスマーケットコンシューマー:ブランドの知名度、 信頼性を最も重視する消費者層。スタンダード化した商品を購入する価格志向の消費者層
マーケット概要的には
・マスマーケット
・価格志向にマッチした価格(価格競争状態)
となりますので、どのマーケットグロース位置なのか、次のフェーズに移行するのか、伸び悩みシュリンクするのかなどは、自社だけではなく同一市場でビジネスを展開している事業者のマーケティングにも大きく関与されてきます。(悪貨が良貨を駆逐するのは、日本のサプリマーケットが端的な事例です。)
そこでは、下記の3つのポイントが益々重要になってきています。
1.持続する本物の成長機会になっているか?
2.消費者ニーズに結び付いているトレンドとなっているか?
3.科学的(エビデンス)根拠があるトレンドとなっているか?
Nutoritionのトレンドについて
2021年に消費者=顧客の価値観が大きく変わったわけではないですが(突然何かに影響されないのが食のトレンドです。COVID-19で変わったように思えるだけですが、トレンドファクターは変わっていません。)大きなトレンドとして。私たちが見聞していることを数年ほど前からを踏まえて敢えて抽出して見ましょう。(将来は予測できないって、誰かが言っていましたよね。でも、将来から今の事業を設計しないと成功しないのですが。過去の延長線上では変化はあるけど、イノベーションのタイミングが創れないです。)
「ナチュラルヘルシー」と「ウェイトウェルネス」
これは、永遠のテーマですね、実現するために展開されているソリューション要素が、
・高プロテイン
・低GI(Glycemic Index(グリセミック・インデックス)の略で、食後血糖値の上昇度を示す指標)
・満腹感持続(錯覚満腹感など、「体が欲しがるもの」ではなく「脳が欲しがるもの」への対応)
です。
ナチュラルヘルシーは、オーガニックで訴求を増しています。そのマーケットのカテゴリーは、
・スーパーフルーツ(高い栄養素を含むフルーツ):ルバーブ・なつめ・サジー・イチジク・アサイー・梨・モリンガ・ゴジベリー(クコの実)・カムカム・マキベリー・カクタスフルーツなどキリがありません。
・ミラクルグレイン(雑穀)ですが、海外ってすごく幅広いです。
Millets・Fonioとか
・グルテン(gluten)フリー:「グルテニン」と「グリアジン」というたんぱく質が絡み合って「グルテン」になります。
*グルテンフリー認証マーク GFCO*(Gluten-Free Certification Organization) (日本で取得しているブランドあるのでしょうか?)
・グリーンフード:植物由来原料で、抗酸化作用のある栄養素が豊富に含まれ、またカロリーも低く食物繊維も豊富な食材(スーパーフード一部でもある):野菜・スピルリナ・アスタキサンチン
・スーパーシード:チアシード・キヌア・アマランサス・フラックスシード・ヘンプシード・ゴマ・かぼちゃ・ひまわりなどです。耳にされたことがあると思います。(今、何処で売っているのでしょうか?)
言い換えれば、「食品素材が元来持つ健康効果を活かした食品」という消費者にとって分かりやすいコンセプトです。
(日本だと、青汁、クロレラ:ユーグレナ、野菜ジュースなどですね)
この領域でみなさんがお気づきかとは思いますが、欧米でトレンドとなった素材やコンセプトが、数年後に日本でブームになるケースが多いということです。日本で定着トレンドになっているかは別です。(タイムマシンなのか、コピーキャットなのかは別ですが)
日本では下火になっていますが、スーバーシードの1つ、チアシードは
「スーパーフード」
「ナチュラルヘルシー」
「腸の健康・環境ウエルネス」
「プロテイン」
というキーワードトレンドをベースにしてマーケティング拡張してに成功しています。
腸環境ウエルネス
腸、腸内環境(フローラってのもありました)については、日常のコンテンツ・情報で聞かないことはないトレンドテーマですね。「腸環境ウエルネス 」は新たなフェーズになったようです。
もはや乳製品(ヨーグルトなど)のみの市場ではなくなりました。(乳製品には、一部逆風もありますが。)
腸は、「第2の脳」。
精神状態(ムード:睡眠)や、脳内環境(認知など)にも影響があると言われるようになっています。
「腸環境ウエルネス 」は、「お腹の中だけの問題ではない」という科学的根拠に裏付けられつつあるようですね。そもそも食事の基本なので、わかりやすくて、なんとなくでも、ベネフィットを訴求しやすいですね。
マーケティングロジックとしては、
「腸での消化吸収と活力(エナジー)、メンタル、ストレス」
で関連づけていく研究結果をエビデンスに、ロジックを構築しています。(ヨーグルト、乳酸菌の二の前を踏まないようにしています。)
腸内細菌(腸内フローラは、バズワードで終わったのでしょうか?)を含めた腸のプロセスシステム(これは、今までは結構いい加減というか、曖昧なプロセスで説明されていました。Cピスさんが拡げたマーケティング手法ですね。研究・啓蒙サイト→コーポレイト→コマースサイトを、リタゲ等でストーカーするなど)と
認知、不安感、鬱、体重管理、肥満、糖尿病、自己免疫疾患、アレルギー、ぜんそく、ストレス
などとの、ウエルネスクレームとの関連性に関する論文の発表数が増えていいるようです。
ただし、FDAなどのデータを見る限り、この領域において研究は、まだまだ初期段階で始まったばかりであり、どのような食品が腸内細菌に良い変化をもたらすのか、また、その根拠など単純には答えられていません。(1年や2年で有意差は出ないです。*日本の厚生労働省は推奨ですが。ここら辺の違いも面白いです。)
腸内の効果に関する直接的なメカニズムはまだ発見・検証されていませんが(そもそも出来るのかな?プロセスがトラッキング出来ないのでマーカーだけでは・・・・)、研究者は、特定の機能性を持つ菌株(ビフィズス菌ってどんだけあるのって、最近感じませんか? その前に、乳酸菌もそうでしたが)について研究する方向にシフトしているようです。
「善玉菌が多い方がよい」だけではもうダメで、特定の健康懸念(睡眠、ストレス、うつ、減量、免疫サポートなど)をターゲットとして様々な異なる健康問題に対応する、特定の菌株対策がトレンドになっています。
(最近、どうして、乳酸菌で睡眠に良いかわからないけど広告多いですよね。先ほどの 第二の脳 のロジックです。)
(後述する、細分化:セグメンテーション&フラグメンテーション)
余談:
乳製品でも、静かなトレンドが起きています。新しい商品分野としては、「腸の不快感」をもたらすA1プロテインを含有していないことが特徴であるA2ミルク(乳中に含まれるたんぱく質の約8割はカゼイン カゼインの約3割はβ―カゼインで、そのβ-カゼインがA2タイプの遺伝子を持った乳牛から搾乳されたミルク)などです。
これは「腸の不快感」の1つを解消する手段です。
FODMAPS食品* (fermentable,oligosaccharides,disaccharides, monosaccharides, and polyolsの略)「短鎖炭水化物」という腸で発酵しやすい、オリゴ糖(これってプレバイオの代表格でもありますが)、2糖類、単糖類、ポリオールなど。を摂取すると炎症を起こすので摂取を控える食事療法として認知されつつもあります。(白人系がすべて、乳製品に強い体質ではないということです。)
も、USAではトレンド化していますが、日本ではくるのかな?とは思っています。(乳製品のおいしさが普及していかないので・・・)
植物由来の食品、飲料マーケット、トレンドの伸張
動物性の食品・乳飲料から、植物由来の食品・飲料へのトレンドは、
・ベジタリアン
・ビーガン
・フレキシタリアン
でなくても気になるトレンド領域になってきました。(違いは調べてみてください。こだわりが感じられます。 ただ、言われるほど絶対数は多くありません。10%超えたくらいです。ただ、エリアやクラスターをセグメントすれば効果的なマーケットサイズです。)
飲料系では
・ココナッツミルク
・アーモンドミルク
・オーツミルク
のマーケットトレンドが成長するようになり、先述べた「腸環境ウエルネス」メッセージをアピールしています。(日本なら、今は、豆乳?・甘酒?
ですかね。)
プロバイオティクスとしては、
・発酵食品
・コンブチャ(紅茶キノコ)を始めとするキノコ(中医漢方には既にあるソリューションです。)
などが、マーケット・トレンドとして成長し、顧客に浸透し始めているようです。
(プロバイオだけでは、ダメで、プレバイオティクスも同時に摂取する必要性と有効性を訴求し始めています。)
プロバイオティクス乳製品の成功から、グルテンフリー、乳糖フリーを謳った植物性乳代替食品は、顧客が食品を選択すカテゴリーとなりつつあります。
「腸環境ウエルネス」と、そこから想定イメージされる「体感性」に対する顧客のニーズが主な要因ではあります。一方でベネフィットの「実感」を測定できるものが無い一面もあります。
身体に良さそうを、「食品>素材>成分カテゴリー」として訴求して、コミュニケーションを進めていくことが大事なポイントです。
(あくまでも、「食」カテゴリーです。:薬機法などの遵守は当然です。)
また、一方で、単なる「〇〇フリー」や「プロバイオティクス」訴求のみに注力すべきではありません。それは購買要因の影響度ファクターとしては薄いです。
プラントフード(植物性食品)
プラントフード(植物性食品)は、トレンドとなってきています。しっかりと定着するには、もう少し時間がかかります。(VBが採算に載ってこない可能性が未だあります。)
(トレンドってどのカテゴリーもそらそうですが。都市部で、所得が高く層、学歴が高いかどうかは所得との因子関係だと思っています。特に、健康志向の強い消費者が存在するってことです。)
これらの消費者は、メディア、SNS、などメディアからセレブなどが発信している情報として受け止めています。炭水化物(動物性)を減らしたい、摂取する炭水化物を良質なものにしたい、という行動変容で選択しています。
1.新規性への欲求
2.ナチュラルな機能性
3.糖質制限
4.高たんぱく質/低炭水化物
が、プラントフード(植物性食品)のキーワードのようです。
ここに相互関連する、消費者のトレンド・嗜好・トレンドとして確立されたものとしては、精製された小麦などは炭水化物としてよくない(グルテンフリーまでは行かない)。特にパンやパスタを避けるべきだと認識を持つ顧客と同じセグメント・クラスターでもあります。が広がっていることは身近な出来事だと思います。別の視点では
即席(easy-to-prepare)食品に替わって
better-for-you(BFY)伝統食材
に価値ウエートを置くようになりつつあるのが、このカテゴリーの顧客です。
かと言って、代替素材としての価値は理解していても、摂取というか食事方法を工夫しないと普及しません。(人って手間は省きたい)
毎食、代替素材の野菜などで、麺や、生地や、コメみたいに見た目を加工したり、肉パテのようにするわけにはいきません。
そのために、他のカテゴリーでもトライされている方法が有効のようです。
1.スナック化(後述)
2.非乳飲料として乳製品ぽい商品
3.主食に代替え調理済み野菜
4.肉代替食品に整形(加工)して提供
することなどがポイントの様です。これは、主食の代替品や1人分の食事に利用できる便利な即席食品にとってのビジネスチャンスでもあります。
こんなイベントも開催されるようになりました。Sponserなどのリンクからトレンド事例が分かるかと思います。
https://www.plantbasedworldexpo.com/sponsors.asp
有名な企業
食品、飲料のスポーツ化
どの国でもそうですが、生活のあらゆるシーン(オケージョン)で、スポーツ化は、とても多くのサービス・ソリューションとして提案され、消費者にとり入れられています。アスレチック、スポーツやスポーティーなことが、顧客に求められて、愛される傾向は目新しいものでは無いようです。
現在のように、スポーツが、ファッション・アパレルやプレジャー・余暇時間、フード・スナック・ドリンクにまで大きく伸張、展開していること無かったと言われています。
スポーツニュートリションというカテゴリーの確立
スポーツニュートリションはメインストリームになったと言えるでしょうか?
たんぱく質を多く含有することを特徴として、スポーツ愛好家に向けたフード・ドリンクなどの食品が、SM/Dg’SのフェイスにMD展開され、既存ブランドがスポーツフード化へ転向しています。
SKUを増やすとか、サプリ有効成分を付加したような表記(必須量にはなっていないなどの突っ込みとことが多々ありますが。)を展開して、マーケットトレンドを追い風にしようと標榜しています。
実際は、「完全にナチュラル」で、あまり特性を持たないフード・ドリンク食品が、スポーツを意識してフード・ドリンク食品を摂取する人々にとって、より魅力的なカテゴリーとして変容して受け入れられているようです。
顧客自信のフード・ドリンクの嗜好と志向に合わせた、ナチュラルフード・ドリンク食品を探求しています。
従来の数多くのスポーツフードのように、人工的な成分で埋め尽くされた原材料リストを掲げるフード・ドリンク食品は徐々に顧客から敬遠されてきました。(体感はこちらの方が、確実ではあります。)
それを踏まえて、フード・ドリンク食品・飲料に健康的でスポーティーなイメージを植え付けることは、「普通の食品」メーカーが、1つの成功へ導く推進力ともなっています。
スポーティーなブランドを新設するよりは、既存商品をスポーツ化してリニューアル販売することの方が多いということはご存知のとおりです。
(スポーツ選手などを、アンバサダーアイコンとして利用するって当たり前になっていますが、本当マーケティングトレンドとして、事業者にとってまだ効果的かどうかはまだ検証していません。展開事例が多すぎて成功のためのファクターかどうかの差が特定出来ないです。失敗も多いので。これは、有名人を利用したサプリメント、コスメのマーケティングと同じ方向に向かっていると判断しています。)
スポーツ化のペルソナとしてのペルソナヒント
・ファッション&ギア:
ライトなスポーツというより、運動用ウエア(アスレチック・アパレル athletic apparel:DTCにはとても多くのブランドがあります。)を着て、1日の運動量などを測定するウェアラブル機器「FitBit」「Apple watch」など
(数多くのGearがスマフォブランドだけではなくマーケットにはあります。価格と機能の違いが判別できないので解りませんが、顧客はどう選択しているのでしょうか?)を装着して、アプリと連動してバイタルログを計測・保管(分析は出来ないと思っています。)する。
体験したエクササイズをシェアすることも、行動としてトレンドのようです。(この行動心理学については、調査してみます。おまちください。)
・朝食:
プロテイン入りの果物や野菜のスムージー(スムージーは、アメリカでは冷凍もありDTCとして成長しています。スティックタイプのドライや、常温パック、どちらも、保存料問題や、SDG’s視点などからは片手落ちの面であります。もあります。ニッチから深耕して成功するオケージョンがありますね。)
・靴:
重い機能性のない、革靴や、ハイヒールから、ローヒール、ウオーキングタイプの靴をはじめとするスニーカーへのシフトなど、カジュアル・スニーカー伸張は目を見張るものがあります。(山のように、D2Cブランドがあります。)(スニーカーブランドからスポーツウエアへのアイテム拡張などの事例は限りがありません。既存アパレルからのスポーツウエアへの展開より伸張性は高いようです。)
・ウェルネス指向のアパレル(「アスレジャー」
との使いわけ
・仕事の後(アフターワーク):
チェリー(後述)かビート(繊維、カリウム、鉄、葉酸および抗酸化物質)ルートのジュースを飲んでランニング。リカバリーには、チョコレート(後述)ミルク。
・パーソナルジムで、プロテインドリンクやスナック
・ヨガ・フィットネスで、ハーブティー(後述)ドリンク
この2つで、顧客カテゴリーは大きく違い、訴求して支持される成分・商品も大きく変わります。
・夕食:
「クリーン」で健康的で新鮮な食事。最近はクリーンで美味しく、高たんぱく質で良い炭水化物を含んだ食事や、「meal prep(500~600kcal以下のヘルシーな、お弁当)カテゴリー」などを宅配するD2C企業が登場してきています。(個食化、パーソナライズ化のトレンドでもあります。)
このような生活は、
1981~96年までに生まれた層をミレニアル世代(またはジェネレーションY)
97年以降に生まれた層をポストミレニアル世代(またはジェネレーションZ)である、20代後半から30代では普通になりました。
たとえ運動や身体を動かす事をあまりしていなくても、この世代はスポーティーなライフスタイルイメージを求めています。
コミュニケーションのバックボーンとして、フィットネスに関するソーシャルメディア&ブログ(メディアとしても捉えています。)、オンラインでのパーソナルトレーニング、顧客同士情報・意見交換の場などが多数存在するとともに、ブランドもその場(プレイス)やオウンドコンテンツを提供してマーケティングを展開しています。
エクササイズや栄養、科学やインスピレーションに関する情報に、消費者の欲望の際限は無いと言わざるを得ないです。
スポーツ化トレンドへのポイント
・アクティビティに結び付けたブランドアイデンティティの構築
週末の楽しみ程度のアクティビティでも十分です。
キャンプがスポーツかどうかは別として、トレッキングもそうですね。デイリーとは別のシーンであるアクティビティが必要です。
・1食分の個包装、外出先で食べられる摂取形態での提供
シリアルバーとか、カップドリンクとか、ゼリーとか。アイディアは無限かも知れません。
・スポーツ愛好家をブランドアンバサダーとして起用・展開する
有名セレブでなくても、特定のスポーツにおいて知られているような人で充分かも知れませ。プロスポーツ、コンテスト全盛時代なので、地域スポーツでの選手でも対象には困まらない時代ではあります。(ただ、一方で認知と好き嫌いがあるので、細分化:セグメンテーションはされます。)
・アクティビティと結び付けるメッセージやイメージを発信するために、ソーシャルメディアを大いに活用する
Instagramで、スポーツ中に自社の商品が食べられている画像をアップするは言うまでも無く定番・鉄板施策です。
→日本では、コマース出来ないので、誘導だけになりますので、ダイレクトCV効果は疑問ですので工夫は要ります。
TikToKで、スポーツ中に自社の商品が食べられている動画をアップする。
→そのまま、Shopify連携コマースが可能なので導線としてはベストです。
などの事例は、説明するまでも無いと思います。
・自社商品の成分についてスポーツにおけるメリットが科学的に裏付けられているとベター
科学的根拠はヘルスクレームを謳うほど高度な物でなくてよいというか、この展開方法はイメージ的になります。←そもそもSRは少ないと思います。(PubMed®でサーチしています)
成長のためのマーケティングとしてスポーツに結び付けることは、健康的で手軽な商品のブランドにとってマーケットチャンスの1つでありますね、効果的に実施できるマーケティング選択肢ではあります。(サプリメントもそうです、事例は別途機会があれば)
パーソナライゼーション
パーソナライゼーションは、商品サービス購入時に、顧客の課題と嗜好性をヒアリングして、自社サービスをキュレーションするというプロセスです。USAのD2Cで展開が始まり「”Quiz”」という表現がされています。
(医療的な質問は、日本では薬機法に抵触しますので十分にご注意ください。くれぐれもUSAの質問をそのまま展開しないでください。)
・アパレル から始まり
・サプリメント
・コスメ
・ヘアケア
・そして、フード
・ヘルスケア&パーソナルケア
へとカテゴリー領域を拡げています。
そこでは、購入後の顧客の変化(バイタルや、身体、顔、体感など)を「見える化」するとともに、摂取や継続(再購入も含め)の動機付けをするために、モバイルアプリやウェアラブル端末との連携サービスを提供しているようになりました。
個々の身長、体重、睡眠パターン、心拍数、日々の活動状況に基づいた
個別のパーソナルアドバイス(リアルタイム→同期Syncか、非同期asynchronous対応か、AIか、Human対応どうかは様々です。)から、遺伝子プロファイル、身体の代謝バランスに基づいたサービスまで益々詳細になっています。
食材という物(物理的な)を販売・購入していただいているのですが、実際はこのサービスに価値があるのかも知れません(CRMの発展形とも捉えることもできます。)
これは、FemTech領域から、ウエルネス、ヘルスケアの領域までひろがっていることはご存知のとおりです。
単なる、サブスクリプションモデルではなく、モノからサービスへ付加価値をシフトしているということでしょうか。
*アプリ仕様について:個人的には、色々調べましたが、仕様・機能の違いは出せないと捉えています。収集したデータから何を導き出すかですが、バイタルだけで何かを語ることは難しいと捉えています。
スマートウオッチから得られるデータもまだまだ少ないですよね。
多分このビジネスモデルって・・・・・別の目的が・・・・
顧客とサービス事業者の双方にとっての、ベネフィットは、
ライフスタイル・パーソナライゼーションとして「見えるか」出来て、同じ数字・ログを共有してコミュニケーションできるっていうことです。
食生活や健康に関する活動を顧客自身でログ・コントールしていることでの安心を提供することだと捉えています。それを信頼に変えていくことが出来るかは、コミュニケーション(CRM)設計次第です。
顧客は、健康ブロガーやフィットネス・リーダーが推奨する健康情報、アドバイスを参考にして、グルテンや乳糖、加工食品、動物性食品、炭水化物などが、非健康・不健康だといった情報に触れると、生活態様(パターン)から排除してみたりしているでしょう。
自分用に、商品選択などカスタマイズできるアプリとツールなどを使ってみたりして、健康あるいはダイエットのために何をするか、何をしたか(ルーティン化してみたい)を、自ら定めたい、定めたものを選択したい顧客(診断プロセスから、提案されて、自分で選択して、アレンジして、その時の自分解に出会い、納得するという一連の行動態様)に活用されていると言えます。(情報の非対称性が端的に出ますので、オウンドメディアやロジックの整備はとても重要です。)
その中でも、最新技術(テクノロジーかどうかは別)に関心のある顧客は、テクノロジー・パーソナライゼーションで、DNA検査や詳細なその他の検査を受けて疾病リスクや、自信の遺伝子学的観点などから診断された身体の情報を入手し身体に適した食生活や運動などを取り入れ、行動から変化させ、より健康な生活を維持し疾病予防に繋げようと試みることを志向しています。
このようなサービスを提供する事業者や医学的コミュニティ(日本ではこれから自由診療の拡張版で生まれてくると想像できます。マーケティング施策で別記事にしますが、2B2Cマーケットの構築はこれからマストです。)から情報を取捨選択しています。
このパーソナライズトレンドの、重要なキーワードは、
・ダイエット&ウエイトコントロール(マネージメント)
・運動パフォーマンスの測定とログと共有
・健康 ヘルスとウエルネスの融合
です。
身体情報などパーソナルデータを元にした食事・フィットネスのコーチングや、FitBitなど他のツールからの活動状況(歩数、消費カロリーなど)との連携、ダイエットのための食事プランの提案と食品宅配など、個々の生活・活動に合わせた、利便性の高い複数のアプローチ方法(食事制限はほどほどで、エクサイズでとか、食事とヨガでとかの組み合わせ)や、付帯サービス提供など、総合的なウェイト&ウェルネスサービスに、昇華・収斂していくと想像されます。
単なるDNA検査や個人情報管理だけではなく、検査結果(は、納得性の担保です)を元にパーソナライズされたサービスを提供することに価値を置くことが重要で、細分化=パーソナライズされた顧客ニーズに応えることがポイントです。それが、結果としてブランドポートフォリオ構築となります。
パーソナライズの次のトレンドとしては、在宅健康診断(HealthCareのテックを、Wellnessに応用)は、
・Nutorition:栄養
・パーソナルケア
が顧客との関係を深め、商品ソリューションをパーソナライズとしてアレンジメント:調整するため、より説得力のある方法の1つになると思われます。
・ペットも診断の時代ですけど
CPG:消費財(Consumer Packaged Goods)ブランド事業者が、パーソナライズに重点を置くにつれて、商品推奨のためのAIを利用したアルゴリズムなどのテクノロジーが一般的になってきたことはご説明しました。(アプリ化)
それだけでは、納得性に限界があるため、一歩踏み込んで、在宅でのバイオグラフテストでパーソナライズをさらに一歩進めているということです。
これらの診断テストは、健康または生物学的パラメーターを定量化して、ペット、美容、栄養などのカテゴリー全体で、より独自にパーソナライズ化して、ソリューション・フォーミュラーをアレンジ:調整されたカスタマイズ商品として顧客に提供しようとしていることです。
バイオメトリクス=健康診断のデータは、今までの「Quiz:クイズ」形式よりもカスタマイズされた効果的な商品提供と、プロセスを生み出すことができると考えられています。
カスタマイズされたサプリメント療法のために、在宅血液検査を使用するDTC企業が数多く創業しています。このビジネスモデルって商品提供ではなく、データ付きの個人情報を提供するモデルなのですよね。(実は、ヒントは後ほど)
このタイプのカスタマイズは、一般的には、ペットや赤ちゃんなどのカテゴリで機会があると捉えています。
事例としては、マイクロバイオームテストまたは血糖モニタリングを使用して、自宅で自分の健康状態を監視できるようにしています。綿密かつ定期的に監視できるため、そのデータを相互にどう利用するかです。
モット重要なこと。
一般的に、DTCに限らず顧客とのCRMモデルは、Fの回数・6か月とか1年とかの購買パターンに基づいて、アウトリーチしています。
一方で、診断に基づいての顧客へのアプローチは商品サービスを選択し、購入する際に「顧客の将来のCLVを見通して」コミュニケーションマーケティングすることが可能だということです。
診断サービスを提供しているD2Cとのコラボサブスクリプションビジネスはとても有効な施策、マーケットです。
DNA検査サービスタイプも顧客に人気がありますが、ターゲット絞って商品をレコメンド:推奨することで、次のレベルのサービスにアップグレードさせていくことを設計しています。また、その可能性を追っかけています。
遺伝的健康素因を理解する手段としてDNA検査を選択しているのも、アメリカ的ですが、この分野のDTCとしては、顧客が診断とプロセスの結果をダイエットや、スポーツ・ウエルネス・フィットネスなどの活動計画などの実用的なライフスタイルの変化と結び付けて、ベネフィットとして役立つパートナーシップコミュニケーション設計を企画して検討しないと、顧客の結果は同じになります。
炎症(Inflammation)慢性的炎症
これは、構造的に理解することがとても工夫が必要です。身体の免疫システムなどが身体を外からの異物からどれだけ守れるかというものと、一旦定義してみましょう。具体的な炎症症状としては、
・体重増加(肥満)
・口腔環境悪化
・うつ発症
などがあげられています。
抗炎症食品・食材としては、USAでトレンドとしてウオッチ出来るものが
(エビデンス引用は、文末にリンク張っておきます。100近くあります。)
1.ベリー類
苺・ブルーベリー・ラズベリー・ブラックベリー
ベリーは、食物繊維、ビタミン、ミネラルが豊富に含まれている小さな果物です。ベリーはアントシアニンとして知られている抗酸化物質を提供します。これらの化合物は、炎症を軽減し、免疫力を高め、心臓病のリスクを軽減する可能性があります。ナチュラルキラー細胞(NK細胞)を生成し、免疫システムが適切に機能し続けます。
2.DHA・EPAを多く含む魚
サーモン・イワシ・ニシン・サバ・アンチョビ
タンパク質と長鎖オメガ-3脂肪酸EPAおよびDHAの優れた供給源です。
最近は、クリル(南極オキアミ)から取れるクリルオイルがとても伸張しています。
EPAとDHAは、メタボリックシンドローム、心臓病、糖尿病、腎臓病につながる可能性のある炎症を軽減します。
あなたの体はこれらの脂肪酸をレゾルビンやプロテクチンと呼ばれる化合物に代謝します。これらは抗炎症作用があります。

3.ブロッコリーなどのアブラナ科の野菜
カリフラワー、芽キャベツ、ケール(一時期、青汁・スムージで流行りましたね)と一緒にアブラナ科の野菜です。
炎症を引き起こすサイトカインとNF-kBのレベルを下げることで強力な抗炎症作用を持つ抗酸化物質であるスルフォラファンの最高の供給源の1つです。
心臓病やガンのリスクが低下することがわかっています。これは含まれる抗酸化物質の抗炎症効果に関連している可能性があります。
4.アボカド
アボカドは、数少ないスーパーフードと思われるものの1つです。
炎症から保護する、カリウム、マグネシウム、繊維、心臓に健康的な一不飽和脂肪が豊富に含まれています。
それらはまた、癌のリスクの減少に関連するカロテノイドとトコフェロールを含んでいます。
1つの化合物は、若い皮膚細胞の炎症を軽減する可能性があるそうです。
5.緑茶・抹茶(その他各国のお茶(Tea)もトレンド入りしています。)
緑茶の抗酸化作用と抗炎症作用、特にエピガロカテキン-3-ガレート(EGCG)と呼ばれる物質含有量は、炎症を軽減し、病気につながる可能性のある損傷から細胞を保護すると言われて、ブランド化しています。(日本では注目されませんが)心臓病、ガン、アルツハイマー病、肥満、その他の症状のリスクを軽減します。
EGCGは、炎症誘発性サイトカインの産生と細胞内の脂肪酸への損傷を減らすことにより炎症を抑制すると言われています。
6.ピーマンと唐辛子・ついでに香辛料
ピーマンと唐辛子には、強力な抗炎症作用のあるビタミンCと抗酸化物質、ケルセチン、シナピン酸、フェルラ酸、および強力な抗炎症効果を持つ他の抗酸化物質が豊富です。
ピーマンは抗酸化ケルセチンを提供し、炎症性疾患であるサルコイドーシスの人々の酸化的損傷の1つのマーカーを減らす可能性があります。
唐辛子にはシナピン酸とフェルラ酸が含まれており、炎症を抑え、より健康的な老化につながる可能性があります。
7.きのこ
世界中に数千種類のキノコが存在しますが、食用で商業的に栽培されているキノコはごくわずかです。一部の食用キノコ(トリュフ、ポートベローマッシュルーム、椎茸)は、炎症を軽減する可能性のある化合物を誇っています。きのこはカロリーが非常に低く、セレン、銅、およびすべてのビタミンB群が豊富です。それらはまた抗炎症保護を提供するフェノールおよび他の抗酸化剤を含んでいます。
これ以外では、コンブチャ(紅茶キノコって知っていますか?)や、サルノコシカケ、冬虫夏草などがトレンドです。(中医なのですが。)
8.ブドウ
ブドウには、炎症を抑えるアントシアニンが含まれています。レスベラトロールなどのブドウに含まれるいくつかの植物化合物は、炎症を軽減することができます。それらはまたいくつかの病気のあなたの危険を減らすかもしれません。
心臓病、糖尿病、肥満、アルツハイマー病、眼疾患など、いくつかの病気のリスクを減らす可能性があります。
多くの健康上の利点がある別の化合物であるレスベラトロールの最高の供給源の1つです。
アディポネクチンのレベルが上昇しました。このホルモンのレベルが低いと、体重増加と癌のリスクの増加に関連しています。
ブドウは、ワイン、果汁の抽出後の残渣を発酵有効利用することで、コスメやサプリメントの素材としても活用されていることは、既知だと思います。
*余談
ブドウに限らず。食品残渣からの有効成分には、注目されると良いです。とても大きな可能性があります。(成分効果と、収益性(原価率))
・古くは、チーズ生産からの、ホエー
・おから。大豆豆腐の成分
・にんにくの皮
・リンゴなどの果物の皮
・緑茶は、淹れたあとの葉の方が有効成分が高い
とか。事例にはこと欠かないです。
9.ターメリック
ウコンは、カレーなどインド料理によく使われるスパイスです。強力な抗炎症栄養素であるクルクミンの含有量で大きな注目を集めています。クルクミンと呼ばれる強力な抗炎症化合物が含まれています。ウコンは、関節炎、糖尿病、その他の病気に関連する炎症を軽減します。
黒コショウからのピペリンと組み合わせて毎日1グラムのクルクミンを摂取すると、吸収を大幅に高めることができます。メタボリックシンドロームの人々の炎症マーカーCRPが大幅に減少しました。
しかし、ターメリックだけで顕著な効果を体験するのに十分なクルクミンを得るのは難しいかもしれません。(健康障害もあります。)
単離されたクルクミンを含むサプリメントを服用することははるかに効果的です。クルクミンサプリメントはしばしばピペリンと組み合わされ、クルクミンの吸収を2,000%高めることができます。
という、展開も生まれてきてます。
10.エクストラバージンオリーブオイル
エクストラバージンオリーブオイルは、あなたが食べることができる最も健康的な脂肪の1つ(アマニとかいろいろ出てきますが)です。不飽和脂肪が豊富で、地中海式食事の主食であり、多くの健康上の利点を提供します。抗酸化物質であるオレオカンタールも有意性が提唱されています。
エクストラバージンオリーブオイルは強力な抗炎症効果をもたらし、心臓病、脳腫瘍、ガン、その他の深刻な健康状態のリスクを軽減する可能性があります。
CRPと他のいくつかの炎症マーカーは、毎日1.7オンス(50 ml)のオリーブオイルを摂取した人で有意に減少するそうです。
11.ダークチョコレートとココア
ダークチョコレートは美味しくて濃厚で満足感があり、炎症を抑える抗酸化物質フラバノールも含まれています。病気リスクを減らし、より健康的老化につながるかもしれません。
ただし、これらの抗炎症効果を享受するには、少なくとも70%のカカオを含むダークチョコレートを選択するようにとのことです。
12.トマト
トマトは栄養の大国です。ビタミンC、カリウム、およびリコピン、印象的な抗炎症特性を持つ抗酸化物質が豊富です。
リコピンは、いくつかの種類の癌に関連する炎症誘発性化合物を減らすのに特に有益である可能性があります。
トマトのカロテノイドは、脂肪源によく吸収される栄養素であるためオリーブオイルで調理すると、吸収するリコピンの量を最大化できると言われています。
13.さくらんぼ
タルトチェリー・スイートチェリーは美味しく、炎症と戦うアントシアニンやカテキンなどの抗酸化物質が豊富です。甘くて酸っぱいサクランボには、炎症と病気のリスクを減らす抗酸化物質が含まれています。
をなど含む乳製品やジュース、果実・野菜飲料などは、一般メディアやソーシャルメディアで話題となっているともに、今後ビジネス機会が期待されています。これらにおいては状況は同じで「消費者に分かりにくい」「科学的裏付けが十分でない」といった課題も浮上しています。
消費者がベネフィットを実感する方法もあるようですので、研究の進捗を見守りたいと思っています。(というくらいに、食系って多様性・多面性があるということです。)
慢性的炎症は、食のライフスタイル訴求ですので、
・オーガニック食品を食べる。
・緑の濃い野菜を食べる。
・魚油豊富な食事を摂る。
・プロバイオティクス、発酵食品を摂る。
・加工糖類の摂取を控える。
・未加工、コールドプレスしたエクストラバージンオイルを使用する。
など、様々なトレンドワードが思いつかれるはずです。
栄養食のマーケティングの本質的なこととして、科学的エビデンスとして炎症を直接的に示す唯一のバイオマーカーは存在しないことが最大課題・テーマです。
サイトカイン、ケモカイン、脂質、急性期たんぱくや白血球、好中球、Tリンパ球、好酸球、単核白血球などの血中マーカーの複数が、バイオマーカーの候補として検証されているようです。
そのため、炎症について科学的に正しく理解している顧客もまだ多くないのが実情ですので、注意してコミュニケーションしないと後々の自社のブランドを棄損することになるとともに、トレンドマーケットをシュリンクさせることになります。
一方で、科学的に根拠が無いにも関わらず
グルテン=悪者=グルテンフリーブーム
などがあるということは、
顧客が「理解する」ということと「信じる」ということは同じではない
ことが分かります。
→これが、ビジネスチャンスの1つです。
炎症対応商品市場(免疫)の拡大は今後もトレンドとして続くと思われます。(無くならない、解決しないテーマですから)
KFSの一つは
「ナチュラルな機能性」
ですので、科学的エビデンスが研究されている抗炎症素材を活用、展開することです、なぜなら、いままでも見てきたように、「抗炎症」はヘルスクレームとして立証するのは難しいからです。健康意識の高い顧客(付加価値に注目するライフスタイル・コンシューマー)は、自ら情報にアクセスする傾向がありますので、必ずしもヘルスクレームでの訴求は必要ではないからマーケティングとしてグロースさせることが可能だと判断出来るからです。
そこでの開発のポイントのキーワードは
・果実・野菜飲料カテゴリー
・ファミリー向けではなく、シングルサービング(パーソナライズ)の商品。
炎症に関連する症状は多種多様ですが、ただ一つの症状に特化するべきではなく、ナチュラルな機能性からスタートし、周辺環境(顧客の嗜好性の変化)に応じてブランドポジショニング(ラインエクステンションもふくめ)を定めていく方法がベストです。(サプリメント、コスメも同様のマーケティングです)
炎症性食品(逆説的に俯瞰して見てみましょう)を復習
炎症を促進する可能性のある食品を見てみると、抗炎症食品の訴求方法やベネフィットも見えてきます。
これらは、摂取を制限することが巷で喧伝されていますね。(身体に悪いものは美味しいです。)
・ファーストフード
ジャンクフード、ファーストフード、コンビニエンスフード、ポテトチップス、プレッツェルなど
・冷凍食品
いままで食を冷凍化したものと制限しておきます。
・加工肉などの加工食品
ベーコン、ビーフジャーキー、缶詰肉、サラミ、ホットドッグ、燻製肉
・不飽和脂肪酸の一種であるトランス脂肪
ショートニング、部分的に水素化された植物油、マーガリン
揚げ物や部分硬化油には、炎症レベルの上昇にも関連していると話題になりました。
・砂糖で甘くした飲料
ソーダ、スウィートティー、エナジードリンク、スポーツドリンク
これらは、CVSでの売れ筋です。
・精製された炭水化物
白パン、パスタ、白米、クラッカー、小麦粉トルティーヤ、ビスケット
揚げ物:フライドポテト、ドーナツ、フライドチキン、モッツァレラスティック、エッグロール
とても、魅力的で美味しそうな、食べ物たちですね。
プロテイン(ブームからトレンドで、パーソナライズ化)
あらためて言うまでもなく、最注目カテゴリーです。高プロテインダイエットに限らず、プロテインマーケットの伸張は目を見張るものがあります。
これは、ウェイトウェルネス(ダイエットだけではなく、ウエイトコントロール、ボディメイキングなど)としての低糖質食とも密接に関係しています。
ブームになった事例:
パレオ:Paleolithicera食事による炎症を抑えることで慢性疾患のリスクを下げて、体重を減らすダイエット法。
旧石器時代の原始人の食事にならって野菜や肉・魚などの動物性たんぱく質を中心に摂取し、穀類や糖質を避ける食生活をすることによって、ダイエットしようという食事方法のこと。USAではブームでしたが、日本ではイマイチ
ゾーンダイエット:食事による炎症を抑えることで慢性疾患のリスクを下げて、体重を減らすダイエット法。(ボストン大学やマサチューセッツ工科大学の生化学者のバリー・シアーズ博士が考案)病院あるいはウェブサイトで販売されている試験キットを使って3つの臨床マーカー、インシュリンや、炎症をおこすホルモンの値を調べることで状態を確認して、身体をこのゾーン状態にキープすることで、1週間で500gから1kgほど体重を減らすことができるとダイエット方法。主要栄養素を摂取する割合を厳しく設定しています。炭水化物40%、タンパク質30%、そして脂質30%という割合がゾーンダイエットが推奨する割合。この割合が血糖値とホルモンを安定させて、炎症作用を防ぐとされている。面倒(検査・診断・パーソナライズの要件を満たしているのですが)なのと痩せないらしく人気は下降気味。
*余談
USAではダイエット方法は、40程あります。またランキングされています。興味深いので、Diet rankingで検索してみてください。
https://health.usnews.com/best-diet

プロテイントレンドですが、乳製品、ヨーグルト、肉、豆類といった天然素材で摂取することを顧客は嗜好しています。
朝食シリアル、バー、パンへのプロテインを添加することもUSAでは展開されています。プロテインと言えば、まず動物性原料を想定するのが一般的です。高プロテイン摂取のトレンドにより、ベジタリアンになるどころか、実際には肉の消費が増加しているいう不可思議が現象もあります。そのために、後述する、便利な商品フォーマットになった植物性プラント肉のマーケットが芽生えつつあり、注目されている原因でもあります。
プロテインのカテゴリーについて整理して見ましょう。
・乳製品:
チーズ、クワルク(柔らかいフレッシュチーズ)、ヨーグルト(どれだけの種類があるか調べてみてください)等は、プロテイン摂取法として代表選手ですね。
・パン・菓子類:Protein Bread & Confectionery Protein High Protein Snacks
プロテインは添加しづらいフォーマットのようです。食感と、コストに課題があるようです。
Walmartでは売れ筋のようです。
・バー類:Protein Bars
プロテインだけで差別化は出来ないので、マーケティングテクニックが求められるカテゴリーです。(Bar類としても)特定ニッチにフォーカスすることが重要なようです。
Amazon、Walmartでの品ぞろえをみても理解できます。
Food系のD2Cは、WholeSaleありきなので、マーケットプレイスでの展開は定番ですし、Walmartのマーケットプレイスへの出店も簡単です。
USAでは、プロテイン市場はとても大きくここでも掲示している他のトレンドとの掛け合わせでセグメント化が進んでいます。
・食事代替型ダイエット食品 alternative diet food
・スポーツニュートリション
・マルチビタミン+(アメリカ人はマルチビタミン信仰があります。)
マーケティング的な展開としては王道ですが、ファッションモデルやトップアスリート(栄養に対する意識が先を行っているイメージ)、e-ゲーマー(デスクワークだが良好な栄養状態を希求する)をアイコンにしています。

・ボーンブロス:Bone Broth
鶏・豚・牛などの骨、あるいは魚の骨と野菜を一緒に煮込んで作る「ボーンブロス」という、アミノ酸、コラーゲン、ヒアルロン酸など、美容・腸活効果のある栄養素スープです。日本ではどうでしょうか?出汁(だし)パックとコラーゲンのマーケットはありそうですが。
・豆スナック:High-Protein, Bean-Based Snacks
ルピン豆、ヒヨコ豆、植物由来トレンドと、プロテイントレンドに添っています。美味しく植物プロテイン豊富なスナックとしてトレンドを形成しています。日本では大豆(枝豆)が王道ですが、それ以外が伸びないですね。
スナッキング:Snack
どのカテゴリーにも適応できる摂取形態のトレンドですね。マーケットの細分化=顧客の嗜好性多様化への対応のソリューションの1つです。間食だけではなく食事としてもスナックを摂るようになっています。一方で、個別包装や便利な商品フォーマット(賞味期限が長く、小規模生産に適している、そのためリスクが低い)でもあるスナッキングは大きなトレンドです。パーソナライゼーション需要の影響もありますので、ニーズに合わせた1回摂取分量の商品が増えることは理解頂けると思います。
成功と成長の要因としては、顧客(私たちもそうですが)は新規性を好むので、ワクワクするような、また持ち運びやすいデザイン形態に変えていくことがポイントのようです。ヘルスコンシャスなライフスタイルの顧客は、フォーマットや原材料に関わらず、新しく革新的なスナックを食べてみることに積極的だそうです。
1. スナック化はどのフード・ドリンクカテゴリーでも可能
2. 一日中、いつでも、どこでも、スナックタイム
3. 新商品開発に制限はない
4. 小分けによることで利益増
カテゴリー事例
1.乳製品
乳製品は殆どの市場、世界各地において、スプーンで食べる、飲む、絞る等、様々なフォーマットの健康志向の高い顧客のヘルシースナックとして確立、成功しているカテゴリーです。
2.野菜
プラントフードのトレンドと相まって、らせん状のズッキーニや米粒状のカリフラワー等、野菜を用いたビジネスのイノベーションは無制限でコンセプト次第です。
3.パン・菓子類
ポジショニングに説得力があれば、顧客が一番欲しているカテゴリーです。糖分が多い美味しい食品というイメージも活用できます。
サイズ設計や、クッキーやケーキを摂りたいニーズにも適応できます。
炭水化物。ってどうなの。健康に良いのか悪いのか。どっちなの?
低炭水化物ダイエット
グルテンフリー
は、しっかりと顧客に認知されトレンドとして健在です。炭水化物は悪者というイメージは醸成されていて、価値判断としては定着しています。一方で、植物性食品、低炭水化物・高脂肪(LCHF; low-carb hi-fat)食(良い脂肪が見直されていることを忘れないでください)等も、トレンドして成長をはじめています。
顧客は「炭水化物」の摂取の仕方(ライフスタイル)、食事の炭水化物の質について、識別タグをつけるようになったと言われているようです。(自分にとって、良い、悪いとか、〇〇だから、良いとか、××だから悪いとか)
例えば、
「顧客は炭水化物のタイプを見極めようとしています、加工が最小限の果物や野菜は(高炭水化物でも)ヘルシーと理解して、判別して摂取する行動をとっています。本当の問題は摂取量なのですが」
「全粒穀物はヘルシーな炭水化物源である」が卑近な事例です。
また「『炭水化物』という言葉は否定的な意味合いを持ちますが、全粒穀物、果物、野菜等は問題はない」
と、判断・区別しています。
近年のエビデンスでは間違いだと指摘しているにも関わらず、食事摂取指針は炭水化物を多く摂取するよう勧めていることを、健康意識の高いミレニアル世代は信じていないとのリサーチ結果もあります。
細分化(セグメンテーション)
このトレンドウオッチで、とても重要な影響ファクターでもあるインターネット・ソーシャル情報をもとに、顧客は自分自身の食事摂食プランを、選択して、試して、自ら考案するようになっています。そのため、影響というか接触したメディアによって(時と場合で影響度が変わります。)行動価値・態様が「細分化」されていきます。これは、パーソナライゼーションと相互に関連しています。また、その結果、商品がプレミアム化への振れていく強いファクターになってしまっています。
顧客は、「専門家」ではなくブロガー・インフルエンサーなどのポスト(投稿)により注目(そもそも、専門家からの引用でもありますが)し、判断材料としての価値ウエイトをかけているようです。(特に、日本とアジアはそうです。KOLとかですね。)
自分に合った食事パターンや食品・素材選択を行うようになっています。(これは自慢か、〇〇欲求かどうか別として、ポスト投稿行為をするのでより拡散します)、そして、何が効果的かを、気軽に試すようになって来ました。その結果、マーケティング的にはマーケットの細分化が進んでいきます。(ここで見間違いをしないでくださいね。本当のニーズは同じで、選択価値が違うだけです。サブスクリプションモデルが成立しなくなってきているのと、CLVがとてもロングタームになるってことです。)
各々が自分に最適なもの、スタイルを選択するということは、ターゲットはどんどん細かく、分散して発現・接触・購買・リピートするようになります、それは、マーケティングとCRMコミュニケーションの粒度が細かくなるということです。
さらには、ブランドが(ある程度の)「規模:日本なら、10億、30億、100億」に達することも難しくなります(これは、サプリメント、コスメでもそうです。対象人口数だけの問題でもないです)。一連のプレミアム価格のニッチから、そのうちいくつかが、大きなニッチカテゴリーに成長するパターンがこれからの定番になりそうです。(少し成長すると、グレーマーケットが生成されるので、そこで企業のコミュニケーション力が問われてきます。)
その他トレンド
「かつては脂質と砂糖を除けばBFY(better-for-you)のシンプルな訴求で、ニーズは満たされていました。
現在は、ヘルシーの定義が、下記のKeywordのように多様化、モザイク化しています。(ポジティブな購入ファクターではないけど、あったらいいなのプラスオンファクターです。)
・原料の由来とトレーサビリティ
・認知度・啓蒙アグリケーション
・フェアトレード
・サステナビリティ(〇〇ウオッシュは難しい問題です。)
ジェネレーション区分としては、
・ミレニアル世代
・高所得かつ高学歴の年配者達(団塊世代)
が大きなマーケットです。食品・飲料に対する、選択価値(嗜好性が少し違いますが)を、健康とウエルネスの視点を加味することで、顧客は変えていっています。
情報を様々なタッチポイントで手に入れていますので、どのようにヘルシーな食生活をおくるかを自分自身で判断する傾向が醸成されています。(また、知見・体験能力として身に纏ってしまいます。)、そうした中で、健康効果から見直される天然食品系の食材・素材もありますし、(ナッツ、チョコレート、タマゴ、赤ワイン等)、新しく発見(大体は、知られざる世界の地域の食生活からですね)される食材も多く提案されます。
マーケットボリュームとプライシング
新ブランドは、マーケット規模とそれに関連しての顧客数、購買頻度的にトップラインが自ずから制約されてきます。
ライフスタイル・コンシューマー(人口の20-30%、プレミアム価格を支払う顧客層)をターゲットにすることになります。低ボリュームの生産量ゆえ、高コストを回収する必要があるために必然的になってしまいます。そのためには、これまで以上に細分化された顧客市場を狙った、コミュニケーションからブランド価値を構築していき、SKUを増やすことで隣接する顧客、マーケットへ蚕食することを考えます。(ベキかも)
「売れる」と「売れない」見極めるためには、
日本市場と海外USA市場の違い、顧客ニーズの違いを理解することがとても重要なことは当然です。コピーキャット・タイムマシン経営で出来ることと出来ないことがあります。
良くありがちですが、USAでは〇〇市場が、1兆円だから、日本は人口1/3だから3000億円はあるだろう・・・(USAの平均体重70Kgだけど、日本は50㎏も加味されていないし、そもそも、食習慣が違うよね。穀類の摂取方法とかが)
ヘルスベネフィットによって、消費者が取り入れている食品形態が違うってことです。顕在市場なのか、潜在市場(開拓)なのか、そのカテゴリーでのヘルスベネフィット(サーチしてみてください。20-40とかのKeywordがあります。)のポテンシャルを見極める必要があります。
ヘルスベネフィット例
体力
健康維持・増進
疲労回復
体質改善
筋肉強化・維持
感染予防
栄養
栄養バランス
血液
血行促進
高血圧・血中脂質・血糖値
貧血
美容・スタイル
美肌・肌ケア
減量と痩身
発毛・育毛
口内系
関節・骨系
消化器系
排泄系
冷え性
体臭
睡眠
アレルギー
認知・脳機能
更年期
女性特有の課題
妊娠前後
ストレス系
そして、がん
これらに対して、法律で定義された、提供カテゴリーとして日本では下記のカテゴリーがあります。
「トクホ」
「機能性表示食品」
「その他の健康食品」→ここ
「食品」→ここ
「医薬品」
「その他」
顧客の対応の事例から
腸内環境ウエルネスの「整腸・便秘の改善」ヘルスベネフィットでは、
「トクホ/機能性表示食品」よりも「健康食品」利用者が多く、それよりも「食品」で対応する顧客が圧倒的ということです。
腸内環境2.0を、提供する、成分・素材から見ると
「乳酸菌・ビフィズス菌」は、機能性飲料>機能性食品>サプリメントの順になります。サプリメントは機能性飲料(表示ではない)の1/10以下という生活・選択行動です。
サプリメントよりもTopラインが大きくなるのが、Nutiritonカテゴリー食品、飲料マーケットの魅力だと理解頂けるでしょうか。
今回は、俯瞰情報だけですが、別記事で飲料系のトレンドや、プロテイン、スポーツ、スナックについても俯瞰してマーケット参入ポイントをUSAの事例から導き出していきたいと思っています。
参考文献データ
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22133051/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24512603/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26773014/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26501271/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22111516/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21242652/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18541602
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3775255/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24860193
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22326554
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21142420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26829184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25465932
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21593509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12094621
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21129940
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25705128
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25054107
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19813713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26447150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15632265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20936426
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23196671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20370896
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15350981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17584048
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26299975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17584048
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26299975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22100562
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17719033
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12115659
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21324570
http://www.hindawi.com/journals/omcl/2016/3571614/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18188410
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25505823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23543896
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26559695
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24262531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25332995
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20231522
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26180583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24699803
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24055518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23224687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18265479
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17569207
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26088351
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26007179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25688638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22407780
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25618800
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23150126
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9619120
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26055507
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25733165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26410343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17391565
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24925270
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21443487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20179144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24566441
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19776136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24376420
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24302679
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16877960
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16198843
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20491642
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24379011
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23970935
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25469376
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15927929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20944519
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26545642
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19857054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23343675
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16549461
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31314878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15051604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24552752
http://nutritiondata.self.com/facts/vegetables-and-vegetable-products/2348/2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20096093
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
