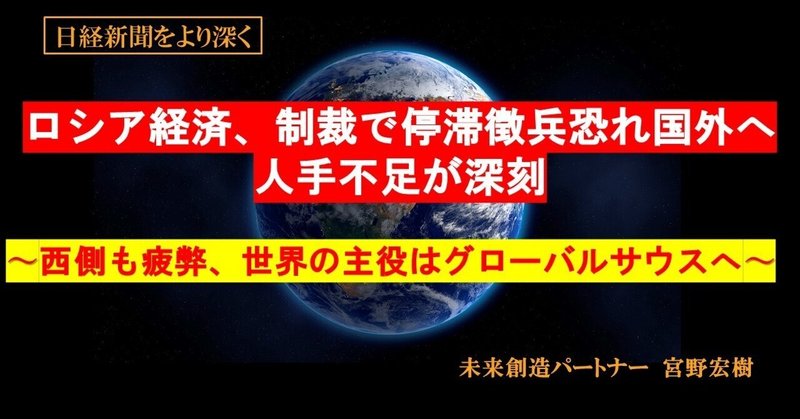
ロシア経済、制裁で停滞徴兵恐れ国外へ 人手不足が深刻~西側も疲弊、世界の主役はグローバルサウスへ~【日経新聞をより深く】
1.ロシア経済、制裁で停滞徴兵恐れ国外へ
国際通貨基金(IMF)の1月の推計によると、米欧の経済制裁の影響からロシアの2022年の実質国内総生産(GDP)成長率は2.2%減だった。エネルギーインフラや産業施設を攻撃、占領されたウクライナは30%減(同国中央銀行推計)と大きく落ち込んだ。
23年は両国とも0.3%のプラス成長が見込まれるが、侵攻開始前の経済規模には届かない。ロシアでは失業率の低下と働き手の不足が鮮明になっている。ロシア連邦統計局によると、失業率は2022年春以降4%を割り込み、12月は3.7%と過去最低の水準で推移する。
22年9月、プーチン大統領は部分動員を発令し、30万人超の予備役を招集した。ロシア中央銀行は「動員の影響と企業の労働力需要が増加する中、多くの分野で人手不足が深刻化している」と指摘する。徴兵を恐れ国外に逃れた若者も多い。人手不足に高度人材の「頭脳流出」が重なり、今後の成長を制約しそうだ。
12月、主要7カ国(G7)と欧州連合(EU)などはロシア産原油の取引価格に上限を設ける制裁を発動した。割安な価格でロシアが新興国に原油を販売する動きが広がったため、指標となるウラル原油と北海ブレント原油との価格差が拡大、ロシアの1月の石油・ガス収入は前年同月比46%も減った。
日本勢を含む外資系自動車メーカーの撤退やサプライチェーン(供給網)の混乱でロシアの新車販売は低迷が続く。22年は前の年に比べて6割減少し、撤退メーカーを補うかたちでロシア車のシェアが高まっている。
ロシア経済の厳しさが報道されていますが、西側諸国にも支援疲れが見られます。
2.ウクライナ戦争が始まってからの世界事情
2022年2月24日のロシアによるウクライナ侵攻から1年。世界のパワーバランスが大きく変わろうとしています。その象徴となるのが、第二次世界大戦以来、再び戦場となったヨーロッパと西側諸国の疲弊です。
2023年1月に英国が英国製主力戦車「チャレンジャー2」の供与を表明しました。その後、米国は最新鋭の主力戦車「M-1エイブラムズ」を、ドイツはヨーロッパで広く保有されている自国製主力戦車「レオパルト2」を、ウクライナへ供与すると発表しました。
それに対し2月2日、ロシアのプーチン大統領は旧ソ連がナチス・ドイツに勝利した「スターリングラード攻防戦」終結80年式典で、「我々は再びドイツの戦車に脅かされている」と演説の中で発言しました。
2月13日にはウクライナ東部の戦略的要衝であるバフムトがロシア軍の激しい攻撃を受けています。新たな大規模攻撃の前哨戦とも受け止められ、ヨーロッパでは今後、独ソ戦(1914年~45年)以来の大戦車戦が勃発してもおかしくない状況といわれています。最も、戦車の供与はそれほど早くは進まない、また戦車の操縦はそれほど早くはできるようにならないなども指摘されてはいます。
ただ、ヨーロッパの歴史に刻まれる凄惨な戦いの一つが独ソ戦です。そこを思い起こさせる今の事情が危機であることには違いありません。
独ソ戦は、旧ソ連の工業都市スターリングラードにおける半年に及ぶ市街戦で2000万人以上が死傷しました。ロシア・ウクライナ両国の国境で行われた「クルクスの戦い」はドイツ2800両、ソ連3000両の戦車が激突した史上最大の戦車戦でした。

ロシア、ウクライナの停戦へ向けては両国の主張になお、隔たりがあります。ロシアはクリミアはもちろん、ドンバス地方は譲れません。ウクライナは全土の領土回復を主張します。西側は武器の供与など支援を続けますが、ロシアには資源も資金もあります。
仮に、西側の主力戦車を得たウクライナが併合した4州を奪還しても、ロシアは空爆を続けることができます。一方で、ウクライナにとって降伏はロシアに統治を委ねることを意味し、絶対に認められません。停戦に向けては、「戦争による疲弊によって、継続したくない」ということになるか、もしくは、どちらかの「勝利」または「かなりの優位」が必要になるでしょう。
現状、西側は武器の供与を続けていますが、西側支援の限界も見えてきており、逆にロシアは大規模な攻勢をかけている模様です。また、強硬姿勢の米国でも下院は共和党が支配しており、支援継続も一枚岩ではなくなってきています。
西側のリーダーたちは、バイデン政権の動きに引きずられるように対ロシア強硬姿勢を保っていますが、内実は支援疲れとなってきています。
3.グローバルサウスの存在感
G7を中心とした西側先進諸国が戦争で消耗する中、存在感を高めているのが、中国やインド、トルコといった新興国・発展途上国からなる「グローバルサウス」です。今年、人口が世界一となるインドのように膨大な数の生産年齢人口と、豊富な天然資源を武器に世界経済の主役の座を西側諸国から奪いつつあります。
これらの国々は経済のグローバル化の恩恵を受けて成長してきました。インドではデジタル分野の成長も目覚ましく「シリコンバレーよりベンガルールだ」とまで言われるようになってきました。
そのインドのモディ首相は、西側諸国とグローバルサウスの橋渡し役を本気で努めようとしているようです。
グローバルサウスとは米欧とロシア・中国との分断の中で、どちらにも与しない存在です。
2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナへの侵攻は米中対立が続く中での出来事であり、世界の分断をさらに深めることになりました。ウクライナを支持する米欧側につくのか、それともロシア側につくのか、世界中が踏み絵を迫られることになりました。
ところが、どちらにも与しない国が相当数あることが明らかになってきました。侵攻直後の2022年3月2日に開催された国連総会でロシアに対する非難決議を採択すると、193か国のうちインドや中国、ベトナム、南アフリカなど35カ国が棄権しました。4月7日の国連緊急会議会合で、ロシアの国連人権理事会理事国としての資格停止を求めた決議を採択した際には、棄権する国がさらに増加。ブラジル、エジプト、メキシコ、タイ、インドネシアといった新興経済大国を多数含む58カ国に上りました。
これらの国々を含め、発展途上国・新興国のほとんどは、米欧や日本など西側諸国が課している対ロシアの経済制裁に加わっていません。そうした国々は「グローバルサウス」のメンバーと称されます。ウクライナ侵攻は、その独特の行動にスポットライトを当てることになりました。
グローバルサウスとは、アジア、中東、アフリカ、ラテンアメリカの地域に含まれる発展途上国や経済新興国の総称です。ただし、ここでいう「サウス」は単に、これらの国々が主に南半球に位置しているという地理的な位置を表しているだけではありません。これらの国々で見られる経済発展の遅れや政治・社会不安定が、先進諸国である「北」によって作り上げられた世界政治・経済の構造に起因するという認識から、「北」に対する「南」という呼び方がなされているのです。
このグローバスサウスの存在感が注目されたのが、2022年11月にバリ島で開催されたG20首脳会議でした。
インドネシアはここで、独自の外交力を発揮しました。西側諸国によるロシア排除のの要求を一貫して拒否しました。軍事侵攻に対しては交渉による平和的解決を呼びかけつつ、G20は経済協力を話し合う場であって対立を持ち込むべきではないとの立場を貫き、姿勢がぶれることはありませんでした。
ジョコ・ウィドド大統領自身が各国首脳にサミットへの参加を呼びかけました。ジョコ大統領は22年6月、ドイツで開かれたG7サミットに参加後、ウクライナの首都キーウを訪問してゼレンスキー大統領と会談。その足でモスクワに飛んでロシアのプーチン大統領とも会談し、両首脳にG20サミットへの出席を求めました。
両国の首脳を訪問したのは、アジアの首脳では初めてでした。ジョコ大統領が紛争当事国の両首脳と会談できたのは、インドネシアが西側にもロシア側にも与しない中立の立場をとり続けていたからこそでした。
11月にバリ島で開催されたG20首脳会議は、そうしたインドネシアの外交努力が結実したものとなりました。プーチン大統領は出席を見送り、ラブロフ外相が代理出席しましたが、ロシア側の出席を理由にボイコットした国はありませんでした。また、外交当局によるギリギリの交渉により、実現は難しいと思われていた首脳宣言の採択にもこぎつけました。
首脳宣言は冒頭部分で「G20は安全保障問題を取り上げる場ではないが、世界経済に深刻な影響を及ぼしていることに鑑みて軍事侵攻について触れる」とした上で、「ほとんどの国がウクライナの戦争を非難」し、「核兵器の使用や威嚇は許されない」と明記しました。一方で、「情勢に関して他の見解や異なる評価もある」と併記することでバランスをとり、首脳宣言に対するロシアの同意を取り付けました。
その上で、「本来」の議題であった保険分野の国際協力、食料・エネルギー安全保障、気候変動対策、デジタル経済の促進といった経済協力に関する項目を盛り込みました。ロシアのウクライナ侵攻後に開かれた主要な国際会議では、対立によって共同宣言の採択が見送られ続けていたため、首脳宣言の採択を成し遂げたインドネシアの努力に、各国は賛辞を送りました。
グローバルサウスの国々は数百年にわたって欧米諸国の植民地支配を受けた苦い経験を持ちます。独立後も、政治・経済的に先進国に従属する立場へ追いやれました。欧米の大国に対する根強い不信感を背景に、特定の国の支配は受けない、指示には従わないという想いをどの国も持っています。
ウクライナ侵攻や米中対立が深刻化する中、対立する両陣営はグローバルサウスを自らの陣営に引き入れようと躍起になっています。しかし、非同盟運動の歴史を知れば、グローバルサウスの国々が短期的な利益と引き換えにいずれかの陣営に加わることはないということが明らかになってくるのではないでしょうか。
かつて支配する側にいた「北」の先進国は、グローバルサウスの源流を良く理解して、彼らの行動を分析しなければなりません。グローバルサウスの各国がそれぞれにとる一つの行動から「どちらの味方」と見るのは、間違っています。グローバルサウスは、どちらに与するのではなく、自らの意思を明確にしていく時代に入ったということです。
インドネシアを引き継いで23年のG20議長国となったのはインドです。インドも、インドネシアとならんで冷戦時代から非同盟運動を牽引してきた「サウス」の大国です。インド政府は、23年1月に「グローバルサウスの声サミット」と題するオンライン会合を主催し、G20ではグローバルサウスの代弁者として振る舞う意志を示しました。
G20議長国は、インドの後もブラジル(24年)、南アフリカ(25年)とグローバルサウスの国々が続けて務めることが決まっています。国際社会におけるグローバルサウスの影響力がますます高まっていくことは間違いありません。
西側先進国の論理で世界秩序を保つことはもはや難しくなるでしょう。そして、決してロシアも自らの論理で世界を支配したいとは思っていません。
一刻も早く戦争が終結することを願いますが、戦後は、西側先進国の論理だけではない世界、グローバルサウスが発言力を持ち、世界は違うバランスの上に運営されるのではないでしょうか。
未来創造パートナー 宮野宏樹
【日経新聞から学ぶ】
自分が関心があることを多くの人にもシェアすることで、より広く世の中を動きを知っていただきたいと思い、執筆しております。もし、よろしければ、サポートお願いします!サポートしていただいたものは、より記事の質を上げるために使わせていただきますm(__)m
