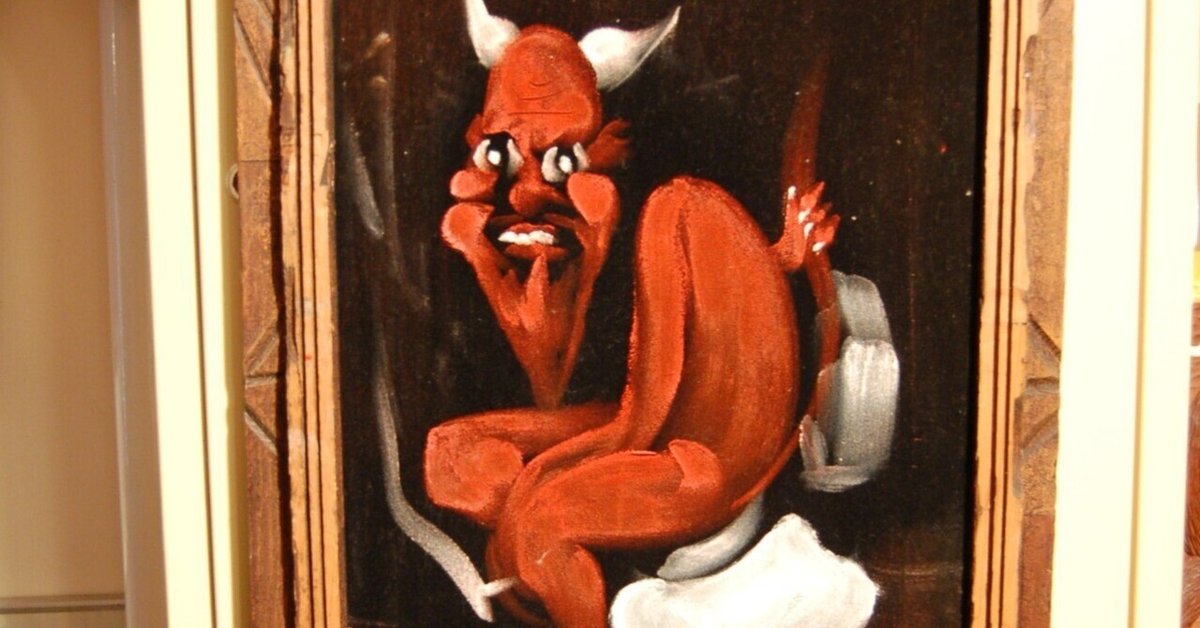
召使いは悪魔をお祓いする ~ポーランド口承文学~
この話は1964年にポーランド東部で採集されたものです。今から60年近くも前ですね。その頃はまだ悪魔も妖も、この地に今よりもずっと広く深く住み着いていたと思われます。
それでは はじまり はじまり~。
あるところに、幾人かの召使を抱えている主人がいたんだよ。あれは女の召使だったな。でな、その主人は悪魔も抱えていたのさ。この悪魔は、屋根裏部屋の臼の中で寝泊まりしていたんだ。そんでな、この主人たちが、客として呼ばれてどこかにでかけるだろう。そうすると、この悪魔はいつでも何か、(その間家で起きていた)話を聞かせてくれたのさ。ま、なんでも話したんだな。
一人の召使には婚約者の男がいたんだよ。男は自分の婚約者のところに通っていたんだな。この召使たちが何をしていたのか、外出先から(女)主人が家に戻ると、悪魔はこの(女)主人に全て話して聞かせたのさ。だから女主人は、召使が自分達がいない間、屋敷で何をしていたのか全てお見通しだったのさ。
ある日主人たちがでかけると、この召使はとつぜん聖水を片手に屋根裏まで登ってきて、悪魔の寝ている臼のなかに聖水をふりかけ、聖なるチョークで臼の周りを囲むように線を引いたんだ。そして、グラグラとした煮え湯を、臼の中にぶちまけたんだ。そうしたら、臼のなかで悪魔がひどい悲鳴を上げ始めたんだよ。最後はその煮えた湯の中でゆで上がっちまったんだな。
主人たちが家に戻ってくると、あの悪魔が姿を見せない。夜遅くになっても、次の日の朝になってもあらわれなかった。女主人は、屋根裏に上り臼の中を見ると、あの悪魔はもう死んでいる。
部屋に戻って召使をつかまえると女主人は言ったのさ。
「お前!あいつを始末するなんて、一体全体お前に何をしたっていうんだい」
「あたし、その悪魔のこと、何も知りません」
召使は何も知らないっていうだよ。
それでも、召使は悪魔を始末してさ、全てがおわったんだよ。

こういう民具は見ていてウキウキします。(画像はwikipediaから拝借)
さて、召使が使ったチョーク、これはキリスト教の教義に特に興味を持っていない人には「なんなの、それ」でしょうか。ポーランドでは1月6日は「東方の三賢人の日」で、あれですね、イエスの誕生をお祝いするために遠くからやってきた3人の賢者がとうとうイエスが生まれたエルサレムの馬小屋にたどり着いた、万歳、という日です。で、現在この日には水とチョークと香をお清めする日です。ということで、聖水はわりと広く知れ渡っていますけど、チョークにも聖チョーク(日本語名、なんだろう・・・)というものがあるのだそうです。ちなみに、ポーランドではクリスマスから2月の頭にかけて、神父さんが見習いをひきつれて信者の家を回ります。そして訪問が終わると、その家のドアにK+M+B(ラテン語版だとC+M+B)で「キリストの祝福を(この家に)」と、このチョークで書くんですね。
信じるかどうかはひとまず横に置いておいて、民話などを理解するときにその時の社会状況や宗教を知らないと「はてさて、なんのこっちゃ」と思う事、しばしばありますね。私はキリスト教徒ではないのでこれを「知識」として学習する必要があります。実を申しますと、私も今回の聖チョーク?は「あれま」と、その存在自体が初耳でございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
