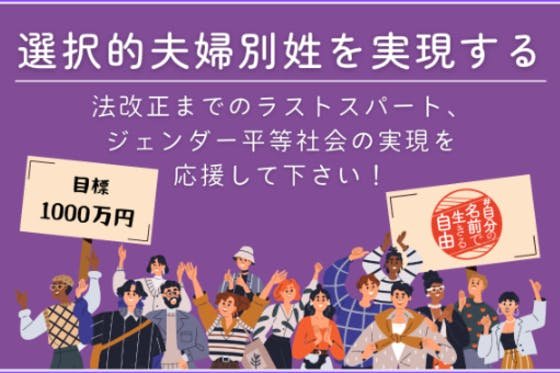2人とも、名字を変えずに結婚しました。〜後半〜
前半のnoteでは、結婚を決めてから事実婚契約書を締結するまでに私が「経験したこと」を書いた。これから事実婚を考えている方で「どんなことが起きるんだろう」と気になる方はこちらも併せてどうぞ。
結婚を決めてから事実婚契約書の締結までに、私が感じた悲しみや苦しみ。
私の気持ちの背景に何があったのか、分析してみた結果を書いてみる。
1.結婚を決めた時の、名字についての周りの反応
職場での反応
パートナーは同僚のため、結婚を決めてすぐ2人で職場に報告をした。みなさん祝福してくださり、とても嬉しかったのを覚えている。その話の流れで「名字が変わっても、うちの職場では旧姓も使えるし書類なども変える必要はないよ」と言ってくださった。私たちから確認しなくてもそこまで気を回してくださったのはとても嬉しかった。でも、その言葉のほとんどは“私の方を見て“言われた。
もちろん全く悪気なくむしろ気を遣ってくださっているのは分かっていた。だからそう言ってくれた方が悪いとかは全く思っていない。でも、私はこう思った。「名字を変える可能性があるのは私だと思われているんだな」
幼馴染の反応
結婚を決めてすぐ、地元から関東に出て来た幼馴染たちと会う機会があった。幼馴染たちには直接報告しておきたいと思い、パートナーと婚約したこと、名字は変えたくないから事実婚などの形を考えていることを話した。私を含めて女性が3人、男性が2人の集まりだった。
その中の女性の1人は「私も名字を変えたくなくて...!」と共感してくれ、もう1人の女性も「そういうこともできるんだ!」と反応してくれた。
話してよかったと思っていたその時、男性の1人からパートナーの名前を聞かれた。隠すこともないと思い名字だけ伝えると、私のことを「○○さん!(※パートナーの名字)〇〇さん!」と呼び始めたのだ。私が「名字を変えたくない」という話をしているその場で。
私は耳を疑った。
何度も「だから変えないって言ってるじゃん」「違うから」と言っても聞く耳を持ってもらえず、結局お店を出るまでそう呼ばれた。
私が名字を変えることが当然だと思われ、久しぶりに会う幼馴染にまで強制される。何が起きているのか分からなかった。
私は、その幼馴染とは、しばらく会わないことを決めた。
相手には言っていないから、結婚して付き合いが悪くなったとか思われているんだろうけど。
我慢して改姓した友人からの反応
私より少し前に結婚した友人には、結婚に関することを色々聞いていた。久しぶりに会った日に名字を変えたくないことを話すと、「私も最初はそうだったよ〜」「でも最近、自分の名字への執着とか、なんかそういうのを手放そうと思ったの」「段々慣れてくるもんだよ」と言われた。
彼女なりに必死で適応した結果なのだと思う。私が改姓する時がきたら少しでも楽な気持ちでできるように励ましてくれていると分かったから、本当にありがたい気持ちだった。
でも同時に、「私が執着しているのはよくないことなのか...」「慣れられない私はいけないのか...」という気持ちにもなってしまった。
2.女性として受けている抑圧
抑圧とは、「個人(またはグループ)が特定のグループまたはアイデンティティに所属しているという理由で、不当な行為が行われたり政策が制定されたりすること」をいう(Baines, 2022)。
社会、制度、文化的な抑圧もあれば、個人レベルでの抑圧もある。ここまでの私の経験を、私が女性として受けた抑圧として考えてみる。
・日本では別姓での結婚が法的に認められていないこと(制度的抑圧)
・結婚において96%の夫婦が男性側に名字を合わせていること(社会、文化的抑圧)
・結婚をすれば「私が名字を変える側」として周囲の人に思われること(文化的抑圧)
・私から意思表明をして、名字を変えたくない理由を何度も説明しなければならなかったこと(個人的抑圧)
・事実婚夫婦の住民票記載の方法は自治体の「解釈」によって変えられてしまうこと(制度的抑圧)
・私自身も「私が名字を変えればこんなことで悩まなくて済むのかな」「名字を変えてしまった方が楽なのかな」「私がこだわりすぎなのかな」と思っていること(個人的抑圧(内在化))
など
私は事実婚に至るまでの過程で、泣き虫だから泣いていたわけではない。心が弱いから泣いていたのでもない。
その背景には女性を抑圧する社会構造があり、そういう社会構造を維持する特権をもっている人たちがいて、そういう人たちが作る社会に私は泣かされたのだ。
*
ここで、ニュースキャスターとしてご存知の方も多いであろう安藤優子さんの記事を引用したい。
「女性への認識は、ほんわりといつのまにか自然発生的に日本社会に植え付けられたものではなくて、よくよく研究してみると、自民党の政党戦略として、戦後一度も見直されることなく、常に、戦略的に、再生産されてきた。このことを私たちは知るべきです」
「夫婦別姓だって『選択制』であって、みんなにそうしてくれと言っていない。法案が出されたのが30年前なのに、先日の岸田総理の答弁は『自民党内の意見も踏まえ、しっかりと丁寧に検討していく』と。何十年検討すれば気が済むわけ?私たち死んじゃうわ、という感じですよね。防衛費の増加はあんなに簡単に決めるのに、なぜ夫婦別姓は決まらないのか。ちょっとおかしくない?って」
3.私が起こしたアクション
「名字を変えたくない」と気持ちを決めた時から、ほんの些細なことから自分にとってはチャレンジングなことまで色々な行動を起こしてみた。
身近な人に、積極的に話した
「同僚」との会話の中で「名字を変えたくなくてこういう手続きをしています」、「無事、事実婚をしました」というのを意識的に話した。そういう気持ちで生きている人がいることを知ってもらいたかったから。みんなからは「いいね」「ソーシャルアクションだね」「おめでとう」と、話すたびに肯定してもらって嬉しかった。
「両家の家族」に私たちの気持ちを知ってもらおうと、結婚式の時にしおりを作って配布した。もちろん結婚を決めた時に説明したけど、どういう気持ちで、どういうことと戦っているのかを知って欲しかったから。私自身としては、これから結婚を考えることがあるかもしれない妹や弟に、「こういう選択肢もあるんだよ」というのが届いていたらいいなという気持ちも込めて。
この「note」も身近な人に伝えるアクションの一つ。前半のnoteの冒頭に書いたように、この記事を書くのはかなりエネルギーが必要だった。でも、世界のどこかにいる誰か1人にでもこういう選択をした私がいることを伝えられたらと思って書いた。
市議会議員さんに連絡、市議会で取り上げられた
前半のnoteに書いた通り住民票の手続きで市役所と戦った時、だれに相談したらいいか分からないけどとにかく誰かに聞いて欲しくてTwitterで探していたところ、居住市にパートナーシップ制度を最初に提案してくれた市議会議員さんを見つけた。
藁にもすがる思いで長文のメールをしたため送ったところ、数日で返信をくださり、なんとその半月後の議会で取り上げてくださった。その議会で何かが変わったわけではないけど、「声を上げたら届くんだ」という成功体験になった。
ゼクシィにコメントを投稿、掲載された
前半のnoteで紹介した、事実婚の手続きについて詳しく記事にしてくださっている應武さんには、事実婚契約書を締結できた時にお礼の連絡をしていた。
その後、「ゼクシィに載りませんか」と連絡をもらい、2023年4月21日発売のゼクシィにコメントを寄せたところ、掲載された。

私は一文のコメントのみの登場だけど、この特集で感動したのは、"男性側の名字に合わせたカップル"、"女性側の名字に合わせたカップル"、"別姓で事実婚をしたカップル"それぞれ2組ずつ詳しく取材されているところ。「どの選択肢も同じだけ可能性がある」というメッセージが、とてもいいなと思った。

「まずふたりのスタイルを考えることから」という特集で、名字もいろいろ、働き方もいろいろあって、それぞれに必要な手続きの概要まで載っている。
この記事をすぐに読んでくださった方がいれば、今まだコンビニや書店で手に入れられると思うのでぜひ。
こういう特集を継続的に掲載してもらいたいし、今後は同性婚も取り上げてもらいたい。
陳情アクションに参加している
選択的夫婦別姓の法制化のため、全国的に活動している「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」。
それぞれ参画しているメンバーが居住市・勤務地の地方議会に陳情をする活動をしているのだが、私もそれに加入した。
私の居住市の議会ではまだ意見書が可決されていないため、同じ市に住む方と協力して今後アクションを起こしていく予定。
この「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」は、2025年までの法制化を目指して、現在クラウドファンディングに挑戦中。選択的夫婦別姓を1日でも早く実現したいと考えている方、ぜひこちらから詳細ご覧ください。
4.パートナーと話した選択的夫婦別姓について
事実婚契約書を締結した日に、パートナーと選択的夫婦別姓について思うことを話した。一部を紹介する。
S=私、鈴木。
P=パートナー。
内在化されている抑圧
S:結婚するにあたって夫婦別姓にするか/しないか議論したじゃん。コメダとかで喋ったやつ。あれは本当に心折れそうだった(笑)
P:それは俺の賛同がなくてってこと?
S:いや違う違う。
P:どうしたらいいのかってこと?
S:うん。〇〇(パートナーの名前)はそうは思ってないと思うけど、どうしても自分の中に偏見みたいな、やっぱり「女が変えるべきである」みたいな考えがあって、だからずっと申し訳ない気持ちとか、私に全ての判断が委ねられている感覚みたいなのがあって。それが結構苦しかった。また、子どもが生まれます、とか、相続が、とかその度に思い出すことになるんだろうなとは思うけど。
P:今もそう?心折れそう?
S:ちょっと乗り越えたかな、とりあえず手続きが無事に終わって。でもずっと心の中にはあるよね、やっぱり申し訳ないみたいな気持ちとか、なんかあった時にやっぱり私が名前変えておけばよかったと思うのかな、みたいな。
P:それはもう、なってから考えたらいいよ。「こうしときゃよかった」みたいなの言い出したら、それはもう結果論だから。そうならないためにちゃんとこうやって手続きと議論を交わしてきたわけじゃん。
S:そうだね。
パートナーとの関係性
S:でもやっぱり、名前を変えない、っていう決断はしてよかったと思ってる。
P:よかった。
S:それは本当にありがとう、って思う。
P:俺は自分の姓に対してそんな執着みたいなこととかないからあれだけどさ、親とかも分かってくれてよかったな、って思う。
S:そうだね、それはそう。〇〇のご両親にお話しした時めっちゃ緊張したもん。
P:これからも、有耶無耶なまま「もういいです」みたいな感じはやめようね。
S:「もういい、法律婚しよう」みたいな?
P:それだけに限らず。自分の中にそういう気持ちがあるのに押し殺して、とか。そういうのはやめよう。
S:そうだね。そういう違和感をちゃんと認める、みたいなのができるのは、〇〇との関係性がちゃんとあるから、って私は感じる。「〇〇には話しても大丈夫」っていう。
P:それはこれからも言って?(笑)
S:そうやって言ってくれるじゃん、いつも。
P:隠したりすることなんてないから(笑)
S:それは誰との間でもできるかって言われると違うからさ。いつもありがとう。
P:どういたしまして。
身近なアクション
P:なんやかんや、少しずつ前に進んでる感じがするのも「すげえな」って思って見てる。
S:何が?
P:そうやって声を上げるとかさ。ちょっとした変化でも起きてるじゃん。それがすげえな、って思うよね。
たった一通メール送ったとか、ちょっとした時間で一言その話をしたとかさ。それだけで結構な変化が起こるじゃん。議会で取り上げてもらったとか。それをすること自体はそんなに難しいことのように聞こえないかもしれないけど、でもそれをしない人の方が大半なわけじゃん。でもそれをして、こういう風にちょっとでも何かしらの変化が起きてるのがすげえなって思ってる。
S:人に恵まれてるからだと思うよ、私は。そうやって受け止めてくれる人がいるわけで。
P:それは人徳じゃない?
S:いやあ、それはどうやろ。必死さ?(笑)
P:大事だと思うよ。
S:たまにそういう必死さが働くんだよね。「これはどうしても許せない」みたいなのとか「こうしないと気が済まん」みたいなエネルギーが出てきて。久しぶりかも、ここまで必死になってるのは。
P:アドボカシー*1だね。
S:アドボカシーだね。まだ、もうちょっと頑張るから。
(*1 アドボカシー: 直訳では「擁護」「代弁」「支持」といった意味。権利を守ったり主張したりする活動のことを広く指す)
選択的夫婦別姓についての考え方
S:ああ、早く選択的夫婦別姓、実現しないかな。
P:逆の考え方してみたら?
S:どういうこと?
P:別姓にすることを選べますよ、じゃなくて、同姓にすることも選べますよ、にしたらいいんじゃない?
S:そうそう、だから「選択的」なんだけどね。
P:「選択的」は別に「別姓」だろうが「同姓」だろうがどっちでもいいんでしょ?元々みんな別なんだから。
S:そうなんだよ。
P:したい方は一緒にしていただいて、みたいな。
S:まさにそう。一緒にしたい人はしたらいいんだよ。選択的夫婦別姓を望んでる人は「一緒にしたくない」って感覚なんじゃなくて、「自分の名前のままでいたい」って気持ちなだけなんだよね。
P:それが今は「一緒にしなきゃいけない」って言われてるから。
S:そう。同姓にしたい人はしてもらったら全然いい。おめでとう、って思うし。
P:ほんと頭固えよな。
S:本当そう。もういいじゃん、ってね、思うわけよ。
P:じゃあいま結婚してる人たちがみんな別姓になったからって何かじゃあ変わるかって別に何も変わらないやろって。
S:なんも困らんよね。「子どもが悲しむ」とかも、結局「家族はみんな同じ名字」っていうのが当たり前の社会だからであって。学校で親のフルネームなんて聞かれた?「〇〇君のお母さん」って感じじゃんね。
P:そう、本当に。なんなら子ども同士で同じ名字のやつもいるし。
S:そうだよね。でも〇〇が私の考えを聞いて「それもいいんじゃない」って言ってくれたのがすごい嬉しかった。
P:美乃里に話を聞いて「確かにそうだよな」って思うことが多かったから。名字が一緒じゃなかったら家族って思わないかって言ったら別に全然そんなことねえな、って。
S:そうだよね。それが「家族の絆だ」みたいに言う人もいるけど。
P:父方のじいちゃんばあちゃん、母方のじいちゃんばあちゃん、もちろん名字違うわけじゃん。でも普通に自分と名字が違うからじいちゃんばあちゃんじゃありませんって思うかって「いや、そんなことねえ」って思うし。
S:そうだよね。
P:子どもの感覚ってそういうもんじゃん。子どもの頃から名字の違いで血縁かどうかを判断してたかって言ったら全然そんなことなくて、関わった時間とかでしょ。
S:うんそうね、そっちの方が関係性に大事だったりするよね。
P:名字がうんぬんなんていうのは大人が勝手にレッテル貼ってるだけでしょ。
S:本当にそう思う。私も小さい頃に母がぽつっと「名前変えたくなかった」って言ったことがあって。すごい覚えてるんだけど。その時、「え、戻せばいいじゃん」って普通に思ったんだよ。結婚するときに名前変えなきゃいけないとか、その知識さえもなかった時だったけど。「なんで変えなきゃいけなかったの?」ってめっちゃ思ったし。「母が自分がよかったと思えてる名前で生きてほしい」って思ったんだよね。「自分と同じ名字じゃなきゃやだ」っていうことよりも。
抑圧と特権
S:もしどっちも「名字を変える/変えないどっちでもいいです」だったら、何か誰か意思がある人の意見に従うことになってたのかな。
P:それか、もしくは抑圧にそもそも流されていくかもしれんしね。一般的に男性に姓を合わせることが多いんでしょ、だって。
S:うん。男性の特権みたいなのは感じる?
P:感じる感じる。だって世の中そんなもんだらけでしょ。
S:じゃあ私が名字を変えたくないっていう話をして「いや、でも女が変えるべきやろ」みたいなふうにならんかったのはなんで?私の意思が強かったから?
P:そこに明確な根拠がないからじゃない?美乃里が変えることでのメリットもなかった、に意味は等しいかも。しかも事実婚とか契約書を作る方法とかもちゃんと探してくれてたから、それでいいじゃんって思ったから言わなかったのかな、って思う。
S:興味深いですね。特権は、持ってる人は無自覚なのね。で、抑圧されてる側はすごい感じる。
P:そうだろうね、だから男で生まれてる以上、俺はそれを感じることはないだろうと思う。
S:そんな中で今回は私の、その抑圧されてる側の気持ちをちゃんと汲んで、フェアな選択肢を取れるようにしてくれたじゃん。
P:「変えたくない」っていう人に変えろっていう筋合いもなかったみたいな感じよ。
S:「変えたくない」って言ってたのは大きいのかな、じゃあ。
P:そうよ、絶対そう。「変えたくないんだね、じゃあいいんじゃない」みたいな。
S:ああね、なるほどね。
P:言われてみれば「確かにそうだな」っていうのもたくさんあったから、だから俺は「変えてほしい」なんて微塵も思わなかった。
S:なるほど。個人のレベルではそうなんだよね、多分。別に男の人たちだって、女の人に名前を変えてほしいっていう強い意識があるわけじゃないじゃん。
P:ないよないよ、よほどのことがない限り。
S:でも文化的にそう、みたいなさ。昔は女性にも選挙権がなかったわけだし。そう思うと頑張ろうって思う。
P:でも変わってはきてるね。
S:少しずつ。こういう話を自分の中に消化して、いま仕事でも取り組んでる反抑圧的ソーシャルワーク*2 のことをちゃんと落とし込もうという長い道のりです。
P:気が済むまでやってくれ。
S:やろうと思います。
P:まあこうやって話をするくらいしかできないけど。
S:いやあ、ありがたいです。私が考えたことを喋ったりするだけで私の勉強になるから。また話を聞いてください。
P:うん、もちろん。
S&P:ありがとう。
(*2 反抑圧的ソーシャルワーク: Anti-Oppressive (Social Work) Practice (=AOP)。社会の権力構造、それによって起きている抑圧に立ち向かうソーシャルワークのこと)
*
最後に
事実婚は、選びたくて選んだ選択肢ではない。
名字を変えたくなくて「結婚しない」ことを選んでいる人たちもいる。
この記事では結婚するにあたり悲しかったこと、苦しかったことばかり書いてきたけど、それ以上に嬉しいこと、楽しいこと、幸せだと感じることの方が多い。
私は毎日、幸せに暮らしている。
パートナーと同じ名字にしたい人も、生まれ育った名字のままでいたい人も、同じように結婚のかたちを選べるように。
「2人とも、名字を変えずに結婚しました。」も当たり前の社会になるように。
1日でも早く、選択的夫婦別姓の法制化を望みます。
*
(引用)
Bains, D., Clark, N., Bennett, B. [2007] 2022, Doing Anti-oppressive Social Work: Rethinking theory and practice, 4th ed, Halifax & Winnipeg: Fernwood Publishing.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?